仕事始めと御用始めの意味は?使い分けを教えて!
「仕事始め」と「仕事初め」はスマートフォンなどで検索するとどちらも出てくるようになっているのでどっちが正解なのか直ぐには判断できません。
今回はどちらが正解なのかを詳しく解説し、御用始めとの違いについても解説いたします。
2025年の仕事始めがいつなのか、使い分けするにはどうしたらいいのかも調べていきましょう。
「仕事始め」と「仕事初め」どっちが正解?
新年の始まりと共に、私たちの仕事も新たなスタートを切ります。
この時期、よく耳にするのが「仕事始め」と「仕事初め」という言葉。
どちらが正しいのか、ちょっとした疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
まず、結論からお話しすると、「仕事始め」が正しい表現となります。
この理由を探るためには、日本語の奥深さに少し目を向けてみる必要があります。
「始め」と「初め」、似ているようで、実は使い分けがあるんですよ。
例えば、「始める」という言葉は、何かをスタートさせる、再開するという意味合いがあります。
例えば、「またジムに通い始めた」という時に使います。
つまり、何かを「開始する」ときの「始める」なんですね。
一方で、「初め」という言葉は、人生で初めての経験や出来事を指します。
例えば、「人生で初めての海外旅行」といった場合に使うのが「初め」です。
「ファーストエクスペリエンス」のような感じでしょうか。
では、お正月に行う書道、いわゆる「書き初め」はどうでしょう。
これは新年最初の書道であり、一年で「初めて」行う書道ですから、「初め」という言葉が使われるんですね。
こうしてみると、「新年になって初めて仕事を始める」という行為は、「仕事始め」と表現するのが適切です。
新年の初めての仕事ではありますが、仕事を「スタート」させるという意味合いが強いため、「始め」が使われるのです。
実は、あるアンケート結果によると、7割以上の方が「仕事始め」という表現を使っているそうです。
これは、多くの人が無意識のうちに、言葉の意味を正しく捉えている証拠かもしれませんね。
間違えやすい理由の一つに、パソコンやスマートフォンでの文字変換が挙げられます。
また、「書き初め」という似たような言葉が存在するため、つい混同してしまうこともあるのではないでしょうか。
「書き初め」は新年の風物詩として頭に残りやすいため、それに引っ張られて「仕事初め」と誤って使ってしまうこともあるかもしれません。
さて、このように日本語には微妙なニュアンスの違いがあるため、時には混乱を招くこともありますが、それがまた日本語の魅力の一つですよね。
新年の始まりに、こんな言葉の小話を知るのも、新たな一年のスタートにふさわしい気がします。
今年も一つ一つの言葉を大切に、素敵な一年を過ごしましょうね。
仕事始めと同じ意味
- 官公庁など行政機関:御用納め、御用始め
- 証券取引所:大納会、大発会
仕事始めと御用始めとの違いは?
新しい年の始まりには、新たな気持ちで仕事を始めることが多いですよね。
でも、ちょっと待ってください。よく耳にする「仕事始め」という言葉、そして少し古風な「御用始め」という言葉、この二つの違いってご存知ですか?
仕事始め vs 御用始め
まず、「仕事始め」とは、文字通り新年の休み明けに仕事を再開することを指します。
これは、企業や店舗、学校など、様々な場所で使われる一般的な表現です。
新年の挨拶としてもよく用いられますね。
一方、「御用始め」という言葉は、少し特殊です。
こちらは主に官公庁や行政機関で使われる言葉で、新年の業務開始を意味します。
もともとは、民間企業でも使われていたのですが、少し堅苦しい印象があるため、現在ではあまり一般的ではなくなっています。
表現の変遷
| 時代 | 表現 | 使用される場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 昔 | 御用始め | 官公庁・民間企業 | 堅苦しい印象 |
| 現在 | 仕事始め | 一般的な職場 | よりカジュアルな表現 |
時代劇での「御用だ」
さて、時代劇でよく耳にする「御用だ」というセリフ。
これは、お上の命令で何かをする、という意味が込められています。
実は、これも「御用始め」と同じく、行政機関や官公庁で使われる言葉の一つなんですよ。
というわけで、新年の「仕事始め」と「御用始め」の違いについてお話ししました。
今は「仕事始め」という言葉が一般的ですが、歴史を振り返ると、言葉の使い方一つでその時代の文化や社会の変化が見えてくるものですね。
今年も一年、皆さんにとって素晴らしい年になりますように。
仕事もプライベートも、新たな気持ちでスタートしましょうね!
「仕事始め」「御用始め」それぞれの意味

それでは仕事はじめと御用始めのそれぞれの意味をより深く掘り下げてみましょう。
ほとんど意味は変わらないと言われていますが、辞書などでも同じような意味で記載されているのでしょうか。
使われ方の違いを含めてチェックしていきましょう。
仕事始め
まず「仕事始め」から見ていきましょう。
この言葉は、一般的に民間企業で使われることが多いです。
新年が明けて、その年の業務が正式にスタートすることを意味しています。
例えば、私たちがよく知っている会社やお店などで、新年の挨拶として「仕事始めました」というフレーズを耳にすることがありますよね。
実は、NHKなどの公共放送でも「仕事始め」という言葉が意識的に使われているんですよ。
御用始め
一方、「御用始め」は、少し格式の高い言葉として知られています。
宮中や幕府、政府など、国や公の機関で使われることが一般的です。
こちらも意味自体は「仕事始め」と同じで、新年になって初めての業務開始を指します。
ただし、1960年頃までは民間企業でも使われていたそうですが、’御用’という言葉が持つ「お上の仕事」というニュアンスが、少し堅苦しく感じられるようになり、徐々に使われなくなったと言われています。
現在では、公務員の方々が「御用納め」や「御用始め」という表現を使うことが多いですね。
それでは、この二つの言葉の違いを表にしてみましょう。
これで、より明確に理解できるはずです。
| 項目 | 仕事始め | 御用始め |
|---|---|---|
| 使用される場所 | 民間企業、一般的な職場 | 宮中、幕府、政府などの公的機関 |
| 意味 | その年の業務開始 | その年の業務開始 |
| 歴史的背景 | 現代的な表現、広く使われている | 昔は広く使われていたが、現在は公的機関で主に使用 |
| 語感 | カジュアル、親しみやすい | 正式、やや堅苦しい |
このように、同じように見えても、実はそれぞれに独特の背景や使われ方があるんですね。
新年の挨拶として、これらの言葉を使う際には、その違いを意識してみると、より一層、新年のスタートを楽しむことができるかもしれませんね。
使い分けはどうしたらいい?

仕事始めや仕事納めという言葉と御用始めや御用納めといった言葉の使い方は、行政機関に勤めているかどうかで判断すると良いでしょう。
いわゆる民間企業に勤めている人は仕事始めや仕事納めという言葉を使えば問題ありませんし、逆に市役所といった公務員の方々は御用納めや御用始めといった使い方をするのが正解となります。
それよりも若い人達は挨拶されるよりも先に挨拶する方が印象やイメージが大きく異なりますので、笑顔で仕事始めの日は先に挨拶するようにしましょう。
職場に入ったら上司から順に挨拶「新年おめでとうございます、本年もよろしくお願いします。」と笑顔で挨拶してください。
通りすがりの挨拶にならないように立ち止まって挨拶する意識も重要です。
また、基本的にどのように表現するのかはその職場にいる方々の会話の端々から拾っていけば問題ないので、どのように表現するのか迷ってしまったときはちょっとしゃべるペースを抑えつつ聞き耳を立てて動くようにしましょう。
それだけで、どのような言葉を使っているのかわかるようになるので溶け込みやすくなります。
気になる部分がありましたが、スマートフォンなどを使って時間がある際に気になった言葉を調べるようにしてください。
2025年の仕事始めはいつ?

これは仕事の内容によって大きく変わってくるのでなんとも言えません。
まず、御用納めや御用始めといった言葉の使い方をする官公庁の年末年始のお休みは、毎年12月29日から1月3日までと決まっております。
つまり、仕事納めが12月28日で仕事はじめが1月4日ということです。
仕事始めも1月4日が仕事はじめとなります。
つまり12月29日から1月3日までがお正月休みとなるところが多いと言うことです。
有休を使わなくても6日間ほど休めるという計算になります。
ただし、銀行のような12月30日まで仕事をしているような会社の場合は2022年の仕事納めが12月30日となって仕事はじめが2025年1月4日となるでしょう。
仕事納めの時期はずれるところもあるかもしれませんが、仕事始めは多くの企業で同じになるのでは無いでしょうか。
9日間もお休みがあればちょっとした海外旅行も視野に入りますので、先に予約しておくことも重要になっていきます。
仕事始めの挨拶は?
「本年もよろしくお願いします」は万能です。
新年にまず迷うのが、「どう挨拶するか」ではないだろうか。
いつもなら、上司や同僚に会ったら「おはようございます」で済みますが、今年はじめてのご対面となると悩ましいです。
「おはようございます」といえばよいか、それとも「あけましておめでとうございます」といえばよいか……。
結論からいうと相手に合わせるのが正解です。
もちろん、基本は「あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます」と丁寧に新年の挨拶をするのがベストです。
- あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
- 新年おめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。
まとめ
以上、いかがだったでしょうか。
今回は仕事始めと仕事初めの違いについて解説し、御用始めと仕事始めの違いについても解説しました。
正しい使い方は「仕事始め」であり「御用始め」との違いは行政機関に勤めているかどうかというのもわかりやすい違いでしょう。
メールで文章を作るときも仕事初めではなくしっかりと仕事始めとなるように意識してください。
一般企業に勤めている人は問題なく仕事始めや仕事納めという表現をすることができますので特に悩むことは無いでしょう。
ちなみに、その違いだけ理解しておけば相手の言葉から「この人は行政機関に勤めている人だ」という事が直ぐにわかるようになっているのです。



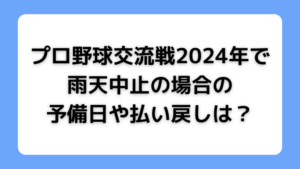






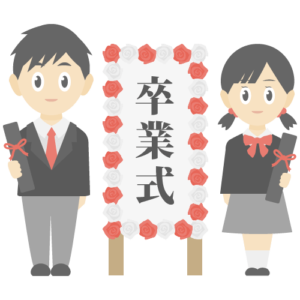
コメント