2025年はいつ書初めをすればいいの?書き初めの意味や由来やおすすめの言葉や熟語は?
正月に行う書き初めには込められた意味があり、由来が存在します。
今回はこの書き初めの由来や意味について詳しく解説し、いつ行うのかも解説いたしましょう。
子供への説明を簡単にする方法や定番の言葉といった気になる情報も盛り込んでいきますので、ぜひご覧ください。
書き初めはいつ
書き初めは、2025年1月2日に行うのが、一般的です。
書道や茶道、三味線などのお稽古ごとは「1月2日から習い始めると上達する」と言われていて、この日を初稽古の日とする習い事は多いようです。
書き初めの由来や意味
日本の伝統文化には、新年を迎える際のさまざまな行事がありますが、その中でも特に意義深いのが「書き初め」です。
この行事は、新年の2日目に行われることが一般的で、その由来と背景には深い歴史が刻まれています。
書き初めの由来
書き初めの起源は、平安時代に遡ります。
当時、宮中の文人たちが行う「吉書初め」という行事がその始まりとされています。
この行事では、元旦にその年初めて汲んだ清らかな水(若水)で墨をすり、恵方を向いて詩歌を書くという儀式が行われていました。
一般への普及
江戸時代に入ると、寺子屋の普及により、書き初めは庶民の間にも広まり始めます。
この時代になると、書き初めは単なる文人の行事ではなく、一般の人々にも親しまれる文化となりました。
書き初めと仕事始め
書き初めが正月の2日目に行われるようになった背景には、仕事始めの日との関連があります。
古くから、2日は農家では畑や山の神を祀り、商家では初荷を出すなど、新年の仕事準備が始まる日とされていました。
この日に、その年の目標や抱負を書き記す書き初めを行うことが、良いスタートとされたのです。
明治時代の変化
明治時代に入ると、書道が学校教育の必修科目となり、書き初めはさらに盛んに行われるようになりました。
この時代の教育改革により、書き初めは教育の一環としても重要視されるようになったのです。
現代の書き初め
現代では、書き初めは新年の抱負や目標を書き記す行事として、学校や家庭で広く行われています。
この伝統的な行事を通じて、新年の決意を新たにし、一年のスタートを切る意義が込められています。
書き初めは、単なる文字を書く行事ではなく、日本の文化と歴史を感じることができる特別な行事です。
新年を迎える際には、この伝統を大切にしながら、自らの目標や抱負を心に刻む機会として活用することができるでしょう。
書初めの意味
新年が始まると、日本の伝統的な行事の一つとして「書き初め」が行われます。
これは、新しい年に向けて、文字を美しく書く技術を向上させる願いを込めた行事です。
特に1月15日には、「どんど焼き」という特別な行事があります。
この日、人々はお正月飾りや書き初めの作品を集め、一箇所に積み上げて燃やします。
この習慣は、新年の健康と安全を祈願するためのもので、書き初めの半紙を炎に投じることで、文字が上達すると信じられています。
また、新年の2日目には、その年の目標や決意を書き記す習慣があります。
この行為は、新年の仕事や学業が成功することを願って行われます。
書き初めには、ただ文字を書くだけでなく、深い意味や目的があります。
この行事を行う際には、手漉き半紙や手漉き和紙など、質の良い書道用紙を選び、一文字一文字に心を込めて書くことが大切です。
それによって、新年の抱負や願いがより強く表現されるのです。
| 行事 | 日付 | 意味・目的 |
|---|---|---|
| 書き初め | 新年 | 文字の上達を願う |
| どんど焼き | 1月15日 | 無病息災を祈願し、書き初めの半紙を燃やす |
| 目標記入 | 新年の2日 | その年の仕事・学業の成功を願う |
新年の始まりに、書き初めで自分の願いや目標を表現してみてはいかがでしょうか?
書き終わった書き初めはどうしたらいいのか?
書き終わった書き初めは、飾って読み返し、気持ちを新たにするといいでしょう。
そして、歳神様が滞在する期間といわれる「松の内」(1月7日、または15日)までは飾っておくとよいそうです。
書き初めは実はそこで書いたものをどんど焼きで燃やすまでが一連の行事となっているので、自分たちが行く予定のあるどんど焼きを行う日までには終わっていないといけないでしょう。
書き初めや古いお札が天高く舞い上がるほど願いが叶うとか字が上達するといわれていますので、子供たちと一緒にどんど焼きに行ってどこまで舞い上がったのか確認することを推奨します。
一昔前まではこのどんど焼きも1月15日の小正月に行われていたのですが、地方ごとにタイミングが異なるようになっているので確認したほうがいいです。
15日ではなく15日に近い日曜日にずらしているところが多くなっています。
ちなみに、小学校の課題で書き初めが用意されることが多いのですが、提出が終わって家に持ち帰りそのまま捨てる人も多いでしょう。
それは実は縁起が悪いことなので、どんど焼き前に提出できてかえってきている場合は燃やしてあげるように意識してください。
書初めを子供へ簡単に説明するには?

これはなかなか難しいですが、ある程度納得できる理由が用意できているのならその理由を中心に解説するといいでしょう。
まず、書き初めをする理由を聞かれたら「字が綺麗になりますようにという願いを込めているから、きっと上達する」ということと「目標や抱負をきちんと記載することで自分が今年1年何をやりたいのかはっきりさせることができる」ということを必ず説明してあげてください。
難しい言葉を使っても納得しにくくなってしまいますので、「目標をはっきりさせる」とか「字がうまくなるという願いが込められている」という言葉を簡潔に伝えることが大切です。
また、どんど焼きで燃やして高く舞い上がるとそれだけその願いが叶うようになると説明すると書いて終わりではないということも認識してくれるので、今部分もきっちりと伝えて上げましょう。
何らかのスポーツクラブに入っている子や部活動を行っている子ならば目標や抱負がはっきりしていることも多いでしょうし、それだけ書きやすくなるのが書き初めなのです。
書道用品や道具の選び方

書道用品は義務教育の宿題として用意されている場合、学校から指定されているものを用いるのが最適解となりますが、大人が改めて書き初めを行う場合一からそろえなければいけないケースが多いです。
学生時代のものを大事に保管している人もいるでしょうが、引っ越しや一人暮らしなどで紛失及び持っていないという人も多いでしょう。
用意する道具は「八つ切り(やつぎり)」という大きさの紙、書き初め用の太めの筆、名前を書くための細い筆、下敷き、硯、墨汁です。
この中で個人的に最も気を付けてもらいたいのが筆で、安すぎるのは選ばないほうがいいと思います。
せめて500円くらいの筆を用意しましょう。
駄目な筆ではうまく書くことも困難なので、やる気がそがれてしまいます。
逆に筆の質がいいと結構綺麗に書けますので、そこそこ質のいいものを用意してください。
ただし、筆は授業の時だけ使うような人でも2年も使えば駄目になるものが多いので、定期的に買い替えるようにしましょう。
書初めにはどんな言葉を書けばいい?
何らかの大会に出る予定があるなら「優勝」とか「入賞」と記載すればいいですし、大人の方々で特に浮かばないという人でも「身体健勝」とか「無病息災」といった体が元気であることを願って四字熟語を記載すればいいでしょう。
少年野球クラブの所属しているような野球少年ならば「130km/h投げる!」とか「ホームランを打つ!」でもいいですし、サッカークラブに所属しているなら「点をたくさん取る」とか「完封試合を続ける!」といった文章になってもOKです。
車の運転が多い仕事に就いている方は「交通安全」でももちろんOKとなっています。
このように実は書き初めは子供のほうがかなり書きやすく、社会人の大人のほうが書きにくいものとなっているので、大人の方々で久しぶりに書き初めをやろうと思うと詰まってしまう確率が高くなっています。
あまり何も浮かばないという人は四字熟語やことわざをいろいろと調べてその中から気に入ったものを選びましょう。
四字熟語なら日進月歩・切磋琢磨・一所懸命・一念発起・笑門来福などが候補になります。
努力や希望や未来といったシンプルな言葉でももちろんOKとなっています。
書初めの定番の言葉は?

目標を記載するのではない場合は定番の言葉をかくのが一般的です。
その中でも最も多いのは
- 初春
- 初日の出
という言葉です。
これは何も浮かばなかった時の定番となっています。
それ以外には
- 未来
- 努力
- 平和
- 希望
- 健康
といった言葉が定番となっています。
四字熟語も定番ですが、難易度がかなり上がりますのでまずは二文字の熟語からチャレンジしてください。
そこで問題なければ
- 一念発起
- 初志貫徹
- 獅子奮迅
- 心機一転
- 明鏡止水
- 誠心誠意
- 無病息災
- 一期一会
- 一日一生
- 温故知新
- 切磋琢磨
- 有言実行
- 文武両道
- 大器晩成
- 公明正大
- 自重自愛
などの定番となっている言葉を記載すればいいでしょう。
ここまでの言葉でもしっくりこないという人はネット上にある四字熟語などをひたすら読みふけって、見つけるのがいいでしょう。
その中には必ず座右の銘となるものがありますので、時間がある時に目を通すことを強くお勧めします。
個人的にも参照にしているサイトはこちらの「座右の銘にしたい四字熟語一覧【公式】(http://4ji.za-yu.com/)」を活用してください。
カテゴリー別に四字熟語が分けられていますので、その中から自分の今の気持ちに即したものを直感で選ぶといいでしょう。
年間人気四字熟語ランキングなども記載してあるので、そちらから覗いてみるのも正解です。
過去には不撓不屈や一意専心、乾坤一擲や初診貫徹といった言葉が人気だったようです。
書き初めの由来や意味と2025年はいつ?のまとめ
以上、いかがだったでしょうか。
今回は書き初めにおける由来や意味やお勧めの言葉について記載しました。
書き初めは字がうまくなるようにという願いもありますが、自分の目標や抱負を見つめなおす時間でもありますので、大人であればあるほど実は難易度が高いのが書き初めだったのです。
なんとなく仕事をしているという人やなんとなく生活しているという人にいきなり書き初めを推奨すると多くの方が戸惑います。
自分が何のために働いているのか、生きているのかを今一度見つめなおすチャンスと考えて挑んでみてください。




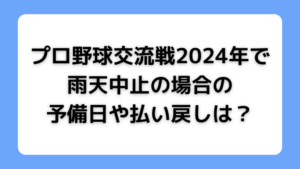






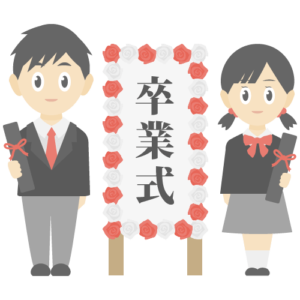
コメント