藪入りという言葉、耳にしたことはありますか?
時代劇の一場面で聞いたことがあるかもしれませんが、その意味や由来はご存知でしょうか。
この言葉は、江戸時代に生まれた日本の伝統的な風習を表しています。
では、藪入りとは一体どのようなもので、どんな意味が込められているのでしょうか?
また、その読み方やいつのことを指すのか、気になる方も多いはずです。
この記事では、藪入りの読み方からその深い意味、由来に至るまでを丁寧に解説していきます。
日本の美しい文化と歴史を感じながら、藪入りの世界に触れてみましょう。
- 藪入りの意味や由来、それが江戸時代の風習であること
- 藪入りが年に2回、特定の日に設定されていた理由
- 奉公人や嫁いだ女性が実家に帰ることができた背景
- 藪入りの語源とその複数の説
- 現代の正月やお盆の帰省習慣と藪入りの関連性
藪入りとは
藪入りとは、奉公人や結婚をして嫁いできた女性などが実家に帰ることができる日のことで、江戸時代から広まった風習と言われています。
藪入りの読み方
藪入りは、「やぶいり」と読みます。
藪入りの意味や由来
藪入りは、主に商家で働く人々が年に二度、実家に帰ることが許された日です。
この日は、1月16日と7月16日の前後に設定されていました。旧暦では、1月16日は小正月、7月16日はお盆にあたります。
このため、現代でいう「正月休み」「お盆休み」として、藪入りの日が利用されていたのです。
江戸時代、多くの家庭では経済的な理由から、子どもたちが若いうちに他家に奉公に出されることが一般的でした。
特に、田舎から都市部の商家に出される子どもたちは、丁稚奉公と呼ばれ、家計を支える重要な役割を担っていました。
これらの奉公人は、一年の大半を雇い主の家で過ごし、家族と離れて暮らすことが常でした。
藪入りは、そんな奉公人たちにとって、年にわずかながらも家族と再会できる貴重な機会でした。
通常、奉公人には定期的な休暇は与えられていなかったため、藪入りの日は彼らにとって大変特別な意味を持っていました。
この日、雇い主は奉公人に対して、小遣いや新しい衣服を与え、彼らの帰省を支援していました。
一方、実家にいる家族も、子どもたちの帰省を心待ちにし、彼らの好物を用意して歓迎の準備をしていました。
しかし、全ての奉公人が実家に帰省できるわけではありませんでした。
距離やその他の事情で帰省が叶わない場合、彼らはもらった小遣いを使って、芝居を見に行ったり、町で買い物を楽しんだりしていました。
このような奉公人の存在もあり、藪入りの日は多くの露店が立ち並び、賑わいを見せていたのです。
藪入りは、ただの休日ではなく、家族愛や絆を再確認する大切な日であり、当時の人々の生活の中で特別な位置を占めていました。
現代においても、このような伝統的な風習を知ることは、日本の文化や歴史を深く理解する上で非常に価値があります。
藪入りの語源は?
日本の言葉の中には、その起源をたどると、驚くほど興味深い背景が見えてくるものがあります。
その一つが「藪入り」という言葉です。
この言葉は、ただの日常用語ではなく、日本の歴史や文化を映し出す鏡のような存在です。
まず、一般的に知られている説の一つに、「宿入り(やどいり)」が転訛(てんか)したというものがあります。
この「宿入り」とは、文字通り「宿に入る」ことを意味し、特に田舎から都市部の商家などに奉公に出た人々が、実家に帰る際に使われた言葉です。
当時の交通手段の限られた状況を考えると、実家に帰るまでに何度も宿泊する必要があったことから、この言葉が生まれたと考えられます。
もう一つの説は、奉公人の出身地がしばしば藪が深い田舎であったことに由来します。
この説によると、実家に帰るためには、文字通り藪の中を通らなければならなかったため、その行為自体が「藪入り」と呼ばれるようになったとされています。
この説は、日本の自然環境や当時の生活様式を色濃く反映しています。
さらに、他にも興味深い説が存在します。
例えば、実家に帰ることができない奉公人が、実家に帰ったかのように見せかけるために藪に隠れた、あるいは藪で遊んで時間を潰したという話も伝えられています。
これらの説は、当時の社会状況や人々の心情を垣間見ることができるものです。
「藪入り」という言葉は、単に実家に帰るという行為を指すだけでなく、日本の歴史や文化、人々の生活様式を映し出す、深い意味を持つ言葉なのです。
このように、一つの言葉が持つ背景を知ることで、私たちはその言葉をより豊かに感じ、日本の文化や歴史を深く理解することができるのではないでしょうか。
藪入りとはいつのこと?
藪入りは、一年に二度、1月16日と7月16日に設けられていました。
この日は、奉公人や職人の弟子たちが、年に二度だけ実家に帰省できる大切な日でした。
旧暦を使用していた時代の日本では、1月15日の小正月と7月15日のお盆が、それぞれの前日にあたります。
これらの日は、家族や親族が集まり、祭りや行事を行う特別な日でした。
藪入りは、これらの行事が終わった後、奉公人たちが一息ついて故郷に帰ることを意味していました。
藪入りの期間
藪入りの期間は、商家や職人の主人の裁量によって異なりました。
一部の人々は、その日だけを休みとして過ごすこともあれば、数日間のまとまった休暇を取ることもありました。
特に、遠方に実家を持つ人々にとっては、この期間が貴重な帰省の機会となっていました。
藪入りと女性
藪入りは、奉公人や職人の弟子だけでなく、嫁いだ女性にとっても重要な期間でした。
嫁いだ女性は、この時期に実家に帰り、家族と再会する機会を持ちました。
特に子供を連れての帰省は、数日間にわたることが一般的でした。
現代との比較
現代の私たちにとっては、年に二度しか休みがないというのは想像もつかないことかもしれません。
しかし、当時の人々にとっては、この藪入りが年間のハイライトであり、心待ちにしていた休息の日だったのです。
藪入りと日本のことわざ
「盆と正月が一緒に来たよう」という言葉は、今でも使われることがありますが、これは藪入りの風習が由来となっています。
この言葉は、何か嬉しいことや特別な出来事があった時に使われ、藪入りがいかに特別な日であったかを物語っています。
藪入りは、ただの休日ではなく、家族との再会、故郷への帰省、そして一年の労をねぎらう大切な時でした。
この風習を通じて、当時の日本の社会や文化、人々の生活が垣間見えるのではないでしょうか。
藪入りと正月やお盆との関係

藪入りは、1月16日、7月16日の前後に、住み込みで働いている商家の主人の許可を得て、実家に帰ることができる日という意味です。
旧暦では藪入り前日の1月16日は小正月、7月16日はお盆のため、今で言う「正月休み」「お盆休み」を藪入りと呼んでいたわけです。
現代では、お正月やお盆になると、多くの人がUターンラッシュを経験しながら実家へ帰省します。
この風習は、実は藪入りの名残と言われています。
第二次世界大戦後、働き方が変わり、藪入り自体は廃れましたが、その精神は今も残り、正月やお盆に実家へ帰る習慣が根付いているのです。
藪入りと閻魔賽日
興味深いことに、旧暦の1月16日と7月16日は「閻魔賽日」とも呼ばれていました。
この日は、「地獄の釜の蓋も開く」とされ、地獄で罪人を煮る鬼たちも休息を取る日とされています。
この日には、閻魔堂へのお参りや、お寺で「地獄相變圖」を拝む習慣があったそうです。
藪入りの現代への影響
藪入りの風習は、現代の日本社会においても、家族の絆を大切にする心として受け継がれています。
正月やお盆の帰省は、ただの休日ではなく、家族や故郷との絆を再確認する大切な時間となっているのです。
このように、藪入りは日本の伝統と現代の生活が交差する、とても興味深い文化の一つです。
年に二度の特別な日が、今日まで色々な形で私たちの生活に影響を与えているんですね。
藪入りと俳句や落語の関係

藪入りは正月とお盆の年に2回あり、1月16日(日付けは前後する)の藪入りをそのまま「藪入り」、7月16日(日付は前後する)の藪入りを「後の藪入り」と呼んでいました。
それぞれ、新年の季語、初秋の季語として俳句に詠まれています。
また、藪入りは落語にも登場します。
三代目三遊亭金馬の演目で、簡単な内容は次の通りです。
❝藪入りで子どもが戻ってくることになった父親は、子どもが帰ってきたら美味しい物を食べさせて、色々な場所へ連れて行ってやりたいと思っていました。
そこに子どもが帰ってきて、先に銭湯に行かせることにしました。
子どもの持ち帰った荷物の中には、高額なお金が入っている財布があり、それを母親が見つけます。
奉公先から持たされたお小遣いにしては大金のため、子どもが何か悪事を働いているのではないかと勘繰る父親と母親。
そこに子どもが戻って来たので父親が尋ねると、「人の財布の中を見るなんて下衆だ。これだから貧乏人は嫌だ」と言われて喧嘩になってしまう。
父親が「それならこのお金はどうしたんだ」と聞くと、「店に出たねずみを警察に持っていき、懸賞に参加してもらったお金(※)だ。
主人に預かってもらっていたものを、藪入りだからと返してもらった」と説明する。
これを聞いた両親は「立派になった」と褒めたたえ、「これも主人への忠のおかげだ」と言った❞
というもの。
忠とは主人に対して裏表なく接することを言い、忠誠や忠義に通じる言葉です。
この忠とねずみの鳴き声の「チュウ」がかかった言葉遊びとなっています。
(※)日本ではペスト患者が出た翌年から、ペストを媒介するねずみを一匹五銭で買い上げていたそうです。
役所や警察にねずみを持っていくと引換券と交換になり、銀行などで換金することができたそうです。
これとは別に懸賞があり、現在の紙幣価値で5万円や10万円が当たるチャンスがあったといわれています。
なお、この懸賞及びねずみの買取は10年で打ち切られたそう。
それは、ペストの流行が収まったからではなく、ねずみに子どもを産ませて小遣い稼ぎをする人が後を絶たなかったからといわれています。
藪入りのまとめ
藪入りとは、江戸時代に広まった風習で、奉公人や嫁いだ女性が年に2回、実家に帰れる特別な日を指します。
1月16日と7月16日の前後に設定され、旧暦の小正月とお盆にあたります。
この日は、家族との再会や絆を深める大切な時間で、現代の正月やお盆の帰省の習慣にも影響を与えています。
藪入りは、日本の伝統と家族愛を象徴する美しい文化であり、その歴史や意味を知ることは、日本の文化をより深く理解する上で価値があります。
この記事のポイントをまとめますと
- 藪入りは江戸時代からの風習で、奉公人や嫁いだ女性が実家に帰れる日
- 年に2回、1月16日と7月16日の前後に設定されていた
- 旧暦の小正月とお盆にあたり、現代の正月休みやお盆休みの起源
- 奉公人には通常、定期的な休暇がなく、藪入りが唯一の帰省の機会
- 雇い主は奉公人に小遣いや新しい衣服を与え、帰省を支援
- 実家では家族が奉公人の帰省を心待ちにし、好物を用意
- 帰省できない奉公人は、もらった小遣いで芝居や買い物を楽しむ
- 「藪入り」の語源には「宿入り」が転訛したという説がある
- 別の説では、藪の中を通って帰ることから「藪入り」と呼ばれた
- 藪入りは家族愛や絆を再確認する大切な日で、特別な意味を持っていた
- 「盆と正月が一緒に来たよう」ということわざは藪入りが由来
- 現代でも、藪入りの精神は家族の絆を大切にする心として受け継がれている




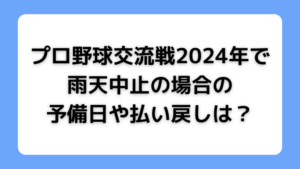






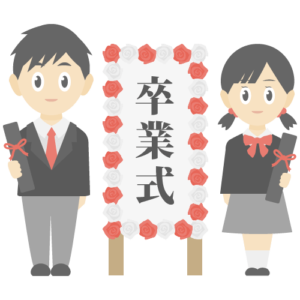
コメント