小正月とは?2025年のはいつ?正月や大正月との違いは?
お正月の話題を探ってみるとたまに登場するのが「小正月」というワードです。
今回はこの小正月とは一体どのような意味があるのか、由来はあるのか、お正月との違いは何なのか、飾り付けはどうしたら良いのか、小正月の行事とは一体何なのかを紹介いたします。
小正月に全く馴染みがないという方はここだけ見ても欲しい情報がすべて見られるようになっています。
小正月2025年はいつ?
日本の伝統的な祝日である小正月は、2025年には1月15日に祝われることになります。
しかし、この日付は地域や文化によって異なることがあり、一部の地域では1月14日から16日までの3日間を小正月として祝う場合もあります。
さらに、14日の日没から15日の日没までを小正月とする地域もあれば、1月1日から15日までを小正月とする地域もあります。
小正月とは、新年の祝いの終わりを告げる日であり、大正月(1月1日から7日まで)とは対照的な意味合いを持っています。
しかし、関東地方では松の内が1月7日までとされることから、小正月も7日とする考え方が生まれています。
また、どんど焼きのタイミングが小正月と関連付けられていたのですが、ハッピーマンデー制度によって日付がずれることがあり、小正月の正確な日付を特定するのが難しくなっています。
小正月までがお正月期間とされ、その後に鏡開きを行うのが一般的です。
使用済みの正月飾りは、伝統的には1月15日のどんど焼きで燃やされていました。
かつては成人の日が1月15日で祝日だったため、この日にどんど焼きを行うのが一般的でしたが、ハッピーマンデー制度により成人の日が1月の第2月曜日に変更されたことで、どんど焼きのタイミングも変わりました。
このように、お正月期間である松の内の日付は関東や関西で異なり、小正月の目安となるどんど焼きのタイミングも地域によって異なります。
そのため、小正月の「正解」は一概には言えない状況です。
それでも、小正月に関連するイベントの多くは全国的に1月15日に行われています。
そのため、一般的には1月15日を小正月と考えるのが妥当でしょう。
小正月とは
日本の文化には、年間を通じてさまざまな伝統的な祭りや行事が存在します。
その中でも、特に興味深いのが「小正月」と呼ばれる行事です。
この小正月は、毎年1月15日に行われる特別な日で、日本の伝統的な暦において重要な位置を占めています。
小正月の意味と由来
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 日付 | 1月15日 |
| 目的 | 1年間の健康と福祉を祈願 |
| 伝統 | 歳神様(としがみさま)をお見送りし、厄払いを行う |
| 名前の由来 | 旧暦の正月(大正月)に対して、1月15日を小正月と呼ぶ |
小正月は、新年の始まりを祝うお正月の延長として位置づけられています。
この日は、新年にお迎えした歳神様をお見送りし、同時に、厄払いや1年間の健康と幸福を祈願する日でもあります。
この行事の名前の由来は、旧暦における正月(大正月)と1月15日(小正月)の区別に由来しています。
旧暦では、新月が月の初日とされ、15日は満月にあたります。
古来より、満月は特別な力を持つと考えられていたため、新年の最初の満月である小正月も、特別な意味を持つ日とされてきました。
正月と小正月と大正月との違いは?
日本の伝統的な祝日には、正月、大正月、そして小正月という3つの異なる期間があります。
これらはそれぞれ独自の意味と祝い方を持っています。
以下に、これらの期間の違いを詳しく解説します。
正月
正月は、文字通り1年の最初の月を指します。
これは1月全体を意味することがありますが、一般的には特に1月1日から3日までの期間を指すことが多いです。
この期間は「正月休み」として知られ、新年を祝うための休暇となっています。
大正月
大正月は、1月1日の元旦から1月7日までの期間を指します。
この期間は、新年を迎えるための準備と祝賀行事が行われる時期です。
特に、歳神様を迎える儀式や神社への初詣などが行われます。
大正月は、新年の始まりを祝うための重要な期間とされています。
小正月
小正月は、1月15日に当たります。この日は、大正月とは異なり、五穀豊穣や家庭的な祝いが中心となります。
小正月は、新年の喧騒が落ち着いた後の穏やかな祝いとして位置づけられています。
以下の表は、これら3つの期間の違いをまとめたものです。
| 項目 | 正月 | 大正月 | 小正月 |
|---|---|---|---|
| 日付 | 1月1日〜3日 | 1月1日〜7日 | 1月15日 |
| 主な祝い方 | 正月休み、新年の祝賀 | 歳神様を迎える儀式、初詣 | 五穀豊穣、家庭的な祝い |
これらの期間は、日本の伝統的な祝日の中でも特に重要なものであり、それぞれ異なる意味と祝い方を持っています。
小正月の食べ物

小正月で良く取り上げられる食べ物は邪気を払う力を持つとされている小豆です。
元々豆は「魔を滅する」という意味が込められているので、鬼退治に使われたり日本の祭事ではかなりの頻度で登場します。
小豆そのものにもかなりの栄養成分が含まれている食べ物ではありますが、昔の人達は鬼や魔を滅するこの小豆を使って無病息災を願っていたのでしょう。
食べ方もいくつかありますが、基本的には小豆粥にして食べるところが多く、ぜんざいを食べる地域もあります。
この小正月と鏡開きをセットにして小豆粥に鏡餅を入れる地域もあるようです。
ちなみに、地域によってはこの小豆粥の炊きあがりによってその年の吉兆を占う祭事を行っていたという情報もありますので、やはり小豆や豆はこのような神事や祭事で頻繁に登場することがよくわかります。
他にはこの小正月のタイミングでどんど焼きを行うことも多かったので、このどんど焼きでお餅を焼いて食べると無病息災で過ごせるといった風習もありました。
今日は #小正月🔥
小豆粥を食べ邪気を払う慣わしや、お正月の松飾りやしめ縄などを焼く #左義長 が行われます。年の初めに家内安全と無病息災を祈願します。書き初めも一緒に燃やして、筆の上達を願いましょう!(地域によってどんど焼きなど様々な呼び方があります。)#1月の年中行事 pic.twitter.com/jJb5ONrBMr— Calendia(カレンディア)【公式】 (@Calendia_NB) January 15, 2022
小正月 小豆粥の作り方
動画「小豆粥の作り方/おかゆレシピ/ばあちゃんの料理教室/小正月(1月15日)に1年の健康を願って食べる」は、小正月に食べる小豆粥の作り方を紹介しています。
ポイント
- 小豆粥は、米と小豆を一緒に炊いた粥で、ハレの日に食べる伝統的な料理です。
- 材料は、米180ml(1カップ)、ゆで小豆大さじ3、塩小さじ1/4、煮汁+水900mlです。
- 作り方は、お米を洗い、鍋にお米と煮汁、水、塩を加えて炊くだけです。
- 小豆粥は新年にぴったりの料理で、1年の健康を願って食べられます。
作り方の詳細
- 小豆を軽く水洗いし、鍋に入れて豆の3倍くらいの熱湯を加え、すぐに煮始めます。
- 強火にかけ沸騰したら差し水を加え、再沸騰後ザルにあけ、アク抜きをします。
- 再び豆の3倍くらいの水を加え強火で沸騰後中火で豆の芯が柔らかくなるまで煮ます。
- 芯まで完全に柔らかくなる手前で小豆を取り出し、小豆と煮汁に分けて冷まします。
- お米を洗います。
- 鍋にお米と煮汁、水、塩を加えて、お米が柔らかく煮えるまで炊いたら出来上がり。
※お餅を入れても良いです。
小正月の飾り物は何?

このように小正月は色々と行われるのですが、具体的にどのような祝い方をすれば良いのか、飾り方をどうすれば良いのかよくわからないという人も多いでしょう。
実際に調べて見たところ、基本的にこの小正月のタイミングでお正月飾りを片付けるのであえて飾ることについて触れているところは非常に少ないです。
探してみると小正月には餅花(もちばな)を飾るというものがありましたので、飾るとしたらこの餅花は紅白の餅をヤナギやヌルデやエノキなどの木に飾って稲穂に見立てましょう。
この行動から花正月と呼ばれることもあります。
また、蚕が盛んだった地域は豊作祈願よりも蚕が無事に育つことを祈る行事となっており、餅や団子で作った玉を蚕に見立てて木の枝にくっつけていたようです。
他にはアワの穂に見立てて粟穂稗穂(あわぼひえぼ)と呼ぶ地域もあるとのことです。
このように調べてはみましたが、あまり一般の方々が簡単に飾り付けを行える行事ではないので、あまり飾り付けは意識する必要は無いでしょう。
おはようございます
本日は小正月。新年の準備に忙しかった女性がー息つける時期にて女正月とも
稲穂に見立てた餅花で豊作を祈り、小豆粥で無病息災を願う
平安の古より連綿と続く伝統行事。天の安らぎと健やかな日常への願いは昔も今も
本日も健やかで楽しい一日を(*^_^*) pic.twitter.com/QNVPehyhgs
— 唐司 誠@行政書士@さいたま市 (@tounosu_makoto) January 14, 2022
古来、正月14日の日没より16日までを「小正月」または「花正月」と呼び、朝には小豆粥を食べたと『土佐日記』や『枕草子』にも記されています。
「繭玉飾り」をつくり豊作の予祝をする地域もあります。
また、「元服の儀」を小正月に行ったことから「成人の日」になったとされています pic.twitter.com/gzBfXLApNw
— 株式会社 うがふくや【公式】 (@ugafukuya) January 14, 2019
小正月の行事

小正月の行事として一番夢医だったのが、どんど焼きや左義長とも呼ばれる火祭りなのですが、ハッピーマンデー制度によって成人の日がずれてしまったのでこのタイミングも15日ではなくなっております。
火祭りはもともと悪魔祓いという意味が込められており、たばねた青竹を立ててそこに書き初めや短冊等を取り付けて燃やした物です。
この燃やすタイミングで陰陽師が歌いはやしたと言われています。
この火祭りが一般の方々に広まって多くの地方でも取り入れられるようになりました。
ここで地方の特色が出るようになり様々な願いが込められるようになり、「火に当たると若返る」とか「燃え残った木は虫除けや火除けに使える」とか「書き初めを燃やして天高く舞い上がると字が上達する」と言われるようになりました。
また、神社によっては粥占の神事を小正月のタイミングで行っているところもあります。
小豆を使うところもありますが、各種の穀物で粥を炊いて占うところも多く小豆だけではないようです。
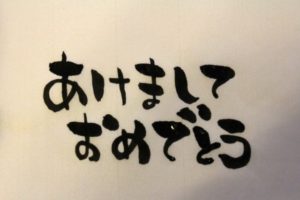

小正月はいつ?のまとめ
以上、いかがだったでしょうか。
今回は小正月についてまとめて参りました。
小正月は現代日本人にとってかなり馴染みの薄いイベントです。
成人の日が動いてしまったことなどでなかなか覚えることが少ない日ではありますが、探ってみると今でもその風習はかなり残っていることがわかります。
どんど焼きや粥占の神事もかなり有名なので、小正月を意識してこれらのイベントに参加してみてはいかがでしょうか。
意識していないだけで、今でも参加可能なイベントが行われているので注目しておきましょう。







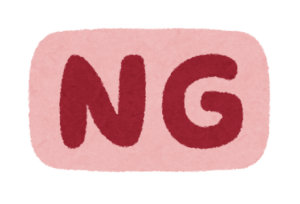




コメント