丑三つ時と言うと、幽霊が出る不吉な時間と覚えている方も多いでしょう。
「草木も眠る丑三つ時・・」と語り始める怪談でも丑三つ時が登場しますが、丑三つ時とはいつ(何時から何時のこと)を指すのでしょうか。
丑三つ時には怖いイメージがある一方で、その意味や由来を知っているという方は以外と少ないかも知れません。
丑三つ時の読み方もわからないという方もいらっしゃるかも知れませんね。
そこで今回は、丑三つ時について調べてみました。
丑三つ時には幽霊が出るのか、呪いのわら人形との関係なども合わせてご紹介します。
丑三つ時とは
丑三つ時とは、現代の時間でいうと午前2時から2時30分の間を指す言葉で、これはまさに深夜の中心時刻となります。
古代の日本の人々は、自然界の動きや気の流れを非常に重視していました。
昼間は「陽」の気が支配的で、活動的な時間とされていました。
一方、夜は「陰」の気が強まるとされ、特に「うしみつ」の時間帯は、その陰の気がピークに達すると考えられていました。
この時間帯には、陰の気が最も強力であるため、妖怪や霊的な存在が現れやすいとも言われていたのです。
そのため、古代の人々はこの時間に特別な儀式を行ったり、注意を払って過ごしていたと言われています。
読み方
丑三つ時は「うしみつどき」と読みます。
由来
昔の日本では、現在のように時間を数字で表す以外に、『延喜式(えんぎしき)』と呼ばれる十二支で表す方法がありました。
十二支とは、子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥から成るもので、現在も干支で用いられていますよね。
(正確には干支は「十干」と「十二支」の組み合わせです。)
夏になるとよく耳にする「土用の丑の日」も、延喜式によって十二支で日にちを示したもので、その中で土用と呼ばれる期間の丑に当たる日を土用の丑の日としています。
十二支は時間の他にも、月や日、方角などにも当てはめられ、昔の生活には欠かせないものだったと言われており、丑三つ時の「丑」とは、十二支を時間に割り当てた時の丑の時間ということになります。
しかし、一日が24時間なのに対し、十二支はその半分の12しかないので時間の割り当てが上手くいきません。
そこで、一つの十二支に対して2時間を枠とし、さらにその2時間を30分ほどに4等分し、それぞれを「一つ時(一刻)」「二つ時(二刻)」「三つ時(三刻)」「四つ時(四刻)」としたのです。
このようなことから、丑三つ時とは丑の時刻の3番目の時刻ということがわかります。
丑三つ時は何時?
 「丑三つ時」は現在の時間で表すと午前2時~2時30分の30分間に相当します。
「丑三つ時」は現在の時間で表すと午前2時~2時30分の30分間に相当します。
「丑の刻」というのが午前1時~3時の2時間を指し、「丑三つ時」は「丑の刻」を30分ずつ4つに分けた中の3番目の時間という意味で、午前2時~2時30分を指すのです。
・丑一つ時は午前1時~1時30分
・丑二つ時は午前1時30分~2時
・丑三つ時は午前2時~2時30分
・丑四つ時は午前2時30分~3時
ということになります。
つまり、丑三つ時とは午前2時~2時30分の間の30分を表すということになります。
午前2時から2時30分と言えば、人はもちろんのこと、街中が寝静まっている時間ですよね。
「草木も眠る丑三つ時・・」から始まる怪談の意味も、これでよくわかる気がします。
裏鬼門は何時?
陰陽道において、鬼門を北東、裏鬼門を南西とし、その方向は「陰」と「陽」の境界に位置し、不安定な方角とされています。これは不吉な出入り口とされています。
この方向を時間に関連づけると、鬼門は丑の刻と寅の刻、一方、裏鬼門は未の刻と申の刻に該当します。具体的には、鬼門は午前1時から午前5時まで、裏鬼門は午後1時から午後5時までという時間帯になります。
丑三つ時にやってはいけない事
盛り塩
厄除けや魔除けの風習として、現在も行われている盛り塩。
鬼門に近づき、霊の気配が強くなる丑三つ時に行うのは効果的に思えますが、このタイミングで盛り塩をしたり、取り換えたりすると、霊を取り込んでしまうことになるので避けた方がよいと言われています。
午前1時~3時に盛り塩を取り換えることはあまりないと思いますが、取り換えるなら午前中に行いましょう。
合わせ鏡
合わせ鏡とは2枚以上を鏡を向き合って置くことです。
これによって霊界へと通じる道ができてしまうと言われており、特に丑三つ時は避けた方がよいと言われています。
お経を唱える、合掌して頭を下げる
このような行為は、周囲に浮遊している霊を取り込んでしまう恐れがあるそうです。
また、お経を唱えた後に水を飲み干すと、水に入った霊を自分の体に取り込んでしまうとも言われているそうです。
丑三つ時が怖い、危険と言われる理由
丑三つ時は真夜中で、何とも言えない不気味な雰囲気が漂う時間帯として知られていますが、なぜ他の特定の時刻ではなく、特に恐れられるのでしょうか?
丑三つ時は鬼門の方角
丑三つ時が恐れられる理由の一つは、その時間帯が「鬼門」と呼ばれる方角に位置することです。
十二支を方角に対応させた際、この時間帯は北東の方角に当たります。
古代から「鬼門」と呼ばれる方角は、邪悪な存在や鬼が出入りするとされ、吉兆ではないと考えられていました。
このため、丑三つ時が「鬼門」と関連づけられ、恐れられるようになりました。
丑三つ時は「陰」の強い時間
中国の陰陽五行思想において、「丑三つ時」は一日の中で最も「陰」のエネルギーが強いとされています。
これは時間帯が夜中であり、日中の「陽」の活力が衰え、逆に「陰」の要素が支配的になるからです。
この「陰」のエネルギーが最も高まる時間帯とされ、古代の人々は「丑の刻」を不気味な時間と捉え、幽霊や妖怪が活動する可能性が高いと考えました。
陰陽道に由来する丑三つ時の恐れ
丑三つ時の恐れは、中国の陰陽道に起源を持ちます。
古代中国では、「丑」は「陰」を、「寅」は「陽」を象徴し、その間に位置する「うしとら(艮)」は「鬼門」と結びつけられました。
このため、丑三つ時と「鬼門」は深い関連性を持ち、恐れられるようになったのです。
丑三つ時は「陰」と「鬼門」が結びついた時間帯として、不吉とされたのです。
丑の刻参りの呪術儀式
丑の刻参りは、丑三つ時の不気味さを一層増幅させる要素の一つです。
この儀式では、呪いの対象とする相手を象徴する藁人形に五寸釘を打ち込むことが一般的です。
正確な方法には複数のバリエーションがありますが、一般的には白装束を着て、相手の髪の毛などを藁人形に入れ、毎晩「丑の刻」に五寸釘を打ち込むと言われています。
この儀式を7日間続けると、呪いが成功すると信じられていますが、誰かに見られると呪いが自身に跳ね返るとも言われています。
それゆえ、「丑三つ時」独特の雰囲気がこの儀式に影響を与えていると言えるでしょう。
丑三つ時に幽霊が出るって本当?
これには、「陰陽五行」と呼ばれる中国発祥の自然哲学が関係しています。
陰陽五行とは、世の中のあらゆるものは「陰」と「陽」に分けられるという考え方(五行は火・水・木・金・土の5つですが、ここでは関係がないので省略します)です。
上記でも触れた通り、昔は十二支で時間や月、日、方角などを表しており、陰陽五行思想によると丑は陰、丑の次である寅は陽になります。
そして、丑と寅の時刻の中間に当たる丑寅(午前3時)は、方角で表すと北東になります。
北東は陰陽道においては「鬼門」がある不吉な方角とされています。
このようなことから、丑寅にほど近い丑三つ時は開いた鬼門から幽霊や魔物がやって来る時間だと考えられるようになりました。
また、丑の時刻の中で丑三つ時が最も陰の力が強いと言われていたことも、丑三つ時には幽霊が出るという話に拍車をかけたのではないかと思われます。
呪いのわら人形について
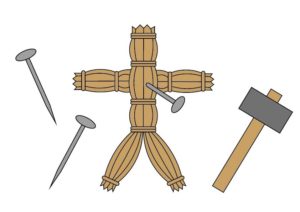
呪いのわら人形とは、殺したいほど憎い相手を思いながら、わら人形に五寸釘を打ち込むと、その人形と同じように相手が苦しむというものです。
怪談やテレビの心霊特集などで見聞きしたことがある方も多いと思います。
このわら人形と丑三つ時は、実は関係があります。
なぜなら、呪いを成就するには、これらの儀式を丑の時刻に行わなければいけないからです。
そして、呪いのわら人形の儀式は相手に知られてしまうと効果がなくなってしまうので、こっそりと行わなくてはいけません。
わら人形を使った呪術は江戸時代頃に生まれたと言われていますが、現在も行っている人がいるかは不明です。
とは言え、五寸釘を刺したわら人形を相手に送りつけたとして、脅迫容疑で逮捕されている事案が発生しています。
呪いのわら人形に効果がある・ないに関わらず、呪いが罪に問われることがあるので注意しましょう。
丑の刻参りの意味は?

丑の刻参りは、平安時代は祈願成就のための儀式だったのが、「宇治の橋姫(※)」の話を元にした能の『鉄輪』により、現在のような形になったと言われています。
その典型は、白装束を着た女性が、ろうそくを立てた鉄輪を頭に被り、神社の御神木に呪いをかけたい相手に見立てたわら人形に、金づちで五寸釘を打ち込むというものです。
(地域によっては、鏡を首からぶら下げるというところもあるようです)
この行為を7日間行い、その間誰にも見られることがなければその願いが叶えられるというものです。
相手に見立てたわら人形で、五寸釘を打ち込んだ部分が病になると言われていました。
浮気癖のある人に対しては、手に五寸釘を打ち込むと女性に手を出さなくなるとも言われていたようです。
丑の刻参りはその名の通り、丑の刻(午前1時~3時)に行うものですが、より鬼門に近くなる丑三つ時に行うのがよいとされていました。
そのため、丑三つ参りとも呼ばれています。
なお、丑の刻参りを誰かに見られてしまうと、呪いが自分のところに返ってくると言われています。
(※)妬む相手を取殺す(亡霊などが憑りついて人を殺すこと)ために、鬼神となるため貴船神社に願ったという伝説。
鬼門の方角について

鬼門とは、鬼が出入りをする方角を意味し、その起源は中国の説話や地形の問題など諸説あります。
それが日本に伝わった際に、陰陽道や神道などの影響を受けて、万事に忌むべき方角として知られるようになりました。
鬼門は丑と寅の間で、北東になります。
そのため、幕府は鬼除けとして、鬼門にあたる北東に大きなお寺を建てたそうです。
なお、陰陽道では鬼門となる北東だけではなく、その反対側の南西(裏鬼門)も不吉な方角とされていました。
このような考え方は現在でも根付いており、家を建てる時などに、鬼門・裏鬼門の方角には、玄関や門、キッチン、トイレ、風呂場などの水回りは避けた方がよいと言われています。
丑三つ時の同義語
丑三つ時は夜遅い時間を指す言葉であるため、この時間を表現するための同義語が存在します。
具体的な代替表現には、「真夜中」、「深夜」、「夜分」、「夜半」などがあります。
「真夜中」は夜の中間点を指し、正午の対極にある午前0時前後の30分程度を表します。
「深夜」は夜遅い時間帯を示し、時には正子(午前0時)の時間帯としても使用されることがあります。
「夜分」は夜の時間帯、つまり日が完全に沈んで暗くなった時間帯を指します。
「夜半」は、「やはん」または「よわ」と読み、午前0時前後を示す言葉です。
丑三つ時に関するよくある質問
丑三つ時はどんな危険がありますか?
丑三つ時とは、夜中の2時から2時30分の間を指す言葉で、この時間帯は「草木も眠る」と形容されるほどの静寂が広がります。伝承や民間信仰によれば、この時間は霊界と現世の境界が薄くなり、幽霊や霊的な存在が出没しやすいとされています。そのため、古くからこの時間帯は不吉とされ、特に霊感が強いとされる人々は、丑三つ時には外出を避けるなどの習慣があったと言われています。
丑三つ時が不吉とされる理由は?
丑三つ時は陰陽道の考え方に基づき、鬼門と同じ方向に位置するため、鬼が現れて災害を引き起こすと信じられているから不吉とされています。
丑三つ時に入浴するとどうなる?
丑三つ時(午前2時)に入浴をすると1年間健康でいられるという言い伝えがあり、真夜中でもお湯に浸かる人の行列ができるほどだという。
丑三つ時とは昔の時刻で何時ですか?
丑三つ時は、古くの時間の区分で、丑の時間を4つに分割した中の3番目を指す。現代の時計で言うと、午前2時から2時30分の間を示し、この時間帯は妖怪や霊が現れるとされている。
丑三つ時 なぜ 幽霊?
古い時代には、昼間は陽の気が、夜は特に真夜中には陰の気が最も強まるとされていました。また、丑三つ時は方角でいうと丑寅(東北)に該当し、これは鬼門として知られ、そこから幽霊が現れるという信仰がありました。
草木も眠るとはどういう意味ですか?
「草木も眠る丑三つ時」という表現は、夜の中でも最も静かで暗い時間帯を指す言葉です。この時間帯は、人々が深く眠っているだけでなく、自然界の生き物や植物までが静寂に包まれていることを示唆しています。この言葉の中の「草木も眠る」という部分は、その静けさがどれほど深いかを強調するための修飾語として使われています。また、「丑三つ時」は夜中の2時から2時30分ごろを指す古い時刻の言い方で、この時間は一般的に最も静かで、人々の活動がほとんどない時間帯を示しています。
丑三つ時のまとめ
丑三つ時とは、現代の時間帯で言えば午前2時から2時30分の期間を指します。
この時間は、一日の中で最も静寂で真夜中に位置し、「草木も眠る丑三つ時」という言葉が伝えるように、非常に静かな時間帯です。
かつて、陰陽道ではこの時間帯を鬼門と結びつけ、不吉なものが存在すると考えられてきました。
そのため、丑三つ時には鬼や霊、呪術的なものが関連づけられ、不吉な儀式や伝説が生まれました。
古代の人々は時間を干支で表し、更に4つに分けて時刻を区切りました。
その中で「丑三つ時」は午前2時から2時30分までの時間帯であり、北東に位置する鬼門に対応しています。
したがって、幽霊や不吉な出来事がこの時間帯に起こりやすいと信じられてきました。
「丑三つ時」には、合わせ鏡を使う、盛り塩をまく、お経を唱える、水を飲むなどの行動を避けるべきだと言われています。
また、「丑の刻参り」はこの時間帯に行われる呪術的な儀式で、白装束を着た人形に五寸釘を打ち込み、相手に呪いをかけるものです。
このような古代の信念や儀式に触れると、昔の人々の思考や想像力に驚かされます。




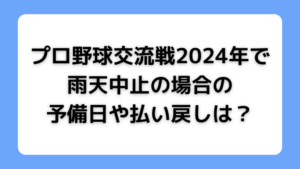






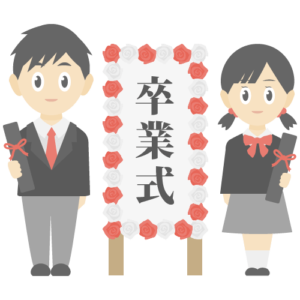
コメント