正月事始めとは?由来や読み方と2025年はいつ?
言葉からなんとなく意味がわかる正月事始めですが、具体的にどのような意味や由来があるのか、明確にいつなのかを把握している人は少ないでしょう。
今回はこの正月事始めについて詳しく解説し、一体何をするのか、お歳暮や大掃除との関係性についても調べていきたいと思います。
ちょっとした知識自慢にも使えるような情報が満載です。
正月事始めとは?
読み方は、「しょうがつことはじめ」です。
「正月事始め」は、単に新年を迎えるための準備というだけでなく、家族の絆を深め、神々への敬意を表す日本独自の文化です。
この行事は、家族が一緒に家を清め、新しい年に向けて心を新たにする大切な時間となります。
1. 煤払い(すすはらい)の伝統
- 由来: 江戸時代に始まったとされ、一年の汚れを払い清める意味があります。
- 方法: 家の隅々まで掃除をし、古いものを整理し、新しい年を迎える準備をします。
- 意義: 物理的な清掃だけでなく、家族が協力し合い、心を一つにすることで、新年を迎える準備を整えます。
2. 「事」の意味
- 祭り事: 「事」とは、祭りや儀式を指す言葉です。
- 年神様への準備: 年神様を迎えるための準備を始める日として、この「事」を「始める」という意味合いで名付けられました。
3. 地域による違い
- 日付の違い: 多くの地域では12月13日が正月事始めですが、地域によっては12月8日から始めるところもあります。
- 風習の違い: 地域によっては特有の儀式や行事が行われることもあり、日本の多様性を示しています。
京都祇園の特別な習わし
京都祇園では、正月事始めが芸妓や舞妓の文化にも深く関わっています。
- 芸妓・舞妓の役割: 彼女たちは、師匠宅やお茶屋を訪れ、新年の挨拶を交わします。
- 感謝の表現: これは単なる挨拶ではなく、一年間の感謝と尊敬を表す重要な行事です。
正月事始めの由来と鬼宿日(きしゅくにち)との関連
12月13日の「鬼宿日」は、正月事始めにも関連があります。
- 吉日の意味: 結婚式を除き、何事を始めるにも吉日とされています。
- 新年の準備: この日から新年の準備を始めることで、良いスタートを切ることができるとされています。
正月事始めは、単なる年末の大掃除以上の意味を持ちます。
家族の絆を深め、新しい年を清らかに迎えるための心の準備、そして地域社会との絆を大切にする日本の美しい伝統です。
この行事を通じて、私たちは新年を迎える準備を整え、心を新たにすることができるのです。
正月事始め2025年はいつ?
2025年の正月事始めは、12月13日(金)です。
一部の地域によってこの正月事始めのタイミングは異なっていますが、江戸庶民にとっては「12月13日」が一般的だったので、基本的にはこの「12月13日」になっていると考えられます。
江戸時代中期まで使われていた宣明暦では毎年12月13日が鬼宿日(きしゅくにち)という日で婚礼以外の物事を行うのに良いとされており、お正月を迎える準備を始める日として適しているといわれておりました。
現在の暦は太陽暦に基づいていますが、「正月事始め」の日は新暦でも12月13日になります。
<12月13日は正月事始め>
正月事始めには、煤払いや松迎え、年男といった習慣がありました。
この日はもともと「鬼宿日」といい、婚礼以外のことは全て吉とされた日。腰が重くなる大掃除のきっかけにもいいかもしれませんね。https://t.co/KcVo6S9Gec pic.twitter.com/3LpHaVyA0O— ウェザーニュース (@wni_jp) December 12, 2021
12月13日は何の日?
12月13日は正月事始めの日であり、この日は何の日になるのかチェックすると高確率で「正月事始め」という言葉が出てきます。
この正月事始めの影響で、実は12月13日は「大掃除の日」に認定されているのです。
他にも数字の「13」が近づけると英語の「B」に見えるとのことで、「Beauty」の頭文字として扱って「美容室の日」としているという情報もあります。
12月は美容室が繁忙期なのでそれにあわせて認定した日なのでしょう。
そして12月13日は語呂合わせで「胃に胃酸の日」に認定されています。
他には「ビタミンの日」「双子の日」にも認定されているようです。
きょう12月13日は
正月事始め
煤払い
松迎え
大掃除の日
ビタミンの日
胃に胃散の日
美容室の日
双子の日誕生花は菊
花言葉は「高潔」 pic.twitter.com/qQkN8aZFMC— はな言葉🌷葉菜桜花子🌷新刊発売 (@hanacotoba_jp) December 12, 2019
正月事始めは何をする日?

この正月事始め、つまりお正月の準備にするべき事は色々とありますが、その中でも昔から続いてきた風習や行事がいくつかあります。
それが「煤払い」と「松迎え」と「年男」です。
この中の1つが文化としてはっきりと残っており、1つはほぼ消えています。
残りの一つは意味が変わった形で残っているようです。
煤払い(すすはらい)
煤払いとは「お正月に歳神様を迎えるために1年の汚れを落として清める事」となります。
江戸城では12月13日に全面的に煤払いをしていたので江戸所民も当たり前のように模倣して12月13日に大掃除をするようになりました。
昔は火種は薪や炭だったので、使えば使うほど天井や壁に煤が溜まってしまうので、徹底的な掃除をすることとは煤を落とすことだったようです。
この煤を落とすための道具である「煤梵天」を用いて天上や掃除をしにくいところまできっちり掃除しいたという情報もあります。
いわゆる1年が終わる前の大掃除とはここからきているという考え方が一般的なのです。
この正月事始めを知らないという人でも正月事始めの風習の一つである「煤払い」名残を当たり前のように受け入れています。
また、大きな商人の家では煤払いが終わった後に祝宴を開いていたという情報もあり、いわゆる年末の忘年会に近いイベントを行っていたようです。
歳神様の考え方や教えが無くなっても、忘年会や大掃除という文化ははっきりと残っています。
松迎え
松迎えとは「門松に使うための松やおせちを調理するための薪などを用意するために山に採取しに行くこと」です。
この松迎えも12月13日に行うので、煤払いも含めるとかなり忙しかったことが予想されます。
こちらの風習は忙しい現代人にはすっかりと消え去ってしまった風習と言えるでしょう。
お正月用に山に採取しに行くというアクティブな人は筆者の周りの人には全くいませんでしたし、薄れてしまった文化だと思います。
おせちや門松という文化や風習は消えてはいませんが、ちょっと寂しい気持ちになります。
年男
新年を迎えるにあたってよく登場するワードの一つが「年男」です。
しかし、現代日本で伝わっている年男は「その年の干支に該当する男性」であり、正月事始めの年男は「お正月の行事を取り仕切る人」と意味が異なっています。
基本的には家長となる長男が大掃除の段取りやお正月の飾り付けや歳神様へのお供え物について色々と取り仕切っていたのですが、色々と忙しすぎたようで時間が空いている家族や奉公人などが対応するようになったようです。
今ではこのように準備や段取りをする人は「お母さん」が該当しているという家庭も多いと思いますので、ある意味「年男」は「お母さん」となっているのです。
正月事始めは正月飾りを飾り始める時期
お正月を迎える準備の一環として、家庭で行われる「正月飾り」の飾りつけについてです。
この風習は、ただ単に飾りをつけるだけではなく、その背後には深い意味が込められています。
正月飾りの飾り始め時期
まず、正月飾りをいつから飾り始めるか、これには一定のルールがあります。
一般的には、12月13日から28日の間に飾り始めるのが良いとされています。
この期間の始まりである12月13日は、「正月事始め」と呼ばれ、この日から新年を迎える準備を始めることができるとされています。
クリスマスとの兼ね合い
しかし、現代ではクリスマスの影響もあり、多くの家庭ではクリスマスが終わる26日以降に正月飾りを飾り始めることが多いです。
クリスマスとお正月、それぞれの飾りつけを楽しむための工夫とも言えるでしょう。
縁起の良い日と避けるべき日
さまざまな理由から飾りを出すのを避けるべき日もあります。
- 12月29日:2と9(苦)で、苦しみが二重と考えられて縁起が悪い。
- 12月30日:旧暦では大晦日に当たる日なので、一夜飾りになるという考え方もある。
- 12月31日:一夜飾りとなり、年神様に失礼に当たる。また、一夜飾りはお葬式を連想する。
現代では、12月25日まではクリスマスの飾りをしている家庭も多いため、正月飾りを出すのは26~28日という方も多いようです。
特に28日は「末広がり」を意味する「八」の付く日のため、縁起が良いとされています。
近年の変化
ただし、現代では30日も一夜飾りと同様に避ける傾向にありますが、旧暦を重視しない家庭も増えています。
時代と共に変わる風習もありますが、伝統を大切にする心は変わらずに受け継がれているのです。
このように、お正月を迎える準備としての正月飾りは、ただ美しく飾るだけでなく、日本の伝統や文化、縁起を考えながら行う大切な行事です。
新しい年を迎える準備をする際には、これらの点を心に留めて、家族で楽しみながら飾りつけを行ってみてはいかがでしょうか。
新年が皆さんにとって素晴らしいものとなりますように。
正月事始めとお歳暮との関係について

お歳暮はお正月用のお供え物を持ち寄るという文化から、日頃の感謝の気持ちを込めてお世話になった人達に送るモノへと変化した風習です。
このお歳暮を贈るタイミングというのが、実は正月事始めが終わったタイミングと言われており、12月13日を過ぎたタイミングが目安とされています。
より具体的には12月13日から20日までにお歳暮を贈るのが理想なのでしょう。
しかし、現代ではお歳暮ギフトを取り扱うお店で早期割引が実施されることも多く、11月に準備が終わって11月中に発送する人も多くなっています。
この12月13日から20日までという期間は個人的にそこまで意識する必要は無いと思っていますが、年をまたぐのは絶対にNGなのでどんなに遅くても12月31日までは届くように送りましょう。
ただし、年末は旅行でいないというケースもありますので、やはり12月20日ごろには届くようにお歳暮を贈った方が良いと思います。
正月事始めと大掃除の関係について

正月事始めにおける煤払いは大掃除の原型とも言われており、今でも年末に大掃除をするという文化ははっきりと残っています。
もともと煤払いは「歳神様を綺麗な環境でお迎えする」ためのものであり、この大掃除が終われば正月飾りを実行するのです。
12月13日は大掃除の日に認定されていることから、正月事始めにおける煤払いの文化ははっきりと残っていることがわかります。
掃除の順番としては、まず神棚をきれいにした後、台所や各部屋を掃除します。
特に台所はかまど神(荒神様)がいて生命につながる料理を作る場所なので、念入りに掃除する場所とされてきました。
昔は「正月事始め」に家族みんなで掃除をして、それが終わると「すす払い団子」をお供えしたり、「すす払い餅」などを食べたりする習慣もあったそうです。
また、掃除の後には「すす湯」と呼ばれるお風呂に入って、家も自分の心身もきれいにしてから年神様を迎える準備に入りました。
「すす払い」は「正月迎え」や「ことはじめ」、「ええことはじめ」などの縁起のいい別名で呼ばれることもあります。
現代では12月13日の行事意識も薄れていますが、正月飾りを買いに行ったり、台所など水回りなどできるところから大掃除を始めたりするのも良いですね。
来たる新年に思いを馳せて「正月事始め」に取り掛かってみましょう。
正月事始めのまとめ
以上、いかがだったでしょうか。
今回は正月事始めとは一体何なのかを記載しました。
「正月始め」ではなく「事」が入るのがポイントで、この「事」が入ることで「正月のための準備をすること」という認識をしやすいと個人的には思っております。
今でも年末に大掃除をするのは当たり前なので、この正月事始めの一部は何年後でも引き継がれていくでしょう。



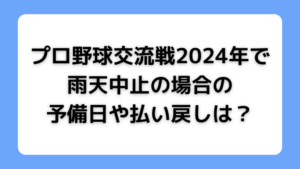






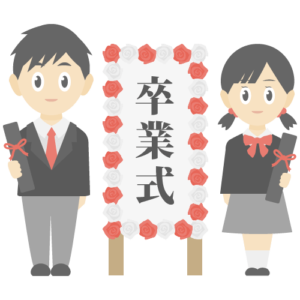
コメント