イースターは何をする日?意味や由来は?
本来のキリスト教の祝祭の意味とは違うものの、毎年12月25日は日本でも数多くのイベントが行われ、恋人達や家族が大切な人と大切な時間を過ごす習慣が根付いています。
色とりどりのクリスマスツリーを飾り、チキンを食べたりプレゼント交換をしてクリスマスを過ごすのは、もはや当たり前のようになっていますが、一方で同じキリスト教の祝祭であるイースターについては「全く知らない」という方が殆どではないでしょうか。
3月の下旬が近くなると、装飾を施した卵のような置物や小物が雑貨屋の店頭に並びますが、「これは何なのだろう・・」と不思議に思ってはいませんか。
実はそれこそが、イースターに深く関係する物なのです。
それでは、イースターとは一体どんな日なのか。卵のような綺麗な置物は何に使われるのか。
もう少し詳しく調べてみることにしましょう。
イースターとは?

イースターとは、十字架に掛けられて亡くなったイエス・キリストが3日後に復活したことに由来する復活祭です。
キリストの関係するイベントと言えば、日本ではクリスマスが有名ですが、キリスト教ではイエス・キリストが生まれた日であるクリスマスよりも重要視されています。
キリスト教が誕生してからクリスマスを祝うまでに長い歳月を要していますが、イースターについては当初から不可欠なものとして存在していたと言われています。
また、復活祭をイースターと呼ぶようになったのは随分後の話のようで、その元となったのもゲルマン神話の春の女神「Eostre」から由来していると言われていますが、実際にははっきりとわかってはいません。
2025年のイースターはいつ?毎年変わるの?
イースターの日付は毎年変わり、決められた日というのはありません。
イースターは、「春分の日が過ぎて最初の満月が出た後の次の日曜日」によって決められ、
2025年は3月31日となっています。
しかし、各国には緯度の違いによる時差があるので、この式に当てはめて計算をすると各国ごとにイースターの日にちが変わってしまいます。
そこで、春分の日を3月21日と定め、さらに満月の日はメトン周期に基づき算出されます。これにより各国の誤差をなくし、一斉にイースターを行うことができるのです。
また、この計算方法は西方教会での決め方であり、正教では異なります。
西方教会の場合
カトリックやプロテスタント、聖公会など、西方教会では「グレゴリオ暦」によってイースターの日にちを決めています。
グレゴリオ暦とは、16世紀のローマ教皇・グレゴリウス13世が導入した太陽暦(地球が太陽を回る周期を基にした暦)です。
現在日本を始め、世界各国で採用されています。
西方教会式だと、一般的に使っている西暦によってイースターの日にちが決まります。
年によって日にちに差はあるものの、イースターは通常3月22日~4月25日の間です。
グレゴリオ暦における向こう4年間のイースターの日にちは、以下の通りです。
2025年:3月31日
2025年:4月20日
2026年:4月5日
2027年:3月28日
東方教会の場合
ロシア正教やギリシア正教といった東方教会(東方正教会)では、ユリウス暦によってイースターの日にちが決まります。
ユリウス暦とは、ローマ皇帝ユリウス・カエサル(ジュリアス・シーザー)が制定した太陽暦で、グレゴリオ暦が採用されるまで広く使用されていたものです。
グレゴリオ暦では毎年日にちが異なる春分ですが、ユリウス暦では3月21日に固定されています。
また、満月の日の計算方法なども一般的に使われているものと異なるため、2つの教派でイースターが大きくズレたり、同じ日になったりするのです。
024年は5月5日になります。
クリスマスよりも大事なイースター!
日本では、まだあまり広まっていないイースターですが、キリスト教圏の国ではキリストの誕生日を祝うクリスマスよりも大事なイベント。
そもそもイースターとは、十字架にかけられて亡くなったキリストが、その3日目に復活したことを祝う「復活祭」なんです。
宗教的にもとても意味のある日で、イースターを祝って、学校が数週間休みになる国もあるそうですよ。
ちなみにイースターという名前の由来は、ゲルマン神話の春の女神「Estore」からきているという説があります。
イースターエッグとイースターウサギについて

イースターが近くなると、雑貨屋などには綺麗な模様が描かれた卵のような形の置物が並んでいます。
この卵のような置物は、実は卵で(現在はチョコレートやプラスチックで作られた卵型のもの)イースターエッグと言います。
また、イースターエッグを運ぶうさぎはイースターバニーと言い、こちらもイースターには欠かせない存在となっているのですが、ではなぜそもそも卵やうさぎが使われるようになったのでしょうか。
まず卵は、生命の誕生を表していると言われています。それと同時に、殻の中にいる時間を経て殻を割って生まれてくる様子がキリストの復活を象徴としているとされています。
そして、うさぎは多産であることから豊穣のシンボルとされていました。これらのことによって、イースターに卵やうさぎが使われるようになったようです。
イースターの楽しみ方
イースターは、春の訪れと共にやってくる、カラフルで楽しいイベントですね。
この時期には、家族や友人と一緒にさまざまなアクティビティを楽しむことができます。
今回は、イースターを盛り上げるためのいくつかのアイデアをご紹介します。
エッグペイント
イースターエッグの作成は、イースターの伝統的な楽しみの一つです。
家族みんなで集まって、生卵の殻をデコレーションしましょう。
まずは、生卵の底に小さな穴を開けて中身を抜き、水洗いして乾燥させます。
もっと手軽に楽しみたい場合は、ゆで卵の殻にペイントするのも良いでしょう。
乾燥した卵の殻には、絵の具やペン、クレヨンを使って、自由に色や柄を描きます。
マスキングテープやシールを使って装飾するのも楽しいですね。
完成したイースターエッグは、籠や鳥の巣のようなディスプレイで飾ると、一層華やかになります。
色にはそれぞれ意味があります。
たとえば、ピンクは愛や喜びを、赤はキリストの血を、紫は謙虚さや高貴さを、緑はキリストの復活や永遠の命を象徴しています。
エッグハント
イースターの朝には、イースターバニーが隠したとされる卵を探す「エッグハント」が楽しまれます。
子どもたちにとっては、この日だけは家の中や庭を自由に駆け回って探索できる特別な時間です。
伝統的にはゆで卵を使いますが、最近ではプラスチック製の卵や、卵やウサギの形をしたチョコレートを使うこともあります。
エッグレース
エッグレースは、スプーンに卵を乗せて走る競争です。
運動会で見たことがあるかもしれませんね。
スプーンが心配なら、おたまや鍋のふたを使うのも一案です。
個人戦、団体戦、リレーなど、さまざまな形式で楽しむことができます。
ゆで卵を使えば、割れる心配も少なく安心です。
エッグロール
イースターエッグロールは、長い柄のスプーンでゆで卵またはイースターエッグを転がす競争です。
このゲームは、キリストの復活を象徴する岩が転がされたという伝承に由来しています。
アメリカのホワイトハウスでは、毎年大統領も参加する大規模なイースターエッグロールイベントが開催されるほど、世界中で愛されている伝統的な遊びです。
イースターは、春の訪れを祝う素晴らしい機会です。
これらのアクティビティを通じて、家族や友人との絆を深め、楽しい思い出を作りましょう。
イースターのまとめ
いかがでしたか。
イースターはキリスト教にとってクリスマスより重要な行事だということがわかりました。
クリスマスのように一大イベントのようになる必要はなくとも、その意味を知っておくことはとても大切なことような気がしますよね。

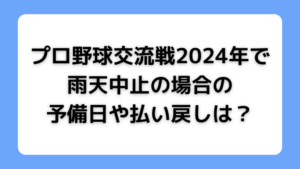






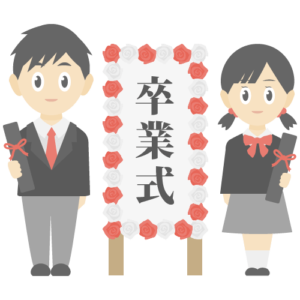
コメント