2025年の初午はいつ?初午祭が開催される神社は?
初午とは、2月最初の午の日のことです。
午は牛(うし)とよく似た字ですが、これは午(うま)と呼びます。
初午はお稲荷さんへお参りに行く日と言われていますが、それはどうしてなのでしょうか。
そこで今回は、初午について調べてみました。
初午の意味や由来、読み方などを詳しく解説していきます!
初午とは?
別なお祭りが行われる日として知られています。
稲荷神社は、豊作や商売繁盛、開運、家内安全などを願う場所として広く親しまれており、初午の日には多くの人々が神社を訪れて祈りを捧げます。
特に有名なのは、京都にある伏見稲荷大社です。
ここでは、初午の日に合わせて大規模な祭典が開催され、参拝者で賑わいます。
また、大阪の玉造稲荷や愛知県の豊川稲荷など、他の地域にもそれぞれ独自の風習や催し物があり、地元の人々にとって大切な日となっています。
お祭りの際には、赤いのぼりが神社周辺に立てられ、祭りの雰囲気を盛り上げます。
また、赤飯や油揚げ、団子などの食べ物が売られ、これらは稲荷神社にちなんだものとして特に人気です。
赤飯は豊作を、油揚げは稲荷神の使いである狐にちなんだものとされています。
初午の日は、単にお祭りを楽しむ日というだけでなく、新しい年の成功を願う日でもあります。
商売を営む人々にとっては、この日に神社を訪れて商売繁盛を祈ることが一年の繁栄につながると信じられています。
また、家族の健康や安全を願う人々にとっても、大切な日となっています。
初午の由来
では、なぜ2月の初午の日に稲荷神社がお祭りを行っているのでしょうか?
稲荷神社とは、京都市伏見区の伏見稲荷大社を総本社とし、全国に約4万社ある神社のこと。
その昔、和銅4年(711年)の2月の最初の午の日に、穀物の神様が稲荷山(伊奈利山)に降りました。
この故事から、稲荷神を祭る祭事が行われるようになったとされます。
旧暦2月の初午の日は今の3月にあたり、ちょうど田んぼや畑の準備を始める時期だったため、豊作を願って稲荷神社に参拝する習慣ができました。
ちなみに、稲荷の名は稲作の「稲生り」から来たとも言われています。
初午の読み方
読んで字の如く、初午は馬を指す言葉となっており、私達が認識している牛(うし)ではありません。
十二支には牛(うし)もいますがその場合は丑と書きます。
このような日付の数え方で有名なものに「土用の丑の日」があります。
土用の丑の日は土用と呼ばれる期間内に訪れる丑の日のことを指し、その時にうなぎを食べるとよいとされていますよね。
丑(うし)も午(うま)も、昔は農作業の担い手として欠かせない存在だったことから、作物の豊作の象徴としてとても大切に扱われていたと言われています。
2025年の初午はいつ?
初午の日はその年によって変わり、必ず毎年同じ日であるとは限りません。
2025年の初午は、2月12日(月)になっています。
上記で触れた通り、昔の日付は十干と十二支の組み合わせによって決められていましたが、十二支が一周するには12日あればよいので、多い月では3回ほど同じ十二支の日が巡ってきます。
そのため、午の日であれば2月の最初に訪れるのを初午、2回目に訪れるのを「二の午」、3回目に訪れるのを「三の午」と呼んでいます。
初午はお稲荷さんへお参りしよう!

初午は稲荷神社へ行ってお参りを行うのが、昔からの風習となっています。
地元に稲荷神社がある場合は、初午に合わせて「稲荷神(いなりしん)」のお祭りが行われており、行ったことがあるという方も多いでしょう。
では、初午と稲荷神社にはどのような関係があるのでしょうか。
稲荷神社の総本社となる京都の伏見稲荷大社の創建は、711年(和銅4年)の2月の初牛の日と言われており、これはこの日に稲荷山(伊奈利山)に祭神が舞い降りたという故事が元になっています。
伏見稲荷大社を創建した秦伊呂具(はたのいろぐ)が、的に見立てた餅に矢を放ったところ、それが白鳥となり伊奈利山へ飛んでいき、そこに稲が生えたことから、「稲が生(な)る」から「稲生(いなり)」→「稲荷」となって伏見稲荷大社が創建されたと言われています。
創建当初は秦伊呂具の氏神が祀られていましたが、稲が豊穣をもたらすものであることから、後に五穀豊穣の神である宇迦の御霊(うかのみたま)が祀られるようになり、以後、2月の初午の日には「初午祭(はつうまさい)」が開かれるようになったと言われています。
なお、現在では初午の日に稲荷神社にお参りすることを「福参り」と呼び、五穀豊穣以外に商売繁盛や家内安全、開運などのご利益が受けられると言われています。
初午祭が開催される代表的な神社は?

初午祭は全国各地の稲荷神社で行われますが、代表的な神社と言ったらやはり、初午祭の発祥となった伏見稲荷大社が挙げられるでしょう。
伏見稲荷神社の初午祭は清少納言や平清盛も参拝した由緒あるお祭りをして知られており、初詣に訪れた参拝客には商売繁盛や家内安全のお守りとして「しるしの杉」が授与されます。
また、それ以外では日本三大稲荷神社の一つである、茨城県の笠間稲荷神社や佐賀県の祐徳稲荷神社の初午祭も有名です。
笠間稲荷神社も祐徳稲荷神社も、初午祭は旧暦と新暦の両方で開催しています。
旧暦と新暦では1ヵ月ほど日数に違いがあるため、2月の初午の日、並びに3月の初午の日にも初午祭が行われるというわけです。
旧暦と新暦の両方で初午祭を行っている稲荷神社は、他にも数多くあるため、お近くの神社に足を運ぶ際には確認してみるとよいでしょう。
なお、日本各地の稲荷神社で行われる初午祭とは、異なる形の初午祭が行われているのが鹿児島神宮です。
こちらは旧暦の正月18日の次の日曜日に開かれるもので、鈴が連なった胸飾りや鞍を付けた馬を足踏みさせ、音楽に合わせて踊っているように見せる「鈴かけ馬踊り」が有名です。
元々は五穀豊穣を願うものでしたが、現在は商売繁盛や厄払いなどの意味を含めて披露されていると言われています。
初午の食べ物いなり寿司を食べる理由は?

初午の日はいなり寿司を食べるという方は多いのではないでしょうか。
これは、稲荷神社の使いであるきつねが、油揚げが大好物とされていたことが由来しています。
(実際のきつねは油揚げが好物というわけではありません)
そのため、稲荷神社では元々油揚げがお供えされていたのですが、初午祭に参拝に訪れた人が気軽に食べられるようにと、油揚げに酢飯を詰めたいなり寿司がふるまわれるようになったと言われています。
また、稲荷神社や初午祭にゆかりのある地域では、初午の日にはいなり寿司を作って食べる風習があるのですが、徐々にその風習が全国へと広まりつつあると言われています。
これに伴い、最近は初午の日にコンビニやスーパーでもいなり寿司が多く並ぶようになってきました。
なお、いなり寿司の形は東日本と西日本では異なり、俵型の東日本に対し、西日本はきつねの耳に見立てた三角が主流となっています。
地方によっては、いなり寿司以外にも初午の日に食べる郷土料理が存在します。
例えば栃木県では「しもつかれ」と呼ばれる鮭の頭や大根おろし、油揚げを煮た料理がふるまわれますし、養蚕が盛んだった地域では団子を繭に見立てた初午団子が食べられているそうです。
初午のまとめ
初午とは、2月に入って最初に訪れる午の日のことを言います。
午の日は旧暦で使われていた日付を表すもので、毎年日付が異なり、2025年は2月12日となっています。
初午の日には日本全国の稲荷神社で「初午祭」が行われ、商売繁盛や家内安全、五穀豊穣などを願って多くの参拝客が訪れますが、中でも初午祭の発祥と言われている京都の伏見稲荷大社や、日本三大稲荷神社の一つとされる茨城県の笠間稲荷神社や佐賀県の祐徳稲荷神社は、有名どころということもあり参拝客が多く訪れます。
初午の日には、稲荷神社のお使いであるきつねにあやかって、いなり寿司を食べる風習があります。
最近はコンビニやスーパーなどでも初午の日に合わせていなり寿司を販売しているようなので、近くで初午祭が行われないという方もチェックしてみるとよいでしょう。



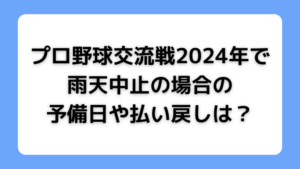






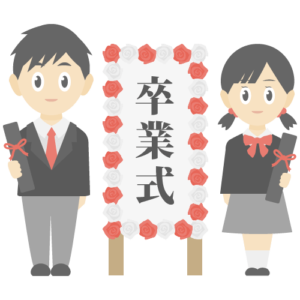
コメント