新暦と旧暦の違いって何?季節のずれはどれくらいあるのか?
季節の移ろいは、私たちの生活に色彩を与え、年中行事のリズムを刻む大切な要素です。
しかし、現代のカレンダーである新暦と、伝統的な旧暦とでは、季節の感じ方に大きなずれがあることをご存じでしょうか。
たとえば、新暦の1月は冬真っ只中ですが、旧暦では春の訪れを告げる時期。
このような違いは、なぜ生じるのでしょうか?そして、私たちの祖先はどのようにこれらの暦を用いて生活していたのでしょうか。
旧暦と新暦の違いを掘り下げ、季節感のずれが私たちの文化や生活にどのような影響を与えているかを、わかりやすく解説します。
日本の四季を巡る旅に出かけるように、この記事を通じて新たな発見をしていただければ幸いです。
旧暦と新暦の違いは何?
私たちの日常生活に欠かせないカレンダーには、実は古くから続く深い歴史があります。
今回は、その歴史の中でも特に重要な「旧暦」と「新暦」の違いについて、わかりやすく解説していきましょう。
旧暦と新暦の基本的な違い
旧暦は、太陽の動きと月の周期を基にした「太陽太陰暦」です。
これは月の満ち欠けを基本とし、一年を12ヶ月で構成しつつ、周期的に閏月を挿入して太陽年に合わせる方式です。
一方、新暦は「太陽暦」に基づき、太陽の動きだけを元に年間の日数を定めています。
現在、日本を含む多くの国で採用されているのは、この太陽暦に基づくグレゴリオ暦です。
旧暦:天保暦
- 採用時期: 1844年(天保15年)から1872年(明治5年)まで
- 特徴: 太陽太陰暦に基づく
- 閏月: 不定期に挿入
新暦:グレゴリオ暦
- 採用時期: 1873年(明治6年)から現在まで
- 特徴: 太陽暦に基づく
- 閏年: 4年に1回、2月に1日を追加
旧暦の名残と現代の習慣
旧暦の名残は、現代の日本においても様々な形で残っています。
特に伝統的な行事や節句にその影響を見ることができます。
節分と豆まき
- 節分: 旧暦における季節の変わり目、特に立春の前日
- 豆まき: 邪気を祓うための儀式。立春の前日に行われることが多い
| 旧暦の節目 | 現代の行事 |
|---|---|
| 立春 | 春分の日 |
| 立夏 | 夏至 |
| 立秋 | 秋分の日 |
| 立冬 | 冬至 |
立春は旧暦では新年の始まりとされていました。そのため、立春の前日に行われる節分は、新しい年を迎える準備として、家の中の悪い気を払い、福を呼び込むための重要な行事だったのです。
現代における旧暦の影響
現代のカレンダーはグレゴリオ暦に基づいていますが、旧暦に由来する行事や習慣は今もなお、私たちの文化の中に息づいています。
例えば、お盆やお正月など、家族が集まる大切な時期は、旧暦に基づいていることが多いのです。
このように、旧暦と新暦はそれぞれ異なる天体の動きを基にしており、その違いは単に日付のズレにとどまらず、私たちの文化や習慣にも大きな影響を与えています。
時代が変わっても、これらの伝統を大切に受け継いでいくことは、私たちのアイデンティティを形作る上で非常に重要なのです。

旧暦と新暦の季節感のずれは?
日本の伝統的な暦法である旧暦と、現代で主に使用されている新暦(グレゴリオ暦)との間には、季節感における顕著なずれが存在します。
このずれは、それぞれの暦が基づく天体の運行の違いに由来しています。
旧暦の基礎知識
旧暦は太陽太陰暦に分類され、月の満ち欠けを基本として一年を構成しています。
これは、月が地球を一周する周期、約29.5日を一ヶ月とし、12回の周期で一年を数える方法です。
しかし、これだけでは太陽の周回周期、すなわち季節と合わないため、約3年に1回の割合で閏月を設けて調整しています。
新暦の基礎知識
一方、新暦は太陽暦に属し、地球が太陽を一周する周期を基にしています。
これは約365.24日で、この周期を12ヶ月に分けて一年としています。
新暦では、季節の変化が一定のリズムで訪れるように設計されており、閏年による日数の調整が行われます。
季節感のずれ
旧暦と新暦では、季節を示す月の指定が異なります。
例えば、旧暦では春は1月から3月までとされていますが、新暦では3月から5月までとされています。
この違いは、旧暦の1月が新暦で言うところの2月頃に相当するためです。
以下の表は、旧暦と新暦の季節の対応を示しています。
| 季節 | 旧暦の月 | 新暦の月 |
|---|---|---|
| 春 | 1月~3月 | 3月~5月 |
| 夏 | 4月~6月 | 6月~8月 |
| 秋 | 7月~9月 | 9月~11月 |
| 冬 | 10月~12月 | 12月~2月 |
この表からもわかるように、旧暦と新暦では1~2ヶ月の季節感のずれが生じています。
旧暦の春が始まる頃、新暦ではまだ冬の寒さが残っていることが多いのです。
季節感のずれの影響
この季節感のずれは、特に伝統的な行事や祭りに影響を与えます。
例えば、旧暦で行われる節分やお花見は、新暦では気候が異なるため、本来の季節感とは異なる時期に行われることになります。
また、農業においても、旧暦に基づいた作物の植付け時期が新暦の気候と合わない場合があります。
現代における旧暦の役割
現代日本では新暦が広く用いられていますが、旧暦に基づく行事や風習は今もなお色濃く残っており、日本の文化的アイデンティティの一部として重要な役割を担っています。
旧暦を理解することは、日本の四季に対する深い敬意と、年中行事の背後にある意味を理解する上で不可欠です。
このように、旧暦と新暦の季節感のずれは、単なる日付の違い以上の文化的な意味合いを持ち、日本の伝統と現代生活の橋渡しをする重要な要素となっています。
旧暦とは
旧暦とは、現代日本で主に使用されているグレゴリオ暦、すなわち新暦に取って代わられるまで用いられていた歴史的な暦のことを指します。
この暦は、天体の動きを基にした太陰暦、太陽暦、そしてその両者を組み合わせた太陰太陽暦の三つの形式に大別されます。
太陰暦、太陽暦、太陰太陽暦の違い
| 暦の種類 | 基準となる天体 | 特徴 |
|---|---|---|
| 太陰暦 | 月 | 月の満ち欠け(新月から次の新月までの周期)を基に月日を決定 |
| 太陽暦 | 太陽 | 地球が太陽の周りを一周する周期(1年)を基に月日を決定 |
| 太陰太陽暦 | 月+太陽 | 月の周期を基本としつつ、太陽の周期を考慮して季節のずれを修正 |
日本における旧暦の導入とその進化
日本では飛鳥時代に、中国から伝来した太陰太陽暦が採用されました。
この暦は、元嘉暦として知られ、日本の歴史の中で初めて正式な暦として用いられたものです。
その後、宣明暦や貞享暦など、時代と共に様々な改良が加えられた暦が使用されてきました。
特筆すべきは、貞享暦以降、日本独自の改良が加えられ、日本の自然環境や文化に即した暦へと進化していった点です。
旧暦の一般的な理解と天保暦
一般に「旧暦」と言えば、明治時代に西洋から導入されたグレゴリオ暦に置き換えられるまでの天保暦を指します。
天保暦は、日本独自の最後の太陰太陽暦であり、明治5年(1872年)の新暦採用まで広く用いられていました。
旧暦から新暦への移行
明治政府は、西洋の科学技術の進歩と国際社会への適応を目指し、1872年に太陽暦であるグレゴリオ暦を公式に採用しました。
これにより、日本は旧暦を離れ、世界で最も広く用いられている暦へと移行したのです。
このように、旧暦は単なる時間の計算方法以上のものであり、日本の歴史や文化、さらには国際関係においても重要な役割を果たしてきました。
今日では、旧暦に基づく伝統的な節句や行事が、新暦の枠組みの中で受け継がれています。
旧暦の春・夏・秋・冬の季節区分
日本の伝統的な暦法における季節の捉え方は、現代のグレゴリオ暦とは異なる独特の体系を持っています。
この体系は、自然の周期と農耕活動に深く根ざしたもので、古くから日本人の生活に密接に関わってきました。
旧暦における季節の区分
旧暦では、季節は月の満ち欠けを基にした太陰太陽暦に従って区分されます。
この暦は、太陽の動きと月の周期を組み合わせたもので、自然界のリズムに調和した生活を送るために用いられてきました。
春(1月~3月)
現代の感覚では1月は冬の真っ只中と捉えられがちですが、旧暦ではこの時期を春の始まりと位置づけています。
この時期は、新しい生命が息吹を感じ始める季節とされ、農作業の準備が始まります。
夏(4月~6月)
4月から6月にかけては、旧暦では夏にあたります。
この時期は、農作物が成長する重要な時期であり、暑さが増すにつれて農作業も本格化します。
秋(7月~9月)
7月から9月は、収穫の季節である秋とされています。
この時期は、稲穂が実り、農民にとっては一年で最も忙しい時期の一つです。
冬(10月~12月)
10月から12月は、旧暦では冬にあたります。
この時期は、収穫後の休息と次の春に向けた準備の季節です。
二十四節気とは
旧暦の季節感にさらに深みを加えるのが「二十四節気」です。
これは、太陽の黄道上の位置を基に季節を24に分けたもので、それぞれの節気は特定の自然現象や農作業に関連しています。
| 節気 | 意味 | 旧暦の月 |
|---|---|---|
| 立春 | 春の始まり | 1月 |
| 立夏 | 夏の始まり | 4月 |
| 立秋 | 秋の始まり | 7月 |
| 立冬 | 冬の始まり | 10月 |
これらの節気は、春分や秋分、夏至や冬至といった天文学的なポイントを基にしており、それぞれの中間点に位置する節気を含めて、季節の変遷を細かく捉えることができます。
新暦を使用する現代でも、旧暦に基づく節気は、季節の変化を感じ取るための指標として、また伝統行事や農業の指針として、多くの人々に親しまれています。
例えば、立春が来ると春の訪れを感じ、夏至が過ぎれば暑さのピークを意識し始めるなど、節気は日本人の季節感を形作る重要な要素となっています。
このように、旧暦の季節区分と二十四節気は、日本の自然と文化のリズムを理解する上で欠かせない知識と言えるでしょう。
現代に生きる私たちも、これらの古い知恵を大切にしながら、四季の変化をより豊かに感じることができるのです。
新暦とは?いつから?
日本における新暦、すなわちグレゴリオ暦の採用は、西洋の文化や科学技術が積極的に取り入れられ始めた明治時代に行われました。
具体的には明治6年(1873年)に施行されたこの改暦は、日本が国際社会に足並みを揃えるための重要な一歩でした。
それまで使用されていた天保暦は、太陽と月の運行を基にした太陽太陰暦であり、季節や農作業には適していましたが、日々のずれが生じるため、国際的な時刻の統一が困難でした。
新暦、つまりグレゴリオ暦への移行は、太陽の周期に基づいたより精密な時間計算を可能にし、西洋諸国との貿易や交流をスムーズに行うための基盤を築きました。
しかし、この太陽暦が今日に至るまでには、古代ローマやエジプトから始まる長い進化の歴史があります。
以下の表は、太陽暦の発展の歴史を概観するものです。
| 暦の種類 | 発祥地 | 一年の日数 | 月の日数 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ローマ暦 | ローマ | 304日 | 不定 | 初期の太陽暦で、季節のずれが大きい |
| エジプト暦 | エジプト | 365.25日 | 30日(12ヶ月)+5日 | 年末に追加日を設け、より精密な計算を実現 |
| ユリウス暦 | ローマ(ユリウス・カエサル) | 365.25日 | 不定 | 4年に1度の閏年を導入し、季節のずれを修正 |
| グレゴリオ暦 | ヨーロッパ(教皇グレゴリウス13世) | 365.2425日 | 不定 | ユリウス暦の誤差を修正し、現在も使用される |
グレゴリオ暦の導入により、太陽年とのわずかなずれを修正し、現在では世界の多くの国々で標準的な暦として採用されています。
この暦は、4年に1度の閏年を設けることで、1年の平均日数を365.2425日とし、季節とのずれを最小限に抑えています。
日本では、このグレゴリオ暦を「新暦」と呼び、明治時代の改革の一環として採用されたことで、国際的な時刻の統一だけでなく、文化や経済の面でも大きな変革を遂げました。
新暦の導入は、日本が近代国家として世界に歩み出すための象徴的な出来事の一つと言えるでしょう。
新暦の春・夏・秋・冬の季節区分
日本は、世界でも稀有な四季の変化を楽しめる国の一つです。
新暦による季節の区分は、気象庁が天気予報を行う際の基準として広く用いられており、それぞれの季節が持つ特徴的な気候を反映しています。
ここでは、新暦に則った季節の区切りと、それぞれの季節が日本人の生活にもたらす色彩と感触について詳細に探ります。
春(3月~5月)
春は、新生活が始まる象徴的な季節です。
3月には桜の開花が南から北へと順を追っていき、日本全土が花見の喜びに包まれます。
北海道のような寒冷地では、春の訪れが少し遅く、5月になってようやく桜が満開になります。
この時期は、新緑が目に鮮やかで、温かな日差しが人々の心を和ませます。
夏(6月~8月)
夏は、活動的な季節として知られています。6月に入ると、気温が25度を超える日が増え、日本各地で夏祭りや花火大会が開催され、夜空を彩ります。
夏はまた、海や山へのレジャーが盛んになり、自然との触れ合いが楽しめる時期でもあります。
秋(9月~11月)
秋は、豊かな収穫の季節です。
9月になると徐々に暑さが和らぎ、10月から11月にかけては、日本全国で紅葉が美しい景色を作り出します。
この時期は、食欲の秋とも言われ、新米や果物などの旬の味覚を楽しむことができます。
冬(12月~2月)
冬は、静寂と落ち着きの季節です。
12月からは冬の訪れを告げるイベントが多く、1月から2月にかけては、寒さが厳しくなります。
特に雪国では、雪景色が広がり、冬ならではのスポーツやイベントが楽しめます。
しかし、地球温暖化の影響により、季節の感覚に変化が見られ始めています。
例えば、5月に30度を超える日が出現したり、1月に雪が全く降らないという現象が起こることもあります。
これらの変化は、未来における季節感のずれを予感させ、私たちの生活に新たな適応を迫るかもしれません。
以下の表は、新暦に基づく季節の区分と、それぞれの季節の代表的な特徴をまとめたものです。
| 季節 | 月 | 特徴 |
|---|---|---|
| 春 | 3~5月 | 桜の開花、新緑、新生活のスタート |
| 夏 | 6~8月 | 高温多湿、夏祭り、海や山へのレジャー |
| 秋 | 9~11月 | 紅葉、収穫の喜び、食欲の秋 |
| 冬 | 12~2月 | 雪景色、冬のイベント、寒さの厳しさ |
このように、新暦による季節の区分は、日本の自然や文化と深く結びついており、それぞれの季節が独自の魅力を持っています。
しかし、気候変動による影響は無視できず、これからの季節の楽しみ方も変わっていくかもしれません。
それでも、四季折々の変化を大切にし、それぞれの季節を最大限に楽しむことが、日本の豊かな自然と共生するための鍵となるでしょう。
閏(うるう)年と閏(うるう)月
太陽の周期と月の周期を基にした暦の仕組みは、古来より人々の生活に密接に関わってきました。
特に、農耕文化を持つ国々では、季節の変化を正確に把握することが重要であり、そのためには精密な暦が必要不可欠でした。
こうした背景から、閏年や閏月という概念が生まれ、今日に至るまで使用されています。
閏年:時間の微調整
地球が太陽の周りを一周するのに要する時間は、実は365日ぴったりではありません。
正確には365.2425日、つまり365日と約1/4日余分にかかります。
この約1/4日が毎年積み重なると、数年で大きなずれが生じてしまいます。
そこで、このずれを調整するために閏年が設けられました。
閏年では、2月に通常は存在しない「29日」が加えられ、4年に1度、累積した余分な日数をリセットします。
閏月:月のリズムを整える
一方で、太陽太陰暦は太陽の周期と月の周期を組み合わせた暦です。
月の周期は約29.5日であり、これを12回繰り返すと354日となり、太陽年の365日とは11日ほどの差が生じます。
この差を補正するために、一定の周期で閏月が挿入され、1年が13ヶ月となることがあります。
この閏月の挿入はランダムに行われるわけではなく、特定の規則に基づいて決定されます。
閏月の決定には「中気」が関わっており、これは冬至から次の冬至までの期間を12等分したもので、そのうち偶数番目にあたる月が閏月となります。
そして、閏月はその前の月の名前を冠することが一般的です。
例えば、5月(皐月)の後に中気がない月が来た場合、その月は「閏皐月」と呼ばれます。
以下の表は、閏年と閏月の概念を整理したものです。
| 項目 | 閏年 | 閏月 |
|---|---|---|
| 目的 | 太陽年の日数のずれを補正 | 太陽太陰暦の日数のずれを補正 |
| 発生頻度 | 4年に1回 | 約3年に7回(19年周期で7回) |
| 追加されるもの | 2月29日 | 1ヶ月 |
| 決定方法 | 4で割り切れる年に追加 | 中気がない月に追加 |
| 特徴 | 固定的な日付に追加 | 変動的な月に追加 |
このように、閏年と閏月は、私たちの暦を正確に保つための重要な役割を果たしています。
現代ではグレゴリオ暦が広く使われており、閏年の概念は引き続き重要ですが、閏月は主に伝統的な太陽太陰暦を使用する文化で見られる特徴です。
これらの知識は、歴史や文化を理解する上で非常に興味深いものです。
暦の分類
太陽暦
太陽暦は、天文学的な観測に基づいて成立した時間の計測方法です。
この暦法は、太陽が地球を一周するのにかかる時間、すなわち地球が太陽の周りを一周する公転周期を基準にしています。
この周期を一年と定義し、日々の生活や農業、宗教行事などの時間を区切るための基盤として利用されてきました。
太陽暦の概要
太陽暦は、季節の変化と密接に関連しており、特に農耕社会においては作物の種まきや収穫の時期を決定するために不可欠なものでした。
太陽の動きは比較的一定しているため、太陽暦は古代から多くの文明で採用されてきました。
グレゴリオ暦とは
現在、国際的に最も広く使用されている太陽暦はグレゴリオ暦です。
この暦法は、1582年にローマ教皇グレゴリウス13世によって導入されました。
グレゴリオ暦では、一年を365日とし、さらに正確な計算のために365.2425日としています。
この小数点以下の日数は、毎年ではなく、一定の周期で調整される必要があります。
閏年の仕組み
グレゴリオ暦における閏年のシステムは、この小数点以下の日数を調整するために設けられています。
具体的には、4年に一度、2月に1日を追加することで、この累積された時間を解消しています。
この結果、閏年は366日となります。
2月が閏月となる理由
なぜ閏日を2月に追加するのかというと、これには歴史的な背景があります。
元々ローマ暦では年の始まりが3月であり、2月は年の最後の月でした。
そのため、年末の2月に日数を調整するという慣習が、グレゴリオ暦にも引き継がれているのです。
グレゴリオ暦の閏年のルール
| 条件 | 説明 |
|---|---|
| 4で割り切れる年 | 閏年とする |
| 100で割り切れる年 | 通常は閏年ではない |
| 400で割り切れる年 | 100で割り切れても閏年とする |
このように、グレゴリオ暦は太陽の周期を非常に精密に反映した暦法であり、現代社会においてもその精度は高く評価されています。
国際的な商取引や科学技術の発展においても、この暦法による時間の計測は欠かせないものとなっています。
太陰暦
古くから多くの文化で用いられてきた「太陰暦」に焦点を当て、その魅力と仕組みを掘り下げてみましょう。
太陰暦とは何か?
太陰暦は、月の周期、すなわち月の満ち欠けを基にした暦です。
月が地球の周りを一周するのにかかる時間、約29.5日を1ヶ月と定めています。
この周期を「朔望月」と呼びます。太陰暦では、新月の日を月の始まり、つまり「1日」と位置づけています。
太陰暦の数学的な課題
しかし、太陰暦には一つの大きな課題があります。
それは、太陽を基準にした太陽暦の1年が約365日であるのに対し、太陰暦の1年は12ヶ月分の朔望月を合計した354日となり、太陽暦と比較して11日も短いという点です。
この差は、年月が経過するにつれて季節と暦のずれを生じさせる原因となります。
太陰暦を採用する文化
この太陰暦は、特にイスラム教社会において重要な役割を果たしています。
イスラム教では、日々の祈りの時間、断食月であるラマダン、巡礼といった宗教的行事が太陰暦に基づいて決定されます。
この暦は「ヒジョラ暦」とも呼ばれ、イスラム教の創始者ムハンマドがメッカからメディナへ移住した出来事を起点としています。
ヒジョラ暦の特徴
ヒジョラ暦は、太陽暦とは異なり、季節の変化とは連動していません。
そのため、ラマダン月や他の祭典が毎年異なる季節に訪れることになります。
これは、イスラム教徒にとって、異なる気候条件下での断食を経験するという宗教的な意義を持つとされています。
太陰暦と太陽暦の比較
以下の表は、太陰暦と太陽暦の違いを簡潔に示しています。
| 暦の種類 | 基準となる天体 | 1年の日数 | 季節との連動性 | 主に使用している文化 |
|---|---|---|---|---|
| 太陰暦 | 月 | 約354日 | なし | イスラム教社会 |
| 太陽暦 | 太陽 | 約365日 | あり | 西暦(グレゴリオ暦) |
太陰暦は、月の美しいリズムに従って時間を刻む独特の暦です。
それは単なる時間の計測方法以上のものを提供し、特定の文化や宗教においては、その年中行事や儀式の根幹をなすものとなっています。
太陽暦が支配的な現代社会においても、太陰暦はその独自性と伝統を守り続けています。
太陽太陰暦
季節の変わり目を告げる太陽、夜空を彩る月の満ち欠け。
これらは農耕や祭事、日々の生活に不可欠な指標でした。
そんな中で生まれたのが、「太陽太陰暦」という独特の時間の計り方です。
この暦は、単に月の周期を追う「太陰暦」に、太陽の周期を組み合わせたもの。
紀元前から用いられてきたこの暦法は、私たちの祖先が自然と調和しながら生きる知恵を結集させた結果です。
太陽太陰暦の仕組み
太陽太陰暦の基本は、月の満ち欠けを基にした太陰暦にあります。
しかし、太陰暦だけでは、1年(約354日)と太陽が同じ位置に戻る太陽年(約365日)との間に約11日のずれが生じます。
このままでは、数年で季節と暦が大きくずれてしまうため、太陽太陰暦では特別な工夫が凝らされています。
3年ごとに約1ヶ月分のずれが生じることから、この誤差を修正するために「閏月」という概念が導入されました。
閏月は、太陽の運行を観察し、特定の年に追加される13番目の月です。
この閏月を挿入することで、暦と季節のずれを調整し、農耕に適した時期や祭りなどの年中行事を適切に行うことが可能になります。
閏月の決定方法
閏月は、年によって挿入する月が変わります。
これは、太陽と月の相対的な位置関係に基づいて決定され、一定の規則に従って設定されます。
例えば、閏2月や閏9月など、その年の天文学的な計算によって決められます。
以下に、閏月が挿入される原則を表にまとめました。
| 年度 | 閏月の挿入月 | 観測基準 |
|---|---|---|
| 第1年 | 閏2月 | 春分点を基にした太陽の位置 |
| 第2年 | 閏7月 | 秋分点を基にした太陽の位置 |
| 第3年 | 閏9月 | 冬至点を基にした太陽の位置 |
このように、太陽太陰暦は、太陽と月の周期を巧みに組み合わせ、年中の行事や農耕に適した時期を知るための重要な役割を果たしてきました。
現代では主流の暦法ではありませんが、この暦法が持つ独自性と、自然のリズムに根ざした知恵は、今もなお私たちに多くのことを教えてくれます。
旧暦と新暦の違いのまとめ
旧暦と新暦、これら二つのカレンダーシステムは、私たちの生活に深く根ざした季節感に大きな影響を与えています。
旧暦は太陰太陽暦であり、月の満ち欠けを基にしており、新暦は太陽暦で、太陽の動きを基にしています。
この基本的な違いにより、旧暦では春が1月から始まりますが、新暦では3月からとなり、約1~2ヶ月の季節感のずれが生じています。
このずれは、節分やお花見などの伝統的な行事や祭りに影響を及ぼし、また農業の植付け時期にも影響を与えることがあります。
旧暦に基づく行事や風習は、現代でも大切に受け継がれており、日本の文化的アイデンティティの一部となっています。
旧暦を理解することは、日本の四季への敬意と、年中行事の背後にある意味を理解する上で不可欠です。
旧暦と新暦の違いを知ることは、私たちの過去と現在をつなぐ架け橋となり、四季の変化をより豊かに感じるための知恵となるのです。







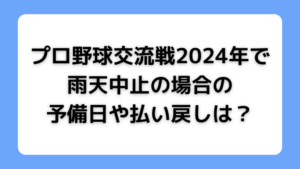






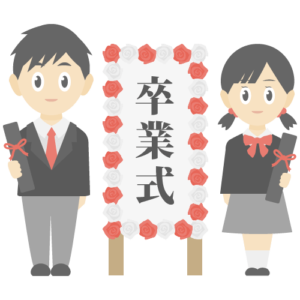
コメント