日本の行事食一覧!行事食は英語ではなんというの?
季節折々の行事やお祝いで食べることが多い行事食ですが、数えてみるとかなりの種類があるのです。
今回は行事食とはそもそも何なのかを記載しつつ、主な年中行事と行事食一覧を簡潔にまとめていきたいと思います。
行事食を英語で言うとどうなるのかもついでにチェックしていきましょう。
行事食1つ1つに大きな意味がありますので、そちらの意味とセットで確認して行くとより歴史や文化を感じられるようになっています。
行事食とは
行事食は、日本の四季折々の風情を映し出す、伝統的な食文化の一つです。
これらの料理は、年間を通じて特定の節目やお祝い事に合わせて用意され、それぞれの時期にちなんだ深い意味や願いが込められています。
例えば、新年を迎える際には、色とりどりのおせち料理が家族の団欒と共にテーブルを飾ります。
節分には、恵方を向いて太巻きを丸かぶりする恵方巻きが登場します。
由来
行事食の起源は古く、多くは自然の恵みに感謝し、また先祖への敬意を表すための儀式から派生しました。
例えば、おせち料理に含まれる数の子は「子孫繁栄」、黒豆は「健康」や「勤勉」を象徴しています。
これらの料理に込められた願いは、食べることで家族に幸運がもたらされるとされてきました。
現代への影響
現代においても、行事食は日本の家庭に欠かせない要素として受け継がれています。
それは単に伝統を守るためだけでなく、家族や友人との絆を深め、日々の生活に彩りと喜びをもたらすためでもあります。
季節の節目と行事食
以下の表は、日本の代表的な行事食とその季節の節目を示しています。
| 季節 | 行事 | 行事食 | 意味・願い |
|---|---|---|---|
| 新年 | お正月 | おせち料理 | 長寿、繁栄、健康など |
| 2月 | 節分 | 恵方巻き | 無病息災、商売繁盛 |
| 3月 | ひな祭り | ちらし寿司、桜餅 | 女児の健やかな成長 |
| 5月 | 端午の節句 | かしわ餅、柏餅 | 男児の健康と出世 |
| 7月・8月 | お盆 | 精進料理 | 先祖の霊を慰める |
| 秋 | 月見 | 団子 | 豊作への感謝 |
| 冬 | 歳末 | お雑煮 | 家族の絆と和 |
行事食は、単なる食事以上の価値を持ちます。
それは、自然や祖先への敬意、家族の絆、そして季節の変わり目を祝う日本独自の美意識を表現しているのです。
これらの料理を通じて、私たちは過去と現在、そして未来をつなぐ文化の継承者となります。
それぞれの行事食に込められた願いや意味を理解することで、私たちはより豊かな食生活と心の充足を得ることができるのです。
行事食とハレの日とケの日について
日本の伝統文化における「ハレ」と「ケ」の概念は、日常と非日常の境界を色濃く描き出すものです。
この二つの言葉は、単なる日付の違いを超え、日本人の生活様式、信仰心、そして社会的行事における根深い意味を持っています。
ハレの日:祝祭の煌めき
「ハレ」とは、文字通りには「晴れ」や「晴れやか」といった意味合いを持ち、日本の暦における特別な日々を指します。
これらは、新年の祝賀から節分、そして五節句といった年間を通じて設けられた祝祭日に至るまで、多岐にわたります。
これらの日々は、単に時間を過ごすのではなく、神々への敬意を表し、家族やコミュニティの絆を深めるためのものです。
祝祭日の食文化
祝祭日には、特別な食事が用意されます。
例えば、お正月にはおせち料理が食べられ、各料理には縁起の良い意味が込められています。
また、節分には恵方巻きを食べ、その年の幸運を願います。
着飾る文化
「ハレ」の日には、特別な衣服を身にまとう習慣もあります。
これは「晴れ着」と呼ばれ、祭事や式典にふさわしい装いで、身を清め、心を新たにする意味があります。
ケの日:日常の営み
一方で「ケ」の日は、日常生活を指す言葉であり、平穏無事な日々を象徴しています。
この言葉は、漢字で「褻」と書かれることもありますが、その難解さからカタカナ表記が一般的です。
日常では、祭事のような特別な食事や衣服は必要とされず、シンプルで機能的な生活が営まれます。
日常の食文化
日常の食事は、季節の変わり目や自然の恵みに感謝しながら、家族団らんの中で楽しまれます。
これには、旬の食材を使った家庭料理が含まれます。
自然との共生
日本人は、自然と共生する文化を長い歴史の中で育んできました。自然現象や季節の変化は、神様の仕業と捉えられ、それに対する敬意を表すための行事が数多く存在します。
行事食の意義
行事食は、単に食べ物としての役割を超え、その時々の節目や祝福を象徴するアイテムとなっています。
これらの食べ物には、豊穣、健康、長寿など、人々の願いが込められています。
以下の表は、「ハレ」と「ケ」の日に典型的な食事と衣服を対比しています。
| 要素 | ハレの日 | ケの日 |
|---|---|---|
| 食事 | おせち料理、恵方巻きなどの特別な料理 | 季節の家庭料理、日常的な食事 |
| 衣服 | 晴れ着(祭事や式典用の特別な衣装) | 普段着(機能的で日常生活に適した衣装) |
| 意義 | 神々への敬意、家族の絆の強化 | 家庭の平和、日常生活の営み |
このように、「ハレ」と「ケ」は日本の文化において重要な役割を果たしており、それぞれの日に応じた食事や衣服が、その日の意義を深め、人々の生活に彩りを加えています。
春夏秋冬の日本の行事食一覧!
それでは具体的に行事食について紹介していきます。
特に有名な行事食には解説もセットにしますので、一緒に確認して行きましょう。
1月の行事食
この中でも特に有名なのがお正月のおせち料理でしょう。
おせち料理は年の初めを祝うために豪華な食べ物がズラッと並びますが、あれらは基本的に縁起がいいものばかりで五穀豊穣や長寿や子孫繁栄などの願いが込められています。
人日の節句は五節句の一種ですが、七夕や端午の節句や桃の節句と比べると知名度は低いでしょう。
この日は七草粥を食べて無病息災を願います。
鏡開きはお正月に歳神様をお迎えするために用意した鏡餅を割ってお雑煮やお汁粉にして食べる日となっています。
2月の行事食
この中でも最も知れ渡っているのが、節分における福豆でしょう。
恵方巻きがコンビニエンスストアを中心に広まったことで恵方巻きも知られるようになっています。
節分では豆まきを行いますがあれは豆に邪気を祓う力があるという風習からきているのです。
ただし、生の豆を豆まきに使うとそこから芽が出てくるので基本的には煎って芽が出ないようにしてから使います(一説には豆まきで使う豆から芽が出ると縁起が悪いとされている)。
節分で用意した煎った豆は「福豆」と呼ばれており食べると健康になると考えられていたのです。
3月の行事食
桃の節句は上巳の節句という名前もありますが、日本では桃の節句という名前の方が圧倒的に知られているでしょう。
桃の節句では対になっているハマグリの貝殻が縁起物として扱われているのでお吸い物として用意されます。
また、魔除けのピンク、清浄勝つ純潔な白、健康な緑という3食揃った菱餅も食べるのです。
ひなあられは雛人形を持って子供達がみせに行くという風習があり、この出歩いた時に食べられるのがひなあられと言われており、そこからきているとされています。
このひなあられも色も菱形と同様の意味が込められているのです。

4月の行事食
・お花見(3月下旬から4月):お花見団子
・花祭り(8日):甘茶
お花見も3色の団子が用意されますが、アレにも意味があります。
まず赤は春の桜の花びらを意味し、白は冬の雪を、そして緑は夏を予感させるヨモギとなっているのです。
また、花祭りは仏教におけるお釈迦様の誕生日であり非常に重要な日となっています。
この日はお釈迦様の像に甘茶をかけるという儀式があるのですが、おの甘茶を飲むことで無病息災に過ごせると言われているのです。
5月の行事食
柏餅に使われている柏は新芽が育つまで古い葉っぱが落ちないという特性から神聖視されており、その特徴から「子供が成長するまで親はなくならない」として子孫繁栄の象徴となっているのです。

6月の行事食
氷の朔日は全く聞いたことが無いという人もいるでしょう。
旧暦の6月1日は宮中で氷室にある氷を食べる「氷室の節会」という行事があり、氷餅や煎り豆といった歯ごたえのあるモノを食べていたようです。
7月の行事食
7月のお盆は関東などの一部地域になります。
8月の行事食
・土用の丑の日(7月20日から8月6日までの丑の日):ウナギ、土用卵、土用餅
・お盆(13日から16日):そうめん、白玉団子、精進料理
関東以外の地域ではお盆は8月になることが多いです。
9月の行事食
10月の行事食
11月の行事食
12月の行事食
行事食を英語でいうと?

行事食を英語にすると「Event meal」となりますが、おせち料理やお雑煮といった行事食はそのままローマ字表記になります。
「おせち料理」なら「Osechi ryori」となって「お雑煮」は「Zoni」となるのです。
伊達巻きは「sweet omlet」でかまぼこは「fish cake」と一部の食べ物は英語変換できますが、基本はローマ字表記と覚えておきましょう。
行事食とは?春夏秋冬の日本の行事食一覧!のまとめ
以上、いかがだったでしょうか。
今回は行事食と主な年中行事について詳しく紹介しました。
行事食はこのように探してみると色々とあるのですが、知名度的に知られていないモノもかなり多いのです。
個人的な見解ですが、クリスマスやハロウィンといった海外の年中行事がなかった昔の方が特殊な行事食を色々と食べていたことが発覚したので、特別な日を本当に大切にしていたと感じております。













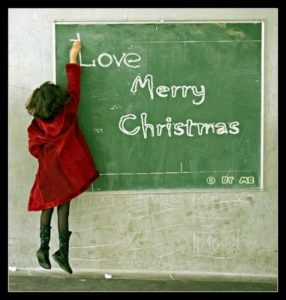
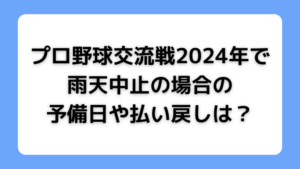






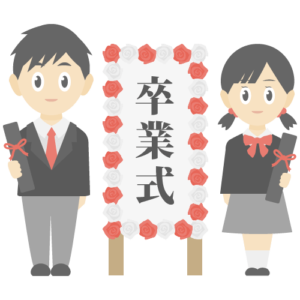
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 行事食とは?春夏秋冬の日本の行事食一覧! 日本の行事食一覧!行事食は英語ではなんというの? […]