早生まれの七五三のお祝いはいつ?写真撮影の時期はいつ?
お子さんの誕生や成長をお祝いする七五三ですが、早生まれのお子さんを持つ親御さんの中には、「七五三のお参りをいつ行えばいいのか」と悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、早生まれのお子さんの七五三について調べてみました。
早生まれの七五三のお参りの時期や、数え年・満年齢のどちらで行うとよいのか、写真撮影の時期などをご紹介します。
早生まれの七五三はいつ?
早生まれの子は、「数え年」と「満年齢」学年など、どちらを基準に七五三を行っても問題ありません。
七五三のお祝い、それは日本の伝統的な成長の節目ですね。
特に、早生まれのお子様をお持ちの親御さんにとっては、いつこの大切な行事を行うべきか、少し頭を悩ませるところかもしれません。
そんな疑問を抱える方々に向けて、わかりやすく解説してみましょう。
まず、早生まれとは具体的にどういうことかというと、それは新年が明けてから桜の花が開く前日、つまり1月1日から4月1日までに生まれたお子様のことを指します。
この期間に生まれたお子様は、学校教育法に基づき、4月2日以降に生まれたお子様よりも1年早く小学校に入学することになるのです。
では、この早生まれのお子様たちの七五三は、いつ祝うのが適切なのでしょうか。
一般的には、満年齢でお祝いすることが多いとされていますが、これには一つの理由があります。
それは、満年齢で祝うことで、同じ学年のお友達と同じタイミングでお祝いができるからです。
しかし、3歳のお祝いに関しては、数え年ではなく満年齢で行うことが一般的です。
これは、3歳のお子様が数え年で祝うと、実際よりも若い年齢でお参りすることになってしまうためです。
一方で、5歳や7歳のお祝いでは、満年齢で祝うと同学年のお友達と一緒にお祝いできないため、数え年で祝うことが多いようです。
これは、お子様が自分のことを自分でできるようになる大切な時期に、同年代のお友達と共に成長を喜び合うためです。
それでは、数え年と満年齢の違いを表にしてみましょう。
これを見ることで、お子様の生まれた日にちに応じて、どの年齢で七五三を祝うかが一目でわかります。
| 生まれ月 | 数え年での年齢 | 満年齢での年齢 |
|---|---|---|
| 1月1日〜11月15日 | +1歳 | 実際の年齢 |
| 11月16日〜12月31日 | +2歳 | 実際の年齢 +1歳 |
例えば、1月に生まれたお子様が実際に3歳になるとき、数え年では4歳となりますが、満年齢では3歳となります。
このように、お子様の生まれた月によって、数え年と満年齢での年齢に違いが生じるのです。
最終的には、お子様の成長と共に、家族の皆様が最も喜び、そしてお子様にとっても意義深い形で七五三を祝うことが大切です。
周りの状況や、お子様の成長具合を見ながら、柔軟に対応していくのが、一番のおすすめと言えるでしょう。
早生まれの七五三のお参りの時期はいつ?
七五三のお参り、特に、早生まれの子どもたちのお参りの時期には、ちょっとした工夫が必要になります。
では、早生まれの子どもたちの七五三は、一体いつお祝いするのが適切なのでしょうか?
伝統的には、七五三のお参りは11月15日に行われるのが一般的です。
しかし、時代と共に変化は訪れ、今では11月15日を中心に、10月中旬から12月中旬までの期間にお参りをする家庭が増えています。
これは、神社が混雑するのを避け、ゆったりとした気持ちでお参りをしたいという願いから生まれた風習です。
さて、お参りの日程を決める際には、特に週末は予約が込み合うことが予想されます。
遠方から祖父母が駆けつける場合など、家族のスケジュールを考慮して、早めに予約を入れることをおすすめします。
それでは、七五三のお祝いをする年齢を、男の子と女の子に分けて、もう少し詳しく見ていきましょう。
男の子のお祝い年齢
- 3歳 – 髪置きの儀:これまで短く刈り込んでいた髪を伸ばし始める、成長の一歩を象徴する儀式です。
- 5歳 – 袴着の儀:男の子が初めて袴を身につけることで、一人前への成長を表します。
女の子のお祝い年齢
- 3歳 – 髪置きの儀:女の子もまた、この年齢で髪を伸ばし始める儀式を行います。
- 7歳 – 帯解きの儀:子ども用の着物から一歩進んで、大人の女性と同じように帯を結ぶことを学ぶ重要な節目です。
これらの儀式は、子どもたちの成長と健康を祝福し、家族の絆を深める大切な瞬間です。
それぞれの儀式には、深い意味が込められており、子どもたちの新たなステージへの移行を家族が祝福します。
以下の表に、七五三の儀式とその内容をまとめましたので、参考にしてくださいね。
| 儀式名 | 祝い年齢 | 内容 |
|---|---|---|
| 髪置き(かみおき) | 数え年3歳 | 子どもの髪を伸ばし始めることで、健やかな成長を願う儀式 |
| 袴着(はかまぎ) | 数え年5歳 | 男の子が初めて袴を身につけ、成長を祝う儀式 |
| 帯解き(おびとき) | 数え年7歳 | 女の子が子ども用の着物から卒業し、帯を自ら結ぶことを学ぶ儀式 |
七五三は、ただのお祝い事ではありません。子どもたちの一生に一度の大切な節目として、心を込めてお祝いしましょう。
そして、早生まれの子どもたちも、この美しい伝統を存分に楽しんでほしいと願っています。
七五三は満年齢・数え年どちらでお祝いする?
七五三のお祝いする際に「満年齢」か「数え年」かで迷われる方も多いですよね。
さて、どちらでお祝いすればいいのでしょうか?
まず、「数え年」とは、日本の伝統的な年齢の数え方です。
これは、お子様がこの世に生を受けた瞬間を1歳と数え、その後は毎年1月1日に年を重ねていくというもの。
一方、「満年齢」は、西洋式で、生まれてから実際に経過した正確な年数を指します。
現代では、多くの方が「満年齢」でお祝いをされることが一般的になっています。
しかし、昔ながらの「数え年」でお祝いをする家庭もまだまだあります。
例えば、2月1日に生まれたお子様の場合、満年齢では2歳と9ヶ月で七五三を迎えますが、数え年では3歳となりますね。
このように、早生まれのお子様の場合、数え年でお祝いすると、実際の年齢よりも一つ上の年齢でお祝いすることになります。
では、どちらの方法でお祝いすれば良いのでしょうか。
これは、お子様の成長具合や、ご家族の考え方によって異なります。
まだ小さくてお祝いが負担になると感じる場合は、満年齢でゆっくりお祝いするのも一つの方法です。
しかし、お子様が幼稚園や小学校に通い始めると、同級生と一緒にお祝いをしたいという気持ちが強くなるかもしれません。
そんな時は、数え年でお祝いをすることで、同級生と同じタイミングで七五三を迎えることができるのです。
七五三は毎年11月15日前後に行われることが多いですが、これはあくまで一般的な目安です。
大切なのは、お子様が主役のこの日を、家族みんなで幸せに過ごすこと。
お子様のペースに合わせて、最適なタイミングでお祝いを選ぶことが、何よりも素敵な七五三を創る秘訣ですよ。
さて、ここで「満年齢」と「数え年」の違いを簡単にまとめた表をご覧ください。
| お子様の誕生日 | 満年齢での七五三 | 数え年での七五三 |
|---|---|---|
| 2月1日生まれ | 2歳と9ヶ月 | 3歳 |
| 5月1日生まれ | 3歳と6ヶ月 | 4歳 |
| 8月1日生まれ | 3歳と3ヶ月 | 4歳 |
※七五三は11月15日前後にお祝いすることが多いため、上記は11月にお祝いする場合の月齢を示しています。
満年齢
私たちの年齢を問われたとき、心の中でパッと浮かぶ数字、それが「満年齢」です。
この数え方は、まるで新しい命が芽吹く春のように、生まれたその瞬間をゼロのスタートと捉え、一年の周期でひとつずつ大切な歳を重ねていきます。
誕生日のお祝いとともに、新たな一歳を加えるこの方法は、まるで毎年訪れる成長の節目を祝福するかのよう。
現代の日本で私たちが「何歳ですか?」と尋ねられた際に答えるのは、この満年齢のことがほとんどです。
数え年
一方で、「数え年」は、生まれたその瞬間をもう既に一歳と数え、新年の訪れと共にまた一つ歳を重ねるという、昔ながらの愛らしい数え方。
例えば、雪がちらつく12月の終わりに生まれた子も、新しい年の幕開けとともに、あっという間に「2歳」と呼ばれるようになります。
特に早生まれの子供たちにとっては、周りの友達よりも少しだけゆっくりと歳を数えることになるので、まるで冬の寒さをゆっくりと春へと変えていくかのような、のんびりとした時間の流れを感じさせてくれます。
この二つの歳の数え方は、私たちの生活に寄り添いながら、それぞれの時代や文化の中で大切にされてきました。
表にまとめてみると、一目で違いがわかりやすいですね。
| 年齢の数え方 | 説明 | 特徴 |
|---|---|---|
| 満年齢 | 生まれた時を0歳とし、誕生日に1歳を加える | 現代的で明確、国際的にも通用 |
| 数え年 | 生まれた時を1歳とし、新年を迎えると1歳を加える | 伝統的で情緒的、早生まれの子に優しい |
どちらの数え方も、私たちの歳月を温かく見守ってくれる存在です。
日々の暮らしの中で、ふとした瞬間に思い出してみるのも、一つの楽しみかもしれませんね。
早生まれの七五三の写真撮影の時期は?

七五三のお参りと写真撮影を同日に行う場合もありますが、人混みに疲れているところに写真撮影となると、小さいお子さんでは体力・気力ともに限界を超えてしまうこともありますよね。
そのため、お参りと写真撮影は別日にする親御さんが多く、七五三(一般的に10月中旬から12月中旬の間)のお参り前に写真撮影をすることを前撮り、お参りの後に撮ることを後撮りと言います。
ここではそれぞれの撮影時期をご案内するとともに、早生まれのお子さんの場合のメリットやデメリットをご紹介します。
前撮り
前撮りは七五三のお参り時期の前に撮ることを言います。
写真スタジオでは4月には前撮りのキャンペーンが始まり、およそ11月くらいまで続きますが、早生まれのお子さんの場合は、日数が前倒しになればなるほど幼い状態での撮影となるため、着物を嫌がったり、思うように写真を撮らせてくれないなどの問題があるかも知れません。
しかしその一方で、赤ちゃんらしさを残した状態で和装をするので、貴重な思い出に残りやすくなります。
あえて赤ちゃんらしさを残して撮影をしたいという方は、前撮りを選ぶのがよいかも知れません。
なお、前撮りは4~6月の早い段階が人気のようです。
夏を過ぎると日焼けなどで顔などが浮いてしまう恐れがあるため、日焼けする前に写真を撮りたいという親御さんの希望が多いからと言われています。
後撮り
後撮りは七五三のお参り時期が終わる12月~1月に行われます。
前撮りよりも混雑しないので、比較的希望する日に予約することが可能なことや、早生まれのお子さんの誕生日に近いため、より3歳や5歳、7歳に近い状態での撮影が可能になります。
また、夏に日焼けをしてしまってもこの頃には落ち着いているので、肌の色があまり気にならずに撮影ができるメリットもあります。
デメリットとしては、外での撮影を考えている場合に秋らしさがなくなり、殺風景になってしまう可能性があることや、インフルエンザの流行時期となるため体調管理に気を配る必要があることなどが挙げられます。
七五三の時期はずらしてもいい?

七五三は11月15日の前後1ヵ月の期間中に行う方が多いですが、小さいお子さんにとっては、着慣れない着物での神社への参拝だけでも大変な負担になってしまいます。
その上、写真撮影、親族との食事会を同じ日に行うとなると多忙を極めます。
このようなことから、七五三は必ずしも11月15日の前後の1ヵ月の期間中に行わなくてはいけないと、決めつける必要はありません。
あくまでも目安として受け止め、一番はお子さんの体調が安定しているタイミングを見計らって行うのがよいでしょう。
ただし、真夏や真冬はお子さんの体調が崩れやすい時期ですし、一般的な期間を大きく外してしまうと、神社によっては千歳飴などの七五三のお祝いの品がない場合もあります。
早生まれの七五三はいつ?のまとめ
早生まれのお子さんがいる親御さんにとって、七五三はいつ行けばよいのか?というのは悩む部分だと思います。
3歳の場合はお子さん自身に「お友達と一緒がいい」という感覚がまだないので、そこまで気にする必要はないですが、5歳、7歳となると幼稚園や小学校の同級生と一緒のタイミングがよいと思う子もいるかも知れません。
そのような場合は、早生まれのお子さんは数え年で七五三を行うと同級生と一緒にお祝いすることができます。






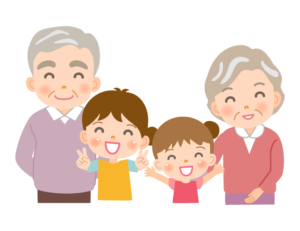


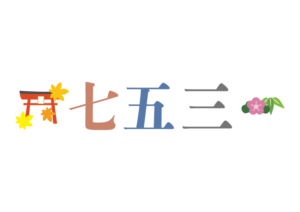


コメント