2025年の七五三はいつ祝う?お参りに行くタイミングや記念撮影はいつがベスト?
七五三はこどもの成長をお祝いする行事ですが、その意味や由来はよくわからない方も多いのではないかと思います。
また、七五三は満年齢でするのか数え年でするのか、どちらが正解なのか知りたいという方も多いはずです。
そこで今回は、七五三について調べてみました。
七五三はいつ祝うのか?男の子と女の子ではお祝いが違うのかなども合わせて解説します。
2025年 七五三はいつ祝う?
2025年の七五三は11月15日(金)です。
日本の伝統的な節目として親しまれている「七五三」は、子どもたちの成長を祝う特別な日です。
この行事は、子どもたちが健やかに成長することを願い、家族が集まってその節目を祝います。
では、この七五三がなぜ毎年11月15日に行われるのか、その背景にはどのような歴史があるのでしょうか。
七五三の由来と歴史的背景
七五三の起源は、日本の江戸時代にさかのぼります。
特に、この日を祝日と定めたのは、徳川幕府の第3代将軍である徳川家光とされています。
彼は自身の息子である後の第4代将軍・徳川綱吉の5歳の誕生日を、11月15日に盛大に祝ったことから、この日が子どもの成長を祝う日として定着したと言われています。
しかし、この日付にはさらに深い意味があります。
当時の日本では陰暦が使用されており、月の満ち欠けによって日々が計算されていました。
陰暦の15日は、新月から数えて15日目にあたり、夜空にはほぼ満月が輝いています。
満月は古来より縁起が良いとされ、人々の生活において重要な意味を持っていました。
さらに、陰暦の月は現在のグレゴリオ暦のように数字で表されるのではなく、十二支によって名付けられていました。
そして、冬至を含む11月は「子の月」と呼ばれ、十二支のサイクルの始まりを告げる月とされていました。
この「子の月」にあたる11月15日が、満月の日と重なることから、この日が七五三のお祝いに選ばれたとされています。
七五三の現代における意義
現代においても、七五三は日本の文化として大切にされています。
この日、3歳と5歳の男の子、そして3歳と7歳の女の子は、伝統的な衣装を身にまとい、家族と共に神社へ参拝します。
この行事を通じて、子どもたちの健康と長寿を祈り、家族の絆を深める機会となっています。
七五三の日には、多くの家族が記念写真を撮影し、子どもたちの成長を記録に残します。
また、子どもたちは「千歳飴」と呼ばれる長い飴をもらい、これが長寿と健康を願う象徴とされています。
七五三の概要
以下の表は、七五三に関する情報を整理したものです。
| 年齢 | 性別 | 行事の内容 |
|---|---|---|
| 3歳 | 男女 | 袴や着物を着て神社での参拝 |
| 5歳 | 男子 | 袴を着て神社での参拝 |
| 7歳 | 女子 | 着物を着て神社での参拝 |
このように、七五三は単なる年中行事ではなく、日本の文化や歴史、家族の絆を象徴する大切な日として、今もなお多くの人々に愛され続けています。
毎年11月15日には、日本全国の神社が華やかな装いをした子どもたちとその家族で賑わい、新たな思い出が刻まれていくのです。
七五三のお参りのタイミングはいつがベスト?
日本の伝統的な成長の節目である七五三は、子供たちの健やかな成長を祝う大切な行事です。
この祝祭日は、歴史的に11月15日に行われるのが一般的でしたが、現代の社会ではその慣習が少し変化しています。
なぜ11月15日ではない日に七五三を行うのか?
11月15日は伝統的に七五三の日とされていますが、この日に全ての家庭が神社を訪れると、混雑が避けられません。
そのため、多くの家庭がこの日に固執せず、10月中旬から12月中旬にかけてお参りを行うようになっています。
平日にお参りするメリット
週末は多くの家族で賑わいますが、平日は比較的空いているため、落ち着いて七五三のお参りを行うことができます。
事前に神社に予約を入れることで、スムーズにご祈祷を受けることが可能です。
11月15日以外の日にお参りする場合
11月15日にお参りできない場合でも、七五三を行うには適切なタイミングがあります。
以下の表は、七五三のお参りに最適な時期を示しています。
| 月 | おすすめの時期 | 注意点 |
|---|---|---|
| 10月 | 中旬から終わり | 混雑を避けるため平日が望ましい |
| 11月 | 15日以外の日 | 伝統的な日を避けることで混雑を避けられる |
| 12月 | 中旬まで | 年末の忙しさに入る前に |
六曜と七五三
六曜は日本の暦における特別な日の一つで、吉日や凶日を示します。
本来、七五三と六曜は直接関係はありませんが、良い日を選ぶという意味で、多くの家庭が六曜を参考にしています。
| 六曜 | 意味 |
|---|---|
| 大安 | 最も吉とされる日 |
| 赤口 | 午前中は吉、午後は凶とされる |
| 先勝 | 午前中は吉、午後は凶とされる |
| 友引 | 吉凶が半分ずつの日 |
| 先負 | 午前中は凶、午後は吉とされる |
| 仏滅 | 凶とされる日 |

家族の意見を尊重する
六曜を重視するかどうかは家庭によって異なります。
お参りの日を決める前に、ご両親や義理のご両親の意見を尊重することで、後のトラブルを避けることができます。
七五三のお参りは、伝統的な日付に固執する必要はありません。
混雑を避け、家族でゆっくりとした時間を過ごすためには、平日や六曜を考慮した日程を選ぶと良いでしょう。
大切なのは、子供たちの成長を祝い、家族の絆を深めることです。
七五三の記念撮影はいつする?
七五三の記念撮影には、当日撮影に加え、前撮り、後撮りという選択肢もあります。
それぞれの違いを確認しておきましょう。なお、前撮りはおおむね4月頃から始まります。
お子さまの体調や成長、ご家族の都合に合わせて時期を決めるとよいでしょう。
| 当日撮影 | |
|---|---|
| メリット |
|
| デメリット |
|
| 前撮り | |
|---|---|
| メリット |
|
| デメリット |
|
| 後撮り | |
|---|---|
| メリット |
|
| デメリット |
|
七五三は満年齢と数え年どちらでお祝いするの?

現在、日本では満年齢による年齢の数え方が一般的となっているので、数え年と言われてもピンと来ない方が多いと思います。
しかし、七五三を始め、お祓いなどで神社に行くと満年齢以外に数え年の表記があるので、数え年でやるべきなのかと悩む方も多いでしょう。
数え年は第二次世界大戦前の日本で、主流で使われていた年齢の数え方です。
数え年では生まれた時がすでに1才で、以後はお正月を迎えるたびに1つ年を重ねるため、12月の生まれの場合は、翌月の1月には2才になっている計算方法です。
これに対し、満年齢は第二次世界大戦後に日本で使われるようになった年齢の数え方で、生まれた年を0才とし、以降は誕生日が来ると1才ずつ年を重ねていくことになります。
昔は年齢の数え方は数え年しかなかったので、七五三も当然ながら数え年で行っていましたが、現在の場合はどちらで行っても構わないとされています。
ただし、地域によっては今も七五三を数え年で行うのが常識としているところや、祖父母世代においては数え年で行うものと考えている方も多いので、その辺は相談してみるとよいでしょう。
七五三のお祝いは男の子と女の子で違う?
日本の伝統的な節目として知られる「七五三」は、子どもたちの健やかな成長を祝う風習であり、その起源は平安時代にまで遡ります。
この風習は、子どもたちが特定の年齢に達することを祝い、家族が集まってその節目を共に喜びます。
しかし、このお祝いには男の子と女の子で異なる伝統が存在します。
以下に、それぞれの性別で行われる儀式とその背景について詳しく解説し、表を用いて情報を整理してみましょう。
男の子の七五三
髪置きの儀(3歳)
平安時代、子どもたちは生後7日目に初めて髪を剃り、その後3歳までは坊主頭で過ごすのが一般的でした。
3歳になると、これまでの成長を祝い、髪を伸ばし始める「髪置きの儀」を行います。
この儀式は、子どもが健康に成長し、これからも長い人生を送ることを願う親の思いが込められています。
袴儀の儀(5歳)
5歳の男の子にとっての大切な節目は「袴儀の儀」です。
ここで初めて、男性の伝統的な衣装である袴を身につけます。
これは子どもが一人前の男性へと成長していくことを象徴し、社会的な一員としての自立を促す意味合いがあります。
女の子の七五三
髪置きの儀(3歳)
女の子も3歳で「髪置きの儀」を行いますが、男の子とは異なり、女の子の場合は髪を結い始めることを意味しています。
これは女性としての美しさや礼儀を身につけ始めることを象徴しています。
帯解の儀(7歳)
7歳になると女の子は「帯解の儀」を迎えます。これまで簡易的なひもで結んでいた着物を、本格的な帯で結ぶようになります。
この儀式は、女の子が一人前の女性へと歩み始めることを示し、より複雑で格式のある着付けを覚えることになります。
七五三の儀式の比較
| 年齢 | 男の子の儀式 | 女の子の儀式 |
|---|---|---|
| 3歳 | 髪置きの儀 | 髪置きの儀 |
| 5歳 | 袴儀の儀 | – |
| 7歳 | – | 帯解の儀 |
この表は、七五三における男の子と女の子の儀式の違いを明確に示しています。
男の子は3歳と5歳で、女の子は3歳と7歳でそれぞれ異なる儀式を行います。
これらの儀式は、子どもたちの成長と健康を祝うとともに、社会的な役割や性別に応じた行動規範を教え、伝統を次世代に伝える重要な役割を果たしています。
七五三は単なるお祝い事にとどまらず、日本の文化や社会の中で子どもたちがどのように見守られ、育てられてきたかを象徴する行事と言えるでしょう。
現代においても、多くの家族がこの伝統を大切に守り、子どもたちの一生に一度の節目を祝福しています。
七五三のお参りに行く神社はどこ?
日本の伝統的な成長の節目である七五三は、子どもたちの健やかな成長を祝い、地域の守護神である氏神様に感謝の意を表する大切な行事です。
この風習は、子どもが無事に七歳、五歳、三歳を迎えられたことを、神様のご加護に感謝し、これからのさらなる健康と幸福を祈願するために行われます。
氏神様とは?
氏神様は、その土地に住む人々を見守り、守護する神様です。
日本の各地域には、その地を護る神様が祀られており、地元の人々にとっては、日々の生活の中で自然と親しまれている存在です。
七五三のお参りでは、これらの神様に対して、子どもたちの成長を見守っていただいた感謝の気持ちを伝えるのが伝統的な慣わしとされています。
地域の神社選び
もしもあなたが引っ越しをしたばかりで、地元の氏神様がどの神様なのか不明な場合や、出身地と異なる場所に住んでいる場合でも心配はいりません。
以下のような方法で、お参りする神社を見つけることができます。
- 地域の案内所や役場で尋ねる: 新しい住まいの地域の氏神様について、地域の案内所や役場などで尋ねることができます。
- 近隣の神社を訪れる: 特定の氏神様にこだわらない場合、近くの神社を訪れてお参りをすることも一つの選択肢です。
- インターネットで検索する: 現代ではインターネットを利用して、自宅の最寄りの神社を探すことも可能です。
七五三の日の準備
七五三の時期は多くの家族で賑わいます。そのため、以下の点を考慮してお参りを計画することが大切です。
- 混雑を避ける: 参拝者が多い時間帯を避け、子どもが疲れないように早めの時間帯にお参りを済ませることをお勧めします。
- 服装の準備: 伝統的な着物や羽織、袴など、子どもたちの晴れ着を事前に準備しましょう。
- 写真撮影: 成長の記念に、神社の境内や鳥居で家族写真を撮ることも忘れずに。
七五三のお参りに適した神社の選び方
| 選択肢 | 利点 | 注意点 |
|---|---|---|
| 地元の氏神様の神社 | 地域の守護神への感謝を直接伝えられる | 氏神様を事前に調べる必要がある |
| 近隣の神社 | アクセスが容易 | 地域の守護神との関連が薄れる可能性 |
| インターネットで検索 | 情報が手軽に得られる | 正確な情報かどうかを確認する必要がある |
最終的には、お子さんが主役のこの特別な日を、家族全員で楽しむことが最も重要です。
準備を万全にして、七五三のお祝いを心に残る素晴らしい思い出にしましょう。
七五三のお参りの服装は?
七五三とは、子どもたちの成長を祝う日本の伝統的な祭りです。
この特別な日には、3歳、5歳、7歳の子どもたちが、彼らの健やかな成長を祈願して、家族と共に神社へ参拝します。
この日の装いは、ただの服ではなく、子どもたちの未来への願いを込めた象徴的な意味を持っています。
神社での参拝:伝統的な和装の魅力
多くの家族は、七五三のお祝いで神社への参拝を予定しています。
この時、伝統的な和装を選ぶことは、日本の文化を尊重し、子どもたちにその美しさを伝える絶好の機会です。
着物は、色鮮やかで繊細な柄が特徴で、子どもたちをより一層華やかに彩ります。
記念撮影:写真館でのレンタルサービス
現代では、記念撮影を写真館で行う家族も少なくありません。
多くの写真館では、撮影用の着物をレンタルしており、そのまま参拝にも使用できるサービスを提供しています。
これは、特に着物を所有していない家族にとって、便利で経済的な選択肢となります。
レンタルが難しい場合:フォーマルウェアの選択
もし着物のレンタルが叶わない場合でも、フォーマルな洋装で参拝することは全く問題ありません。
男の子はジャケットに、女の子はワンピースを選ぶと、きちんとした印象を与えることができます。
家族の服装:和装は必須ではない
七五三のお祝いに同行する親御さんの服装については、和装にこだわる必要はありません。
スーツやジャケットなど、きちんとした洋装であれば、参拝にふさわしいとされています。
服装選びのポイント
以下のテーブルは、七五三の参拝時に適した服装を年齢別にまとめたものです。
| 年齢 | 男の子 | 女の子 | 親御さん |
|---|---|---|---|
| 3歳 | 袴付きの着物 | 被布セット | スーツ、ドレス |
| 5歳 | 羽織袴 | 着物 | スーツ、ドレス |
| 7歳 | 羽織袴 | 振袖風の着物 | スーツ、ドレス |
和装を選ぶ際は、伝統的な色合いや柄を選び、洋装を選ぶ際は、落ち着いた色のフォーマルウェアを選ぶことが望ましいです。
また、アクセサリーや小物も、その日の装いを引き立てる重要な要素です。
七五三は、子どもたちの一生に一度の記念日です。
そのため、服装選びには特別な注意を払い、この日を家族全員で心に残るものにしましょう。
七五三のお参りにあると便利な持ち物
七五三は、日本の伝統的な成長の節目を祝う行事です。
子どもたちが3歳、5歳、7歳の重要な歳に達したことを祝い、神社で健やかな成長を祈願します。
この特別な日には、子どもたちが華やかな着物や羽織を身にまとい、家族で神社を訪れます。
しかし、この美しい伝統は、準備が不十分だと予想外の小さなトラブルに見舞われることも。
そこで、七五三のお参りに臨む際にあると便利な持ち物をご紹介します。
必携アイテムリスト
| アイテム | 説明 | なぜ必要か |
|---|---|---|
| 予備の靴 | 普段履き慣れたもの | 着慣れない靴による靴擦れを防ぎ、子どもの不快感を軽減します。 |
| 靴下 | 予備を含む | 靴擦れの対策として、または汚れた際の交換用として。 |
| 着替え | 衣装 | お参り後の食事や移動で衣装が汚れた場合のため。 |
| ハンドタオル | 帯の調整用 | 着物の帯がずれた際に、調整や固定のために使用します。 |
| 軽食 | スナックやおにぎり | 長い待ち時間にお腹が空いたときのための簡単な食事。 |
詳細な説明と追加のヒント
- 予備の靴: 七五三では、子どもたちが普段とは異なる、正装用の靴を履くことが多いですが、これが原因で靴擦れを起こすことがあります。そんな時に備えて、履き慣れた靴を持参すると、子どもが疲れてしまった時にも安心です。
- 靴下: 新しい靴との摩擦を防ぐためにも、予備の靴下を持参することは大切です。また、天候や地面の状態によっては靴下が汚れることもあるため、交換用を準備しておくと安心です。
- 着替え: お参りの後にレストランでの食事や、他の場所への移動を予定している場合、子どもが食べ物で衣装を汚してしまう可能性があります。着替えを持っていると、そんな時でも慌てることなく対応できます。
- ハンドタオル: 着物や羽織は動き回る子どもたちにとってはずれやすいもの。帯が緩んできたら、ハンドタオルを帯と体の間に挟むことで、ずれを防ぎます。
- 軽食: 神社は特に七五三の時期には多くの家族で賑わいます。参拝までの待ち時間が長くなることも考えられるため、子どもがお腹を空かせてぐずることがないように、軽食や飲み物を準備しておくと良いでしょう。
七五三のお参りは、子どもたちの成長を祝う大切な日です。
この日を快適に、そして楽しく過ごすためには、事前の準備が重要です。
上記の持ち物リストを参考に、家族での素敵な思い出作りをサポートしてください。
小さな心配りが、一生の思い出に残る一日を作ることでしょう。
七五三が喪中と重なったらどうしたらいい?
日本の伝統的な節目のお祝いである七五三は、子どもたちの健やかな成長を願い、特定の年齢に達した際に行われる重要な行事です。
しかし、家族に不幸があった場合、この祝い事をどのように扱うべきか迷うことがあります。
ここでは、喪中に七五三が重なった際の対処法について考察します。
喪中期間とは
喪中とは、家族などの身内が亡くなった後の一定期間を指し、この間は祝い事を控えるという慣習があります。
通常、この期間は故人が亡くなってから次の年の年末までとされています。
この期間内には、結婚式や祝宴などのお祝いごとを避けるのが一般的です。
七五三と喪中の重なりについて
七五三は、子どもが無事に成長したことを祝う行事であり、3歳、5歳、7歳の子どもたちが神社に参拝し、健康と長寿を祈願します。
しかし、喪中にこの行事が重なると、祝い事を控えるべきかどうかという問題が生じます。
喪中における七五三の対応
喪中に七五三が重なった場合、以下のような選択肢が考えられます。
- 忌中期間の確認: 忌中とは故人の四十九日が明けるまでの期間を指し、この期間内は特に祝い事を控えるべきとされています。忌中が終わっていれば、喪中であっても七五三のお祝いを行うことが可能です。
- 時期の調整: 忌中が終わった後、喪中であっても七五三を行うことは一般的に受け入れられています。ただし、故人に対する敬意を表し、控えめな祝い方を選ぶ家庭もあります。
- 年齢の問題: 七五三は数え年で行うのが伝統的ですが、喪中を理由に一年延期すると、数え年でも満年齢でもない年齢で行うことになります。この場合、翌年に改めて祝うか、または家庭内で小規模に祝うという選択があります。
家庭ごとの対応
七五三の祝い方は、家庭や地域によって異なるため、喪中における対応も家庭ごとに異なります。
以下は、一般的な対応の例です。
| 喪中の状況 | 七五三の対応例 |
|---|---|
| 忌中期間中 | 祝い事を控え、忌中が明けてから改めて行う |
| 忌中明け後 | 喪中であっても七五三を行うが、控えめに祝う |
| 翌年に延期 | 数え年の問題を避けるため、翌年に正式な祝いを行う |
喪中に七五三が重なった場合、忌中が明けていれば神社への参拝は問題ないとされていますが、家庭や地域の慣習、故人への敬意などを考慮して、それぞれの家庭で適切な判断をすることが大切です。
祝い事を控えることは故人への哀悼の意を示すと同時に、生きている子どもたちの未来への願いを込めた行事である七五三をどのように執り行うか、慎重に考える必要があります。
七五三とは?
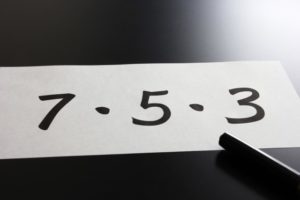
今のように医療が発達していなかった昔は、こどもの死亡率が高く、3才まで生きていることはとても大変なことで、7才まで生きることができるのはもっと大変だったそうです。
そのため、「7才までは神の子」ということわざが生まれ、文字通り7才までは人の子ではなく神様から預けられた大切な命だと思って育てようという意識が高かったと言われています。
平安時代には、3才、5才、7才を節目として、こどもの成長をお祝いする行事を行っていましたが、時代の移ろいとおもにその風習は武士の間にも広まり、江戸時代になると庶民へと浸透していきます。
明治時代になると、3才、5才、7才に行う行事を合わせて「七五三」と呼ぶようになり、医療が発達してこどもの死亡率が低くなった現代でも、こどもの成長をお祝いする行事として定着しています。
七五三いつ祝う?のまとめ
七五三は平安時代に行われていた「髪置きの儀」「袴儀の儀」「帯解の儀」を、3つ含めた総称となっています。
元は宮中行事でしたが、江戸時代には庶民へと浸透し、明治時代になると七五三という現在の呼び名で呼ばれるようになります。
七五三でお参りに行くのは、氏神様が祀られている地域(地元)の神社が基本となります。
七五三にお参りに行く場合には、お子さんは写真館で貸し出された衣装があればそちらでもよいですし、和装で長時間出歩くのが難しいなら、ジャケットやワンピースなどのフォーマルな洋装でも構いません。









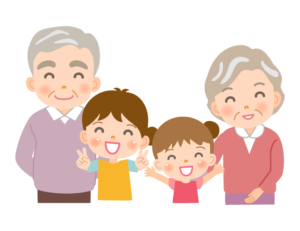


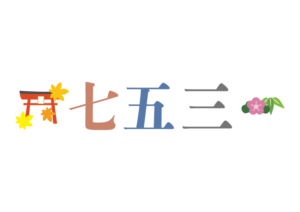


コメント