七五三のお祝いの年齢は満年齢それとも数え年のどっち?
「七五三」とは、日本における子供の健やかな成長を顕彰し、その節目を家族で祝う伝統的な儀式です。
この慶事は、子供たちの順調な成長に対する感謝の意を神前に捧げ、今後の更なる健康と発展を願う目的で実施されます。
ただし、七五三のお祝いにあたっては、どのように年齢を数えるかに関して疑問を抱く人もいます。
本文では、七五三における年齢の計算方法と、その由来及び現在の風習について詳細に説明します。
七五三は数え年か満年齢どっちの年齢で祝うと良いのか?
日本の伝統的な節目として親しまれている「七五三」は、子どもたちの成長を祝う大切な行事です。
この行事は、子どもたちが無事に成長していることを神様に感謝し、これからの健やかな成長を祈願するために行われます。
しかし、この七五三を祝う際に、年齢の数え方について疑問を持つ方も少なくありません。
そこで、この文章では、七五三の年齢の数え方について、その背景と現代の慣習について詳しく解説します。
七五三の年齢の数え方
満年齢とは?
満年齢は、西洋式の年齢の数え方で、生まれた日から次の誕生日を迎えるまでを0歳とし、誕生日が来るたびに1歳を加えていく方法です。
この数え方は、現代日本で最も一般的に用いられており、公的な文書や日常会話での年齢表記にも採用されています。
数え年とは?
一方、数え年は、日本古来の年齢の数え方で、生まれた瞬間を1歳とし、新年を迎えるごとに1歳を加えていく方法です。
この数え方は、過去には広く用いられていましたが、現在では主に一部の伝統行事や法要などで見られるのみとなっています。
七五三の祝い方
七五三では、
- 男の子は3歳と5歳
- 女の子は3歳と7歳
の節目にお祝いをします。
これは、子どもの健やかな成長と長寿を願う日本の美しい風習です。
昔と今の変遷
過去には数え年を用いて七五三を祝っていましたが、現在では満年齢でお祝いするのが一般的です。
しかし、地域や家庭によっては今でも数え年でお祝いする慣習を守っている場合もあります。
どちらの年齢を用いるべきか?
七五三を祝う際には、基本的には満年齢を用いるのが現代の標準ですが、数え年で祝うことに特別な意味を見出す家庭もあります。
そのため、どちらの年齢で祝うかは、家族の意向や地域の慣習によって異なります。
七五三の年齢表
以下の表は、数え年と満年齢の違いを分かりやすく示しています。
特に、11月15日以前と以後の生まれで、数え年と満年齢の差が生じることを示しています。
| 節目の年齢 | 1月1日〜11月15日生まれの満年齢 | 11月16日〜12月31日生まれの満年齢 |
|---|---|---|
| 3歳 | 2歳 | 1歳 |
| 5歳 | 4歳 | 3歳 |
| 7歳 | 6歳 | 5歳 |
この表を参考に、ご家族が七五三をどのように祝うかを決める際の一助となれば幸いです。
最終的には、お子様の健やかな成長を祝うこの行事を、家族でどのように祝うかが最も重要です。
伝統を大切にしつつ、現代の生活様式に合わせた形で七五三を祝うことが、この美しい日本の風習を未来に繋げていくことにもつながります。

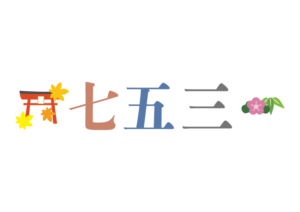
七五三は満年齢の子供と数え年の子供を組み合わせる場合も
「七五三」は、子どもたちの健やかな成長を祝う行事です。
この行事は、3歳と5歳の男の子、そして3歳と7歳の女の子の成長を祝うものとして知られています。
しかし、時代の変化と共に、七五三のお祝いの仕方にも柔軟性が生まれています。
特に、子どもの年齢の数え方に関しては、昔ながらの「数え年」と現代的な「満年齢」のどちらを用いても良いとされており、家族にとって都合の良い形でお祝いが行われるようになりました。
七五三の年齢の数え方
| 年齢の種類 | 説明 |
|---|---|
| 満年齢 | 実際に生まれてからの年数を数える方法。 |
| 数え年 | 生まれた年を1歳と数え、その後は新年を迎えるごとに1歳を加える伝統的な方法。 |
この柔軟性は、特に複数の子どもがいる家庭にとって大きなメリットをもたらします。
例えば、年子である兄弟がいる場合、実年齢と数え年が一致する年に、2人同時に七五三のお祝いを行うことができます。
これにより、家族はお祝いの準備や参拝にかかる時間と労力を節約できるのです。
具体的なパターン例
| ケース | 例 |
|---|---|
| 年子の兄弟 | 実年齢5歳の兄と数え年5歳の弟を同時にお祝い |
| 早生まれとその下の兄弟 | 早生まれで満年齢5歳の兄と実年齢2歳の弟を同時にお祝い |
特に複数の子どもを持つ家庭にとって大きな恩恵をもたらしています。
例えば、年子の兄弟がいる家庭では、実年齢と数え年が一致するタイミングで、2人同時に七五三のお祝いを行うことが可能です。
これにより、家族は準備や参拝にかかる時間と労力を節約できます。
このように、七五三のお祝いは、子どもたちの成長を祝うという本来の意味を大切にしつつ、現代の家庭のニーズに合わせて進化しています。
親御さんたちは、子どもたちの成長をより手軽に、そして経済的な負担を減らしながら祝うことが可能になり、この伝統的な行事がより身近なものとなっているのです。
七五三は、ただの形式ではなく、家族の絆を深め、子どもたちの未来への期待を込めた大切な日です。
そのため、お祝いの方法は柔軟に、そして家族のスタイルに合わせて行われるべきでしょう。
現代の七五三は、伝統を守りつつも、それぞれの家庭の個性や事情を尊重する形で進化を続けています。
早生まれや11月・12月生まれの子は七五三はいつしたらいいの?
伝統的には「数え年」で七五三を行うのが一般的でした。
数え年とは、生まれた年を1歳と数え、その後は新年を迎えるごとに1歳を加える年齢の数え方です。
しかし、現代では「満年齢」を用いることが多くなっています。
満年齢は、実際に生まれてからの正確な年数を指します。
早生まれの子どもたち、つまり1月から4月に誕生した子どもたちや、11月15日以降に誕生日を迎える子どもたちは、七五三をどの年齢で行うかについて、以下のような選択肢があります。
早生まれの子どもたちの場合
- 数え年で祝う: 早生まれの子どもたちは、数え年で早めに七五三を行うことができます。これは、身体的、精神的成長が満年齢よりも進んでいる場合に適しています。
- 満年齢で祝う: 一方で、満年齢に基づいてお祝いを行うことで、子どもがより成熟してからの参拝となります。これは、学年が上がった後や次の誕生日前に行うことが一般的です。
11月15日以降に誕生日を迎える子どもたちの場合
- 数え年で祝う: 11月15日以降に誕生日がある子どもたちは、数え年によると次の年に年を取ることになるため、実際よりも1歳多く数えられ、早めに七五三を迎えることになります。
- 満年齢で祝う: これらの子どもたちも、満年齢に基づいてお祝いを行うことができます。これは、実際の年齢に合わせてお祝いを行うため、子ども自身にとっても親御さんにとっても無理のない選択となります。
七五三のお祝いのタイミングを決める際の考慮事項
- 子どもの成長具合: 子どもの身体的な成長や精神的な発達を考慮して、お祝いのタイミングを決めることが重要です。
- 子どもの性格: お祝いに参加する子どもの性格や行動パターンを考慮し、無理なく参加できる時期を選ぶべきです。
- 家族の都合: 家族のスケジュールや予算も考慮に入れ、無理のない計画を立てることが大切です。
七五三のお祝いのタイミングに関する表
| 子どもの誕生月 | 数え年でのお祝い | 満年齢でのお祝い |
|---|---|---|
| 1月 – 4月(早生まれ) | 早めに祝う | 学年が上がった後 |
| 11月15日以降 | 次の年に祝う | 実際の年齢で祝う |
最終的には、七五三のお祝いは子どもたちの健やかな成長を祝うものであり、形式にとらわれず、家族にとって最も意義深い方法で行うことが最良です。
親御さんは、子どもの個性や家族の状況を最優先に考え、最適なタイミングを選ぶことが大切です。
満年齢で七五三のお祝いをするメリットやデメリットは?
誕生日に合わせて七五三ができるので、数え年のように混乱することがないのがよいですよね。
では、満年齢で七五三をする場合、他にどのようなメリットやデメリットが考えられるのでしょうか。
満年齢で七五三を行うメリット
- 成長の一致
満年齢は実際の年齢と一致しているため、子どもの身体的・精神的成長が儀式に求められる行動に適していることが多いです。例えば、お参りの際に静かに振る舞うことが求められる場面で、子どもがその期待に応えやすくなります。 - 着物の着こなし
体の成長が進むにつれて、着物を美しく着こなすことができるようになります。満年齢では、子どもの体型が着物のサイズに合っていることが多く、見栄えの良い写真を残すことができるでしょう。 - 髪型の多様性
三歳の女の子の場合、髪置きの儀を行う際に、満年齢であれば髪の量も多く、様々な髪型を楽しむことができます。これは、子どもの個性を生かした記念撮影にもつながります。
満年齢で七五三を行うデメリット
- 急激な成長の変化
子どもの成長は予測が難しく、1年の違いで大きく変わることがあります。特に三歳の子どもは、日々の変化が著しく、満年齢でお祝いを行うと、赤ちゃんらしい特徴が薄れてしまう可能性があります。 - 袴や着物のサイズ問題
五歳の男の子が袴を着る際、満年齢であると体格が大きくなっている可能性があります。その結果、標準的なサイズのレンタル衣装ではサイズが合わないという問題が生じることがあります。
以下の表は、満年齢で七五三を行う際のメリットとデメリットをまとめたものです。
| 満年齢での七五三 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 成長の一致 | 行動が儀式に適している | 急激な成長による変化 |
| 着物の着こなし | 体型に合った着こなしが可能 | 赤ちゃんらしい特徴の喪失 |
| 髪型の多様性 | 個性的な髪型が楽しめる | 袴や着物のサイズ不一致 |
このように、満年齢で七五三を行うことには、子どもの成長に合わせた祝いができるという大きなメリットがありますが、一方で、成長の速さによる予期せぬ変化に対応する必要があるというデメリットもあります。
七五三をどのようにお祝いするかは、それぞれの家庭の価値観や子どもの成長具合を考慮して決めることが大切です。
数え年で七五三のお祝いをするメリットやデメリットは?
数え年とは、生まれた瞬間が0才ではなく1才とし、以後1月1日を過ぎるたびに1つずつ年齢が加算されていく年齢の数え方です。
そのため、実年齢よりも1~2才早く年をとるのが特徴となっています。
つまり、3才の七五三は数え年であれば2才で行うのが通常です。
では、数え年で七五三を行う場合には、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。
数え年での七五三のメリット
- 伝統的な祝い方への敬意
数え年でのお祝いは、日本の古来からの風習を重んじる行為です。この方法を選ぶことで、祖先が大切にしてきた文化を尊重し、子どもにもその精神を伝えることができます。 - 早めのお祝い
数え年では、実年齢よりも1~2歳早くお祝いを行います。これにより、子どもの無邪気な魅力や幼さが色濃く残る時期に記念を残すことが可能です。 - 写真での思い出作り
若干年齢が若いため、子どもの可愛らしさがより際立ちます。プロのカメラマンによる撮影では、その一瞬一瞬を美しく切り取り、家族の宝物となる写真を残すことができます。
数え年での七五三のデメリット
- 子どもの機嫌との戦い
数え年でのお祝いは、子どもがまだ小さいため、お祓いや参拝の際に気分が乗らないことが多く、予定が立てにくい側面があります。 - 昼寝との兼ね合い
若干年齢が若いため、昼寝の時間とお祝いの時間が重なると、子どもがグズる原因になり得ます。この点は、特に計画を立てる際に注意が必要です。 - 髪の毛の問題
実際には2歳で迎える数え年の3歳では、髪の量が少ない子どももいます。これに対応するため、写真館ではウィッグを用意している場合もありますが、自然な姿での撮影を望む親御さんにとっては悩ましい問題です。
表による比較
| 年齢の種類 | 七五三の年齢 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 数え年 | 2歳、4歳、6歳 | ・伝統的な祝い方 ・早めのお祝いで幼さを残す ・あどけない表情の写真撮影 |
・子どもの機嫌に左右されやすい ・昼寝の時間との調整 ・髪の量が少ない可能性 |
このように、数え年での七五三のお祝いは、伝統を重んじる意義深い行事でありながら、現代の生活リズムとの兼ね合いで様々な課題があります。
親御さんたちは、これらのメリットとデメリットを踏まえた上で、お子様にとって最も良い形でのお祝いを選択することが求められます。
七五三の時期に身内に不幸があった場合はどうする?
人生には予期せぬ出来事が起こり、喜びの時に不幸が重なることもあります。
ここでは、そんな時にどのように対処するかを、わかりやすく解説していきます。
不幸があった場合の対応
不幸とは、ここでは身内の方が亡くなられた場合を指します。
日本には古くから、死を「穢れ(けがれ)」と捉える文化があり、一定期間、神事やお祝い事を控える風習があります。
これを「忌中(きちゅう)」といい、故人との関係によって期間が異なります。
忌中の期間
| 続柄 | 忌中の期間 |
|---|---|
| 親・配偶者 | 50日 |
| 祖父母 | 30日 |
| 兄弟姉妹・子ども | 20日 |
| 親せき | 1~3日 |
この期間中は、神社への参拝や祭事を避けるのが一般的です。
七五三をどうするか
七五三は結婚式などと異なり、生命の誕生と成長を祝う行事であるため、忌中にあたっても必ずしも中止する必要はありません。
しかし、忌中の期間内に神社への参拝を予定している場合は、以下のような選択肢が考えられます。
- 忌中の期間を避けて七五三を行う: 忌中の期間が終了してから七五三のお祝いを行うことで、故人を敬いつつ子どもの成長を祝うことが可能です。
- 家族内で静かに祝う: 外出せずに家庭内で祝うことで、故人を思いやりながらも、子どもの節目を祝うことができます。
- 写真撮影のみ行う: 神社への参拝を避け、記念撮影のみを行うことも一つの方法です。後日、改めて参拝を行うことも可能です。
喪中(もちゅう)との違い
喪中は、忌中とは異なり、故人の死後一定期間(通常は一年)喪に服す期間を指します。
七五三に関しては、喪中であっても行事を行うことが一般的に受け入れられています。
七五三は、子どもたちの成長を祝うとともに、家族の絆を深める大切な行事です。
不幸があった場合でも、故人を尊重しつつ、子どもの成長を祝う方法を選ぶことが大切です。
文化や伝統を重んじながらも、柔軟に対応することで、家族の幸せを願う心は変わりません。

七五三はいつ祝う?
七五三を祝う時期は、いつからいつまでと決まっていません。
一般的には、11月15日です。
最近は、11月15日にこだわらず、10月から11月の休日など、ご家族が揃うのに都合の良い日に行われています。
また、七五三に六曜(大安や友引など)は関係ないと言われていますが、それでもやはり「大安の土・日曜・祝日」にはお参りの参拝客が集中しやすく、総本社的な大きく有名な神社ではお日柄のいい日には、境内が七五三の参拝客で埋まってしまうほどの状況になります。


七五三を祝う年齢は数え年?満年齢?のまとめ
七五三のお祝いは、子どもが無事に成長したことを祝う行事です。
満年齢でも数え年でもどちらでもおめでたいもの。
子どもの今後の成長と幸せを願い、家族みんなで素敵な思い出となるような行事にしたいですね。





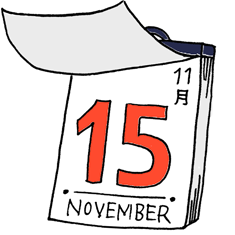


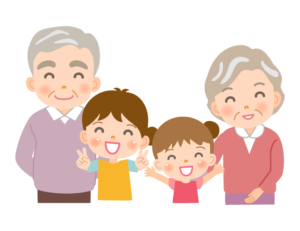



コメント