七五三は、なぜ、3歳、5歳、7歳で、お祝いなの?
七五三といったら、3歳、5歳、7歳でするのが、当然のようになっていると思いますが、なぜ、これらの歳でお祝いをするようになったのかは、ご存知でしょうか。
ここでは、その理由について説明してみようと思います。
どうしてこれらの年齢で、七五三を祝うようになったのか不思議だという人も、参考にしてもらえたらと思います。
七五三を3歳・5歳・7歳それぞれの歳で祝う意味合いは何?
七五三とは、子どもたちの成長を祝い、健やかな将来を願う日本の伝統的な行事です。
それぞれの年齢には、深い意味が込められており、古来から受け継がれる美しい風習があります。
では、この素敵な節目を、もう少し掘り下げてみましょう。
三歳 – 髪置(かみおき)の儀とは?
かつて、子どもたちは神様からの贈り物として大切に育てられてきました。
三歳になるということは、その子が無事に成長し、親としての責任を全うすることができた証とされています。
この年齢になると、子どもは「髪置の儀」を経て、これまでの坊主頭から髪を伸ばし始めることを許されます。
これは、子どもが長寿であることを願い、また、社会の一員として迎え入れる意味があります。
綿帽子をかぶせる風習は、子どもが健康で長生きすることを祈る親の愛情の表れです。
五歳 – 袴着(はかまぎ)の儀とは?
五歳の男の子にとって、袴をつけることは一つの大きな節目です。
これは「袴着の儀」と呼ばれ、子どもが社会に出ていく準備を始めるサインとされています。
袴をつけることで、男の子は「男らしさ」を身につけ、学びや社会での役割を学び始めることが期待されます。
この儀式は、子どもが周囲から一人前と認められ、自立への第一歩を踏み出す重要な瞬間を象徴しています。
七歳 – 帯解き(おびとき)の儀とは?
七歳の女の子にとって、紐を帯に変える「帯解きの儀」は、子どもから少女へと成長する過程での大切な通過儀礼です。
これまでの子ども用の着物から一歩進み、大人の女性がするような帯を結ぶことで、社会的にも女性としての自立と成熟を意味します。
この儀式は、女の子がこれからの人生で女性としての役割を果たしていくことへの期待を込めて行われます。
これらの儀式は、子どもたちの健やかな成長と幸せを願う親心から生まれた、日本の美しい伝統です。
七五三を迎える子どもたちが、これらの儀式を通じて、自分の新たなステージへの一歩を踏み出すことを祝福しましょう。
以下の表は、七五三の各儀式を簡潔にまとめたものです。
| 儀式名 | 祝い年齢 | 儀式の内容 |
|---|---|---|
| 髪置の儀 | 数え年3歳 | 子どもが髪を伸ばし始めることを許される儀式 |
| 袴着の儀 | 数え年5歳 | 男の子が初めて袴をはくことで、社会的な成長を促す儀式 |
| 帯解きの儀 | 数え年7歳 | 女の子が子ども用の紐を外し、大人の帯を結ぶことを許される儀式 |
これらの儀式を通じて、子どもたちの一生に一度の大切な節目を、家族や親戚が共に祝い、未来への願いを込めるのです。
七五三は、ただの行事ではなく、家族の絆を深め、子どもたちの心に大切な思い出として刻まれるべき日なのですね。
七五三では男の子と女の子で、お祝いをする年齢が違う
七五三とは、子どもたちの成長を祝う、日本の伝統的な行事です。
この素敵な行事には、男の子と女の子で異なる年齢の節目があり、それぞれに意味が込められています。
まず、3歳のお祝いは「髪置き」と呼ばれる儀式に由来しています。
平安時代には、この年齢で男女問わず髪を伸ばし始めることをお祝いしました。
この風習は、子どもたちの健やかな成長と長寿を願う親心から生まれたものです。
次に、5歳の男の子にとってのお祝いは「袴着」と称されます。
これは、男の子が初めて袴を身につける儀式で、一人前の男性への第一歩を象徴しています。
袴は武士の服装としても知られ、勇ましさと成長を祝う意味があります。
そして、7歳の女の子のお祝いは「帯解」と呼ばれています。
これは女の子が初めて大人の女性と同じように着物の帯を締める儀式で、女性としての美しさと礼儀を身につける大切なステップを表しています。
これらの儀式は、子どもたちが健康で文化的な成長を遂げることを願う親の愛情の表れであり、現代においてもその精神は受け継がれています。
それでは、七五三のお祝いにおける年齢ごとの意味を、表を使って分かりやすくご紹介しましょう。
| 年齢 | 性別 | 儀式の名称 | 意味合い |
|---|---|---|---|
| 3歳 | 男女共通 | 髪置き | 子どもの健やかな成長と長寿を願う |
| 5歳 | 男の子 | 袴着 | 一人前の男性への成長を祝う |
| 7歳 | 女の子 | 帯解 | 女性としての美しさと礼儀を身につける |
七五三は、ただのお祝い事以上の意味を持ち合わせています。
それは、家族の絆を深め、社会への一員としての子どもの成長を祝福する、大切な日本の風習なのです。
子どもたちの晴れ姿を見守る家族の笑顔が、これからもずっと続いていくことでしょう。
七五三は、なぜ、3歳、5歳、7歳で祝うようになったの?
七五三のお祝いは、日本の伝統的な風習として、長い歴史を持つものです。
この風習は、子どもたちの健やかな成長を祝い、またその一生の幸福を願うために行われます。
では、なぜ特に3歳、5歳、7歳の年齢でお祝いをするのでしょうか。
その背景には、古代中国から伝わる陰陽の思想が深く関わっています。
陰陽説では、宇宙のすべてのものは陰と陽で成り立っており、この二つが調和することで世界は均衡を保っているとされています。
この思想の中で、奇数は陽数とされ、何事も順調に進む縁起の良い数字として扱われてきました。
このため、奇数年齢の3歳、5歳、7歳は、特に重要な節目として認識され、お祝いの対象となったのです。
また、これらの年齢は、子どもたちの「厄年」とも重なるとされ、厄除けの意味合いも込められています。
昔の日本では、乳幼児の死亡率が非常に高く、子どもたちが無事に成長することは容易ではありませんでした。
そのため、3歳、5歳、7歳という年齢で健康に成長していることを祝い、さらなる長寿を願う意味が込められていたのです。
七歳になるということは、子どもが社会の一員として一定の自立を果たす節目ともされており、「第二の誕生」とも称されます。
この年齢になると、文字通り「腰に帯を締める」ことから「帯解(おびとき)」と呼ばれ、子どもが大人の社会に一歩を踏み出す準備を始める時期とされています。
七五三のお祝いでは、子どもたちがこれまで神様のご加護のもと、無事に成長してきたことへの感謝を表し、これからの人生が幸せでありますようにと願いを込めます。
この儀式を通じて、家族は子どもの成長を祝福し、地域社会にその喜びを分かち合うのです。
以下の表は、七五三のお祝いにおける各年齢の意味をまとめたものです。
| 年齢 | 意味合い | 儀式の内容 |
|---|---|---|
| 3歳 | 生命の定着を祝う | 髪置(かみおき)と呼ばれる儀式で、これまで髪を剃っていた習慣から髪を伸ばし始めることを意味します。 |
| 5歳 | 社会的な一員としての第一歩 | 男の子は袴(はかま)を着用し始めることで、成長を表現します。 |
| 7歳 | 自立への一歩 | 女の子は「帯解(おびとき)」と呼ばれる儀式で、自ら帯を締めることを学びます。 |
このように、七五三は単なるお祝い事以上の意味を持ち、子どもたちの一生における大切な通過儀礼となっています。
親としては、子どもの成長を見守り、その節目節目を心から祝福する大切な機会なのですね。
どうして、七五三は、11月15日に行うの?
七五三のお祝いが11月15日に行われる理由には、日本の豊かな自然観や歴史的なエピソードが織り交ぜられています。
この日は、ただの暦の一ページではなく、古来より多くの神様が集うとされる神聖な月、11月の中でも特に意味深い日とされてきました。
11月、それは「神無月」と称される時期。全国の神様が出雲大社に集結するという伝説にちなみ、神々が不在の村々では、人々が神様の目を気にすることなく、心からの感謝を捧げることができる特別な月とされています。
この月には、「新嘗祭」という、一年間の豊作に感謝し、新米を神様に捧げる儀式が行われます。
自然との共生を大切にする日本人にとって、収穫の喜びと感謝の心を神様に伝えるこの行事は、非常に重要な意味を持っています。
また、11月15日は旧暦でいう「霜月の十五夜」にあたります。
この日は、収穫した作物を神様に捧げるための祭りが盛大に行われ、人々は自然の恵みに心からの感謝を表します。
そんな感謝の気持ちが満ち溢れるこの日に、子どもたちの成長を祝う七五三を行うことは、まさに自然との調和と、先祖から受け継がれた風習を重んじる日本人の心情を象徴しています。
江戸時代にさかのぼると、天和元年(1681年)の11月15日には、将軍徳川綱吉の子、徳松の健康と長寿を願うお祝いが行われたという記録が残っており、この日が七五三の行事として定着するきっかけとなったとも伝えられています。
このような歴史的背景も、11月15日が七五三の日として選ばれる理由を強く後押ししています。
七五三で祝われる3歳、5歳、7歳という年齢には、それぞれに深い意味が込められています。
3歳は「髪置きの儀」を迎え、子どもが社会の一員として認められる第一歩を踏み出す大切な時です。
5歳の男の子は「袴着の儀」を通じて、立派な男性への成長を祝います。
そして7歳の女の子は「帯解きの儀」で、子どもから少女へと成長する節目を迎えるのです。
これらの儀式は、単に年齢を重ねたことを祝うのではなく、子どもたちが社会の中で健やかに成長していくことを願い、またそれを共同体全体で支えていくという日本の文化を色濃く反映しています。
七五三は、そんな日本の伝統と文化、自然の循環を讃え、次世代へと繋げていくための大切な行事なのです。
まとめ
七五三のお祝いには、室町時代から受け継がれている儀式が関係していることや、11月15日が七五三のお祝いとして決められている理由など、さまざまな意味が含まれているんですね。
男女においてもお祝いする年齢が異なるので注意が必要です。
七五三の由来やお祝いする意味、どのようなことをするのかを理解して、素敵な七五三をお迎えくださいね。




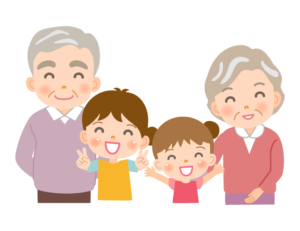


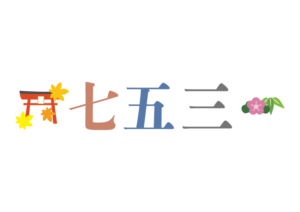


コメント