新年を迎えるにあたり、「初詣に行ってはいけない日」を知ることは、多くの方にとって重要なポイントです。
2025年の初詣では、どの日に神社や寺院を訪れるべきか、またどの時間帯が最適なのか、悩まれる方も多いでしょう。
この記事では、不成就日や受死日など、避けるべき日とその理由を詳しく解説します。
さらに、穏やかで心豊かな初詣を迎えるための最適な日や時間帯についてもご紹介。
新年の幸運を祈る初詣、どのように計画すれば良いのか、一緒に考えてみましょう。
- 初詣で避けるべき日として不成就日と受死日があること
- 2025年1月の具体的な不成就日と受死日の日付
- 忌中(四十九日中)は初詣を控えるべき理由
- 六曜を参考にして吉日を選ぶ方法
- 初詣の最適な時間帯とその理由
2025年初詣に行ってはいけない日は?

初詣において、特に避けるべき日として知られているのが「不成就日」と「受死日」です。
これらは、何事も成就しない、または大凶とされる日であり、新年の願い事をするには適していないとされています。
また、忌中(四十九日中)にあたる場合も、初詣は控えるべきとされています。
- 不成就日
- 忌中(四十九日中)
- 受死日
- 六曜
不成就日
不成就日は、十干十二支の組み合わせによって決定され、新しいことを始めるのに不向きな日とされています。
2025年1月の不成就日は以下の通りです。
- 2025年1月の不成就日: 2日(火)、10日(水)、16日(火)、24日(水)
忌中(四十九日中)
初詣は、新年を迎えるにあたり、多くの人々が神社や寺院を訪れて一年の安全や幸福を祈願する重要な行事です。
しかし、この神聖な時期には、敬遠すべき特定の期間が存在します。
それが「忌中(きちゅう)」、すなわち四十九日の期間です。
忌中とは、家族や親族が亡くなってから四十九日が経過するまでの期間を指し、この時期は故人の魂が来世へと旅立つための準備期間とされています。
伝統的な信仰によれば、この期間中は故人の魂がまだこの世に留まっており、家族との絆を保ちながら来世への道を模索していると考えられています。
そのため、生者は故人の魂が安らかに旅立てるよう、神聖な場所への訪問を控えるべきだとされています。
そのため、新年の祝い事は避けるべきとされています。
受死日
受死日は、仏滅よりもさらに縁起が悪いとされる大凶日です。
この日に始めたことが成功しない、病気になると重篤に至るなどの言い伝えがあります。2025年1月の受死日は以下の通りです。
-
- 2025年1月の受死日: 4日(木)、10日(水)、22日(月)
六曜
年の初めに行う初詣は、一年の幸運を願う重要な行事です。
そこで注目されるのが、「六曜」と呼ばれる暦の特別な日々の概念です。
六曜とは、日本の暦において、日々に割り当てられた六つのラベルであり、それぞれが特定の吉凶を象徴しています。
これらは、日常生活の様々な決定をする際の指針として用いられ、特に新年の参拝日を選ぶ際に参考にされます。
しかし、これらのラベルの意味や、それに基づいた行動の指針を理解することは、時に複雑に感じられるかもしれません。
以下に、六曜の各日が持つ意味と、それに基づく行動のガイドラインを簡潔にまとめた表を示します。
これにより、どの日が最も縁起が良いのか、または避けるべきかが一目でわかるようになります。
| 六曜 | 意味 | 推奨される活動 | 避けるべき活動 |
|---|---|---|---|
| 先勝 | 早い時間帯は吉とされる | 朝のうちに重要な仕事を始める | 午後からの新しい取り組み |
| 友引 | 吉凶が引き分けられる | 社交活動、友人との会合 | 喧嘩や訴訟の始め |
| 先負 | 早い時間帯は凶とされる | 午後からの活動開始 | 朝の重要な決断 |
| 仏滅 | 終日凶とされる | 精神的な内省、平穏な活動 | すべての新しい始まり |
| 大安 | 終日吉とされる | 結婚式や契約など、吉事 | 特になし |
| 赤口 | 昼間は凶とされる | 早朝、夕方の活動 | 正午前後の重要な行動 |
特に「仏滅」は、終日凶とされるため、新しいことを始めるのには適していないとされています。
しかし、これは必ずしも悪いことを意味するわけではありません。
仏滅の日は、内省や精神的なリフレッシュに適しているとも考えられており、静かに過ごすことで、心の平穏を得ることができるとされています。
したがって、仏滅の日に初詣をすることに躊躇する人もいるかもしれませんが、それは一年の計画を練り直し、自己と向き合う絶好の機会とも言えるのです。
新年の初詣においては、六曜を参考にしながらも、自分自身の心の声に耳を傾けることが最も重要です。
伝統的な指針はあくまでガイドラインであり、個々の直感や意志を尊重することが、新たな年を前向きにスタートさせる鍵となるでしょう。
初詣は、新年の幸運を祈る重要な日本の伝統ですが、日選びには注意が必要です。
不成就日や受死日は避け、大安のような吉日を選ぶことが推奨されます。
また、忌中にあたる場合は、故人を敬い、初詣を控えることが適切です。
これらの知識を持って初詣に臨めば、新年をより良い気持ちで迎えることができるでしょう。
初詣で避けるべき時間帯は?
一般的には、夕方以降の時間帯は避けた方が良いとされています。
これは、夕方以降には陰の気が強まり、不浄なエネルギーが溜まりやすいとされるためです。
また、夜間は視界が悪くなり、事故や犯罪に遭遇するリスクも高まります。
さらに、多くの神社仏閣では夕方に閉門するため、余裕を持って参拝することが難しくなります。
穢れ(けがれ)とは何か?
穢れとは、神道や仏教における概念で、不浄や不吉な状態を指します。
この考えに基づくと、夜間、特に暗い時間帯に神社仏閣を訪れることは、神様に対する失礼な行為とされています。
このため、穢れを避け、清らかな状態で神様に祈りを捧げるためにも、日中の明るい時間帯に参拝することが推奨されます。
現代では、これらの慣習を参考にしつつも、自分の生活スタイルや信念に合わせて初詣を行う人も多いでしょう。
大切なのは、新年を迎えるにあたって心新たに、自分なりの形で祈りを捧げることかもしれません。
初詣の最適な時期と時間帯
- 新年の三が日
- 松の内期間
- 旧正月と立春
- 初詣の時期に関する詳細情報
1. 新年の三が日
新年の最初の三日間、すなわち1月1日から3日にかけては、日本中の神社や寺院が最も活気に満ちています。
この期間は、新年の祝祭気分を存分に味わうのに最適な時です。
特に元旦の午前中は、多くの人々が新年の祝福を求めて訪れるため、混雑が予想されます。
2. 松の内期間
松の内は、新年を祝う装飾が家庭や神社に飾られる期間を指し、この時期に初詣を行うことも一般的です。
関東地方では1月7日まで、関西地方では1月15日までが一般的な松の内とされています。
三が日の賑わいが落ち着くこの時期は、静かに祈りを捧げたい方に適しています。
3. 旧正月と立春
旧正月は、太陰太陽暦に基づく伝統的な新年で、1月末から2月初旬にかけて祝われます。
また、立春は二十四節気の中で春の始まりを告げる日で、節分の翌日に当たります。
これらの日は、新年の祝賀が落ち着いた後の初詣にも適しており、混雑を避けたい方には特におすすめです。
初詣の時期に関する詳細情報
| 時期 | 概要 | 日付 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 三が日 | 新年の最初の三日間 | 1月1日 – 1月3日 | 新年の祝祭気分を味わえる |
| 松の内 | 新年の装飾が飾られる期間 | 関東: 1月7日まで 関西: 1月15日まで |
静かに祈りを捧げたい方に |
| 旧正月 | 太陰太陽暦に基づく新年 | 1月末 – 2月初旬 | 日にちが毎年異なる |
| 立春 | 春の始まりを告げる節気 | 節分の翌日、2月4日が多い | 新年の祝賀が落ち着いた後 |
2025年においては、旧正月は2月10日、立春は2月4日となります。
これらの日付を目安に初詣を計画することで、新年の賑わいを避けつつ、心静かに新年の祈りを捧げることができるでしょう。
初詣は、単に神社や寺院を訪れる行為以上の意味を持ちます。
それは新しい年への希望、家族や友人との絆を祝う時間、そして心新たに自己を見つめ直す機会を提供してくれるのです。
あなたがどの時期を選ぶにせよ、初詣は新年の素晴らしいスタートとなるでしょう。
2025年の初詣に最適な日を選ぶためのガイド

新年を迎えるにあたり、多くの方が心新たに初詣を計画されていることでしょう。
しかし、ただ単に神社を訪れるだけではなく、特定の日に参拝することで、その年の運気をより良くするという考え方が日本には存在します。
これらの日は「吉日」と呼ばれ、それぞれに特別な意味が込められています。
以下に、2025年1月における吉日とその意味を詳細に解説し、どの日が初詣に最適かを考察します。
- 吉日とは?
- 2025年1月の初詣に適した日
吉日とは?
吉日とは、伝統的な暦の上で特に縁起が良いとされる日のことを指します。
以下に、主な吉日とその意味を表にまとめました。
| 吉日の名称 | 意味 |
|---|---|
| 一粒万倍日 | 新しい事業や計画を始めるのに適した日で、始めたことが大きく育つとされる |
| 天赦日 | どんな行動をとっても成功するとされる、最も縁起の良い日 |
| 甲子の日 | 六十干支の最初に位置する日で、新たな始まりに適している |
| 寅の日と巳の日 | 金運が上昇するとされる日 |
| 鬼宿日 | 二十八宿の中で最も縁起が良いとされる日で、結婚式などの慶事に適している |
| 天恩日 | 特に婚礼に良いとされる吉日 |
| 大安 | 六曜の中で最も縁起が良いとされる日 |
2025年1月の初詣に適した日
2025年1月には、以下のような吉日があります。
- 1月1日: 元旦は伝統的に厄除けに良いとされていますが、2025年の元旦は一粒万倍日、天赦日、甲子の日、天恩日、そして三が日が重なる非常に縁起の良い日です。
- 1月3日: 三が日の中で、寅の日と天恩日が重なる吉日です。
- 1月5日: 鬼宿日と天恩日が重なります。
- 1月16日: 大安と天恩日、一粒万倍日が重なるものの、不成就日という要素も含まれているため、完全な吉日とは言えないかもしれません。
初詣の際のマナー

初詣は、新年を迎える日本の伝統的な行事であり、多くの人々が神社を訪れて一年の安全と繁栄を祈願します。
この特別な時期には、神聖な場所である神社に対する敬意を表すために、いくつかのエチケットが存在します。
以下では、初詣での参拝時に心がけるべきマナーやルールを、より詳細に解説し、初詣の美しい伝統を守り、心豊かな体験をするための指針を提供します。
- 鳥居を通過する際の礼儀
- 参拝時の服装選び
- 初詣での服装ガイド
鳥居を通過する際の礼儀
鳥居は、神聖な空間と俗世を分けるシンボルとして、神社の入口に設置されています。
この門をくぐる際には、以下のステップに従って礼儀正しく行動しましょう。
- 鳥居の前で一礼:鳥居の前に立ち、静かに一礼をすることで、神域に入る許可を求めると同時に、神様への敬意を表します。
- 鳥居の通過:複数の鳥居がある場合は、最初の鳥居「一の鳥居」から順番に通過します。この際、参道の中央を避け、左右の端を歩くことが望ましいです。中央は神様が通る道とされ、「正中」と呼ばれているためです。
- 退場時の一礼:参拝後、神社を離れる際には、再び社殿に向かって一礼をし、感謝の意を示しましょう。
参拝時の服装選び
初詣では、服装に特別な規定はありませんが、以下の点を考慮して選ぶことが推奨されます。
- 清潔感のある服装:清潔感があり、整った服装を心がけることで、神様への敬意を示すことができます。
- 控えめなスタイル:派手過ぎず、落ち着いた色合いの服を選びましょう。伝統的な和服を着用するのも良いでしょう。
- 季節に合わせた装い:寒い時期の初詣では、防寒対策を忘れずに。しかし、過度にカジュアルなアウターやアクセサリーは避けるべきです。
初詣での服装ガイド
| 推奨される服装 | 避けるべき服装 |
|---|---|
| 清潔で整った服 | 汚れたり乱れたりした服 |
| 落ち着いた色合い | 派手な色や大きなロゴ |
| 季節に合わせた防寒服 | 過度にカジュアルなアウター |
| 伝統的な和服(可能であれば) | 短すぎるスカートや露出の多い服 |
初詣は単なる年始の行事ではなく、日本の文化と精神性を象徴する重要な習慣です。
上記のエチケットを守ることで、神聖な場所である神社に対する敬意を示し、新年の祝福を受ける準備を整えることができます。
参拝は心を込めて行うものであり、これらのマナーはその心を形にするものです。初詣での行動一つ一つに意味があり、それを理解し実践することで、より充実した体験ができるでしょう。
初詣に行ってはいけない日や時間帯は?のまとめ
初詣は新年を祝う大切な日本の伝統ですが、日選びには注意が必要です。
特に避けるべき日は「不成就日」と「受死日」。
これらは何事も上手くいかない、または大凶とされる日です。
また、忌中(四十九日中)には初詣を控えましょう。
六曜にも注意して、吉日を選ぶことがおすすめです。
穏やかな新年を迎えるために、これらの日を避けて初詣に出かけてみてはいかがでしょうか。
この記事のポイントをまとめますと
- 初詣は新年を祝う日本の伝統的な行事
- 特に避けるべき日は不成就日と受死日
- 不成就日は何事も成就しない日
- 受死日は大凶とされる日
- 忌中(四十九日中)は初詣を控えるべき
- 六曜を参考に吉日を選ぶことが推奨される
- 夕方以降の時間帯は避けた方が良い
- 穢れとは不浄や不吉な状態を指す
- 初詣の最適な時期は新年の三が日や松の内期間
- 旧正月や立春も初詣に適した時期




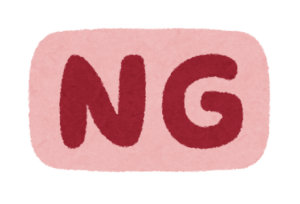






コメント