季節によって違う雨の名前と種類!
雨が降ると、通勤通学に支障が出たり、洗濯物が干せない、外出が減る、傘を持ち歩くのが面倒など、何かとネガティブな気持ちになることが多いですよね。
雨が降るとどこかで自分の代わりに誰かが泣いている・・なんて歌もあった気がします。
とにかく、なんとなく淋しい気持ちになってしまうのが雨ではないでしょうか。
しかし、雨は生活する上では欠かせない貴重な水源です。
特に昔は水を溜めておくには限界があったため、農家の方々にとってはまさに恵みの雨だったと言えます。
そんな雨には、実はいくつも名前や種類があることをご存知でしたか?
また、季節によって呼び名が違う場合もあるのです。
そこで今回は、知っているようであまり知られていない、雨の様々な種類や名前について調べてみました。
日本人と雨の関係
日本の風土や文化に深く根差した「雨」という存在、その魅力について、少し詳しくお話ししましょう。
日本の気候と雨
これは、四季がはっきりしており、特に雨が多いことが特徴です。
世界的に見ても、日本の降水量は多い方に入ります。
この豊かな雨量が、日本の自然や文化に大きな影響を与えているんですよ。
雨と日本人の生活
昔から日本人にとって、雨は非常に身近な存在でした。
農業が盛んな日本では、雨は作物を育てるための恵みとして受け入れられてきました。
しかし、一方で、生活においては雨が原因で不便を感じることも少なくありませんでした。
そんな中でも、日本人は雨を独特の視点で捉え、様々な名前をつけてその変化を楽しんできたのです。
雨の名前の多様性
日本では、雨には400以上の名前があると言われています。
これは、先人たちが雨を細かく観察し、その特徴や降り方、季節ごとの変化に応じて名前をつけてきた結果です。
例えば、「霧雨(きりさめ)」、「夕立(ゆうだち)」、「五月雨(さみだれ)」など、それぞれの雨には独特の特徴があります。
今回はそんな雨の種類や名前を、季節ごとに詳しくご紹介したいと思います。
春の雨の種類と名前
春の訪れと共に、私たちの心もウキウキと躍るような気持ちになりますよね。
新しい生活の始まりを告げる入学式や入社式など、春は新たなスタートを切る季節。
しかし、春の雨が降ると、なんだか心が少し沈んでしまうこともあります。
そんな春の雨には、実は様々な名前が付けられていて、それぞれに特徴があるんですよ。
霧雨(きりさめ)
春の訪れと共に現れる「霧雨」は、まるで霧のような繊細さを持っています。
この細かい雨粒は、植物にとってはまさに恵みの雨。新しい命を育む春の芽吹きを優しくサポートします。
人々にとっても、霧雨は心を穏やかにし、新しい季節の始まりを感じさせる優しい雨。
霧雨の中を歩くとき、その柔らかな雨粒が肌に触れる感覚は、まるで自然からの優しい抱擁のようです。
桜雨(さくらあめ)
春の代表的な景色といえば、桜ですよね。桜が美しく咲き誇る3月下旬から4月上旬にかけて降る雨を「桜雨」と呼びます。
桜の花びらが雨に濡れて、より一層風情を感じさせてくれるんです。
春時雨(はるしぐれ)
春に降る雨の中でも、特に「降ったり止んだり」を繰り返す雨を「春時雨」と言います。
春の日差しと雨の織りなす風景は、なんとも言えない趣がありますね。
花時雨(はなしぐれ)
桜の季節に降る「春時雨」を特に「花時雨」と呼びます。
桜の花と雨が織りなす風景は、春ならではの美しさを演出してくれます。
春霖(しゅんりん)
3月から4月にかけて、天気が不安定になりやすい時期に降る雨を「春霖」と言います。
この時期の雨は、春の長雨とも呼ばれ、春の訪れを感じさせてくれます。
菜種梅雨(なたねづゆ)
関東地方より西で、3月下旬から4月上旬にかけて見られる天気の崩れ方を「菜種梅雨」と呼びます。
この時期に降る雨は、菜の花の種まきに適した時期であることからこの名前がつけられました。
春雨(はるさめ)
春雨は、3月下旬から4月にかけて、静かにしとしとと降る雨のことを指します。
春雨は、穏やかで心地よい雨音を奏で、春の訪れを優しく告げてくれます。
春の雨にはそれぞれに名前があり、その名前には日本の四季を感じさせる風情が込められています。
春の雨の名前を知ることで、雨の日も少し違った楽しみ方ができるかもしれませんね。
梅雨の雨の種類と名前
梅雨の季節、それは日本の風物詩のひとつですよね。
湿気が高く、じめじめとした空気が漂うこの時期は、少し憂鬱になることもありますが、その一方で、梅雨特有の雨の名前には、日本の自然や文化に根差した美しい言葉が多く存在します。
今日は、そんな梅雨の雨の種類と名前について、少し詳しくお話ししましょう。
五月雨(さみだれ)
「五月雨」とは、文字通り旧暦の5月、つまり現在の6月頃に降る雨を指します。
この言葉は、梅雨の代名詞のような存在です。昔の人々は、この時期に降る雨を「さみだれ」と呼び、自然の恵みとして受け入れていました。
この雨がもたらす恵みによって、田畑は潤い、作物は育ちます。
入梅(にゅうばい)
「入梅」とは、梅雨の始まりを告げる言葉です。
梅の実が熟し始めるこの時期に雨が降り始めることから、このように呼ばれるようになりました。
入梅の時期は、地域によって異なりますが、一般的には6月初旬から中旬にかけてとされています。
走り梅雨、迎え梅雨
「走り梅雨」や「迎え梅雨」とは、梅雨入り前の5月中旬から下旬にかけての、不安定な天気を指す言葉です。
この時期は、本格的な梅雨に入る前の、いわば前触れのような時期です。
送り梅雨(おくりばい)
「送り梅雨」とは、梅雨明けを控えた時期に降る雨のことを言います。
この雨が過ぎ去ると、いよいよ夏が本格的に始まることを意味しています。
戻り梅雨(もどりばい)
「戻り梅雨」とは、梅雨が明けたと思ったら、再び雨が降り始める現象を指します。
この時期の雨は、しばしば夏の暑さを和らげる役割を果たします。
卯の花腐し(うのはなくだし)
「卯の花腐し」とは、旧暦の4月から5月にかけて降る雨のことを言います。
この時期は、卯月(うづき)と呼ばれ、卯の花(エニシダなど)が咲く季節です。
しかし、この雨によって花が傷んでしまうことから、この名前がつけられました。
梅雨の雨には、それぞれに意味が込められ、日本の四季を象徴する美しい名前が付けられています。
このような雨の名前を知ることで、梅雨の時期も少し楽しく感じられるかもしれませんね。
夏の雨の種類と名前

夏は、それまで快晴だったのが突然猛烈な雨に襲われるイメージが強い時期ではないでしょうか。
ちなみに、よく使われる「夕立」は、夏に降る雨の呼び名です。
この他にも、日本古来の伝説にちなんだ雨の名前も存在します。
その日に降った雨は、もしかしたら天から降り注ぐ涙かも知れないなんて、ちょっとロマンチックな気持ちになりますよね。
夕立(ゆうだち)
夏の夕方、突然空が暗くなり、雷を伴って激しく降り注ぐ雨を「夕立」と呼びます。
この夕立は、まるで一日の疲れを洗い流すかのように、短時間で激しく降り、そしてすぐに止むのが特徴です。
夕立が過ぎ去った後には、清々しい空気が広がり、夏の夜の訪れを感じさせてくれます。
翆雨(すいう)・緑雨(りょくう)
初夏、新緑が眩しい季節に降る雨を「翆雨」または「緑雨」と言います。
木々や草花が雨に濡れ、一層鮮やかな緑色に輝く様子は、まさに自然の美しさを象徴しています。
この雨は、新しい季節の始まりを告げ、生命の息吹を感じさせてくれる特別な雨です。
半夏雨(はんげさめ)
夏至から11日後、半夏生(はんげしょう)の頃に降る雨を「半夏雨」と呼びます。
この時期は、田植えが終わり、稲が成長する大切な時。
農作物にとって恵みの雨となり、豊作を願う農家の人々にとっては、まさに待ち望んだ雨なのです。
洗車雨(せんしゃあめ)
7月6日に降る雨を「洗車雨」と言います。
この名前は、七夕伝説に登場する織姫と彦星が会うために乗る牛車を洗う水にちなんでいます。
この雨は、二人の再会を祝福するかのように、優しく降り注ぎます。
酒涙雨(さいるいう)
そして、7月7日の七夕に降る雨は「酒涙雨」と呼ばれます。
織姫と彦星が年に一度の再会を果たした後、再び離れ離れになる切なさを、涙に例えた名前です。
この雨は、愛し合う二人の深い絆と、切ない想いを象徴しています。
これらの雨の名前は、日本の自然や文化、伝説に深く根ざしており、それぞれが独特の物語性を持っています。
夏の雨に耳を傾け、その名前の由来を思い浮かべると、雨音がさらに心地よく感じられるかもしれませんね。
秋雨の種類と名前
気温が安定している時期なので外へ出かけたい気持ちを家の中で抑えているのも、なかなか根気がいりますよね。
しかし、秋の長雨が過ぎると季節は本格的に冬へと移行します。
このように、雨は季節の節目に降ることも多く、一雨ごとに次の季節へと近づいていきます。
秋雨(あきさめ)
秋雨は、夏の終わりから秋の深まりにかけての期間、具体的には8月下旬から10月にかけて見られる長雨のことを指します。
この時期、日本は高気圧に覆われ、湿った空気が長く留まるため、じっとりとした雨が続くのが特徴です。
秋雨は、ただ憂鬱な雨ではなく、稲穂の成長を助ける大切な役割も担っています。
また、この雨が過ぎ去ると、空気が澄み渡り、秋の深まりを感じさせる美しい景色が広がります。
秋入梅(あきついり)
秋入梅は、秋の長雨が始まる時期を指す言葉です。
梅雨と聞くと、多くの方が初夏を思い浮かべるかもしれませんが、秋にも梅雨を思わせるような雨があるんです。
秋入梅は、9月中旬から10月初旬にかけての約1ヶ月間ほどが、秋の長雨に入る期間ということです。
長雨(ながあめ)
秋の終わりに訪れる「長雨」は、じっくりと時間をかけて自然に恵みをもたらします。
この連続する雨音は、まるで季節の移ろいを告げるメロディー。
長雨は、自然界にとってはゆっくりとした水分補給の時間。
木々や草花にとっては、冬に備える大切な時期です。
私たち人間にとっては、この長雨の期間は、内省や心を落ち着かせるのに最適な時。
窓の外を見ながら、温かい飲み物を手に、ゆったりとした時間を過ごすのにぴったりです。
秋の雨は、時には憂鬱な気分をもたらすかもしれませんが、自然のリズムに身を委ねることで、心の中にも新しい季節の訪れを感じることができます。
窓の外を見ながら、一杯の温かいお茶を楽しむ時間は、秋の雨ならではの贅沢かもしれません。
また、雨上がりの清々しい空気や、雨に濡れた紅葉は、秋の風情を一層引き立ててくれます。
冬の雨の種類と名前
冬の季節には、雪だけでなく、さまざまな種類の雨が私たちの日常に訪れます。
この季節特有の雨は、その美しさとともに、時には厳しい寒さをもたらすことがあります。
今日は、そんな冬の雨の種類とその名前について、少し詳しくお話ししましょう。
時雨(しぐれ)
「時雨」とは、秋の終わりから冬の始まりにかけて見られる、一時的なにわか雨のことを指します。
この雨は、まるで季節の変わり目を告げるかのように、ふと降り出してはすぐに止む、という特徴があります。
冬の訪れを感じさせる、しっとりとした雨ですね。
山茶花梅雨(さざんかづゆ)
この雨は、名前の通り、山茶花が美しく咲く11月下旬から12月上旬にかけて降る雨です。
この時期は、まだ本格的な冬の寒さには至っていないため、雨も比較的穏やかで、冬の訪れを優しく感じさせてくれます。
氷雨(ひさめ、ひあめ)
氷雨は、晩秋から初冬にかけて降る、氷の粒が混じった冷たい雨です。
この雨は、空気中の水滴が凍ることで生じ、まるで小さな氷の粒が降ってくるような感覚を覚えます。
冬の寒さが本格化する前触れとも言えるでしょう。
凍雨(とうう)
凍雨は、文字通り氷が雨のように降る現象です。
特に、雪が雨に変わる瞬間によく見られます。
この雨は、地面に触れると凍ることが多く、外出時には滑りやすくなるので注意が必要です。
村時雨(むらしぐれ)
村時雨は、一時的に強く降る雨を指します。
この雨は、ある地域に集中して短時間に降り注ぎ、その後はすぐに止むという特徴があります。
まるで、雨がその地域を訪れては去っていくような、移り変わりの速さが特徴です。
寒雨(かんう)
寒雨は、その名の通り、冬の時期に降る冷たい雨を指します。
この雨は、冬の寒さをより一層感じさせるもので、外出時にはしっかりと防寒対策をすることが大切です。
霙(みぞれ)
冬の寒空の下、私たちの頬を優しく撫でるのが「霙」です。
この独特の降水現象は、雨と雪が混じり合ったような、まるで冬の魔法のようなもの。
空から舞い降りる小さな氷の粒は、雪ではなく、雨でもない、まさにその中間。
冬の寒さが深まる中、この霙は季節の変わり目を教えてくれる特別なサイン。
冬の寒さを和らげるような、ほんのりとした温もりを感じさせてくれます。
これらの冬の雨は、それぞれに独特の美しさと厳しさを持っています。
冬の寒さに負けず、これらの雨を楽しむことで、季節の移り変わりをより深く感じることができるでしょう。
お出かけの際は、適切な服装でこの冬の雨に備えてくださいね。
番外編:恵みの雨の種類と名前

雨には外出が不便になる、洗濯や買い物などの家事ができないといった、悪いイメージを持つ方も多いですが、一方で雨が降らないと農作物の成長に影響が出てしまうことになります。
特に夏の暑い時期は、日照りによる植物や穀物のダメージが懸念されることから、雨は私達にとっても恵みであると言えるでしょう。
ここでは、恵みの雨に関する名前をご紹介したいと思います。
穀雨(こくう)
春の終わりごろ、種まきや田植えの時期に降る雨を「穀雨」と呼びます。
この名前、実は二十四節気の一つでもあるんですよ。
昔の人は、この穀雨を待って農作業を始めたと言われています。
春の優しい雨が、種や苗にとってはまさに生命の水。
穀物が健やかに育つための大切な時期なんですね。
瑞雨(ずいう)
夏になると、植物たちは日差しをいっぱい浴びて大きく成長します。
でも、暑さが厳しいと水分が不足しがち。
そんな時に降る雨が「瑞雨」。
穀物の成長を助ける、まさに恵みの雨です。
甘雨(かんう)
「甘雨」は、タイミングが良い時期に降る雨のこと。
植物や穀物にとって、ちょうど良いタイミングで潤いを与え、成長を促してくれるんです。
まるで自然が計算してくれたかのような、絶妙なタイミングの雨なんですよ。
喜雨(きう)
夏、日照りが続くと、植物たちは水分不足に悩まされます。
そんな時に降る雨が「喜雨」。
まさに植物たちが喜ぶ雨ですね。
この雨があるおかげで、農作物は乾燥から救われるんです。
慈雨(じう)
「慈雨」もまた、日照りが続いた時に降る雨。
植物や穀物にとって、まるで慈しみのように潤いを与えてくれます。
この雨があるからこそ、植物たちは乾燥から守られ、健やかに成長できるんですね。
雨の日はちょっと憂鬱かもしれませんが、こんなにも大切な役割を果たしているんですね。
次に雨が降ったら、ちょっと違った目で見てみるのもいいかもしれませんね。
雨の種類と名前のまとめ
雨には降る季節や降り方によって様々な名前があることがわかりました。
これらを全て区別することは難しいですが、名前があることを知るだけでも、雨をこれよりもずっと身近に感じるのではないでしょうか。
日本は他の国に比べ、降水量が2倍近くも多い、言わば雨大国。
雨を避けずには暮らしていけないのであれば、少しでも明るい気持ちで迎えられるといいですよね。






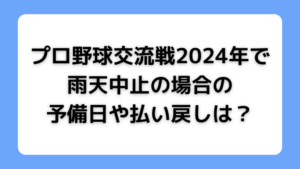






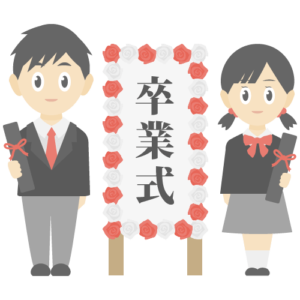
コメント