「入梅」と「梅雨」はどちらも雨の季節に関連しているけど、ちょっと違うんです。
この違いがわからないと、カレンダーを見て「入梅って書いてあるけど、梅雨入りはまだ?」と混乱しちゃいますよね。
実は、入梅と梅雨の違いを知ると、日本の季節の移り変わりがもっとわかりやすくなります。
この記事では、入梅と梅雨の違いを詳しく説明して、季節の楽しみ方や役立つ情報をお伝えします。
さっそく読んでみましょう!
- 入梅と梅雨の違いがわかります
- 入梅の意味と由来がわかります
- 梅雨の季節の特徴がわかります
- 入梅いわしについて知ることができます
入梅と梅雨の違いは?
入梅とは?
入梅は雑節の一つで、「にゅうばい」と読みます。
入梅(にゅうばい)とは、雑節のひとつで「暦の上で梅雨が始まるとされている日」のこと。
昔は暦の上の入梅を知ることで、梅雨に入るおおよその時期を見極め、農作業の目安にしていたと言われています。
また、入梅には、梅の実が熟す時期、梅雨に入る時期という意味があります。
しかし実際の梅雨入りは地域や年によって差があるため、現在では気象庁の発表する「梅雨入り宣言」が実際の梅雨入りの目安になっています。
雑節については後に詳しくご紹介していますが、雑節は知らなくても節分や彼岸なら知っているという方は多いのではないかと思います。
節分も彼岸も雑節の一種なので、入梅とは仲間と言うことになります。
梅雨とは?
梅雨(つゆ)は、日本特有の季節のひとつです。
春が終わり、夏が始まるころに、雨や曇りの日が多くなるんです。
梅雨のことを知ると、日本の自然や文化についても深く理解できますよ。
まず、「梅雨」という言葉について説明します。
「梅雨」とは、漢字で「梅の雨」と書きます。
これは、梅の実が熟す時期にたくさん雨が降ることから来ています。
昔から日本では、この時期に梅の実が美味しくなるとされていて、特別な季節として大切にしてきました。
もうひとつの「梅雨」の漢字の書き方には「黴雨(ばいう)」があります。
この「黴(かび)」は、湿気が多くなるとカビが生えやすくなることを意味しています。
だから、梅雨の時期は湿気対策がとても大切なんです。
そして、「梅雨」を「つゆ」と読むのは、雨の「露(つゆ)」から来ています。
植物にとって雨は恵みなので、この読み方はとてもぴったりなんです。
日本の農業でも、この時期の雨は作物が成長するためにとても大事なんです。
また、梅雨の始まりを指す言葉に「栗花落(ついり)」があります。
これは、栗の花が落ちるころに梅雨が始まることを表しています。
自然のサイクルと深く関わっている日本の季節感をよく表していますね。
梅雨の時期は、雨が多く湿度が高くなります。
だから、家の中の湿気対策が必要です。一方で、この時期の雨は自然の恵みでもあります。
梅雨をよく知ることは、日本の自然や文化をもっと深く理解するための大切なステップになります。
入梅と梅雨入りの違い
たとえば、カレンダーに6月10日が入梅と書かれていても、その日に必ず梅雨が始まるわけではありません。
でも、気象庁が「梅雨入り」と発表した場合は、その日から梅雨が始まるのが確実です。
ただし、梅雨入りの発表は、具体的な気象条件(きしょうじょうけん)があるわけではありません。
毎日雨や曇りの日が続いて、これからも雨が多い日が続きそうなときに発表されることが多いです。
そのため、梅雨入りの後に天気が予想外に晴れることもあります。
| 項目 | 入梅 | 梅雨入り |
|---|---|---|
| 決め方 | 太陽黄経に基づく | 気象データに基づく |
| 発表者 | 暦の専門家 | 気象庁 |
| 確実性 | 日にちが決まっている | 気象データにより確実 |
| 天気予報 | 必ずしも雨ではない | 梅雨が始まるとほぼ確実に雨や曇りが多い |
このように、入梅と梅雨入りは似ているようで違う点がたくさんあります。
分かりやすく説明しましたので、これで違いがはっきりと理解できると思います。
2025年の入梅はいつ?
2025年は、6月11日(水)です。
この日からおよそ30日間(7月10日頃まで)が梅雨の時期ということになります。
入梅は、元々は二十四節気の「芒種」が過ぎてから最初に訪れる壬(みずのえ)の日とされていましたが、現在は太陽黄経が80度になる日を入梅としています。
参照URL: 国立天文台 令和7年(2025年)暦要項
入梅の由来
「入梅」という言葉、一体どこから来たのでしょうか。
実は、この言葉には興味深い背景があるんですよ。
まず、一つ目の説は、中国の暦に由来しています。
中国では古くから、梅の実が熟す時期に降る雨を「梅雨」と呼んでいました。
この時期は、日本で言う6月ごろにあたり、ちょうど梅干しや梅酒を作り始める時期と重なります。
農業にとっても重要なこの時期、雨が多く降ることから「入梅」という言葉が生まれたとされています。
日本においても、この時期は稲作にとって重要な水源となるため、農業との深い関連が感じられますね。
もう一つの説は、少し風流な解釈が含まれています。
梅雨の時期は湿気が多く、カビが生えやすい環境になります。
この「カビ」を表す漢字「黴」は、読み方が「バイ」と同じです。
しかし、「黴雨」という言葉はあまり良い印象を与えませんよね。
そこで、同じ「バイ」と読む「梅」に言葉を変えたという説があります。
実際に梅雨の時期には、クローゼットや食品にカビが生えることがよくあります。
このように、少し嫌なことを風流な言葉に置き換えるのは、日本の文化にもよく見られる特徴です。
どちらの説も、日本の自然や文化と深く結びついていることがわかります。
梅雨の時期はジメジメとして不快に感じることも多いですが、このような背景を知ると、少し違った視点で季節を楽しむことができるかもしれませんね。
入梅いわし
梅雨の訪れと共に、日本の食卓にも季節の変わり目が訪れます。
特に注目されるのが、「入梅いわし」と呼ばれるマイワシです。
この時期に水揚げされるマイワシは、まさに旬の味覚を楽しむための逸品。
日本では、いわしといえば主にマイワシ、ウルメイワシ、カタクチイワシの3種類が知られていますが、入梅いわしはその中でもマイワシに限定されます。
6月から7月にかけての梅雨入りの時期に捕れるマイワシは、産卵前で栄養を蓄えているため、脂がたっぷりとのっていて非常に美味。
この時期のマイワシは、1年の中でも特に脂の乗りが良く、その味わいは格別です。
鮮度が命のマイワシは、新鮮なうちに味わうことが大切。
特におすすめの食べ方は、お刺身です。三枚におろしたマイワシのお刺身は、そのままでも、少しの薬味と共にいただくと、その深い味わいと豊かな脂の旨味が口いっぱいに広がります。
また、入梅いわしは、栄養価も高く、健康にも良い食材として注目されています。
豊富なオメガ3脂肪酸は心臓病のリスクを減らす効果があるとされ、ビタミンDやカルシウムも豊富に含まれています。
これらの栄養素は、骨の健康を支えるだけでなく、免疫力の向上にも役立ちます。
梅雨の季節は、じめじめとした天気に気分も沈みがちですが、入梅いわしを味わうことで、少しでもその憂鬱を吹き飛ばし、日本の美味しい季節を楽しんでみてはいかがでしょうか。
「入梅の候」とは?読み方は?意味は何?
入梅の候は、「にゅうばいのこう」と読みます。
入梅の候は、手紙やはがきを書く際に時候の挨拶に使う言葉です。
時候の挨拶とは、天候などに応じた季節感や心情を表す言葉で、拝啓などの頭語の後に続ける文章となります。
友達などに気軽に出す手紙やはがきには使うことは少ないかも知れませんが、ビジネスシーンでは時候の挨拶が必要不可欠となるケースが多くあります。
いざ使う時になって、よくわからない・・となってしまう前に、常識として覚えておくのがよいですよね。
なお、入梅の候に関しては、北海道在住の方に送る場合は使用はできません。
なぜなら、北海道には梅雨がないと言われているからです。
そのため、北海道に本社がある取引先や恩師などに手紙やはがきを送る時は、例え入梅の時期であっても入梅の候を使わないようにしましょう。
入梅の時期に使える時候の挨拶には、「初夏の候」や「梅雨の候」「長雨の候」などがあります。

入梅の候の時期はいつからいつまで使えるの?
時候の挨拶は、入梅の候だけではなく、二十四節気の節気ごとに存在します。
そして、節気の期間に伴って使用する事項の挨拶が変わります。
例えば、2025年の立春は2月3日、次の雨水が2月19日となっているのですが、立春の候は立春となる2月3日から雨水となる前日までの2月18日まで、雨水の候は2月19日から次の節気である啓蟄が3月6日なので、3月4日まで使うことができます。
ただし入梅の場合、二十四節気のように次の節気があるわけではありません。
そのため、明確にいつからいつまで使えるという期間が決まってはいません。
また、入梅に対して梅雨が明けることを「出梅(しゅつばい)」と言います。
出梅は夏至の後の最初の庚(かのえ)の日と言われていますが、入梅の候は出梅の頃まで使用できません。
なぜなら、入梅には梅雨の入る時期という意味があるからです。
このようなことから、入梅の候は一般的に 6月の上旬から中旬頃まで使える時候の挨拶となっています。
「入梅の候」の使い方を事例を踏まえて教えて!
入梅の候を使った、手紙やはがきの書き方をご紹介したいと思います。
入梅の候に限らず、時候の挨拶を使う場合には、基本的には「頭語」+「時候の挨拶」+「健康などを気遣う言葉」がセットになります。
頭語は拝啓や謹啓などの言葉で、これらを使う場合は最後は必ず結語(敬具、かしこなど)を使うのも忘れずにしましょう。
それでは、入梅の候を使った例文をご紹介します。
●拝啓 入梅の候、貴社におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
●拝啓 入梅の候、皆様方は益々ご活躍の事と存じ上げ申します。
●拝啓 入梅の候、ぐずついた天気が続いていますが、お元気でお過ごしでしょうか。
また、入梅の候ではありませんが、入梅の時期にも関わらず梅雨になっていない時は、「入梅とは言うものの、天候に恵まれ、今年は空梅雨になりそうですがいかがお過ごしですか?」のような使い方もできます。
入梅と梅雨の違いのまとめ
入梅(にゅうばい)と梅雨(つゆ)は似ているけど、実はちょっと違うんです。入梅はカレンダーに書いてある日で、昔からこの日くらいに梅雨が始まるよ、と予想するためのものです。2025年は6月10日が入梅です。一方、梅雨入りは気象庁が発表するもので、実際に梅雨が始まった日を指します。だから、カレンダーに入梅と書いてあっても、必ずその日に梅雨が始まるわけじゃないんです。梅雨入りは毎日の天気を見て決まるので、少し違うんですね。
この記事のポイントをまとめますと
- 入梅は「にゅうばい」と読む
- 入梅は暦の上で梅雨が始まるとされる日を指す
- 梅雨入りは気象庁が発表する実際の梅雨の開始日を指す
- 2025年の入梅は6月10日
- 入梅と梅雨入りは意味が異なる
- 入梅は雑節の一つである
- 梅雨入りは気象データに基づいて決定される
- 入梅は太陽黄経が80度になる日で決まる
- 梅雨は春の終わりから夏の始まりにかけての雨季である
- 入梅は梅雨入りの予測日である
- 梅雨入りは実際の天候に基づく
- 入梅は農作業の目安として使われてきた
- 入梅の候という時候の挨拶がある
- 入梅と梅雨入りは必ずしも同じ日ではない
- 入梅いわしは梅雨の時期に旬のマイワシである
- 梅雨は日本の風土に根付いた現象である
- 梅雨の時期は梅の実が熟す時期である
- 入梅は中国の暦に由来する








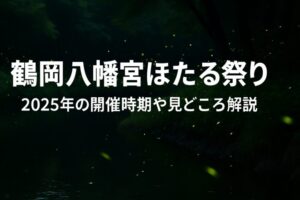



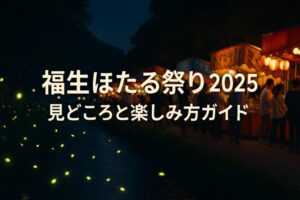

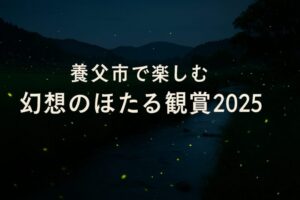

コメント