夏至は毎年変わるって本当?2025年の夏至はいつなんだろう?
と疑問に思っている人は多いのではないでしょうか。
夏至とは、一年で昼の長さが一番長い日を指し、日本では古くから大切にされてきた日です。
でも、毎年夏至の日が変わるのはなぜか、その意味は何か、気になるところですよね。
さらに、夏至の時期に旬の食べ物や風習も知りたいところです。
この記事では、2025年の夏至の日や、その意味、そしておすすめの食べ物について、わかりやすく紹介します。
- 2025年の夏至がいつかがわかります。
- 夏至の日が毎年変わる理由がわかります。
- 夏至の意味とその日照時間の長さがわかります。
- 夏至に食べるとよい旬の食べ物や各地の風習がわかります。
夏至の日は毎年変わる!
夏至の日は天体の動きに合わせて決まるので、毎年同じ日ではありません。
でも、毎年だいたい6月20日、21日、22日のどれかになります。
この日付が決まるのには、地球の「地軸の傾き」と「公転」、そして多くの国で使われている「太陽暦」が関係しています。
具体的には、次のような感じです。
| 年 | 夏至の日 |
|---|---|
| 2019 | 6月22日 |
| 2020 | 6月21日 |
| 2021 | 6月21日 |
| 2022 | 6月21日 |
| 2023 | 6月21日 |
| 2025 | 6月21日 |
| 2025 | 6月21日 |
毎年2月になると、国立天文台が翌年の夏至の日を発表します。来年の夏至の日がいつになるのか、チェックしてみてくださいね。
参考URL:令和 6年(2025) 暦要項
夏至の意味は?
夏至とは、一年で日の出から日の入りまでの時間がもっとも長い日のことを言います。
二十四節気の一つで、暦上ではそれが起こる日を指しますが、天文学的には太陽が夏至点を通過する瞬間の時刻を指すこともあります。
昼や夜の長さで季節の変わり目を知るという意味では、春分・秋分・冬至などもありますよね。
一方、一年で昼が最も短い日を冬至と言いますが、東京で昼時間の長さを比べると夏至と冬至では5時間もの差があるそうです。
2025年の夏至はいつ?

2025年の夏至は6月21日(日)となっています。
(節季として考えると6月21日から7月5日までです)
より正確に黄径が90度になったタイミングまで記載されており、それは6月21日の12時32分となっております。
このタイミングが黄径90度になった瞬間といえるのです。
参考資料:令和6年(2025)暦要項 二十四節気および雑節 – 国立天文台暦計算室
夏至の算出方法は簡単に言うと、西暦を4で割った余りの数が日にちになるため、4の倍数の年であるうるう年を基準(0)として計算します。
365日の超過分が毎年蓄積され、うるう年でリセットされる形となっています。
これにより、ここ数年は6月22日が夏至となった翌年がうるう年になっていることがわかります。
2025年以降の夏至の日は?
2055年までは夏至の日は全て6月21日となっています。
また2056年からは6月20日が夏至になる日も現れます。
さらに過去には6月23日に夏至だったこともあったようですが、1904年~2055年までは6月21日もしくは22日になることが多いようです。
夏至の日照時間!

夏至の日照時間は、14時間50分程度です。
ちなみに、冬至の日照時間は、9時間45分程度ですので、夏至と冬至の日照時間の差は5時間程度もあるのです。
どうして夏至の日が一番暑くならないの?
夏至の日って、一年で一番昼が長い日なんです。
太陽が長い時間出ているから、もっと暑くなると思うかもしれませんね。
でも、日本の場合、夏至の時期は梅雨の季節と重なることが多いので、実はそれほど暑く感じないんです。
でも、梅雨と重ならなくても、夏至の日が一番暑いとは限りません。
どうしてかというと、実は一日の中で一番気温が高くなるのは、太陽が一番高くなるお昼の12時ではなくて、1~2時間後の方が多いんです。
これは、気温が上がる理由が太陽の高さだけじゃないからなんです。
太陽の光で温められた地面や建物が、その熱を空気に伝えるからなんですね。
同じことが一年を通じても言えるんです。
夏至の前って、雨が降って涼しい日が多いですよね。
そのせいで、夏至の日に太陽が一番高くなっても、地面や空気がまだ十分に温まっていないんです。
だから、夏至の日に一番暑さを感じないんですよ。
夏至と冬至の違いは?
夏至は、一年で最も昼が長く、夜が短い日。
一方の冬至は、一年で最も昼が短く、夜が長い日です。
これは夏至の場合、太陽が一年で一番北よりから登り、お昼に空の最も高い場所を通って、一番北よりに沈むからで、太陽が出ている時間が長くなるために、おのずと昼が長くなり、夜が短くなります。
冬至の場合はこの逆で、太陽が一年で一番南よりから登り、お昼に空の最も低い場所を通って、一番南よりに沈むため、太陽が出ている時間が短くなり、夜が長くなります。
ただし、だからといって夏至が一年で最も日の出が早く、日の入りが遅いわけでも、冬至が一年で最も日の出が遅く、日の入りは早いわけでもありません。

夏至の時期の旬な食べ物は何?
夏至に食べる旬な食べ物や風習に則った食べ物をいくつか紹介します。
たこ
タコは関西を中心に夏至になると食べる風習があります、
ただし、イカ・タコ・カニ・貝類は明確な旬はないという意見もあります。
夏みかん
通常のみかんの旬は冬ですが、夏みかんの旬は4月から6月なので夏至ともぴったりでしょう。
あんず
あんずは旬が短いのですが6月7月が旬の食べ物なので夏至のタイミングにぴったりです。
さくらんぼ
山形で有名なサクランボは6月から7月上旬までが旬となります。
メロン
メロンは旬が長く5月から8月が旬となります。
とうもろこし
夏のお祭りで大活躍なトウモロコシは7月と8月が旬です。
枝豆
枝豆の旬は6月から8月です。
オクラ
夏バテ予防効果があるオクラは6月から9月が旬となります。
みょうが
みょうがは旬の期間が長く6月から10月までとなります。
はも
はもは6月の下旬から7月上旬、そして10月と11月という2回旬がある魚です。
あゆ
鮎は6月から8月が旬です。
かんぱち
かんぱちは6月から9月が旬となります。

夏至の風習や習慣は?
古来より太陽信仰が盛んだった日本では、昼の時間が最も長くなるタイミングである夏至に対して強い意識を抱いていた傾向にあり、それにまつわる風習が現代にも残っている事が多々あるのです。
その風習をより具体的に確認して行きましょう。
関東
関東では夏至になると神様へのお供えとして新しい小麦で作った焼き餅を用意したり、食べるといった行為があります。
関西
大阪近郊では夏至から半夏生までの期間にタコを食べるという風習があります。
これはタコのような8本足で稲の根がしっかりと地面に張ることを意識した祈願です。
香川
うどんで有名な香川県は毎年7月2日がうどんの日に制定されており、夏至になるとうどんを食べるのです。
京都
京都では水無月という和菓子を食べますが、こちらは祈願と言うよりは神道にまつわる「祓」を意識しモノと言われております。
奈良
奈良県もどうやらと関東と同じで新しい小麦で作った焼き餅を用意すると言われております。
福井県(大野市)
福井県では夏至になると焼き鯖を食べるという風習があります。

夏至の時期の花は?
次は夏至のタイミングに綺麗咲く花を見ていきます。
あじさい
梅雨のタイミングで明るく彩られるあじさいは簡単に育つ下司の花の一つです。

ききょう
秋の七草にも該当する桔梗は実は春から秋まで楽しめる花なのですが、桔梗にとって最適なドジョウが減って日本でもあまり見ない花になってしまいました。
べにばな
多年草である紅花は6月下旬~7月上旬が見頃の花です。
くちなし
花が咲くまで3年程度かかるくちなしは6月頃に咲く花です。
夏至の候の使い方
微視ネスの挨拶に夏至の候を使うこともできますので使い方や例文を見ていきましょう。
夏至の候は時候・季節の挨拶に該当しており、二十四節気における夏至のタイミング、つまり6月22日頃から7月7日頃まで使う時候の挨拶となります。
夏至の候を使った例文
使い方はシンプルで、「拝啓 夏至の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます」というよくある時候の挨拶と同じ用い方となります。

夏至の季語について
夏至は季語としても用いられます。
季節はもちろん夏で、分類は時候に該当します。
例句としては、正岡子規の「夏至過ぎて吾に寝ぬ夜の長くなる」とか高浜虚子の「夏至今日と思ひつつ書を閉ぢにけり」などがあります。
夏至を英語で言うと?
夏至を英語で表すと「summer solstice」が該当するでしょう。
「Solstice」は太陽の到達点とか最高点、極点という意味があり冬至を表すときにも使います。
夏至は毎年変わるのまとめ
夏至は毎年変わるんです。2025年の夏至は6月21日です。
この日は、一年で昼の時間が一番長い日なんですよ。
夏至の日は毎年6月20日から22日の間で変わります。
地球の地軸の傾きと公転の関係で決まるからです。
また、夏至の日は14時間50分くらいも日照時間があり、冬至と比べると5時間も長いんです。
でも、梅雨の時期なので暑く感じることは少ないです。
夏至の日には旬の食べ物や各地の風習も楽しんでみてくださいね。
この記事のポイントをまとめますと
- 夏至は毎年6月20日から22日の間で変わる
- 2025年の夏至は6月21日
- 昼の長さが一年で最も長い日である
- 夏至の日は14時間50分程度の日照時間がある
- 冬至と比べて日照時間が約5時間長い
- 夏至の日は毎年2月に国立天文台が発表する
- 夏至の日は地球の地軸の傾きと公転の関係で決まる
- 夏至の日は太陽暦を基に決まる
- 夏至の日が一番暑い日ではない
- 夏至は梅雨の時期と重なることが多い
- 夏至の日の気温は地表や空気の温まり方で決まる
- 夏至には旬の食べ物がある
- 夏至の時期に旬な食べ物にはタコや夏みかんがある
- 各地に夏至にまつわる風習がある
- 関西ではタコを食べる風習がある
- 夏至の頃に咲く花にはあじさいがある
- 夏至の候は時候の挨拶として使える
- 夏至は英語で「summer solstice」と言う
- 夏至は二十四節気の一つである
- 昼や夜の長さで季節の変わり目を知る
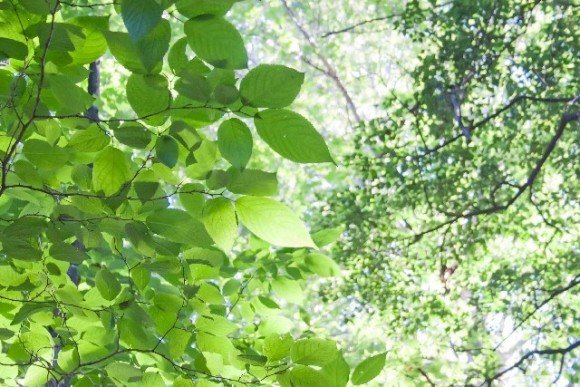






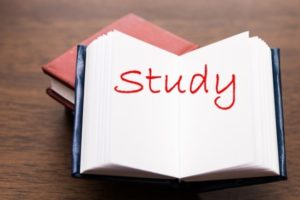







コメント