小正月とは?小正月の食べ物や行事食は何?
お正月と言えば、新年の幕開けをお祝いしながらおせち料理やお酒に舌鼓を打ち、子供達はお年玉を楽しみ待っている様子が思い浮かびますよね。
日本国内誰も行う伝統行事ですが、では、小正月と聞いて何が思い浮かぶことはあるでしょうか。
正月に「小」という文字がついた小正月。あまり見聞きした記憶のない言葉のような気がしますが、実はとても重要な意味を持っています。
そこで今回は、小正月について調べてみました。
小正月とは一体どのような行事なのか、由来や食べ物など、小正月にまつわる話をご紹介したいと思います。
小正月の食べ物や行事食は何?

新年を迎えた後の小正月は、古来より多くの地域で特別な食事が楽しまれてきました。
ここでは、小正月にちなんだ食事の背景とその意味を、現代の読者にも親しみやすい形でご紹介します。
小正月は、旧暦の1月15日にあたり、新年の行事として重要な位置を占めています。
この日には、家族が集まり、健康や幸福を願いながら特別な食べ物を共にします。
小豆粥(あずきがゆ)
小豆粥は、小正月の朝に食べることで知られる伝統的な食べ物です。
小豆をふんだんに使ったこのお粥は、その鮮やかな赤色が邪気を払い、福を呼び込むとされています。
この信念は、中国の古い風習に根ざしており、日本の古典文学にもその記述が見られます。
具体的には、「枕草子」や「土佐日記」にも触れられており、日本の食文化におけるその重要性が伺えます。
小豆粥を食べることで、1年間の健康と安寧を祈願するのです。
また、このお粥には、お餅やカボチャを加えて風味豊かにアレンジすることも推奨されています。
おぜんざい
一方で、小豆粥と同じく赤い小豆を使用した「おぜんざい」を食べる地域もあります。
特に、鏡開きで使用した鏡餅を入れて食べることで、新年の祝いを再確認し、家族の絆を深める意味合いも含まれています。
お団子・お餅
さらに、小正月にはお団子やお餅を食べる風習もあります。
これは「左義長」や「どんど焼き」といった火祭りの際に行われることが多く、聖なる火で焼かれた食べ物を口にすることで、厄払いや健康を祈るという意味が込められています。
小正月の食べ物とその意味
以下の表は、小正月に食べる伝統的な食べ物と、それぞれの食べ物が持つ意味をまとめたものです。
| 食べ物 | 特徴 | 食べる意味 |
|---|---|---|
| 小豆粥 | 赤い小豆を使用したお粥 | 邪気を祓い、無病息災を願う |
| おぜんざい | 小豆と鏡餅を合わせた甘味 | 家族の絆を深め、新年を祝う |
| お団子・お餅 | 火祭りで焼いたものを食べる | 聖なる火で厄払いと健康を祈願 |
これらの食べ物は、単に美味しいだけでなく、それぞれが持つ深い文化的意味を理解することで、食事の時間がより豊かなものになります。
小正月の食文化は、日本の伝統を今に伝え、新しい年の幸せを願う大切な習慣の一つです。
今日はハワイの1月15日。旧正月といいますか、小正月といいますか。
とにかく、小豆粥の日です!邪気を取り除くというのであれば今の世の中にぴったりです」!
いただきまーす! pic.twitter.com/rCorbvLk61— つんく♂ (@tsunkuboy) January 15, 2021
1月15日は小正月、小豆粥の日です。小豆の赤色が邪気払いになります。
肌荒れや抜け毛、髪のパサつき、顔色が悪い、爪がかける、こむら返り、不眠や不安感などは血虚といわれます。
この血虚対策にも赤色の食べ物がいいので小豆粥などおすすめです。トマト、なつめ、お肉などの赤色も意識下さいね! pic.twitter.com/RDH653sN5R
— 土屋幸太郎🍒土屋薬局山形県東根市 (@tutiyak) January 14, 2022
小正月とは

日本の伝統的な行事の一つに「小正月」という風習があります。
これは、新暦の採用により、現代のカレンダーで言う1月1日が新年の始まりと定められた明治時代初期に起源を持ちます。
この変化は、日本の歳時記における重要な節目となりました。
大正月と小正月の区別
新暦導入以前、日本では旧暦を用いており、正月の期間は現在の1月1日から15日までとされていました。
しかし、新暦の採用後、正月の期間が短縮され、特に2つの期間に分けて考えられるようになりました。
- 大正月:新年の元日から「松の内」までの期間を指し、この時期は新年の祝賀と家族の絆を深めるための行事が行われます。松の内はかつては1月15日までを指していましたが、現在では1月6日または7日までとする地域が多く見られます。
- 小正月:1月15日を中心とした祝日で、正確には1月14日の日没から15日の日没までを指します。この日は、大正月の賑わいが落ち着いた後の、もう一つの新年を祝う日として位置づけられています。
小正月の意義
小正月は、大正月の忙しない日々の後、特に女性たちが労をねぎらい、実家に帰省するなどしてリフレッシュするための時期として重んじられてきました。
このため、「女正月」とも呼ばれることがあります。
年末年始にかけて家族や社会のために尽力した女性たちが、この時期には自分自身の時間を持ち、休息を取ることが奨励されています。
現代における小正月の変化
現代では、小正月をもって正月の行事が終わりとされ、日常生活への移行点となっています。
しかし、地域によっては小正月を祝う習慣が薄れ、忘れ去られつつある場所もあります。
それでも、伝統を重んじる地域や家庭では、小正月にちなんだ行事や食事を楽しむことで、年始の祝福を再び感じる機会としています。
小正月の現代的な解釈
小正月は、新しい年のスタートにおける忙しさから一息つくための大切な時期として、現代でもその精神を受け継いでいます。
家族や友人との時間を大切にし、新年の抱負を再確認する機会ともなっています。
このように、小正月は日本の文化において、過去から現在に至るまで、人々の生活に息づく伝統行事として、その形を変えながらも大切にされています。
小正月はいつ?

小正月は1月15日です。
小正月とは、旧暦の正月のことを指します。
旧暦(太陰太陽暦)では、月の満ち欠けで1ヶ月を決めており、満月を1日としていました。
そして、一年で最初に満月が見える日を元日としていたのです。
旧暦の正月を現代の暦に直すと、1月15日(14~16日)が該当となるのですが、新暦と暦の正月を区分するために、1月15日を小正月と呼ぶようになったと言われています。


小正月の行事は?

日本の伝統的な祭りである小正月は、新年の祝いの一環として、毎年1月の中旬に行われる特別な行事です。
この時期は、新しい年の豊かな収穫と家族の健康を願う多くの風習があります。
小正月の風習は、地域によって異なる場合がありますが、一般的には以下のような特色ある活動が行われます。
小正月の風習とその意味
- 削り花と粟穂稗穂の飾り付け
- 削り花: 木の枝を削って作られる装飾品で、新年の神様への捧げ物として用いられます。
- 粟穂稗穂(あぼひぼ): 粟や稗の穂を束ねたもので、これもまた豊作を願うシンボルとして神棚に飾られます。
- まゆ玉: 絹糸で作られた装飾品で、新年の清らかさと豊かさを象徴しています。
これらの飾りは、家庭の神棚や入口に設置され、新年の神々への敬意と感謝、そしてこれからの一年の繁栄を祈願するためのものです。
- どんど焼き
- 概要: 正月飾りやしめ縄、門松などを集めて大きな焚火を作り、それを燃やす行事です。
- 意味: どんど焼きの煙は、歳神様が天に昇るための手段とされ、この煙に願いを託すことで無病息災を祈願します。
- 風習: 火にあたることで若返りの効果があるとされ、また焼いた餅を食べることで健康を保つとも言われています。
地域による日程の違い
小正月の行事は、地域によって実施日が異なることがあります。
一般的には1月15日に行われることが多いですが、中には松の内が明けた後の1月8日に行う地域もあります。
そのため、参加を希望する場合は、事前に地域の行事日程を確認することが大切です。
小正月の風習と意味
| 風習 | 説明 | 目的 |
|---|---|---|
| 削り花の飾り付け | 木の枝を削って作った装飾品を神棚に飾る | 神様への捧げ物として |
| 粟穂稗穂の飾り付け | 粟や稗の穂を束ねて神棚に飾る | 豊作を願うシンボルとして |
| まゆ玉の飾り付け | 絹糸で作った装飾品を飾る | 新年の清らかさと豊かさを象徴 |
| どんど焼き | 正月飾りを燃やす行事 | 無病息災を祈願し、新年の神様を送る |
小正月の行事は、古くから伝わる日本の文化を色濃く反映しており、現代においても多くの人々によって大切にされています。
これらの行事を通じて、家族や地域社会が一堂に会し、新たな年の始まりを祝うとともに、互いの幸福と健康を願うのです。
秩父・比企地方にみられる小正月の飾り物「削り花(ケズリバナ)」。その年の豊作を願って神棚などに飾られます。
当館モニター前の「削り花」はニワトコの枝。枝の表面をそぐように削って作り、12個の花は12か月を表しているそうです。
資料整理休館前1/16まで飾ってありますので、ぜひご覧ください。 pic.twitter.com/NzLuhMHpiZ— 埼玉県立自然の博物館 (@saitama_shizen) January 11, 2022
新年おめでとうございます。夜半の北風も止んで、2020年最初の朝は穏やかな晴れでした。私の町の正月飾りは、梅枝にニワトコの削り掛けを挿したもの。粟穂稗穂(あぼへぼ)といって、1年の心がけを持ち、小正月までの開花を待ちます。
本年もどうぞよろしくお願いします。 pic.twitter.com/guGfTDjI7R— KantaTerada (@cantillans) January 1, 2020
【年中行事】新年最初の綱島家での年中行事は、小正月の繭玉飾りです。繭玉には米の粉を使い、「八王子千人同心組頭の家」のかまどで蒸し、半分は食紅で色付けをして団子状に丸め、シラカシの木にさして飾りつけました。今年も実り豊かな一年となりますように。#たてもの園 pic.twitter.com/jJ7qgm57ry
— 江戸東京たてもの園 (@tatemono1) January 14, 2021
小正月とはどんな食べ物や行事食があるの?のまとめ
いかがでしたか?
小正月は、小さい正月と書きますが、実際には現在の正月の元祖ともいうべき日だったのです。
また、新暦になり1月1日に正月を行うようになってからも、多くの地域では小正月の行事が残って引き継がれています。
来年は是非、正月だけではなく小正月にも意識を傾け、日本の奥深い伝統や風習を感じてみるのもよいかも知れませんね。
正月の関連記事










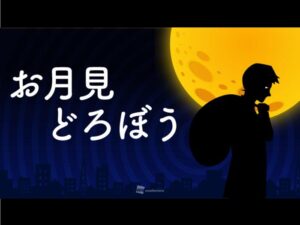


コメント