鏡開きとは?、この言葉を耳にしたことはありますか?日本の伝統的な行事や文化に触れる機会が増える中、鏡開きに関する知識や意味が曖昧になっている方も多いのではないでしょうか。
実は、鏡開きには深い意味や由来があり、それを知ることで日本の文化の魅力を再発見することができます。
また、樽酒の鏡開きとは何が違うのか、その違いを正確に理解することで、さらにその行事の価値を深く感じることができるでしょう。
この記事では、鏡開きの意味や由来、そして樽酒の鏡開きとの違いについて、初心者の方でもわかりやすく解説していきます。
興味を持ったら、ぜひ続きを読み進めてみてください。
- 鏡開きは、正月に食べる鏡餅を割って食べる行事である。
- 鏡開きは、1月11日に行われることが多い。
- 鏡餅は、神様への感謝の意を込めて供えられる。
- 鏡開きの際には、餅を柔らかくして汁物やお雑煮にして食べる。
鏡開きとは
鏡開きは、日本の伝統的な年中行事であり、新年を迎える際の重要な儀式の一つです。
この行事の起源は古く、神仏への感謝と家族の健康や繁栄を願う意味合いが込められています。
正月に神様や仏様に捧げられた鏡餅を下ろし、家族で分け合って食べることで、新しい年の幸運と家族の絆を祈願します。
鏡餅の象徴性
鏡餅は、上下に重ねられた円形の餅で構成されており、その形状は家族の円満や無病息災を象徴しています。
また、鏡餅の名前は、その形が古代の銅鏡に似ていることに由来しています。
鏡は真実を映し出すものとされ、新しい年に向けて家族が真実の心で絆を深める意味も込められています。
鏡開きの儀式
鏡開きの際には、鏡餅を手や木槌で優しく割ります。この行為は、餅を切るのではなく「割る」という点にも意味があり、新しい年の幸運を「切り開く」ではなく「自然に開かれる」よう願う思いが込められています。
家族みんなで餅を分け合い、汁粉や雑煮、かき餅(あられ)など様々な形で楽しみます。
鏡開きの現代的な意義
現代においても、鏡開きは多くの日本の家庭で大切にされている伝統です。
この行事は、忙しい日常から一時的に離れ、家族が集まり新しい年の始まりを共に祝うことの大切さを再認識させてくれます。
また、伝統を通じて子どもたちに家族の絆の重要性や日本の文化を伝える機会ともなっています。
鏡開きの要素とその意味
| 要素 | 意味 |
|---|---|
| 鏡餅 | 家族の円満や無病息災を象徴 |
| 鏡餅の割り方 | 新しい年の幸運が自然に開かれるよう願う |
| 食べ方 | 家族で分け合うことで絆を深める |
| 儀式の時期 | 新年の始まりを家族とともに祝う |
鏡開きは、単なる年中行事を超え、日本の文化と家族の絆の深さを象徴する重要な伝統です。
この美しい習慣を通じて、新しい年の幸運と家族の健康を祈り、日本の文化を次世代に伝えていくことができます。
鏡開きの意味
鏡開きは、文字通り「鏡を開く」という意味を持ちます。
しかし、この「鏡」とは、お餅を指し、新年に家族や親戚が集まって行う行事のことを指します。
この行事では、お正月に飾った鏡餅を割って食べることで、家族の絆を深めるとともに、新しい年の幸運を祈願します。
鏡開きの由来
鏡開きは、日本の古代から続く伝統的な行事であり、その起源は神聖な儀式にまで遡ります。
この行事は、新年を迎える際の神々への敬意と感謝を表すもので、日本文化の核心をなす要素の一つです。
鏡餅:神々への奉納
古来より、鏡餅は神々への奉納品として重要な役割を果たしてきました。
その丸い形は、完全性と繁栄を象徴し、神々との結びつきを強化するための媒体とされています。
家庭での祝福の儀式
新年が訪れると、日本の多くの家庭では、家の中心的な場所に鏡餅を飾ります。
これは、新しい年の安全と繁栄を神々に祈願するための儀式であり、家族の幸福を願う心からの行いです。
鏡開きの瞬間
新年が始まり、一定の期間が経過すると、家族が集まって鏡餅を分け合います。
この行為は、神々の恩恵を家族全員で共有するという深い意味を持ち、一年の健康と幸運を願う象徴的な瞬間です。
家族の絆と新年の願い
鏡開きは、家族の絆を強化し、新しい年の幸せと繁栄を願う重要な儀式です。
この行事を通じて、家族は一致団結し、共に新しい年を迎える準備をします。
鏡開きを英語で言うと
鏡開きを英語で表現すると、「the cutting of New Year’s rice‐cakes」となります。
出典:「鏡開き」の英語・英語例文・英語表現 – Weblio和英辞書
鏡餅と樽酒の鏡開きの違いについて

(出典:鏡開きのいわれは?|月桂冠)
なぜ鏡開きというの
「鏡開き」という言葉は、日本の伝統的な儀式に由来しています。
お正月に家の中心に飾られた鏡餅を取り下げ、家族全員で食べることで、新しい年の安全や健康を祈願する行事です。
ここでの「鏡」とは、鏡餅の形状が平らで円形の鏡に似ていることから名付けられました。
この円形は、家族の絆や無限の繁栄、そして完全なるものを象徴しています。
また、「開き」という言葉は、新しいことの始まりや繁栄を意味しており、家族が一緒に鏡餅を食べることで、その年の幸運や繁栄を共有するという意味が込められています。
一方、地域や家庭によっては「鏡割り」とも呼ばれることがありますが、割るという行為が縁起を悪くするとの考えから、多くの場所では「鏡開き」という名前で親しまれています。
なぜ樽酒を開けるのも鏡開きというの
鏡開きの行事には、樽酒を開ける習慣も含まれています。
樽酒を開ける際の「鏡開き」は、新しい年の始まりを祝うためのものであり、その背景には古くからの信仰や習慣が存在します。
新酒を家族や親戚とともに飲むことで、新しい年の幸運や繁栄を祈願するとともに、家族の絆を深める意味が込められています。
また、樽酒自体にも特別な意味があります。
樽酒は、神事や祭りなどの特別な場面で供されることが多く、神聖視されているお酒です。
新年の「鏡開き」で樽酒を開けることは、新しい年の始まりを神々とともに迎え、その年一年の安全や豊作を祈るという意味があります。
このように、「鏡開き」には、単に新酒を楽しむだけでなく、家族の絆を深める、新しい年の祝福を受け取る、神々への感謝や祈りを込めるといった、多くの意味や背景が存在します。
これらの伝統や習慣は、日本の文化や歴史の中で大切に受け継がれてきたものであり、今後も多くの家庭で続けられることでしょう。
2025年鏡開きはいつやるの?
しかし、関西や一部の地域では1月15日や20日になっていますし、京都や近畿の一部地域では1月4日になっています。
元々は小正月が1月15日までなので1月20日が鏡開きが全国共通の考え方だったのです。
しかし、江戸時代には火事が頻繁に発生して少しでも原因を減らしたいから時期を早めたとか、徳川家光の月命日が20日になってしまったので鏡開きのタイミングもずらして小正月も短くしたなどいくつかの原因で関東地方の鏡開きが11日になったのです。
九州は久留米市の大善寺玉垂宮で行われる「鬼夜」という毎年一月七日の夜に行う追儺の祭事がお正月の区切りという認識だったようで、九州では1月11日が鏡開きのタイミングになったと言われています。
関東以外の地域ではこのように何らかの風習などで1月11日になっている可能性が高いです。
関東に合わせて1月11日に変更したという可能性ももちろんあります。
鏡開きの日付は、基本的に松の内が明けたあとの日です。
ただし、地域によって松の内が明ける日は異なり、鏡開きの日付にも下記のように違いがあります。
| 鏡開きの日付 | 松の内が明ける日 | 地域 |
|---|---|---|
| 1月11日 | 1月7日 | 東日本や九州など |
| 1月15日もしくは20日 | 1月15日 | 関西を中心とする西日本 |
| 1月4日 | 1月15日 | 京都府と近隣の一部地域 |
引用:鏡開きとは?意味・由来や食べ方まで詳しく紹介|マイナビ保育士
鏡開きのやり方
お正月飾りとして飾っていた鏡餅を感謝の気持ちを捧げながら下げて、表面についてしまった汚れは落としてカビは除去してください。
その後は、木槌を使ってかけ声をかけつつ割るだけです。
基本的に1週間以上飾った鏡餅というのはかなりの硬さになっており、最初からひびが入っていることも多いでしょう。
ただし、あまりにも水気が多いと木槌で何回叩いても全く割れなくなってしまいますので、その場合は諦めて半日程度水につけた後にラップで包んでレンジで温めて、手でちぎってしまいましょう。
筆者も鏡餅を実行したことがありますが、加減がわからずかなり粉々になってしかも飛び散ってしまったので、下に新聞紙を敷いたり飛び散っても大丈夫なように囲った方が良いかもしれません。
鏡開きの料理や食べ物
鏡開きは、新年の祝いの一環として行われる伝統的な行事であり、この際にはさまざまな特別な料理や食べ物が振る舞われます。
中心となるのは「鏡餅」で、これは新年の幸せや豊かさを願って供えられるものです。
その他にも、お雑煮やおせち料理といった日本の伝統的な料理が楽しまれます。
お雑煮については、その名の通りさまざまな具材を煮込んだ料理で、地域や家庭によって異なるレシピや具材が用いられることが特徴です。
例えば、関西地方では白味噌ベースのお雑煮が主流であり、関東地方では醤油ベースのものが好まれる傾向があります。
家族の好みや伝統に合わせて、自分たちだけのオリジナルのお雑煮を楽しむことができるのが魅力の一つです。
また、おせち料理は新年を迎える際のお祝いの料理として知られ、各料理にはそれぞれ縁起の良い意味が込められています。
例えば、黒豆は「健康」、伊達巻は「良いことが巻き起こる」などの意味があります。
これらの料理は、新年の始まりを家族や親しい人々と共に祝うためのものであり、日本の文化や伝統を感じることができる特別な時間となります。
鏡開きで使用したお餅の食べ方
最もポピュラーな方法は、お餅をお雑煮という具だくさんの味噌汁や醤油ベースのスープに入れて食べることです。
このお雑煮は、家庭や地域によって異なる具材や味付けがされており、日本全国で様々なバリエーションを楽しむことができます。
また、鏡開きのお餅を焼いて香ばしい風味を引き出し、その上にきな粉や黒蜜をかけて食べる「焼き餅」や「きな粉餅」も非常に人気があります。
特に冬の寒い日には、焼きたてのお餅の温かさときな粉の甘さが絶妙に合わさり、心も体も温まる一品となります。
さらに、鏡開きのお餅を利用して、アイスクリームやフルーツと組み合わせたデザートや、ピザのようにチーズや野菜をのせて焼く「お餅ピザ」など、新しいアイディアで楽しむ方法も増えてきています。
これらの方法で、鏡開きのお餅をさらに美味しく、楽しく味わうことができます。
お正月の三が日を過ぎると硬くなってしまったお餅を、つきたてのように柔らかくして伸びるお餅に戻す方法が紹介されています。
具体的には、フライパンを使用して、サラダ油を薄く引き、お餅を焼く方法が示されています。
焼き上がったお餅は、水を加えてさらに柔らかくすることができます。
この方法で、硬くて食べられなくなったお餅も、再び美味しく食べることができるようになります。
ポイント:
- 硬くなったお餅を柔らかくするための方法として、フライパンを使用する。
- フライパンにサラダ油を薄く引き、お餅を焼く。
- お餅が焼けたら、水を加えてさらに柔らかくする。
- この方法で、硬くなったお餅も再び美味しく食べられるようになる。
- お餅が非常に硬くなった場合、焼く前に一晩水に浸けることで、柔らかくすることができる。
鏡開きでやってはいけないことは?
昔の武士達はとにかく縁起を大切にしており、鏡餅を刃物で切ることを切腹に通じるということでNGとしていました。
この風習は今でも残っており包丁は使ってはいけないと考えられています。
一説には神様の依り代として使われているものに刃物を用いるのは失礼というのもあるのですが、それなら個人的に木槌でドカンドカンと叩きまくるのも非常に失礼だと思ってしまうので、あんまり気にしない方が良いのでしょう。
近年の鏡餅にはパック詰めされているお餅が入っている物がベースとなっているので、ハンマーで割る人はほとんどいなくなってきてはいますが、覚えておいた方が良いマナーとなっています。
鏡開きについて簡単な子供への伝え方

子供にとって年末年始の行事は意味不明であり、とりあえずお休みでお金が貰える日という認識しか無いのかもしれません。
そんな子供達に鏡開きとは何かを説明するときはお年玉と一緒にお餅をあげるのも良いでしょう。
そのときに「神様からパワーをもらった鏡餅とセットで手に入るお年玉はよりパワーアップできる」といった伝え方をするのも良いでしょう。
子供に伝えるときは難しい言葉を使わないで鏡開きの意味を聞かれたら「神様からパワーをもらうため」と答えるのが一番です。
鏡開きを楽しむ方法
鏡開きは、家族や親戚との絆を深める大切な行事です。
そのため、その日を特別なものにするための方法を考えることが大切です。
保育園で鏡開きの日を楽しく過ごすアイデア
保育園での鏡開きの日は、多くの子供たちにとって初めての体験となることが多いです。
この特別な日をより有意義にするためには、まず鏡開きの意味や歴史的背景を子供たちに分かりやすく伝えることが重要です。
例えば、鏡開きが新年の始まりを祝う行事であり、家族や地域の絆を深めるためのものであるということを伝えることができます。
次に、実際の鏡餅の割り方や食べ方を体験することで、子供たちの興味や好奇心を引き出すことができます。
具体的には、子供たちに鏡餅の形や色、香りを感じさせることで、五感を使って鏡開きの日を楽しむことができます。
また、鏡開きの日には、伝統的な日本の遊びやゲームを取り入れることで、子供たちの楽しさを一層高めることができます。
例えば、福笑いや羽子板などの遊びを取り入れることで、子供たちの笑顔や喜びを引き出すことができるでしょう。
最後に、鏡開きの日を通して、子供たちに日本の伝統や文化を理解させることで、より深い意味での楽しさや学びを提供することができます。
保育園の先生や保護者の方々と一緒に、この特別な日を最大限に楽しむための工夫やアイデアを考えることで、子供たちにとって忘れられない思い出となることでしょう。
鏡開きのまとめ
鏡開きは、日本の伝統的な行事として、多くの家庭で行われています。
この行事を通じて、家族や親戚との絆を深めることができるので、その意味や由来を理解し、楽しむことが大切です。
鏡開きを行う際には、上記のガイドを参考にして、家族みんなで楽しい時間を過ごしてください。
この記事のポイントをまとめますと
- 鏡開きは日本の伝統的な行事である
- 新年の神事の一つとして行われる
- 鏡餅を割ることからその名がついた
- 家族や地域の人々が集まり行う
- 神様への感謝の意を表す
- 鏡餅は神様の姿を象徴する
- 割った餅は汁物やお雑煮にして食べる
- 餅を手で割ることで一年の無病息災を願う
- 通常、1月11日に行われる
- 一部地域では日付が異なることもある
- 餅を刃物で切らずに手で割るのが特徴である







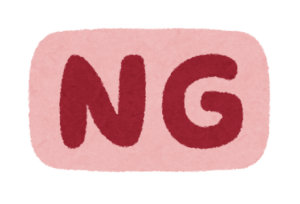




コメント