鏡開き2025年はいつ?おすすめの食べ物は?
鏡開きとは、お正月に歳神様にお供えをしていた鏡餅を下げ、食べる事を言います。
中には鏡餅を下げる事が鏡開きだと勘違いされている方もいらっしゃいますが、下げるだけではなく食べる事がとても大切なのです。
では、それには一体どのような意味があるのでしょうか。
また、鏡開きをする日というのは必ず決まっているものなのでしょうか?
地域によって違いはないのでしょうか?
今回はそのような疑問を丸ごと解決してみようと思います。
鏡開き2025年はいつ?
2025年の鏡開きは1月11日です。
鏡開きを行う日は、一般的には、1月7日までの松の内が明けた1月11日です。
松の内が15日までという地域では、1月15日または20日に行われています。
鏡開きの日程と地域差
鏡開きの日程は地域によって異なりますが、一般的には「松の内」と呼ばれる期間が終わる1月11日に行われることが多いです。
松の内は地域によって終わりの日が異なり、1月7日までとする地域と1月15日までとする地域があります。
そのため、鏡開きの日もそれに準じて変わることになります。
以下の表は、2025年の鏡開きの日程を地域ごとにまとめたものです。
| 地域 | 鏡開きの日程 |
|---|---|
| 関東地方の多く | 1月11日 |
| 関西地方 | 1月15日または20日 |
| 近畿地方の一部・京都 | 1月4日 |
| 松の内が1月7日までの地域 | 1月11日 |
| 松の内が1月15日までの地域 | 1月15日または20日 |
鏡開きとは別名鏡割りと呼ばれており、お正月に神様に供えた鏡餅を下げて食べることです。
ただし、酒樽を利用した鏡開きも別に存在しているので、使い分けには注意しましょう。
基本的に鏡開きというのは年ごとに実行する日が変わるイベントではありませんが、これだけ実行日が別れているイベントでもありますので、なかなかに厄介なのです。
もっと細かく記載すると、関東地方やその他の地方の一部は1月11日になっていることが多く、関西地方では1月15日や20日になっていることが多いです。
そして、近畿地方の一部や京都では1月4日になっている場合もあります。
このように地域ごとにかなりの差があるのが鏡開きとなっていますので、転勤やお引っ越しで住む場所が変わったという方は周りの人と会話して確認しておくと良いでしょう。
基本的には1月11日が多めになっているので、とりあえずの目安は11日と考えておきましょう。
何でここまで鏡開きのタイミングがバラバラになってしまったのかは後に詳しく解説いたします。
関東と関西では、鏡開きの日にちが違うのはなぜ?

「鏡開き」とは、1月11日に実施される行事です。
この風習は、関東地域を中心に広まっており、東北や九州などの多くの地方でも行われています。
一方、関西地域を中心とした場所では、「松の内」が1月15日まで続き、その後に「鏡開き」が行われるのは1月20日です。その間は歳神様が家にいると考えられています。※一般的に「松の内」は、正月事始めとされる12月13日からはじまり、1月7日まで。
また、一部の地域では「松の内」の期間に関係なく、三ヶ日が終わった後に「鏡開き」を行うこともあります。
この関東と関西での日程の違いには、きちんとした理由が存在しています。
鏡開きは一般的に松の内の後に行います。
この松の内は、昔は元日から1月15日とされていたため、鏡開きは1月20日に行われていました。
しかし、徳川家光が4月20日に亡くなったのを切っ掛けに、関東近郊では20日という日が忌日として避けるようになり、これに伴って鏡開きの日も1月20日から1月11日に変更されたのです。
ですが、徳川幕府の力が強く影響しない関西地域では前のまま、1月20日を鏡開きとするところも多く存在するのです。
ちなみに関東では、鏡開きが1月11日に変更されたため、松の内も1月7日までと期間が短縮されています。
鏡開きの意味
鏡開きは、新年を迎えるにあたり、家庭や神社などで飾られた鏡餅を下ろし、家族や地域の人々で分け合って食べる行事です。
この風習には、単に美味しいお餅を楽しむ以上の、深い意味が込められています。
神様との繋がり
日本では、神様へのお供え物をいただくことで、その神聖な力を分けてもらうという信仰が根強くあります。
鏡餅は、新年に家族の安全や豊作を願って歳神様に捧げられるもので、そのお餅を食べることで、神様との結びつきを感じ、神様の恩恵を受けるとされています。
健康と繁栄の願い
鏡開きには、無病息災や家族の健康を願う意味合いもあります。
また、「鏡」が平和や円満を象徴し、「開き」が末広がり、つまり繁栄を意味することから、一年の幸運を願う儀式とも言えます。
縁起の良さと言葉の選び方
日本の伝統では、刃物を使って食べ物を切る行為は、不吉な出来事や武士の切腹を連想させるため、避けられてきました。
特に神様に関わるものに対しては、そのような行為は縁起が悪いとされています。
そこで、鏡餅を「切る」のではなく、「開く」という言葉が用いられるようになりました。
これは、言葉に込められた願いや敬意を表す日本独特の文化的表現です。
長寿の象徴
時間が経過し硬くなった鏡餅を食べることは、丈夫な歯で長生きすることを願う意味も含まれています。
これは、身体の健康だけでなく、精神的な強さや生命力の維持を願う日本人の心情を反映しています。
鏡開きの現代的な解釈
現代では、この伝統的な風習も形を変えつつありますが、その本質的な意味は変わらず、多くの家庭や地域で大切にされています。
鏡開きは、新年の祝福と共に、過去を振り返りながら未来への希望を新たにする機会として、今もなお重要な役割を果たしています。
このように、鏡開きは単なる風習を超え、日本人の価値観や世界観、自然との調和を重んじる精神性を象徴する行事と言えるでしょう。
それは、新しい年に向けての希望と共に、家族や地域社会が一体となって祝う、心温まる伝統です。

鏡開きのマナー!やってはいけない事

鏡開きをする際に、やってはいけない事があります。
包丁を使って切る
それは、包丁などの刃物で鏡餅を切り分ける事です。
歳神様にお供えしていたものに刃を向けるというのは大変な失礼とされています。
そのため、昔から鏡開きの時には木槌などで叩いて割っていたのです。
こうした事から、鏡開きは鏡割り、とも言われています。
松の内が明ける前に食べる
鏡餅は、穀物神である年神様が正月の間に宿る依り代であるとされています。
そのため、松の内が明ける前に鏡開きをしてお餅を食べることは望ましくありません。
鏡餅を食べずに捨てる
鏡餅をいつまでも飾り続けることはせず、松の内が明けたあとは鏡開きをして食べるようにしてください。
長期にわたって鏡餅を飾ることは、家に来た神様に失礼な行為と見なされます。
硬い鏡餅を柔らかくする方法
関東地方では1月11日、関西地方では1月15日もしくは20日に鏡開きを行いますが、その頃になると乾燥してお餅がカチカチになってしまい、包丁で切ることができなくて困ることが多いですよね。
そもそも、鏡餅は氏神様の依り代のため、包丁で切って食べるのは縁起が悪いと言われており、木づちなどで叩き割って食べるのが正解です。
なお、割るという言い方も神様に失礼だということで、鏡餅を下げて食べることを鏡切りや鏡割りではなく、鏡開きと呼ぶようになったと言われています。
硬くなった鏡餅を食べる時に、知っておくと便利なのが電子レンジです。
お餅に水をつけ、レンジで20~30秒程度加熱すると硬かったお餅がやわらかくなり、小分けにしやすくなります。
1度で硬さが変わらなければ、何度か繰り返してみましょう。
その際、一気に長い時間レンジで加熱すると、お餅が溶けてしまうので、20~30秒ずつを様子を見ながら行うようにして下さい。
また、電子レンジを使わずに、鏡餅が入るボールなどに入れて水に浸けて一晩置いておいてもやわらかくなります。
【餅レシピ】硬くなったお餅を柔らかくする方法|伸びるお餅の食べ方
お正月の三が日を過ぎると硬くなってしまったお餅を、つきたてのように柔らかくして伸びるお餅に戻す方法が紹介されています。
具体的には、フライパンを使用して、サラダ油を薄く引き、お餅を焼く方法が示されています。
焼き上がったお餅は、水を加えてさらに柔らかくすることができます。
この方法で、硬くて食べられなくなったお餅も、再び美味しく食べることができるようになります。
ポイント:
- 硬くなったお餅を柔らかくするための方法として、フライパンを使用する。
- フライパンにサラダ油を薄く引き、お餅を焼く。
- お餅が焼けたら、水を加えてさらに柔らかくする。
- この方法で、硬くなったお餅も再び美味しく食べられるようになる。
- お餅が非常に硬くなった場合、焼く前に一晩水に浸けることで、柔らかくすることができる。
鏡開きしたお餅の食べ方

鏡開きとは、お正月にお供えした鏡餅を食べる、日本古来の習慣です。
お供えしていた鏡餅を下げるのが鏡開き、と思っている方も多いですが、神様の依り代である鏡餅を食べることで神様の力を頂くという意味があるため、鏡餅を下げて食べるまでが正しい鏡開きとなります。
鏡餅は大きさによっては一回では食べ切れないこともあるので、いくつか食べ方を知っておくとよいですよね。
そこでここでは、鏡開きした鏡餅の食べ方をご紹介したいと思います。
①お汁粉にする
甘い物は食べるだけで幸せな気持ちになりますよね。
鏡餅をお汁粉にする場合は、焼くよりもしっかりと茹でることでつきたてのような食感になります。
②きな粉餅
お汁粉の準備をするのが面倒という人は、耐熱容器に水と小分けにした鏡餅を入れ、電子レンジで加熱してやわらかくした後、きな粉と砂糖をまぶして食べるのもお勧めです。
同じ方法でずんだやみたらしなども楽しめます。
③おかき
小さく割った鏡餅を、低温の油でじっくりと揚げ、油を切った後塩で味付けして完成です。
④ピザ
電子レンジでやわらかくした鏡餅を綿棒などで伸ばし、上にケチャップを塗ってウィンナーやピーマン、玉ねぎ、トマトなどをトッピングしてチーズをかけてトースターで焼くと、餅生地のピザになります。
なお、お餅を伸ばす時はクッキングシートなどで挟んで行いましょう。
鏡開きはいつ?のまとめ
最近は、お供えする鏡餅はパック入りのものが主流となっているため、実際に鏡開きを行う家庭というのは少ないように思います。
しかし、1月11日に鏡餅を食べる習慣というのは変わらず続けて行きたいものです。
おしるこにして食べる他、小さく割って油で揚げて食べる〝かきもち〟も揚げたての味は格別ですから是非試してみて下さい。






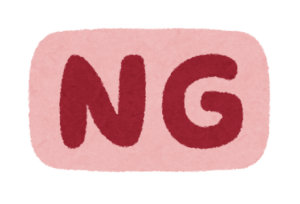




コメント