七五三の神社は、どこを選べばいいの?
子どもの成長を祝い、これからの元気と成長をお祈りする七五三。
この時に、どの神社に行けばいいのか迷ってしまいますよね。
子どものことを思えば思うほど、七五三の神社選びは迷ってしまうものです。
そこで、今回は、神社選びのポイントやお参りの仕方などをご紹介します。
七五三の神社の選び方とポイント
自宅の近くの神社(氏神様)
伝統に則り、まず考えたいのは氏神様へのお参りです。
氏神様とは、その地域を守護する神様であり、地元で生まれ育った子供たちが無事に成長したことへの感謝、そしてこれからの健康と幸福を祈るためにお参りします。
多くの場合、氏神様はご自宅の最も近い神社に祀られています。
アクセスの良さを重視
七五三では、子供たちが晴れ着を身にまとうため、移動のしやすさも大切な要素です。
公共交通機関の駅やバス停から近い神社やお寺を選ぶことで、子供たちの負担を減らし、家族全員でのお出かけをスムーズに行うことができます。
家族のルーツを大切に
また、祖父母の家の近くにある神社やお寺を選ぶことで、家族の絆を深めるとともに、子供たちに家族の歴史やルーツを教える機会とすることもできます。
アクセスしやすい神社・お寺の例
以下に、アクセスの良さと子供たちの体力を考慮した神社・お寺の選び方を、表にまとめてみました。
| 神社・お寺の名前 | アクセス方法 | 特徴 |
|---|---|---|
| 氏神様が祀られている地元の神社 | 徒歩または自転車 | 地域を守る神様への感謝を表す |
| 駅近くの神社・お寺 | 電車やバスでのアクセス | 移動が楽で、晴れ着での訪問に適している |
| 祖父母の家の近くの神社・お寺 | 家族での車移動 | 家族の歴史を感じられる |
七五三のお参りは、子供たちの成長を祝うだけでなく、家族の絆を深める貴重な機会です。
アクセスの良い神社やお寺を選ぶことで、お子様にとっても親御さんにとっても、快適で心に残る一日にすることができます。
この伝統を大切にしながら、それぞれの家族にとって最適な場所を選び、素敵な思い出を作っていただければ幸いです。

お宮参りをした神社
どもが3歳、5歳、7歳になった時に行われる「七五三」。
この儀式は、子どもの健やかな成長を祝い、これからのさらなる発展を祈願するものです。
多くの家族は、お宮参りを行った同じ神社で七五三の儀式を行います。
これにより、子どもは生まれてからの成長を同じ神様が見守ってくれているという安心感を得ることができます。
子どもが大きくなった時にこれらの写真を見返すことで、家族の歴史を振り返り、子どもがどのように成長してきたかを視覚的に確認することができます。
また、子ども自身が自分の成長を感じ取る貴重な手段ともなります。
| 儀式 | 時期 | 目的 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 安産祈願 | 妊娠がわかった後 | 安産を祈願する | 選んだ神社 |
| お宮参り | 生後一ヶ月頃 | 健やかな成長を祈願する | 選んだ神社 |
| 七五三 | 3歳、5歳、7歳の誕生日 | 成長を祝い、さらなる発展を祈願する | 選んだ神社 |
このように、生まれる前から成長の各段階で同じ神社を訪れることは、単に儀式を行うという以上の意味を持ちます。
それは、家族の歴史と神様との絆を形作り、世代を超えて受け継がれる文化の象徴なのです。
どうしても有名な神社で七五三のお参りをしたい場合は?
日本の伝統的な節目として親しまれている「七五三」。
この特別な日に、多くの家族が子どもの成長を祝い、神社への参拝を考えます。
特に、名高い神社でのお参りは、その格式と雰囲気に惹かれる方も少なくありません。
しかし、そうした神社でのお参りには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
事前の準備が肝心
まず、有名な神社では参拝者が多く、特に七五三のシーズンは混雑が予想されます。
そのため、事前の下調べと予約が不可欠です。例えば、お祓いの予約は必須であり、当日になってしまうと受け付けてもらえない場合もあります。
また、専門の業者が常駐している場合も多く、衣装のレンタルや着付け、写真撮影などを一括で依頼できるサービスを利用するのも一つの手です。
駐車場の確認
大きな神社の場合、広い駐車場を完備していることが多いですが、それでも七五三の時期は混雑が予想されます。
事前に駐車場の状況を確認し、可能であれば公共交通機関の利用も検討しましょう。
移動の工夫
神社の境内は広く、移動距離が長いこともあります。
特に、子どもが履く草履では疲れやすいため、帰りは普段履きの靴に履き替えることで、子どもの負担を減らすことができます。
有名な神社を選ぶ際のポイント
神社を選ぶ際には、以下のポイントを考慮すると良いでしょう。
- 駐車場の有無
- 自宅や実家からのアクセスの良さ
- 境内の広さや砂利道の有無
これらを基準に、家族で話し合いを重ね、最適な神社を選ぶことが大切です。
着付けの計画
当日の流れとしては、「着付け → お参り → 脱衣」となります。
着付けは自宅で行うか、神社近くの業者を利用するかによっても、神社選びに影響します。
当日は忙しくなるため、スケジュールをしっかりと立てておくことが重要です。
七五三のお参りは、家族にとって大切な思い出となります。
準備や当日の忙しさはありますが、後に残る写真や思い出を楽しむためにも、事前の計画はしっかりと行いましょう。
そして、子どもの成長を家族で祝い、素敵な一日を過ごしてください。
七五三の神社の選び方は事前のリサーチが大切
日本の伝統的な節句である七五三は、子どもたちの成長を祝い、健やかな未来を願う大切な行事です。
この特別な日には、多くの家族が神社でのご祈祷を受けるために訪れます。
しかし、どの神社を選ぶかは、その日の思い出に大きく影響します。
以下は、七五三の神社選びにおける重要なポイントを、より詳細に拡張し、整理した情報です。
- 事前リサーチの重要性
- 七五三の日は多くの家族で賑わいます。そのため、快適に参拝を行うためには、事前に神社に関する情報を集め、計画を立てることが不可欠です。
- ご祈祷の予約可否
- 事前に予約が可能かどうかを確認し、可能であれば早めに予約を入れましょう。予約がない場合は、当日長時間待つことになる可能性があります。
- ご祈祷の時間
- 受付時間、待ち時間、所要時間を事前に確認し、当日のスケジュールを立てる際の参考にしましょう。
- 初穂料(ご祈祷料)の金額
- 神社によって初穂料は異なります。予算に合わせて選ぶことも大切です。
- 駐車場の有無
- 車でのアクセスを考えている場合は、駐車場の有無や混雑状況を確認しておきましょう。
- 境内の混雑状況
- 七五三の時期は特に混雑が予想されます。混雑を避けるためには、平日や早朝の参拝を検討するのも一つの方法です。
- 境内での写真撮影の可否
- 記念撮影を希望する場合は、撮影が許可されている場所を事前に確認しておきましょう。
神社選びのチェックリスト
| チェックポイント | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|
| 予約可否 | 予約が必要か、当日受付のみか | 予約できる場合は早めに |
| ご祈祷の時間 | 受付・待ち・所要時間 | スケジュール調整に役立てる |
| 初穂料 | 金額 | 予算に合わせて選ぶ |
| 駐車場 | 有無・混雑状況 | 車でのアクセス時に重要 |
| 混雑状況 | 平日・休日・時間帯 | 混雑を避けるための情報 |
| 写真撮影 | 可否・場所 | 記念撮影の計画に |
七五三の日は、子どもたちにとっても親にとっても、一生の思い出となる大切な日です。
神社選びに時間をかけ、事前のリサーチを行うことで、スムーズで心に残る素敵な一日を過ごすことができるでしょう。
七五三のシーズンの神社の混雑と対策
しかし、七五三のシーズンは多くの家族が同じ思いで神社を訪れるため、境内は大変混雑し、駐車場の確保も一苦労です。
このような状況を避けるためには、事前の下調べが不可欠です。
例えば、以下のような対策を立てることが考えられます。
| 対策 | 説明 |
|---|---|
| 事前の下調べ | 神社の混雑状況、駐車場の情報などをウェブサイトや親戚から入手します。 |
| 早めの行動 | 混雑を避けるため、開門時間に合わせて早めに出発します。 |
| 平日の利用 | 可能であれば、休日を避け平日にお参りをすることで混雑を避けられます。 |
| 荷物の最小限化 | 必要最低限の荷物で移動し、子どもが疲れないように配慮します。 |
お子様の負担を考慮した配慮
主役であるお子様が、着慣れない着物や草履で疲れてしまわないように、以下のような配慮が必要です。
- 着物の着心地: 着物は美しい伝統衣装ですが、子どもにとっては動きづらいことも。事前に着慣れる練習をすると良いでしょう。
- 履き替えの用意: 疲れた際には、草履から普段履きの靴に履き替えることで、帰り道の負担を軽減できます。
- 休憩の取り入れ: 神社内での長時間の立ち姿勢は子どもにとって大変です。適宜休憩を取り入れることが大切です。
七五三は、子どもの成長を祝うだけでなく、家族や地域社会との絆を再確認する機会でもあります。
この伝統を大切にしながら、お子様一人ひとりの健やかな成長を願い、心に残る一日を過ごしましょう。
神社の予約の仕方は?いつ予約すればいいの?

お子さんが3才、5才、7才の節目に、神社で七五三のお祝いを考えている親御さんは多いですよね。
しかし、初めてのお子さんの場合、神社でお祓いをしてもらうにはどうしたらいいのか、予約が必要なのかと悩んでしまうことも多いでしょう。
七五三では多くの神社は予約を受けています。
そのため、当日にいきなり飛び込みで行っても、断られるか、受けてもらえても予約を先に済ませるため、かなり待たされるかのどちらかになります。
大人であれば着慣れない服装であっても長時間耐えられますが、子どもはその点では難しいですから、できれば事前に日時を予約してくのがよいでしょう。
現在は七五三が11月15日と決まっているわけではなく、10月の中旬から11月の上旬の間の都合のいい日を選んで行う方が多いです。
予約は神社のHPからアクセスするか、電話で申し込むとよいでしょう。
その際、初穂料(祈祷料)を確認するのを忘れないようにして下さい。
初穂料は神社によって異なるので、必ず確認するようにしましょう。
なお、予約の開始は例年9月の上旬くらいから、それぞれの神社で始まるようです。
早めに予約をしないと希望する日時が埋まってしまう可能性もあるので、七五三を控えている場合はこまめにHPなどをチェックしておきましょう。
神社で参拝をするときの手順やマナーは?

七五三で神社に行く時は、初穂料を払ってお祓いをしてもらう以外にも、お賽銭を入れて参拝をする2通りがあります。
ただし、どちらを選ぶにしても神社に行く以上、参拝の手順やマナーなどはしっかりと覚えておきたいものですよね。
そこでここでは、神社での参拝の仕方について詳しくご紹介したいと思います。
①鳥居のくぐり方
神社には必ず鳥居がありますが、鳥居をくぐる前には服装の乱れなどがないか確認しましょう。
また、鳥居をくぐって参道を進む場合、真ん中は神様のエネルギーの通り道と言われています。
そのため、参道は真ん中ではなく端を歩くようにしましょう。
②手水舎で体を清める
参拝前に手水舎で手と口を清めます。
まずは右手で柄杓をとり、水を汲んで左手を清めます。
次に左手に柄杓を持ち替え、右手を清めます。
再び柄杓を右手に持ち替え、左手の平に水を注ぎ、その水で口をすすぎます。
すすぎ終わったら左手に水をかけて清めます。
最後に柄杓を立て、柄の部分に水を伝わせて柄を洗い、柄杓を元の位置に戻して終了です。
水は最初に一すくいするのみで、後から追加で足してはいけません。
③参拝の方法
神殿に到着したら、真ん中で参拝するのは神様に失礼にあたるので、左右どちらかにずれます。
鈴を鳴らす際は強く慣らしましょう。
これは神様に自分が来たことを知らせるためです。
お賽銭は賽銭箱に投げ入れるのではなく、そっと置くようにして入れます。
お賽銭の後は「二礼二拍手一礼」をします。
二礼をする時は背筋を伸ばし、神前に向かって腰を90度曲げ、深いお辞儀を2回行います。
二拍手は両手を胸の高さに上げ、拍手をします。
手の平を合わせたままでお願いごとをし、終わったら手を下げて深くお辞儀をして終了です。
④お祓いをしてもらう場合
祝詞やお祓いを申し込んでいる時は、水手舎で体を清めた後、社務所に行きます。
⑤神社から出る時
参拝が終わり帰宅する場合は、鳥居の前まで来たら本殿の方へと体を向けてお辞儀をしてから鳥居をくぐって帰るようにしましょう。
神社に行くときの注意点は?
①トイレは済ませておく
小さいお子さんはなかなか上手く行かない場合も多いと思いますが、神社にあるトイレは数が限られており、混みあいます。
そのため、トイレは事前に別の場所で済ませておくのがよいでしょう。
また、着物を着た後はトイレに行きづらくなるので、着付けをする前に必ずトイレに行っておくことも大切です。
②履き慣れた靴を持っていく
普段履き慣れない草履は怪我や転倒の原因になりやすく、子どもが愚図る原因になることもあります。
移動中は無理に履かせず、履き慣れた靴を履かせるのも一つの方法です。
また、草履を事前に履かせて慣らせておくのもよいでしょう。
③初穂料を忘れずに
祝詞やお祓いをする場合は、神社に初穂料を支払います。
初穂料は神社によって異なるので、事前に確認するようにしましょう。
④両親の服装は派手すぎず、カジュアルにならないものを
神社の中には参拝者全員が着物というところもあるため、できれば事前に情報などを確認しておくのがよいでししょう。
(神社の方で特に決めているわけではないですが、由緒ある神社の場合参拝者側が服装に気を遣うことが多いようです)
また、着物以外の服装で行く場合は、派手すぎたりカジュアルになるのは避けて下さい。
七五三の主役はあくまでも子どもですので、子どもを差し置いて親が華美な格好をしたり、逆に普段着と変わりのないような服装も行事にはふさわしくありません。
お父さんはスーツにネクタイ着用、お母さんはジャケットにスカート、もしくはワンピースなどの服装がよいでしょう。
七五三のお詣り当日の持ち物リスト
七五三を迎えるお子さんは、慣れない着物で動きにくく、泣いてしまったり、機嫌が悪くなってしまう可能性があります。
参拝当日に持っていくと良い持ち物をピックアップしました。
| ✔ | 持ち物 | |
|---|---|---|
| 初穂料(のし袋) | ご祈祷をする場合はのし袋に新札を入れて神社に納めます | |
| 履き慣れている靴 | 慣れない草履は神社の中だけでOK。足が痛くなる前に普段の靴に履き替えましょう | |
| 替えの洋服 | 着慣れない着物は動きにくいため、参拝が終わったら着替えられるように用意しておきましょう | |
| タオル | 着物の帯が下がったときに着物と帯の間にはさんで着崩れを直します | |
| 洗濯バサミ | トイレや手洗いなどで着物が濡れるのを避けるため、たもとや裾を留めるのに便利です | |
| ヘアピン | 髪型が崩れたときに使えます | |
| ばんそうこう | 鼻緒ずれしたときの応急処置として使えます | |
| お菓子・飲み物 | お子さんの気分を変えるため、一口で食べられるお菓子や飲み物を用意しておきましょう | |
| シールブック・絵本など | お子さんが待ち時間に退屈しないよう音が出ないおもちゃや遊び道具を持っていくと安心です | |
| 小物を入れるジッパー付きの袋 | 取った髪飾りや濡れたものを入れられる保存袋があると便利です | |
| 暑さ対策グッズ | 残暑が残る時期はハンディファンや保冷剤などで暑さ対策をしましょう | |
| 寒さ対策グッズ | 寒い時期は暖房設備のない社殿もあるため、カイロ・ひざかけなどで防寒しましょう |
七五三の時になぜ、神社にお参りするの?
昔は乳幼児の死亡率が高く、7才まで生きられない子どもが多かったので、子どもは「7つまでは神のうち」と言われていました。
これは、7才になるまでは神様から預かった子どもという意味で、無事に7才まで育った際には神様にお礼をしようというのが七五三の始まりと言われています。
七五三のお祝いを神社で行うのは、その地域の守る氏神様が神社にいるからです。
そのため、本来の七五三では自宅から近い神社で行事を行うのが習わしとなっています。
しかし、最近は神社が近くにない場合や、神社はあっても神主がいくつかの神社を兼任していて、不在であることも増えており、必ずしも近くの神社でなければいけないというわけではなさそうです。
なお、七五三は毎年11月15日に行うとされています。
これは、11月15日は旧暦では霜月の十五夜にあたり、この日が元々作物の収穫を祝う行事が行われていたことから、子どもの成長を祝うのにふさわしい日とされ、あらかじめ日付が決まっています。
ただしこれも、最近は仕事などで忙しい家庭が増えていることから、神社によっては10月の中旬から11月の上旬まで七五三のお祓いが予約できるところが増えているようです。



七五三の神社の選び方のまとめ
いかがでしたか。
地元の神社、有名な神社、お宮参りをした神社。
それぞれに良さがありますね。
どの場所を選んでも、わが子の大切な節目の日、七五三の晴れの日を家族でお祝いできることがいちばんの思い出になります。
それぞれのご家族にとって、素敵な七五三のお参りができるといいですね。
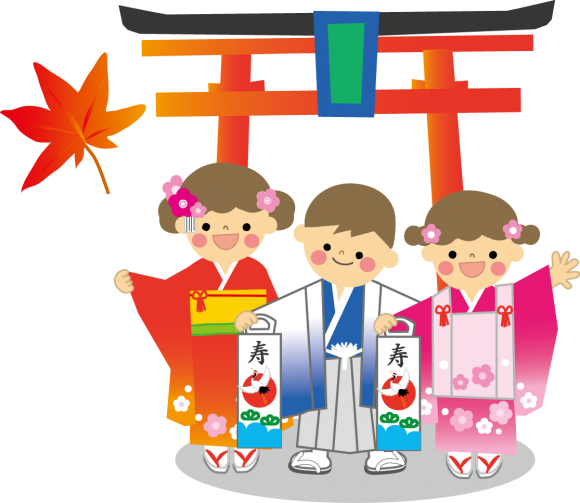





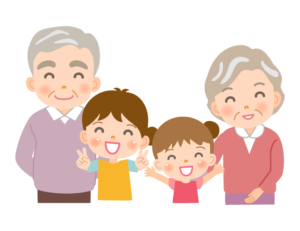


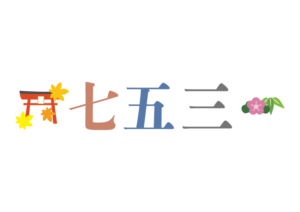


コメント