初秋の候を使う時期や使い方と読み方、例文などをまとめています。
秋の時候の挨拶に使われる初秋の候ですが、秋とは一体いつのことなのか気になりませんか?
紅葉や落葉が綺麗な時期になれば、初秋の候を使うのか知りたいですよね。
そこで今回は、初秋の候について詳しく調べてみました。
初秋の候を使う時期はいつ?
初秋の候は、手紙やメールでの挨拶として、8月上旬から9月上旬に使用できます。
この時期は、夏の暑さが少しずつ和らぎ、秋の気配が感じられるようになる頃を指します。
「秋」と言えば、涼しく紅葉の始まる10月を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、この場合の「秋」は二十四節気に基づいています。
二十四節気とは、古代中国で作られた季節の区分法で、1年を24の節気に分けたものです。
具体的には、立秋から白露までの期間が初秋とされます。
立秋と白露の具体的な日付
- 立秋: 例年8月7日~8日頃
- 白露: 例年9月7日~8日頃
したがって、立秋を過ぎてから白露までの約1ヶ月間が「初秋の候」を使用する適切な時期となります。
この期間はまだまだ暑い日が続くこともありますが、朝夕には涼しさを感じることも増え、秋の訪れを感じさせる時期です。
特に、立秋の日付が近づくと、夏の終わりを告げる虫の音が聞こえ始めたり、空の色が少しずつ変わってきたりと、自然の変化を楽しむことができます。
二十四節気の区分表
| 節気 | 時期 | 季節 |
|---|---|---|
| 立秋 | 8月7日~8日頃 | 秋の始まり |
| 処暑 | 8月23日~24日頃 | 暑さが和らぐ |
| 白露 | 9月7日~8日頃 | 朝露が白くなる |
このように、日本の季節感を豊かに表現する「初秋の候」を用いることで、受け手に季節の移り変わりを感じてもらい、親しみやすい印象を与えることができます。
ぜひ、日常の挨拶やお手紙に取り入れてみてください。
初秋の候の意味や読み方は?
初秋の候は「しょしゅうのこう」と読みます。
秋の初めを表す言葉で、読み方や意味をしっかり理解することが大切です。
初秋とは?
初秋はその名の通り、秋の初めを指します。
具体的には、二十四節気の立秋から始まり、処暑までの期間を含みます。
二十四節気は一年を24の節気に分けたもので、古代中国から伝わった暦法です。
| 節気 | 読み方 | 時期 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 立秋 | りっしゅう | 8月7日頃 | 暦の上で秋が始まる |
| 処暑 | しょしょ | 8月23日頃 | 暑さが和らぐ |
これらの節気を含む初秋は、夏から秋への移り変わりを感じる時期でもあります。
候の読み方と意味
「候」は「こう」と読み、時候や気候、季節を表します。
しばしば「候(そうろう)」と読みたくなりますが、これは「~でございます」という意味になるため、意味が異なります。
例えば、「時候の挨拶」のように使われる「候(こう)」は、季節の挨拶を表すものです。
初秋の候は、季節の移り変わりを感じさせる美しい日本語表現です。
この言葉を正しく理解し、適切に使うことで、より豊かな表現が可能になります。
暦の上での秋の始まりである初秋を意識しながら、季節の挨拶として大切に使いましょう。
初秋の候の正しい使い方は?
8月上旬から9月上旬にかけて使われる「初秋の候」という表現は、実際にはまだ夏の暑さが続いているため、秋というよりも夏を感じる方が多いかもしれません。
しかし、初秋の候を正しく使うためには、この時期の気候感覚を理解し、新暦と旧暦の違いに注意することが重要です。
使い始めるタイミング
具体的には、8月上旬から9月上旬にかけてが「初秋の候」を使うべき時期です。
多くの方が体感的に秋を感じ始める9月下旬や10月に「初秋の候」を使用するのは誤りとなります。
新暦で秋を感じる時期に使いたくなるかもしれませんが、時候の挨拶は旧暦に基づいているため、正確な季節感を持つことが大切です。
季節感のズレについて
旧暦と新暦の季節感のズレは、次の表に示すように、旧暦の各月が新暦のどの時期にあたるかを理解することで明確になります。
| 旧暦の月 | 新暦の対応期間 |
|---|---|
| 1月 | 2月上旬~3月上旬 |
| 2月 | 3月上旬~4月上旬 |
| 3月 | 4月上旬~5月上旬 |
| 4月 | 5月上旬~6月上旬 |
| 5月 | 6月上旬~7月上旬 |
| 6月 | 7月上旬~8月上旬 |
| 7月 | 8月上旬~9月上旬 |
| 8月 | 9月上旬~10月上旬 |
| 9月 | 10月上旬~11月上旬 |
| 10月 | 11月上旬~12月上旬 |
| 11月 | 12月上旬~1月上旬 |
| 12月 | 1月上旬~2月上旬 |
この表からも分かるように、旧暦の8月は新暦の9月上旬から中旬に該当します。
つまり、この時期が「初秋の候」を使う適切なタイミングとなります。
正しい使用例
手紙やはがきで「初秋の候」を使用する場合の例を挙げてみましょう。
- 初秋の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
- 初秋の候、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
このように、旧暦に基づいて適切な時期に使うことで、相手に正しい季節感を伝えることができます。
「初秋の候」は、8月上旬から9月上旬にかけて使うのが正しい時候の挨拶です。
旧暦と新暦の季節感のズレを理解し、適切な時期に使用することで、相手に対して正確な季節の移ろいを伝えることができます。
秋の言葉を正しく使うためにも、旧暦に基づいた時候の挨拶を心がけましょう。
時候の挨拶を使った具体的な書き方(基本文例)
文例をご紹介しますが、基本的な構成が決まっていますので、まずは基本形をどうぞ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1.頭語 | 拝啓 |
| 2.時候の挨拶・書き出し | 〇〇の候、貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 |
| 3.本文・用件 | 本文の内容はここに記入します。手紙を書こうと思った気持ちを思い出しながら、筆を進めてください。 |
| 4.結びの言葉 | 〇〇の季節も過ぎましたが、御社のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。 |
| 5.結語 | 敬具 |
| 6.日付 | 令和〇〇年〇月〇〇日 |
| 7.送り主 | 初秋太郎 |
| 8.宛先 | 〇〇〇〇様 |
ポイント:
- 頭語と結語は決まり文句です。これらはそのまま使用します。
- 時候の挨拶では、季節感を出すことが大切です。季節に合った挨拶を選び、天候や気候に言及して具体的な情景を思い浮かべられるようにします。また、相手の健康を気遣う言葉を加えることで、相手への思いやりを表現します。
- 句読点やスペースを適切に使い、読みやすい文章を心掛けます。
- 親しい友人に対しても、基本的な形式を押さえつつ、個人的なメッセージを加えることで、温かみのある手紙を作成できます。
初秋の候を使った例文
初秋の候を使った時候の挨拶の例文をご紹介します。
仕事先の関係者やお世話になった恩師、友人や知人などに出す手紙やはがきの書き出しに悩んでいるという方は、ぜひ参考になさってみてください。
ビジネスで使う場合
- 謹啓 初秋の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のお引き立てをいただき、ありがたく御礼申し上げます。
- 謹啓 初秋の候、新涼が心地よい今日この頃、貴社ますますご清栄のことと存じ上げます。平素はご愛顧を賜り心からお礼申し上げます。
- 拝啓 初秋の候、貴店ますますご発展のこととお慶び申し上げます。長年にわたりひとかたならぬご高配を賜り、心よりお礼申し上げます。
目上の人に使う場合
- 謹啓 初秋の候、〇〇様にはますますご壮健のこととお慶び申し上げます。
- 拝啓 初秋の候、残暑もようやく和らぎましたが、ご家族様におかれましてはお変わりなくお過ごしとのこと心よりお慶び申し上げます。
親しい人に使う場合
- 初秋の候、今年は格別に残暑が厳しいようですが、お元気にお過ごしですか
- 初秋の候、暑さ寒さも彼岸までと申しますが、皆様もお変わりなくお過ごしでしょうか。
初秋の候の結び文
結び文とは、手紙やはがきの最後に締めくくりとして書く文章のことを言います。
結び文は時候の挨拶に合ったものを使うのがよいでしょう。
ここでは、初秋の候を時候の挨拶に取り入れた場合の、結び文の例文をいくつかご紹介します。
- 実り多き秋をお過ごしになられることを、心よりお祈り申し上げます。
- 立秋とは名ばかりの暑さ続きでございます。夏風邪など召されませぬようご自愛ください。
- 残暑厳しき折、皆様方のご無事息災を心よりお祈り申し上げます。
初秋の候を使うときに注意すること
手紙やはがきに時候の挨拶を取り入れる際、多くの方は相手に対する丁寧な気持ちを表現しようと心掛けますよね。
しかし、特にビジネスで送る手紙やはがきにおいては、時候の挨拶だけでは十分な丁寧さを伝えることが難しい場合もあります。
まず、手紙やはがきの書き出しには必ず「頭語」を使用することが求められます。
頭語とは、文章の冒頭に書く「拝啓」や「謹啓」などの言葉で、これが「こんにちは」という意味合いを持っています。
「拝啓」は「謹啓」よりもさらに丁寧な表現となります。
頭語と結語の対応関係については、以下の表をご覧ください。
| 頭語 | 結語 |
|---|---|
| 拝啓 | 敬具、敬白 |
| 謹啓 | 謹白、謹言 |
たとえば、「拝啓」で始めた文章は必ず「敬具」または「敬白」で終わらせることが必要です。
同様に、「謹啓」で始めた場合は「謹白」もしくは「謹言」で締めくくります。
このように、頭語と結語を正しく組み合わせることで、文章全体がより一層丁寧で整った印象になります。
時候の挨拶自体は非常に丁寧な表現ですが、特に大切な方やビジネスの相手に送る手紙やはがきには、頭語と結語を必ず付け加えるようにしましょう。
これにより、相手に対する敬意や丁寧さをしっかりと伝えることができます。
なお、友人や知人など親しい間柄の場合、必ずしも頭語を使う必要はありません。
親しい関係性に応じたカジュアルな表現を用いることで、より自然なコミュニケーションを図ることができます。
このように、手紙やはがきの書き方には細やかな注意が必要です。
特にビジネスシーンでは、丁寧さと適切なマナーを守ることが重要ですので、ぜひ参考にしてみてください。
初秋の候に関するよくある質問
| 質問 | 答え |
|---|---|
| 1. 「初秋の候」とは何ですか? | 「初秋の候」は手紙の冒頭で使われる季節の挨拶で、初秋を迎える頃の時期を指します。 |
| 2. 「初秋の候」はいつの時期に使いますか? | 主に8月下旬から9月上旬の間に使います。 |
| 3. 「初秋の候」はどのような文脈で使われますか? | 主に手紙やメールの冒頭で、相手への季節の挨拶として使われます。 |
| 4. 「初秋の候」はどのように書くのが一般的ですか? | 手紙やメールの冒頭に「初秋の候、いかがお過ごしでしょうか。」のように書きます。 |
| 5. 「初秋の候」の類義語は何ですか? | 「残暑の候」や「新秋の候」が類義語にあたります。 |
| 6. 「初秋の候」はビジネス文書で使えますか? | はい、ビジネス文書でも使えます。季節の挨拶として適切です。 |
| 7. 「初秋の候」を使う際の注意点は何ですか? | 季節外れにならないよう、適切な時期に使うことが重要です。また、相手に合った丁寧な表現を心がけるべきです。 |
| 8. 「初秋の候」と合わせて使う言葉はありますか? | 「初秋の候、お変わりなくお過ごしでしょうか。」のように、相手の健康や近況を尋ねる言葉と合わせて使います。 |
| 9. 「初秋の候」を使った文例はありますか? | 「初秋の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。」 |
| 10. 「初秋の候」を英語で表現するとどうなりますか? | 英語では “In the early autumn season,” と訳されます。 |
初秋の候以外の8月の時候の挨拶はある?
初秋の候が使える8月には、初秋の候以外にも時候の挨拶があります。
ここでは初秋の候以外の8月に使う時候の挨拶をご紹介します。
残暑の候
8月上旬の立秋から8月末まで使える時候の挨拶です。
この時期には残暑見舞いを出す方も多いと思いますが、残暑の候を時候の挨拶として手紙やはがきを出すことができますよ。
立秋の候
二十四節気の立秋の期間に使える時候の挨拶です。
立秋は例年8月7~8日頃になり、次の節気である処暑が例年8月22~23日頃になるので、それまで使うことができます。
立秋の立つには入る、始まるという意味があるので、まさに秋の始まりに出す手紙やはがきにぴったりの時候の挨拶と言えますね。
処暑の候
二十四節気の処暑にあたる時期に使える時候の挨拶です。
処暑は8月中旬(例年22~23日頃)から9月上旬の白露までとなっています。
処暑には暑さがだんだんと収まるという意味があります。
早涼の候
8月上旬の立秋を過ぎてから、8月下旬まで使える時候の挨拶です。
立秋を過ぎて暦の上では秋となり、少しずつ涼しさを感じるようになりました、という意味で使われます。
現在では8月下旬も最高記録を更新することもありますが、時候の挨拶として使っても問題はありません。
秋暑の候
8月上旬の立秋から下旬まで使える時候の挨拶になります。
暦の上では秋になったにも関わらず、夏のような暑さが続くという意味で使われるものです。
現在の気候にも意味が合っているので、使いやすい時候の挨拶ですね。
Wordであいさつ文や定型文を挿入する方法
仕事上で取引先の相手にあいさつ文を送る、目上の人に手紙やはがきを出す時などに、「書き出しに悩んでしまい、なかなか作業が進まない」なんてことはよくあるのではないでしょうか。
そのような時はWordを利用してみましょう。
Wordにはあいさつ文のテンプレートがあるので、参考にすると作業が捗りやすくなりますよ。
ここではwordを使ったあいさつ文や定型文の挿入方法をご紹介します。
手順
①Wordを開きます
②挿入タブをクリックします
③テキストのところにある「あいさつ文」をクリックします
④あいさつ文の挿入を選びます
⑤何月のあいさつ文を作成するのか、最初に月を選びましょう
⑥月のあいさつ、安否のあいさつ、感謝のあいさつをそれぞれ選びます
⑦選んだら「OK」をクリックしてください
⑧Wordに選んだ文章が表示されます
ポイント
Wordにはあいさつ文だけではなく、あいさつ文の後に続ける「起こし言葉」や「結び言葉」も選ぶことができますよ。
挿入タブ→テキストのあいさつ文をクリックした後、起こし言葉もしくは結び言葉を選んでください。
初秋の候のまとめ
初秋の候は二十四節気の立秋から次の節気である処暑まで使える時候の挨拶です。
具体的な期間は例年8月7~8日頃から22~23日頃になりますよ。
現在ではこの期間と言えばまだまだ夏の暑い盛りとなりますが、時候の挨拶は旧暦に沿って行うものなので問題ありません。
むしろ、体感的に秋を感じる時期に初秋の候を使うのは間違いなので、使用のタイミングには注意をしてくださいね。






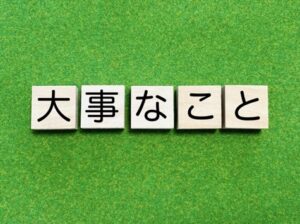

コメント