霜降の候と聞いて、皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか?
この美しい日本語のフレーズは、秋の深まりを感じさせる時期にふさわしい言葉ですが、実際にいつ使うのが適切なのか、その読み方や使い方については意外と知られていないかもしれません。
日本の伝統的な挨拶文化には、季節の移ろいを感じさせる独特の表現が数多く存在します。
その中でも「霜降の候」は、秋の終わりを告げる特別な時期を象徴しています。
しかし、具体的にどのようにしてこの表現を日常のコミュニケーションに取り入れれば良いのでしょうか?
この記事では、霜降の候の正しい使い時や読み方、さらにはビジネスやプライベートでの使い方の例文、そして手紙の結びの言葉まで、詳しくご紹介します。
季節の挨拶を通じて、より豊かなコミュニケーションを目指しましょう。
- 「霜降の候」を使う適切な時期と使用期間。
- 「霜降の候」の読み方と意味。
- 「霜降の候」の正しい使い方の例。
- 「霜降の候」を使うときの手紙の結びの言葉と使い方。
霜降の候を使う時期はいつ?

霜降の候を使う時期は、10月22日頃から11月6日頃となっています。
時候の挨拶によって使える時期は変わり、また期間もそれぞれで違います。
霜降の候は秋の時期に、2週間程度使える時候の挨拶ということになりますね。
霜降の候の意味や読み方は?
時候の挨拶は音読みすることが多く、霜降の候も全て音読みで「そうこうのこう」と読みますよ。
霜降とは霜が降りると書く通りの意味で、候には時期や時候などの意味があることから、霜降の候には「霜が降りる時期になりましたね」という意味があります。
霜降の候の正しい使い方は?

霜降は二十四節気の名称で、その名の通り、霜が降りる時期という意味があります。
しかし、二十四節気は中国の気候が元になっていることや、現在の新暦と二十四節気が作られた旧暦では暦に違いがあることなどから、実際の状況とは異なる場合が多々あります。
霜降も、実際に10月下旬に霜が降りる地域は少なく、紅葉が始まるくらいのタイミングであることが多いでしょう。
ですが、二十四節気にちなんだ時候の挨拶は状況に関係なく使うことができるため、霜降の候は霜が降りていなくても使える時候の挨拶になりますよ。
なお、霜降の霜は霜柱とは違います。
霜降の霜は気温が下がり、大気中の水分が結晶化したものが草木に付着した現象のこと。
一方の霜柱は先に地表の水分が凍り、そこから土中の水分が吸い上げられて凍り、柱となったものを指しています。
霜降は草木につく霜を指しています。
霜降の候を使った例文

手紙やはがきなどを書くこと自体はよくある機会だとしても、霜降の候のような時候の挨拶を使うことは多くはないという方も多いですよね。
特にビジネス関係者や目上の人に使う場合は、失礼のないように注意したいもの。
そこでここでは、霜降の候を使った例文をご紹介します。
書き出しに悩んでしまう方は参考にしてみて下さい。
ビジネスで使う場合
目上の人に使う場合
親しい人に使う場合
なお、親しい人には霜降の候のような時候の挨拶を使う必要はありません。
霜降の候などの〇〇の候は、時候の挨拶の中では漢語調といい、かしこまった表現となります。
ビジネス関係者や目上の人に漢語調を使うのはマナーですが、親しい人に使うとよそよそしくなってしまうので、親しい人に時候の挨拶を使う時は、漢語調よりもカジュアルな口語調を使うのがよいでしょう。
書き出しとしては、例文の霜降の候を外して、「スポーツの秋となりました。ゴルフの調子はいかがでしょうか。」と始めてもよいですし、「二十四節気では霜が降りる時期となりました。
寒さにめげず、お元気にしていますか」のような書き出しがよいでしょう。
霜降の候の結び文
結び文には季節に関係なく使える定型文がありますが、時候の挨拶の季節感に合わせた結び文にすると、文章全体に統一感やまとまりが生まれます。
ただし、結び文には時候の挨拶で使った言葉や内容は使わないようにして下さい。
ここでは、霜降の候の結び文の例文をご紹介します。
霜降の候を使うときに注意すること

霜降の候を使うときに注意したいのは、文章の冒頭にいきなり霜降の候がくるのはマナーとしてNGとなる場合がある、ということです。
特にビジネス関係者や目上の人に送る手紙やはがきなどには注意が必要です。
霜降の候の前に必ず、頭語をつけるようにしましょう。
頭語には様々な種類がありますが、一般的によく使われているのは「謹啓」と「拝啓」です。
これらには「謹んで申し上げます」という意味があり、相手への敬意を表すことができますよ。
また、文章の冒頭に頭語をつけたら、終わりは結語で締めるのもマナーになります。
頭語と結語は対になっており、「謹啓」の結語は「謹言」もしくは「謹白」、「拝啓」の結語は「敬具」または「敬白」と決まっています。
なお、女性のみですが、どの頭語でも結語に「かしこ」をつけることができます。
ですが、「かしこ」はややカジュアルな印象を与えるため、ビジネス関係者や目上の人には使わないようにしましょう。
霜降の候以外の10月の時候の挨拶はある?

霜降の候は10月下旬にしか使えないため、10月上旬や中旬に使える時候の挨拶が知りたい方は多いですよね。
そこでここでは、霜降の候以外に10月に使える時候の挨拶をご紹介します。
菊花の候
菊花の候は10月上旬から11月上旬に使える時候の挨拶です。
菊の花が見ごろの時期になりましたね、という意味がありますが、菊は種類などによって6~12月に咲くため、手紙やはがきなどを送る相手の地域の状況に合わせて使うのがよいでしょう。
なお、菊は秋を代表する花となっていますよ。
金風の候
金風の候は10月全般に使える時候の挨拶です。
金風とは秋に吹く風のことで、金風の候には「心地より秋風が吹く時期になりましたね」という意味がありますよ。
夜長の候
夜長の候は10月上旬から中旬に使える時候の挨拶です。
秋の夜長という言葉もある通り、秋から冬にかけては日中よりも夜が長くなっていきます。
錦秋の候
錦秋の候は10月上旬から11月上旬の立冬の前日まで使える時候の挨拶になります。
紅葉がまるで織物のように美しいという意味がある錦秋は、紅葉が最盛期を迎えたタイミングで使うのがよいでしょう。
ただし、紅葉のシーズンは地域によってズレがあるため、手紙やはがきなどを送る場合には相手の地域に合わせるようにしましょう。
晩秋の候
晩秋の候は10月上旬から11月上旬まで使える時候の挨拶です。
晩秋とは旧暦で秋の終わりを指す名称で、二十四節気の寒露と霜降が該当します。
Wordであいさつ文や定型文を挿入する方法
仕事上で取引先の相手にあいさつ文を送る、目上の人に手紙やはがきを出す時などに、「書き出しに悩んでしまい、なかなか作業が進まない」なんてことはよくあるのではないでしょうか。
そのような時はWordを利用してみましょう。
Wordにはあいさつ文のテンプレートがあるので、参考にすると作業が捗りやすくなりますよ。
ここではwordを使ったあいさつ文や定型文の挿入方法をご紹介します。
手順
①Wordを開きます
②挿入タブをクリックします
③テキストのところにある「あいさつ文」をクリックします
④あいさつ文の挿入を選びます
⑤何月のあいさつ文を作成するのか、最初に月を選びましょう
⑥月のあいさつ、安否のあいさつ、感謝のあいさつをそれぞれ選びます
⑦選んだら「OK」をクリックしてください
⑧Wordに選んだ文章が表示されます
ポイント
Wordではあいさつ文だけではなく、あいさつ文の後に続ける「起こし言葉」や「結び言葉」も選ぶことができますよ。
挿入タブ→テキストのあいさつ文をクリックした後、起こし言葉もしくは結び言葉を選んでください。
霜降の候のまとめ
霜降の候という美しい日本の季節の挨拶は、10月22日頃から11月6日頃に使われます。
この言葉は「そうこうのこう」と読み、霜が降りる時期を表しています。
ビジネスシーンや目上の方への手紙では、敬意を込めた表現として活用できますし、親しい人へはもう少しカジュアルな形で使うこともできます。
また、手紙の結びには季節感を反映した言葉を選ぶことで、より心温まるメッセージを送ることができます。
この記事を通じて、霜降の候の使い方や意味を深く理解し、日本の美しい季節の挨拶を日常のコミュニケーションに取り入れることができるでしょう。
この記事のポイントをまとめますと
- 霜降の候の使用時期:10月22日頃から11月6日頃
- 読み方:「そうこうのこう」と音読み
- 意味:霜が降りる時期を表す
- 二十四節気の一つ:中国の気候に基づく
- 実際の気候とのズレ:旧暦と新暦の違いによる
- 霜降と霜柱の違い:霜降は草木に付着する結晶化した水分
- ビジネスでの使い方:敬意を込めた挨拶として
- 目上の人への使い方:尊敬の念を示す
- 親しい人への使い方:カジュアルな表現が適切
- 時候の挨拶のマナー:頭語と結語の使用
- 他の10月の時候の挨拶:菊花の候、金風の候など

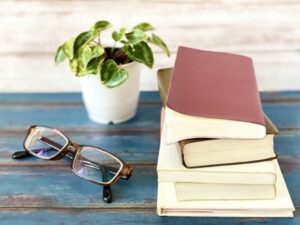

コメント