「惜春の候」っていつ使うの?どんな意味があるの?どう読むの?と思われる方も多いのではないでしょうか。
さらに、例文や使い方、手紙やはがきでの書き方、書き出しから結びまで、正しく、そして心を込めて伝えるにはどうしたらいいのか、迷ってしまうことも。
この記事では、そんな「惜春の候」についてのあらゆる疑問を解決します。
4月上旬から5月上旬のこの美しい時期に、あなたの気持ちを形にするためのヒントをたくさんご紹介します。
読み終わる頃には、誰にでも心温まる挨拶が書けるようになっているはずですよ。
- 「惜春の候」を使う正しい時期が4月上旬から5月上旬であることがわかります。
- 「惜春の候」の読み方が「せきしゅんのこう」であることが理解できます。
- 「惜春の候」の意味や背景、季節の移り変わりに対する心情を表す言葉であることが学べます。
- 手紙やはがきでの「惜春の候」の使い方、書き出しから結びまでの具体的な書き方や例文が得られます。
惜春の候を使う時期はいつ?読み方や意味は?
惜春の候を使う時期はいつからいつまで?
惜春の候は4月上旬から5月上旬まで使える時候の挨拶になります。
旧暦では春を初春・仲春・晩春の3つにわけており、惜春は晩春の季語となるため、晩春に該当する4月上旬から5月上旬に使えるということになりますよ。
ただし、実際に惜春の候を使う場合には注意点も必要です。
詳しくは「惜春の候の正しい使い方」で解説しているので、併せてご覧ください。
惜春の候の読み方
惜春の候の意味
「惜春の候」は「過ぎ行く春を惜しむ季節になりましたね」という意味の言葉です。
「惜春」という言葉には、過ぎ去る春を惜しむ、つまり春の終わりに感じるあの特有の感慨深さが込められています。
暖かくて心地よい春の日々が過ぎ去るのが惜しい、もう少し春の訪れと共に花開いた世界に留まりたい、そんな気持ちを表現しているのです。
一方、「候」という言葉は、季節や気候を指し示す古語です。
したがって、「惜春の候」は文字通りには「春を惜しむ季節」という意味合いになります。
この時期は、自然界が次の季節へと移り変わる準備を始める時であり、人々はその変化に対する感慨を新たにします。
具体的には、この時期の特徴として、暖かな日差しは徐々に強まり、春の花はその彩りを失い始め、新緑の輝きはより一層鮮やかになります。
空は高く澄み渡り、初夏の訪れを告げる風が吹き始めるのです。
人々はこの変わりゆく自然の中で、春の終わりを惜しみつつも、次の季節への期待を胸に新たな日々を迎える準備をします。
「惜春の候」は、そんな移り変わりゆく自然の姿と、それに対する私たちの心情を美しく象徴する言葉です。
この言葉を通して、季節の移ろいの中で感じる一瞬一瞬の美しさや切なさを、改めて噛みしめることができるのではないでしょうか。
惜春の候の正しい使い方は?

旧暦の春は1~3月になり、1月を初春、2月を仲春、3月を晩春としていました。
旧暦と新暦には1ヵ月程度のズレがあることから、旧暦3月は新暦の4月に該当するため、惜春の候は4月上旬から5月上旬に使える時候の挨拶となります。
しかし、4月上旬は春を惜しむ時期というよりは、春真っ盛りと感じる方が多いのではないでしょうか。
それには桜の開花が関係しているかも知れません。
関西や関東では3月中旬から下旬に開花を迎えるため、4月上旬は桜が満開を迎えている地域が多いですよね。
そのため、惜春の候は桜が散った4月中旬から下旬に使うと、しっくりと感じる人が多いでしょう。
また、東北は4月上旬、北海道は4月下旬に開花なので、4月上旬にはまだ桜が咲いていないこともあります。
これらの地域にお住まいの方に出す手紙やはがきに惜春の候を使うなら、4月下旬から5月上旬が最もよいタイミングと言えそうですよね。
惜春の候と桜の開花に関係性はないのですが、「日本人にとって春の象徴である桜を楽しむ前に惜春と言われても・・」と思う方は多いのかも知れません。
地域の状況に合わせて使うタイミングを工夫してみるのがよいでしょう。
惜春の候を使った例文

ビジネス関係者や目上の人に送る手紙やはがきは、書き出しに悩む方は多いですよね。
失礼のないようにするには、どのような文章がよいのでしょうか。
そこでここでは、惜春の候を使った例文をご紹介しますので、ぜひ参考になさってみてください。
ビジネスで使う場合
書き出し文
- 謹啓 惜春の候、貴社におかれましては益々ご盛栄の御事慶賀の至りに存じます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
- 拝啓 惜春の候、貴社にはますますご清栄の由大慶に存じます。日頃は格別のお引き立てをいただき、ありがたく御礼申し上げます。
- 拝啓 惜春の候、貴社におかれましてはなお一層のご発展のことと大慶至極に存じます。毎々格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
結び文
- 春の光が眩しい季節になりました。貴社の更なる繁栄を心から願っています。
- 若草が輝く、美しい時期に差し掛かりました。貴社がさらに忙しく、成功されることを願っております。
- 初夏を感じさせる風が吹き始める季節です。貴社の発展と活躍を深く祈願しています。
目上の人に使う場合
書き出し文
- 謹啓 惜春の候、〇〇様にはいっそうご活躍のことと慶賀の至りに存じます。
- 拝啓 惜春の候、皆様におかれましてはますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。
- 拝啓 惜春の候、〇〇様より一層ご活躍の段と存じます。
結び文
- 緑が生い茂るこの季節にあたり、○○様の更なるご成功を心より願っております。
- 温かな夏風を感じさせる素晴らしい季節になりました。皆様の益々の繁栄を心から祈念しております。
- 五月の澄み切った青空が広がるこの時期、○○様には特に健康管理に注意を払い、充実した日々を送っていただけますようお願い申し上げます。
親しい人に使う場合
書き出し文
- もうすぐ立夏を迎える時期になりました。○○様、お元気でお過ごしでしょうか。
- 心地良い季節が到来し、涼しい風が吹いていますが、風邪などお召しではないでしょうか。
- 新緑が眩しいこの時期、○○様が健康でいらっしゃることを願っております。
結び文
- 野山が緑に包まれる美しい季節がやってきました。○○様も健やかにこの時期を楽しまれますようにお過ごしください。
- 空に向かって勇壮に泳ぐ鯉のぼりを見ることができる季節が到来しました。○○様の一層の成功と飛躍を心から願っております。
- 新茶の香りが漂い始めるこの時期、○○様が健康で何事もなく過ごされますよう、心よりお祈り申し上げます。
結び文とは?
季節に関係なく使える定型文もありますが、時候の挨拶に合わせた季節の事柄などを盛り込むと、文章全体に統一感や風情が出ますよ。
ここでは、惜春の候を時候の挨拶に使った場合の、結び文の例文をご紹介します。
なお、結び文は時候の挨拶と言葉が被らないようにしてください。
- 新緑の眩しい季節 社業一層のご発展とご活躍をお祈り申し上げます。
- 天候不順の時節柄、ご自愛専一にてご精励くださいますようお願い申し上げます。
- 新年度で忙しい毎日と思います。健康にはくれぐれも気を付けてくださいね。
惜春の候を使うときに注意すること

時候の挨拶には漢語調と口語調があり、惜春の候などの〇〇の候は漢語調になります。
漢語調は口語調よりも丁寧な表現になるため、漢語調の時候の挨拶を使えばそれだけで丁寧な文章になると思ってしまう方もいるようです。
しかし、ビジネス関係者や目上の人に送る手紙やはがきでは、いくら漢語調であっても文章の書き出しが時候の挨拶では失礼になってしまいます。
ビジネス関係者や目上の人に送る場合は、時候の挨拶の前に頭語をつけましょう。
頭語とは「拝啓」や「謹啓」などのことで、これらには「つつしんで申し上げます」という意味があり、相手への敬意を示しますよ。
また、頭語には必ず結語がセットとなり、文章の締めくくりにつける必要があります。
「拝啓」の結語は「敬具」または「敬白」、「謹啓」の結語は「謹言」もしくは「謹白」になりますよ。
頭語には「前略」などがありますが、こちらは丁寧な言い方とはならないので、ビジネス関係者や目上の人には使わないようにしましょう。
惜春の候以外の4月の時候の挨拶はある?

惜春の候は4月上旬から使える時候の挨拶ですが、よりよいタイミングとしては4月下旬となるため、使える期間は短めとなっています。
そのため、惜春の候以外に使える4月の時候の挨拶が知りたいという方も多いでしょう。
そこでここでは、4月に使える惜春の候以外の時候の挨拶をご紹介します。
春暖の候
3月中旬から4月中旬まで使える時候の挨拶になります。
春の陽気が少しずつ強くなるという意味があるため、すでに気温が高くなっている地域では使わない方がよいでしょう。
陽春の候
4月初めから終わりまで使える時候の挨拶になります。
陽春とは春の麗らかな陽気で満たされているという意味になりますよ。
ただしこちらも、4月に入ると夏らしい陽気が続く地域もあるため、状況などに合わせて使うのがよいでしょう。
春爛漫の候
4月中に使える時候の挨拶です。
春爛漫とは春の花が咲き乱れている様子を表していますよ。
麗春の候
4月下旬から5月上旬に使える時候の挨拶になります。
麗春とはひなげしのことで、ひなげしが咲く時期に使える時候の挨拶です。
晩春の候
二十四節気の清明(例年4月4日頃)から立夏(例年5月4日頃)の前日まで使える時候の挨拶になります。
旧暦では春を初春・仲春・晩春の3つにわけており、晩春とは文字通り春の終わりの時期を指しています。
Wordであいさつ文や定型文を挿入する方法
仕事上で取引先の相手にあいさつ文を送る、目上の人に手紙やはがきを出す時などに、「書き出しに悩んでしまい、なかなか作業が進まない」なんてことはよくあるのではないでしょうか。
そのような時はWordを利用してみましょう。
Wordにはあいさつ文のテンプレートがあるので、参考にすると作業が捗りやすくなりますよ。
ここではwordを使ったあいさつ文や定型文の挿入方法をご紹介します。
手順
①Wordを開きます
②挿入タブをクリックします
③テキストのところにある「あいさつ文」をクリックします
④あいさつ文の挿入を選びます
⑤何月のあいさつ文を作成するのか、最初に月を選びましょう
⑥月のあいさつ、安否のあいさつ、感謝のあいさつをそれぞれ選びます
⑦選んだら「OK」をクリックしてください
⑧Wordに選んだ文章が表示されます
ポイント
Wordではあいさつ文だけではなく、あいさつ文の後に続ける「起こし言葉」や「結び言葉」も選ぶことができますよ。
挿入タブ→テキストのあいさつ文をクリックした後、起こし言葉もしくは結び言葉を選んでください。
惜春の候のまとめ
「惜春の候」とは、4月上旬から5月上旬にかけて使う時候の挨拶ですね。
春の終わり、つまり暖かい日々が過ぎ去るのを惜しむ気持ちを込めた素敵な言葉です。
読み方は「せきしゅんのこう」。
春の花が散り、新緑が輝き始めるこの時期にぴったりの挨拶ですよ。
地域や状況に合わせて、4月中旬から5月上旬に使うとより感じが良くなります。
手紙やはがきで使う際は、春を惜しむこの美しい季節をお互いに感謝しながら、新たな季節への期待を込めてみてはいかがでしょうか。
この記事のポイントをまとめますと
- 惜春の候は4月上旬から5月上旬に使う時候の挨拶
- 旧暦の晩春、つまり春の終わりを象徴
- 読み方は「せきしゅんのこう」
- 意味は過ぎ去る春を惜しむ季節
- 春の終わりに感じる感慨深さを表現
- 自然が次の季節へ移り変わる準備の時
- 新緑が輝き、初夏の風が吹き始める
- 人々が季節の変化に対する感慨を新たにする
- 春の花が散り始め、暖かな日差しが強まる
- 地域によって使うタイミングが異なる可能性
- 桜の開花後、春を惜しむ気持ちが高まる
- ビジネス文書では頭語と結語を正しく使用
- 頭語「謹啓」や「拝啓」の後に時候の挨拶を配する
- 結語には「敬具」や「謹言」を適切に用いる


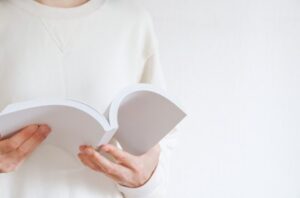

コメント