人日の節句と聞いて、皆さんはどんなイメージをお持ちでしょうか?
端午の節句や七夕といった他の節句はよく知られていますが、1月7日に行われる人日の節句は、意外と知られていないかもしれません。
では、なぜこの日に七草粥を食べるのでしょう?
その背景には、古代中国の陰陽五行説から始まる深い歴史と、日本の伝統的な風習が息づいています。
この記事では、人日の節句の意味や由来、そして七草粥を食べる理由について、わかりやすく解説していきます。
読み進めるうちに、この節句の魅力に気づき、来年の1月7日が待ち遠しくなるかもしれませんね。
- 人日の節句が五節句の一つであり、毎年1月7日に行われること
- 七草粥を食べることによる無病息災と豊作の願いの意味
- この節句の起源が古代中国の陰陽五行説にあること
- 日本における七草粥の風習とその地域ごとの違い
- 七草粥を食べることによるお正月疲れの胃を休める効果
人日の節句とは

人日の節句とは五節句の一つで七草がゆを食べる節句なので七草の節句とも言われています。
この七草粥を食べるという行為には「1年間病気せずに元気に過ごせるように」という願いが込められているのです。
この人日の節句の由来は古代中国の陰陽五行説を由来となっているものであります。
古来中国では1月1日から6日まで動物で当てはめた占いが行われており、1日を鶏の日、2日を犬の日、3日を猪の日、4日を羊の日、5日を牛の日、6日を馬の日としたのです。
そして1月7日は人を占った日ということで人の日としました。
このように指定された日をその対象を殺さない日とし、1月7日は犯罪者の処罰を行わない日となります。
このように人の日とされた1月7日がそのまま「人日の節句」となったのです。
この考え方は平安時代に伝わりましたが、民間に大きく広まったのは江戸幕府が五節句を公式行事や祝日にしたことです。
この五節句の精度は明治6年の1873年に廃止されましたがすでに広まった行事となっていましたので、一部は今でも廃れることなく行われています。
人日の節句の由来!なぜ1月7日なの?

五節句とは1月7日の人日の節句(七草の節句)・3月3日の上巳の節句(桃の節句)・5月5日の端午の節句(菖蒲の節句)・7月7日の七夕の節句(笹の節句)・9月9日の重陽の節句(菊の節句)と5種類あり、この中でも日本で馴染みがあるのは桃の節句と端午の節句と七夕の節句でしょう。
人日の節句は先に記載したように古来中国で1月1日から6日まで動物で当てはめた占いが行われていたことが理由で、1月7日は人を占った日ということで人の日としました。
このように節句の日を見てみると3月3日や5月5日など「奇数が重なる日」となっているのですが、古代中国における陰陽五行説には「奇数は陽となるが、この陽が重なると陰になる」という考え方があり、奇数の重なった日は邪気を祓う必要があると言われていたのです。
つまり、この五節句も元々は邪気祓い目的で行われていたのです。
この考え方は日本に伝わっていた当時も邪気を祓う目的で宴会をするというスタイルで引き継がれていたのですが、民間に伝わるうちに五穀豊穣や無病息災といったプラスの面が取り上げられるようになって、そちらがフィーチャーされるようになりました。
人日の節句の風習

人日の節句の風習はシンプルで、七草粥を食べて1年の豊作祈願や無病息災を願うというものになります。
これも中国から伝わった物で、古代中国では旬の新鮮な七草を食べると自然界から新たな生命力が宿り長生きができるようになるとか、その力で邪気を払えるようになると言われていたのです。
そのため、人日の日に七種類の野菜を入れた汁物を「七種菜羹(ななしゅさいのかん)」と呼ばれて重宝されていました。
元々、日本にも「若菜摘み」という雪の間から芽を出している若菜を摘むという行事があったので、すんなり受け入れられたと考えられています。
しかし、日本にも同じような考え方で伝わっていましたが地域ごとにとれる物が大きく異なるので、地方事の変化がかなりあり七草粥を食べるという風習が残っていたとしても使われる食材が全く違うということも多々あるのです。
人日の節句に七草粥を食べる理由

人日の節句に七草粥を食べる理由は日本では無病息災を願って1月7日に食べられます。
基本的にはこのような無病息災が願われての風習ではありますが、お正月にはガッツリと食べ物や飲み物を摂取してしまうので、胃を休めるという意味で七草粥を食べるという意味もあるのです。
お正月で疲れた胃腸を労るという意味で行うと考えると納得できるでしょう。
ちなみに、この七草は御伽草子の七草草子において説話として語られているのです。
その説話は一人の親孝行者が山に入って祈願した結果帝釈天からお告げがあり春の初めに七草集めてルールに従って食べると若返るというものでした。
このような説話としても残っているので七草が体に良いという風習が遙か昔からあったと言うことがわかります。
絶品七草粥の作り方

参考URL:https://recipe.rakuten.co.jp/recipe/1420002854/
七草粥は地方事の違いがものすごく大きいので、あらゆる人が納得できるような作り方を提供するのは難しいでしょう。
しかし、今では春の七草もお正月になると八百屋さんで当たり前のように売られていますので、入手は楽になっています。
この七草を使った料理の中でも簡単な作り方が上記の「炊飯器で簡単♪七草粥」です。
作り方はとっても簡単で、カブや大根を薄くスライスして葉っぱも刻み、全がゆのラインまで水を入れて雑炊を塩や風だしの素やうす口醤油や七草を入れて炊飯ボタンを押すだけです。
ものすごくあっさりとした七草粥を食べたいという方はこの作り方を基本としてください。
春の七草の種類や覚え方

春の七草の覚え方は丸暗記となってしまいますが、丸暗記でも覚えやすい物と覚えにくい物がありますので、その中から覚えやすい物を見つける必要があるでしょう。
インターネット上をサーフィンしてみると色んな覚え方が登場しますが、個人的にとっても覚えやすかったのは「春の七草の覚え方!”語呂合わせ”と”GIFアニメ”で暗記しよう!(https://wakuwaku-wadai.com/archives/35773.html)」で紹介している「セナはゴッホとすず2つ」になります。
頭文字をつなげて覚えるというのは基本的なやり方となるのですが、うまくつなげられるかどうか、覚えやすい頃になるかどうかはまとめられる人の技量に大きく関わってきますのでセンスの見せ所となるでしょう。
個人的に紹介した「セナはゴッホとすず2つ」はものすごく覚えやすくセンスもあると感じたので、この場で使える覚え方として取り上げさせていただきました。
春の七草は芹(せり)・薺(なずな)・御形(ごぎょう)・繁縷(はこべら)・仏の座(ほとけのざ)・菘(すずな)・蘿蔔(すずしろ)です。
ここでポイントとなるのはそれぞれの頭文字になるので、それをそのままつなげると「せなごはほすす」となってしまうでしょう。
あとはこの順番を崩して覚えやすい形にするか、すずが2つ並ぶからすず2つといった使い方をするかです。
「セナはゴッホとすず2つ」の場合は使っている言葉の順番はセりの「せ」とナズナの「ナ」とハコベラの「は」とゴギョウの「ゴ」とホトケノザの「ほと」とスズナとスズシロ「スズ2つ」となっています。
人日の節句のまとめ
人日の節句、1月7日に行われるこの伝統的な行事は、五節句の一つとして知られています。
古代中国の陰陽五行説に由来し、1年間の無病息災と豊作を願って、七草粥を食べる風習があります。
この節句は、江戸時代に公式行事として広まり、現代でもその名残を見ることができます。
お正月の疲れた胃を休める意味も込められており、七草粥は体に優しい食べ物として親しまれています。
地域によって異なる七草粥の食材も、日本の多様な文化を感じさせてくれるでしょう。
この記事のポイントをまとめますと
- 人日の節句は五節句の一つで、毎年1月7日に行われる
- 七草粥を食べることで1年間の無病息災と豊作を願う
- 由来は古代中国の陰陽五行説に基づく
- 1月1日から6日までは動物を占う日とされ、7日が人を占う日
- 1月7日は犯罪者の処罰を行わない日として特別視された
- 平安時代に日本に伝わり、江戸時代に公式行事として広まる
- 明治6年に五節句の公式行事は廃止されたが、風習は残る
- 七草粥はお正月の疲れた胃を休める意味合いもある
- 地域によって七草粥の食材には多様性が見られる
- 七草粥の具材には、春の七草が用いられる
- 春の七草は「セナはゴッホとすず2つ」で覚えると良い
- 人日の節句は現代でもその名残を見ることができる







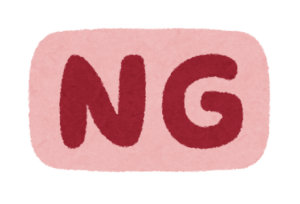




コメント