凶会日という言葉を聞いてこれがどんな日なのかをすんなり答えられる人は少ないと思います。
今回はこの凶会日とはいったいどんな日なのか、意味や由来や読み方を解説しつつ、2025年だといつになるのかも見ていきます。
入籍や結婚そして引っ越しといった慶事との相性もチェックしていきましょう。
そもそもこの凶会日はどう読めばいいのでしょうか。
凶会日とは?意味や由来や読み方は?

凶会日は『くえび』や『くえにち』と読みますが、カレンダーに記載されるときは凶会日よりも『くゑ日』と記載されることが多い凶日です。
カレンダーによっては『くゑ日』ではなく『くしえ』や『くしゑ』と表現されているときもあります。
この凶会日は陰陽五行思想によって誕生したとされている凶日で、陰陽二気の調和がうまく行かないために吉事はしてはいけない日とか万事に忌むべき日という意味があります。
陰陽五行思想が関わっている暦注下段の一つなので、かなり歴史が古く日本の朝廷の陰陽寮が作成したとされる暦の一つ具注暦の頃から用いられてきたと言われているのです。
日本の古暦の一つである『仮名暦略注』によると『倭暦に注する所の悪日なり、華本にいまだ其名目を考えず、然れども大抵吉事に用うべからず』という表記をされています。
この凶会日の日の配当はかなり独特で、月ごとに特定の干支が割り当てられていたのですが宣明暦時代は節切りで貞享暦以降は月切りとなっているのです。
凶会日は旧暦の月切りで割り当てられるようになると一部の配当日が対象外とされるようになり、節切りだった時代と比べると減っているというのも特徴の一つです。
2025年の凶会日はいつ?
凶会日のルールについてまずは確認して行きましょう。
こちらの凶会日のルールを確認すると以下のとおりです。
1月:辛卯・(庚戌)・甲寅
2月:己卯・乙卯・辛酉
3月:甲子・乙丑・丙寅・丁卯・戊辰・壬申・戊申・庚辰・甲申・甲辰・丙申・甲辰・庚申・(癸亥)
4月:戊辰・(己巳)・辛未・癸未・乙未・己亥・丙午・丁未・(丁巳)・戊午・己未・癸亥
5月:丙午・(壬子)・戊午
6月:己巳・丙午・丁未・(癸丑)・丁巳・(戊午)・己未
7月:乙酉・甲辰・庚申
8月:己酉・乙卯・辛酉
9月:(丙寅)・甲戌・(戊寅)・(庚寅)・辛卯・壬辰・癸巳・甲午・乙未・丙申・丁酉・戊戌・(壬寅)・庚戌・甲寅
10月:乙丑・己巳・丁丑・戊子・己丑・戊戌・己亥・辛丑・壬子・癸丑・丁巳・癸亥
11月:戊子・丙午・壬子
12月:戊子・丁未・壬子・(癸丑)・癸亥
それを踏まえた上で2025年の凶会日はどうなっているのかを見ていきましょう。
| 日にち | 旧暦 | 六曜 | 日干支 |
| 2025年1月25日 | 12月15日 | 友引 | 戊子 |
| 2025年2月20日 | 1月11日 | 大安 | 甲寅 |
| 2025年3月16日 | 2月7日 | 友引 | 己卯 |
| 2025年4月10日 | 3月2日 | 仏滅 | 甲辰 |
| 2025年4月14日 | 3月6日 | 友引 | 戊申 |
| 2025年4月26日 | 3月18日 | 友引 | 庚申 |
| 2025年4月30日 | 3月22日 | 赤口 | 甲子 |
| 2025年5月1日 | 3月23日 | 先勝 | 乙丑 |
| 2025年5月2日 | 3月24日 | 友引 | 丙寅 |
| 2025年5月3日 | 3月25日 | 先負 | 丁卯 |
| 2025年5月4日 | 3月26日 | 仏滅 | 戊辰 |
| 2025年5月19日 | 4月12日 | 先負 | 癸未 |
| 2025年5月31日 | 4月24日 | 先負 | 乙未 |
| 2025年6月4日 | 4月28日 | 先勝 | 己亥 |
| 2025年6月11日 | 5月6日 | 仏滅 | 丙午 |
| 2025年6月23日 | 5月18日 | 仏滅 | 戊午 |
| 2025年8月8日 | 7月5日 | 大安 | 甲辰 |
| 2025年8月24日 | 7月21日 | 先負 | 庚申 |
| 2025年10月13日 | 9月11日 | 先勝 | 庚戌 |
| 2025年10月17日 | 9月15日 | 大安 | 甲寅 |
| 2025年11月1日 | 10月1日 | 仏滅 | 己巳 |
| 2025年11月9日 | 10月9日 | 赤口 | 丁丑 |
| 2025年11月20日 | 10月20日 | 大安 | 戊子 |
| 2025年11月21日 | 10月21日 | 赤口 | 己丑 |
| 2025年11月30日 | 10月30日 | 先負 | 戊戌 |
| 2025年12月8日 | 11月8日 | 赤口 | 丙午 |
| 2025年12月14日 | 11月14日 | 赤口 | 壬子 |
このようにかなり独特な割り振りとなっています。
凶会日に避けたほうが良い事は?
『万事に忌むべき日』なので、かなり厄介な日なのです。
特に避けるべきと言われているのが吉事であり、結婚や納車や引っ越しといった慶事に該当する行為はNGとされてしまうでしょう。
この凶会日を意識すると10月はかなり行動しにくくなってしまいますので注意してください。
様々な暦注を調べてきた筆者からすると、この凶会日は現代では圧倒的に知名度が低くなっていますので、とりあえずこういった凶日も存在しているという認識だけもてばいいと思います。
テレビのクイズ番組で『凶会日を何と読む?』といった問題が出そうな気がしますので、出た場合はスラッと読んでドヤ顔をしてしまいましょう。
凶会日に入籍や結婚はいいの?

凶会日は基本的に慶事や吉事との相性が悪い日とされていますので、入籍や結婚といったお祝い事との相性は良くないでしょう。
陰陽寮があった平安時代ならばこの凶会日の結納は避けるべきと注意された可能性も高いです。
しかし、現代ではこの凶会日は圧倒的に知名度が足りていないので重視する必要はないでしょう。
とりあえず知識として凶会日は吉事や慶事との相性が悪いことを覚えておき、入籍や結婚は赤口や仏滅を避けた方がいいと認識した方がいいです。
今でも入籍や慶事における六曜は意識しないとダメなの?
現代の若い人達を中心に六曜などの暦注のような俗信や迷信をまったく気にしていない人は増えています。
しかし、この六曜を含めた暦注は誰が信じているのかわかりませんので大規模な人を招く吉事や凶事の場合は意識しなければいけないのです。
確かに、仏滅や赤口といった凶事に結婚式をすると大安に挙式を挙げるより費用的に安上がりになる事も多いのですが、六曜や風習を信じている人に非難される可能性があるのです。
こういった揉め事に繋がる可能性がゼロではないので、今でも六曜は全く信じていないけど面倒事は避けたいという気持ちで意識している人は大勢います。
個人的にもこういった暦注は信じる義務はありませんし普段は気にする必要はほとんどないと思っていますが、多くの人が集まる場所では知識として役立つ場面がありますので有効活用してもらいたいと考えています。
凶会日に引っ越しは大丈夫?

引っ越しも基本的には慶事や吉事に該当しますので、凶会日を意識した場合は避けた方がいいでしょう。
ただし、引っ越しを絶対避けた方がいい凶日として三隣亡がありますので、凶会日をそこまで意識する必要はありません。
とりあえず、凶会日と慶事や吉事である引っ越しは相性がそこまで良くないということだけ認識しておきましょう。
暦注下段との関係について
暦注というのはいわゆるカレンダーに書かれる日付や曜日といった日時やその日の吉凶であり、上段には日付や曜日といった必須なものを記載し、その下には六曜などの知名度の高い暦注を記載します。
中段には十二直が入って、一番下には選日・二十八宿・九星そして今回紹介した凶会日が含まれている暦注下段などが記載されるのです。
まとめ
以上、いかがだったでしょうか。
今回は暦注下段の1つである凶会日について紹介いたしました。
凶会日は陰陽寮があった平安時代から存在するかなり歴史のある暦注ではあるのですが、現代ではそこまで重宝されることは少ない暦注下段となってしまいました。
現代でも陰陽寮が残っていた場合はおそらく暦注の下段ではなく中段や上段に位置していた可能性はあったと思います。
こういった情報を知っているだけでも知識の幅の広がりを感じるので個人的にはかなり面白いです。
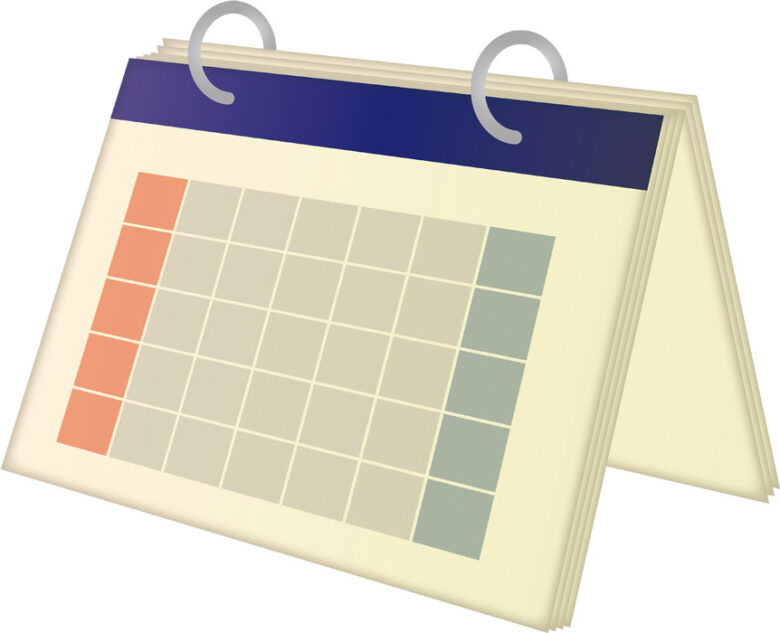










コメント