暦注下段には現代でほとんど用いられないモノも多く、聞いたことが無い言葉も存在します。
今回は現代人にとってはほとんど忘れられつつある暦注の一つ『往亡日』とは何か、意味や由来や読み方を解説しつつ2025年だといったいいつになるのか、避けた方がいい慶事はあるのか、引っ越しや納車などのイベントや行事は大丈夫なのかを見ていきます。
そもそも、この往亡日とはどんな存在なのでしょうか。
往亡日とは?意味や由来や読み方は?
ただし、超マイナーといってもいいレベルで使われていない言葉なのでパソコンやスマホの単語帳には記載されていないでしょう。
頻繁に使うという人は単語登録をしておきましょう。
この往亡日には『往(ゆ)きて亡(ほろ)ぶ日』という意味があり、現代風に解釈すると『何らかの行動を行うと失敗を招いてしまう日』となっています。
ただし、この『何らかの行動』というのはある程度決まっているようで、『どこかに行くのがNG』という意味で出陣や移転や遠出や船出などの行動とは相性が悪いとされていたり、『新しい門出がNG』という意味で結婚や拝官や元服や建築などの行動とは相性が悪いとされているようです。
元々、この往亡日という言葉は陰陽道が由来となっているようで、かつて京が日本の中心であり陰陽師が当たり前のように職業として存在し陰陽寮が存在していた時代にこの言葉はあったとされています。
暦を管理することが昔は権力者の象徴として認識されていましたが、この暦を管理する立場にあったのがその日や時間や年の吉凶を占い星を見る陰陽師にあったのです。
この陰陽寮があった時代に作られていた暦が『具注暦』と呼ばれる暦で、この暦に今回紹介する往亡日があったという情報もあります。
陰陽師という職業が当たり前のようにあった時代では、この往亡日も注目度が高く多くの方々が信じて行動していたかもしれません。
2025年の往亡日はいつ?
まず、この往亡日のルールなのですが二十四節気の節気で区切って考えられており以下のルールが当てはまります。
正月節の7日目、2月節の14日目、3月節の21日目、4月節の8日目、5月節の16日目、
6月節の24日目、7月節の9日目、8月節の18日目、9月節の27日目、
10月節の10日目、11月節の20日目、12月節の30日目。
要するに1年に12回存在する凶日なのです。
これらのルールを当てはめて2025年の往亡日だといつのなるのかを確認して行きましょう。
| 日にち | 節月 | 六曜 | 二十四節気 |
| 2025年2月10日 | 1月 | 先勝 | (立春) |
| 2025年3月18日 | 2月 | 仏滅 | (啓蟄) |
| 2025年4月24日 | 3月 | 赤口 | (穀雨) |
| 2025年5月12日 | 4月 | 友引 | (立夏) |
| 2025年6月20日 | 5月 | 先勝 | (芒種) |
| 2025年7月29日 | 6月 | 大安 | (大暑) |
| 2025年8月15日 | 7月 | 赤口 | (立秋) |
| 2025年9月24日 | 8月 | 大安 | (秋分) |
| 2025年11月3日 | 9月 | 赤口 | (霜降) |
| 2025年12月26日 | 11月 | 赤口 | (冬至) |
往亡日に避けたほうが良い事は?
往亡日にNGとされている行動は先ほど簡単に解説したように『往(ゆ)きて亡(ほろ)ぶ日』という意味があり、『何らかの行動を行うと失敗を招いてしまう日』という意味があります。
色々と調べた限りでは『どこかに行くのがNG』という意味で出陣や移転や遠出や船出などの行動とは相性が悪く、『新しい門出がNG』という意味で結婚や拝官や元服や建築などの行動とも相性が悪いとされていました。
とりあえずお出かけしたり引っ越ししたり移転したりといった移動を主体とするような行事やイベントとは相性が悪い凶日とされています。
出張や転勤初日と被ってしまった場合も相性が悪い日と言えるのではないでしょうか。
しかし、移動がNG行動となってしまうとあらゆる行動ができなくなってしまうのでどこまでがNGと判断するのかで変わってくる日とも言えます。
また、新しい人生の門出という意味がある結婚や元服もNGとされていますし、新しい家を建てる建築もダメとされているのでこの『新しい』というワードがくっつきそうな行動も制限されてしまうでしょう。
いわゆるお店や会社を新たに始める開業や起業をする日としてもあんまり推奨できない日になりそうです。
往亡日に入籍や結婚はいいの?

調べた限りでは新しい門出という意味がある行動は往亡日においてNGとされていますので、結婚や婚約や入籍もNGとされています。
ただし、この往亡日そのものが超マイナーなので赤口や仏滅といった六曜における凶日よりも優先すべきとは言いません。
むしろ往亡日をさえてあえて仏滅や赤口にしてしまった場合、六曜を意識している人達から注意される可能性が高いです。
あくまでも今回紹介する往亡日は『こういったルールに基づいて行動することが推奨されていた暦注下段の一つ』という認識で十分でしょう。
六曜も俗信であり迷信ですが風習として根付いてしまっている部分もまだまだ現代に存在しているので、マイナーな暦注下段よりもこちらの六曜に意識をさいてください。
往亡日に引っ越しは大丈夫?

新しい門出や移動がNGとされている往亡日なのでそれらがミックスされている引っ越しは絶対にNGとされているでしょう。
ただし、先ほども記載したように往亡日はマイナーなので意識して行動する必要はほとんどありません。
引っ越しの場合も優先されることが多いのは六曜であり、建築業界出身の方々ならば六曜よりも三隣亡であるかどうかを意識しています。
特に、三隣亡の引っ越しはNGであると強く認識している建築業界の方々はそれなりにいますので、三隣亡であるかどうかのチェックは引っ越し予定を決める前に必ず行ってください。
往亡日に納車は大丈夫?
これはどのように解釈するのかで変わってくると思います。
新しい門出や移動がNGとされている往亡日ですが、この車が移動にまつわる存在なのでNGという考え方もあるでしょう。
しかし、あくまでも納車は自分が移動するのではなく車を持ってきてもらう行動なのでセーフという考え方もできると思います。
しかし、納車した後に直ぐに運転してしまった場合は移動に関する行動と言えると思いますので、往亡日的にアウトかもしれません。
このようにアウトになったりセーフになったりするのが納車と往亡日の関係なので、都合のいいように解釈して行動するようにしてください。
暦注下段との関係について

往亡日は暦注下段の1つです。
暦注下段は江戸時代以降の暦において下の方に書かれた暦注であり、六曜や十二直などと比べても下の存在として扱われていました。
暦注における上段は日付や曜日といった今でも必須の情報や二十四節気や七十二候などの科学的かつ天文学的な事項が記載され、中段には十二直が記載されます。
六曜は明確なカテゴリー分けがされていないようですが、日付や曜日の下に書かれていたという情報がありますので立ち位置的には中段なのでしょう。
この中段よりも下が暦注下段であり、今回紹介した往亡日もこの暦注下段の一種なのです。
まとめ
以上いかがだったでしょうか。
今回は往亡日についての情報をまとめました。
往亡日はかなりマイナーな暦注下段ではありますが、そこまで難しい暦注下段ではなく概要を聞くとどんな存在だったのかが調べると比較的簡単にわかりました。
しかし、かなりマイナーな暦注下段だったのでネット上での情報もかなり少なく、調べるのに苦戦した暦注下段でもあります。
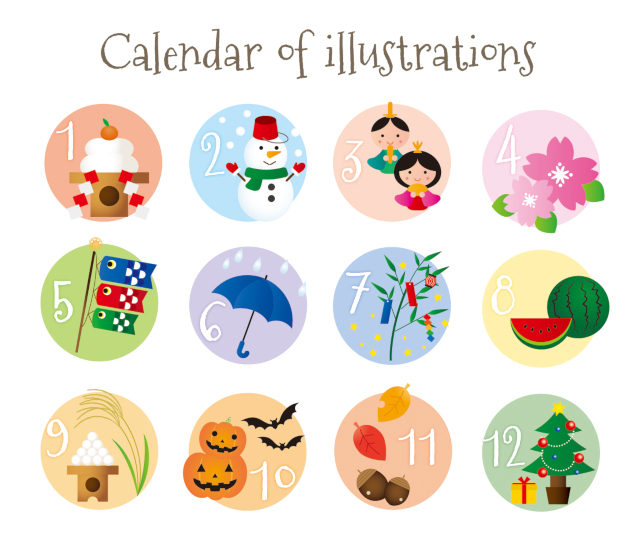










コメント