錦秋の候を使う時期と使い方や読み方を、例文や結び文と併せてまとめています。
時候の挨拶の中ではあまり聞き慣れないのが、錦秋の候ではないでしょうか。
秋と言う字が入っていることから、何となく秋に使う時候の挨拶ということは分かるものの、具体的にいつ頃使うとよいのか知りたいですよね。
そこで今回は、錦秋の候について詳しく調べてみました。
錦秋の候を使う時期はいつ?
「錦秋の候」という言葉は、秋の美しさを表現するのにぴったりのフレーズです。
では、この「錦秋の候」を使うのに最適な時期はいつなのでしょうか。
まず、「錦秋の候」という言葉は、秋の色鮮やかな景色を思い浮かべさせる表現です。
錦のように美しい秋の季節を指し、特に紅葉が美しい時期を想起させます。
この言葉を使うのに最適な時期は、一般的に10月上旬から11月上旬までとされています。
しかし、この時期は一概に決まっているわけではありません。
なぜなら、この時期は毎年異なる気候や自然の変化に左右されるからです。
例えば、ある年は10月に入ってすぐに紅葉が始まることもあれば、別の年は少し遅れて11月に入ってから紅葉が見頃を迎えることもあります。
「錦秋の候」の使用期限については、11月上旬の立冬の前日までとされています。
立冬は旧暦に基づいた季節の区切りで、毎年11月7日か8日頃に設定されます。
この日を境に、暦上では冬に入るため、「錦秋の候」という言葉を使うのはそれまでとなります。
では、11月上旬はまだ秋ではないのでしょうか?
実は、時候の挨拶は旧暦に基づいているため、立冬を過ぎると暦の上では冬になるのです。
そのため、立冬の前日までが「錦秋の候」を使う期間とされています。
このように、日本の伝統的な挨拶には季節の移り変わりを感じさせる美しさがあります。
錦秋の候を使うことで、相手に秋の深まりを感じさせ、季節の挨拶としての役割を果たすのです。
季節の変わり目には、ぜひこの美しい日本語の表現を使ってみてはいかがでしょうか。
錦秋の候の意味や読み方は?
錦秋の候は「きんしゅうのこう」と読みます。
「錦秋」という言葉は、その美しさがまるで錦(にしき)のようだということから来ています。
錦とは、色とりどりの糸で織られた豪華な布のこと。
紅葉が美しく色づくこの季節は、まさに自然が織りなす錦のように、赤や黄色、オレンジに彩られた絶景が広がっています。
一方で、「候」という言葉には、時候や気候、季節を意味する側面があります。
したがって、「錦秋の候」とは、「山々が色とりどりに染まり、紅葉が見頃を迎える季節がやってきた」という美しい時期を指しているのです。
この季節は、日本各地で様々な紅葉スポットが人々を魅了します。
例えば、京都の嵐山や奈良の奈良公園などは、特に有名ですね。
紅葉狩りという文化もあり、多くの人々がこの時期に美しい景色を楽しむために訪れます。
紅葉の美しさは、ただ目で見るだけでなく、日本の文化や歴史、自然への敬愛を感じさせてくれます。
錦秋の候は、日本の四季の中でも特に風情があり、心に残る季節と言えるでしょう。
この美しい季節を感じながら、ぜひ一度、日本の自然が織りなす錦の絨毯を歩いてみてはいかがでしょうか。
きっと、心に残る素敵な思い出ができるはずです。
錦秋の候の正しい使い方は?

先ほどもお伝えした通り、錦秋の候は10月上旬から11月上旬の立冬まで使える時候の挨拶になります。
しかし、近年は紅葉が見ごろになる時期が年々遅くなっており、関東から西では11月中旬から12月上旬になることが多いですよね。
また反対に、北海道や東北はこれよりも早く、9月下旬から10月上旬というところもあるでしょう。
日本は南北に長い地形をしているため、一口に「紅葉が見ごろの時期」と言っても、これだけ時差が生じてしまいます。
錦秋の候には、紅葉が錦の織物のように美しい時期という意味があることから、10月中旬を過ぎてしまうと北海道や東北ではすでに紅葉が終わっている可能性があります。
一方で、関東から西が見ごろを迎える頃には暦の上で冬となっているため、錦秋の候が使えないかも知れません。
時候の挨拶は旧暦時代に作られた二十四節気の名称を用いたものが多いのですが、錦秋は二十四節気の一つということではありません。
そのため、立冬などに関係なく、紅葉が見ごろになった時期に自由に使ってよいのでは?という意見もあります。
ですが、時候の挨拶はあくまでも旧暦に基づいて日取りを決めた上で、手紙やはがきの送り先の状況に合わせて使うのがよいことから、錦秋の候も立冬を過ぎてから使うのは避けるのがよいでしょう。
錦秋の候を使った例文

錦秋の候を使って手紙やはがきを送る場合、相手に合わせた文章を使うことが大切です。
会社の取引先の人と友達が、同じ文章であるのはおかしいですよね。
そこでここでは、ビジネス/目上の人/親しい人へのシチュエーション別に、錦秋の候を使った例文をご紹介します。
ビジネスで使う場合
目上の人に使う場合
親しい人に使う場合
錦秋の候の結び文
ビジネスなどでは「ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします」「引き続きご支援ご厚情を賜りますようお願い申し上げます」と言った定型の結び文を使うことが多いのですが、時候の挨拶に合わせた結び文を使うと、文章全体に統一感が出るのでおすすめです。
ここでは、錦秋の候を時候の挨拶に使った場合の結び文の例文をいくつかご紹介します。
錦秋の候を使うときに注意すること
頭語とは「拝啓」や「謹啓」などのことで、『つつしんで申し上げます』という丁寧な意味があります。
そのため、ビジネス関係者や目上の人に手紙やはがきを送る時は、時候の挨拶の前に頭語を付けるのがマナーになりますよ。
また、頭語には必ず結語が必要になります。
結語は「拝啓」なら「敬具」または「敬白」、「謹啓」なら「謹言」もしくは「謹白」になりますよ。
なお、親しい友人などに送る場合は頭語や結語を使う必要はありません。
錦秋の候以外の10月の時候の挨拶はある?

錦秋の候は紅葉が見ごろの時期を迎えていないと、やや使いにくい時候の挨拶と言えますよね。
10月に手紙やはがきを送る時に、錦秋の候以外に使える時候の挨拶はないのでしょうか。
ここでは、錦秋の候以外の10月の時候の挨拶をご紹介します。
清秋の候
10月初旬から下旬まで使える時候の挨拶になります。
清秋の候には「空が清く、澄み渡った秋の季節」という意味があるため、秋特有の落ち着いた気候が続く時に使いやすい時候の挨拶と言えるでしょう。
紅葉の候
10月中旬から下旬に使える時候の挨拶になります。
錦秋の候とは異なり、紅葉が色づき始めたら使える時候の挨拶のため、使いやすいのではないかと思います。
ただし、紅葉の候を使う時も、相手の地域の状況に合わせて使うのがよいでしょう。
寒露の候
10月上旬から下旬に使える時候の挨拶です。
寒露は二十四節気の一つで、例年10月7~8日頃に該当するため、10月8日以降に使うのがよいでしょう。
寒露には「霜が降りそうなほど寒くなりましたね」という意味がありますよ。
また、使い終わりは次の節気である霜降(例年10月22~23日頃)までになります。
Wordであいさつ文や定型文を挿入する方法
仕事上で取引先の相手にあいさつ文を送る、目上の人に手紙やはがきを出す時などに、「書き出しに悩んでしまい、なかなか作業が進まない」なんてことはよくあるのではないでしょうか。
そのような時はWordを利用してみましょう。
Wordにはあいさつ文のテンプレートがあるので、参考にすると作業が捗りやすくなりますよ。
ここではwordを使ったあいさつ文や定型文の挿入方法をご紹介します。
手順
①Wordを開きます
②挿入タブをクリックします
③テキストのところにある「あいさつ文」をクリックします
④あいさつ文の挿入を選びます
⑤何月のあいさつ文を作成するのか、最初に月を選びましょう
⑥月のあいさつ、安否のあいさつ、感謝のあいさつをそれぞれ選びます
⑦選んだら「OK」をクリックしてください
⑧Wordに選んだ文章が表示されます
ポイント
Wordではあいさつ文だけではなく、あいさつ文の後に続ける「起こし言葉」や「結び言葉」も選ぶことができますよ。
挿入タブ→テキストのあいさつ文をクリックした後、起こし言葉もしくは結び言葉を選んでください。
錦秋の候のまとめ
錦秋の候は10月上旬から11月上旬に使える時候の挨拶です。
錦秋は二十四節気とは直接関係のない言葉なのですが、時候の挨拶は旧暦に沿って行うのが一般的のため、暦の上で冬となる立冬(例年11月7日頃)まで使うようにしましょう。
また、錦秋には紅葉が錦の織物のように美しいという意味があることから、錦秋の候が使える時期であるだけではなく、相手が住んでいる地域が紅葉の見ごろを迎えているかを確認してから、手紙やはがきを送るのがよいでしょう。



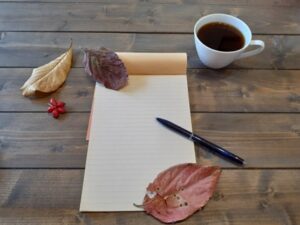

コメント