初雪の候と聞いて、皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか?
この美しい日本の季節の挨拶は、いつ、どのように使うのが適切なのか、多くの方が疑問に思うことでしょう。
特に、初雪の時期は地域によって異なるため、いつこの挨拶を使うのがベストなのか、迷われる方も多いはずです。
本記事では、そんな「初雪の候」の正しい使い方、読み方から、ビジネスシーンやプライベートでの例文、さらには文章の締めくくりとしての結びの言葉まで、幅広くご紹介します。
季節感あふれる挨拶で、あなたのコミュニケーションをより豊かにしましょう。
- 「初雪の候」を使う適切な時期について
- 「初雪の候」の読み方とその意味
- ビジネスや目上の人への手紙での「初雪の候」の使い方
- 「初雪の候」を使った具体的な例文とその文脈
- 「初雪の候」の結びの言葉とそのマナー
初雪の候を使う時期はいつ?
ただし、初雪の候を使う時期については、明確に決まってはいないというのが現状と言えそうです。
その理由については、「初雪の候の正しい使い方」でご紹介します。
初雪の候の意味や読み方は?
時候の挨拶は音読みすることが多いのですが、初雪の候の場合は、初雪は訓読み、候は音読みとなっています。
読み方が混ざっているものの、初雪を「はつゆき」と読むことは難しくないので、初雪の候はすんなりと読める方が多いのではないかと思います。
初雪とは文字通り、(今シーズンに)初めて降る雪という意味があります。
候には時期や時候などの意味があることから、初雪の候は「初雪が降る時期になりましたね」という意味になりますよ。
初雪の候の正しい使い方は?
しかし、初雪の候は12月上旬から中旬に使う時候の挨拶となっています。
初雪の候は「初雪が降る時期になりましたね」という意味があるのですから、10月下旬に初雪が降る北海道に住む方への手紙やはがきなどに、初雪の候を使っても間違いではないように思えます。
ですが、一般的に10月下旬は秋ですし、雪が降る方が稀です。
それに10月下旬に使える時候の挨拶は他にもあるので、わざわざ初雪の候を選ぶ必要もないでしょう。
一方で、12月上旬から中旬であれば、季節は冬になり、多くの地域では気温が下がって初雪が観測されることが多いですよね。
そのため、初雪の候を使っても違和感を抱く人は少ないです。
このようなことから、初雪の候は12月上旬から下旬に使うのがよいとされていますよ。
初雪の候を使った例文
時候の挨拶は日常会話で使うことがないので、どのように書いてよいかよくわからなくなるもの。
そこでここでは、初雪の候を使った例文をご紹介します。
ビジネスで使う場合
目上の人に使う場合
親しい人に使う場合
なお、親しい人には初雪の候ではなく、「初雪が降る時期になりましたね」という表現の方がよいでしょう。
初雪の候などの〇〇の候は、時候の挨拶の中の漢語調と言って、丁寧な表現になります。
親しい人に使うと、相手によっては改まった感じがして違和感を抱くこともあるようですよ。
一方で「初雪が降る時期になりましたね」という書き方は口語調といって、漢語調よりもカジュアルな表現になります。
手紙やはがきなどを送る相手との関係性に合わせて、使う時候の挨拶を選んでみましょう。
初雪の候の結び文
ビジネス文章では季節に関係なく使える定型文もありますが、時候の挨拶の季節感に合わせた結び文にすると、文章全体にまとまりが生まれます。
初雪の候は12月に使える時候の挨拶なので、結び文も12月に関連した言葉や内容にするのがよいでしょう。
ただし、時候の挨拶と結び文に同じ言葉や内容は使えないので、雪に関することは入れないようにして下さい。
ここでは、初雪の候を使った場合の結び文の例文をご紹介します。
初雪の候を使うときに注意すること
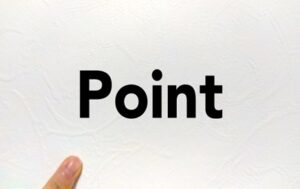
初雪の候を使うときに注意したいのは、手紙やはがきなどを送る相手によっては、文章の冒頭がいきなり初雪の候ではマナーとしてNGになる、ということです。
初雪の候は時候の挨拶の中でも丁寧な表現になるものの、それだけでは十分とは言えません。
特にビジネス関係者や目上の人に送る手紙やはがきなどでは、初雪の候の前に必ず頭語が必要になります。
頭語は「こんにちは」の意味を持ちますが、ビジネス関係者や目上の人にはより丁寧な「謹んで申し上げます」の意味がある「謹啓」か「拝啓」を使いましょう。
また、文章の冒頭に頭語をつけたら、「さようなら」の意味がある結語を終わりにつけるのも、忘れてはならないマナーになりますよ。
頭語と結語は対になっており、「謹啓」の結語は「謹言」もしくは「謹白」、「拝啓」の結語は「敬具」または「敬白」と決まっています。
なお、女性のみですが、どの頭語でも結語に「かしこ」をつけることができます。
ただし、「かしこ」はややカジュアルな印象を与えるため、ビジネス関係者や目上の人には使わないようにしましょう。
初雪の候以外の12月の時候の挨拶はある?

初雪が降る時期は地域によって違いますし、暖かいところでは初雪がない可能性もありますよね。
そのような場合は初雪の候は使えないため、他の時候の挨拶を選ぶのがよいでしょう。
ここでは、12月に使える初雪の候以外の時候の挨拶をご紹介します。
霜寒の候
霜寒の候は11月下旬から12月上旬に使える時候の挨拶です。
二十四節気では毎年10月23日頃が霜降となりますが、10月に霜が降りる地域は少ないのではないかと思います。
霜寒の候は二十四節気の名称ではなく、実際の季節感に合わせた時候の挨拶のため、霜が降りるようになってから使うのがよいでしょう。
師走の候
師走の候は12月全般に使える時候の挨拶です。
12月の和風月名である師走は、天候や状況に関係なく使うことができる時候の挨拶になりますよ。
寒気の候
寒気の候は12月全般に使える時候の挨拶です。
寒気とは書いて字の如く、気温が下がって寒いという意味があるため、実際に寒さが厳しくなってから使うのがよいでしょう。
冬至の候
冬至の候は12月22日頃から1月5日頃まで使える時候の挨拶です。
二十四節気の名称の一つである冬至は、一年で最も日が短く夜が長い日という意味があります。
毎年12月22日頃が該当しますが、時候の挨拶の場合はその日だけではなく、次の節気の小寒までの期間を指すため、2週間ほど使える時候の挨拶ということになりますよ。
年末厳寒の候
年末厳寒の候は12月下旬に使える時候の挨拶です。
時候の挨拶には厳寒の候があり、こちらは1月中旬から下旬に使える時候の挨拶になりますが、年末と付けることで12月下旬に使える時候の挨拶になりますよ。
Wordであいさつ文や定型文を挿入する方法
仕事上で取引先の相手にあいさつ文を送る、目上の人に手紙やはがきを出す時などに、「書き出しに悩んでしまい、なかなか作業が進まない」なんてことはよくあるのではないでしょうか。
そのような時はWordを利用してみましょう。
Wordにはあいさつ文のテンプレートがあるので、参考にすると作業が捗りやすくなりますよ。
ここではwordを使ったあいさつ文や定型文の挿入方法をご紹介します。
手順
①Wordを開きます
②挿入タブをクリックします
③テキストのところにある「あいさつ文」をクリックします
④あいさつ文の挿入を選びます
⑤何月のあいさつ文を作成するのか、最初に月を選びましょう
⑥月のあいさつ、安否のあいさつ、感謝のあいさつをそれぞれ選びます
⑦選んだら「OK」をクリックしてください
⑧Wordに選んだ文章が表示されます
ポイント
Wordではあいさつ文だけではなく、あいさつ文の後に続ける「起こし言葉」や「結び言葉」も選ぶことができますよ。
挿入タブ→テキストのあいさつ文をクリックした後、起こし言葉もしくは結び言葉を選んでください。
初雪の候のまとめ
「初雪の候」は、12月上旬から中旬に使うのが一般的な時候の挨拶です。
この表現は、「はつゆきのこう」と読み、初めて降る雪の時期を意味します。
地域によって初雪の時期は異なるため、使う際は相手の住む地域を考慮すると良いでしょう。
ビジネス文書や目上の人への手紙では、冒頭に「謹啓」や「拝啓」を付け、結びには「謹言」や「敬具」を使うのがマナーです。
親しい人には、もう少しカジュアルな言い回しを選ぶと良いですね。
初雪の候を使った例文も参考にして、季節感あふれる挨拶を楽しんでみてください。
この記事のポイントをまとめますと
- 「初雪の候」は12月上旬から中旬に使う時候の挨拶
- 地域によって初雪の時期が異なるため、相手の住む地域を考慮することが大切
- 「はつゆきのこう」と読み、初雪と候の組み合わせで「初めての雪の時期」を表現
- ビジネス文書では、冒頭に「謹啓」や「拝啓」を、結びに「謹言」や「敬具」を使用
- 親しい人へはカジュアルな言い回しを選ぶと良い
- 初雪の候を使った例文が参考になる
- 頭語と結語は対になっており、正しい組み合わせを使うことがマナー
- 女性はどの頭語にも「かしこ」を結語として使えるが、ビジネスや目上の人には適さない
- 初雪の候以外にも12月に使える時候の挨拶が存在する
- 12月の他の時候の挨拶には「霜寒の候」「師走の候」「寒気の候」「冬至の候」「年末厳寒の候」がある
- 初雪の候は丁寧な表現で、相手によっては改まった感じがすることもある


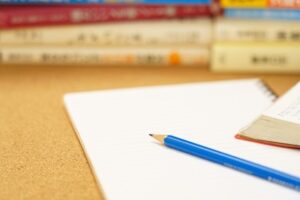

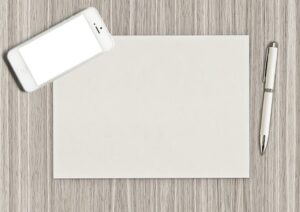









コメント