清明の候を使う時期はいつからいつまで?書き出しや結びの使い方も!
「清明の候」を手紙やメールで使いたいけれど、いつからいつまで正しく使えるのか、その意味や読み方は?さらに、書き出しから結びまでの使い方や書き方に、例文はあるのかと悩んでいませんか。
そんな時候の挨拶に関する小さな疑問も、実は多くの人が持っています。
日本の美しい季節感を表す「清明の候」ですが、間違った使い方をしてしまうと、せっかくの心遣いが台無しに…。
この記事では、清明の候がいつからいつまでの期間に使えるのか、その読み方や意味をはじめ、正しい使い方から例文までをわかりやすく解説します。
初めての方も安心して使えるように、書き出しから結びまでの書き方のポイントもご紹介。
これを読めば、あなたも清明の候を使った文書がスラスラ書けるようになりますよ。
「清明の候」がいつからいつまで使える時候の挨拶であるかがわかります。
「清明の候」の意味と読み方について理解できます。
さまざまな場面での「清明の候」の使い方や例文が学べます。
手紙やビジネス文書での「清明の候」の書き出しや結びの書き方が明確になります。
清明の候を使う時期はいつ?読み方や意味は?
清明の候を使う時期はいつからいつまで?
清明の候は4月4日頃から19日頃まで使える時候の挨拶です。
時候の挨拶の中には明確に期間が決まっていないものもありますが、清明の候は決まっています。
清明の候が4月に使える時候の挨拶と言っても、4月に入ったばかりや下旬には使えないので注意しましょう。
清明の候の読み方
清明という言葉自体を初めて聞いた方でも、それほど難しい読み方ではありませんよね。
清明の候の意味
清明とは、二十四節気の一つで、「清浄明潔」という言葉が語源となっています。
「清浄明潔」には「世の中のすべての物がきらきらと明るく清らかで生き生きとしている」という意味がありますよ。
候は時期や時候などの意味があることから、清明の候は「草や木が芽吹き、生き物たちが活発に活動しはじめる時期になりましたね」という意味になりますね。
清明の候を使った例文
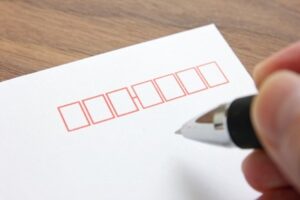
時候の挨拶は、主にビジネス関係者や目上の人など重要な人に使う場合が多いですよね。
文章に失礼がないようにと気を遣いますが、普段使い慣れている言葉ではないので、書き出しに悩んでしまうという方も多いでしょう。
そこでここでは、清明の候をビジネスで使う場合、目上の人に使う場合、親しい人に使う場合それぞれの例文をご紹介します。
ビジネスで使う場合
書き出し文
- 謹啓 清明の候、貴社にはますますご清栄の由、大慶に存じます。毎々格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
- 拝啓 清明の候、貴社におかれましてはなお一層のご発展のことと大慶至極に存じます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
- 拝啓 清明の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のお引き立てをいただき、ありがたく御礼申し上げます。
結び文
- 新年度で忙しい日々を過ごされていることと思いますが、御社ますますのご繁栄を心からお祈りしております。
- 花吹雪美しく舞う季節、貴社におかれましてはいよいよのご多忙をお祈り申し上げます。
- 春うららかな季節となりました。御社の皆様方におかれましても飛躍の春をお迎えください。
目上の人に使う場合
書き出し文
- 謹啓 清明の候、〇〇様にはますますご壮健のことと拝察いたしお慶び申し上げます。
- 拝啓 清明の候、〇〇様にはいっそうご活躍のことと慶賀の至りに存じます。
- 拝啓 晴明の候、先だって格別なご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
結び文
- 春の訪れと共に、美しい季節となりました。どうぞお健やかな春をお過ごしください。
- 植物たちが生き生きと成長するこの季節、皆様方におかれましてもどうぞお健やかにお過ごし下さい。
- 花々咲き乱れる美しい季節を迎えました。何かとお忙しい中かと思いますが、どうぞご自分を大切にしてください。
親しい人に使う場合
書き出し文
- この穏やかな春の光に癒される季節、〇〇様が変わらず健やかに過ごされていることを心より願っております。
- 桜の花が風に乗って舞う、美しい時期が到来しました。長らくお会いしていませんが、お元気でお過ごしでしょうか。
- 春が満開になり、遠出を楽しむには最適な季節になりました。皆様が健康でありますようにと思っております。
結び文
- 素晴らしい天候が続くこの時期は外出に最適ですが、お怪我などされませんようくれぐれもお気を付けください。
- まだ花冷えの日もございますので、どうぞお風邪などひかれませんようお気を付けください。
- 新しい年度や生活が始まるこの忙しい時期ですが、どうぞお健やかに爽やかな春をお過ごしください。
なお、親しい人へ送る手紙やはがきなどでは、必ずしも清明の候のような形(漢語調)を使う必要はありません。
漢語調の時候の挨拶は丁寧な表現となるので、受け取る相手によってはよそよそしさを感じてしまうこともあるでしょう。
そのような場合は、漢語調よりもカジュアルな口語調の挨拶がおすすめですよ。
清明の候の口語調の例文としては
- 「春の光にすべてが輝いて見える時期になりましたね」
- 「草木が芽吹き清々しい季節になりました」
などがあります。
結び文とは?
結び文には季節に関係なく使える定型文がありますが、時候の挨拶に季節感をあわせることで文章全体に統一感が出ますよ。
清明の候は4月に使う時候の挨拶なので、桜や花の見ごろの時期であることや、新年度について触れるのもよいでしょう。
ここでは、清明の候を時候の挨拶に使った場合の結び文の例文をご紹介します。
- 桜花爛漫の好季節、貴社益々のご発展をお祈り致しますとともに、倍旧のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。謹言
- 新年度を迎えられ、社員皆々様には一層のご健勝を心よりお祈りいたします。敬具
- そちらの花便りもお聞かせくださいませ。かしこ
清明の候を使うときに注意すること

清明の候を使って文章を書く時に、特に気をつけたいのは送り先がビジネス関係者や目上の人の場合です。
清明の候という表現自体は丁寧な言い方なのですが、ビジネス関係者や目上の人の手紙やはがきなどで、いきなり書き出しに使ってしまうのはマナーとしてはNGになるからです。
ビジネス関係者や目上の人に使うのであれば、清明の候の前に「謹啓」や「拝啓」などの頭語をつけるようにしましょう。
頭語には他にも種類がありますが、一般的に使われるのは「謹啓」と「拝啓」です。
これらには「謹んで申し上げます」という意味があり、相手に対する敬意を表しています。
なお、親しい人には必ず頭語をつける必要はありません。
例文のところでも触れましたが、漢語調の時候の挨拶を使ったり、頭語をつけることで、かえってよそよそしさを感じてしまうこともあるので注意してください。
文章に頭語をつけたら、終わりは結語で締めましょう。
頭語と結語は対になっていて、「謹啓」の結語は「謹言」もしくは「謹白」、「拝啓」の結語は「敬具」または「敬白」になりますよ。
女性のみ、どの頭語でも結語に「かしこ」が使えますが、「かしこ」はややカジュアルな印象を与えるため、ビジネス関係者や目上の人に使うのは控えた方がよいでしょう。
清明の候以外の4月の時候の挨拶はある?
手紙やはがきなどを送る相手の地域の状況に合わせて、より季節感のある時候の挨拶を選びたいものですよね。
ここでは、清明の候以外に4月に使える時候の挨拶をご紹介します。
桜花の候
3月下旬から4月中旬まで使える時候の挨拶になります。
桜の花と書く通り、春の訪れを感じさせる桜が咲く時期に使いたい時候の挨拶ですよね。
桜が咲く時期は地域によって違うので、手紙やはがきなどを送る相手が住んでいる地域の状況に合わせて使うようにしましょう。
春陽の候
4月中に使える時候の挨拶になります。
春陽とは春らしい暖かい陽気のことを指す言葉のため、春陽の候は「春らしい暖かい陽気が続く時期になりましたね」という意味がありますよ。
春爛漫の候
4月中に使える時候の挨拶です。
春爛漫とは春に咲く花が咲き乱れる様子を表しているので、春爛漫の候は「春に咲く花が咲き乱れる時期になりましたね」という意味になりますね。
麗春の候
4月下旬から5月上旬に使える時候の挨拶です。
麗春はひなげしの別称で、麗春の候には「ひなげしが咲く時期になりましたね」という意味があります。
使える期間は4月下旬からとなっていますが、地域によっては中旬頃に咲くところもあるようです。
麗春の候は二十四節気の名称ではないので、そのような場合は4月中旬であれば使っても問題はないようですが、立夏を過ぎると使えないので注意しましょう。
晩春の候
4月上旬から5月上旬まで使える時候の挨拶になります。
晩春とは旧暦の春の終わりの時期を指す言葉です。
二十四節気の清明(例年4月4日頃)から立夏(例年5月4日頃)の前日まで使える時候の挨拶になりますよ。
穀雨の候
4月下旬から5月上旬に使える時候の挨拶です。
穀雨とは二十四節気の一つの名称で、清明の次の節気になり、例年4月20日頃から5月4日頃の期間を指しています。
Wordであいさつ文や定型文を挿入する方法
仕事上で取引先の相手にあいさつ文を送る、目上の人に手紙やはがきを出す時などに、「書き出しに悩んでしまい、なかなか作業が進まない」なんてことはよくあるのではないでしょうか。
そのような時はWordを利用してみましょう。
Wordにはあいさつ文のテンプレートがあるので、参考にすると作業が捗りやすくなりますよ。
ここではwordを使ったあいさつ文や定型文の挿入方法をご紹介します。
手順
①Wordを開きます
②挿入タブをクリックします
③テキストのところにある「あいさつ文」をクリックします
④あいさつ文の挿入を選びます
⑤何月のあいさつ文を作成するのか、最初に月を選びましょう
⑥月のあいさつ、安否のあいさつ、感謝のあいさつをそれぞれ選びます
⑦選んだら「OK」をクリックしてください
⑧Wordに選んだ文章が表示されます
ポイント
Wordではあいさつ文だけではなく、あいさつ文の後に続ける「起こし言葉」や「結び言葉」も選ぶことができますよ。
挿入タブ→テキストのあいさつ文をクリックした後、起こし言葉もしくは結び言葉を選んでください。
清明の候のまとめ
清明の候は4月4日頃から19日頃まで使える時候の挨拶です。
この時期は、「清浄明潔」という意味を持ち、自然がきらきらと輝き始める美しい瞬間を象徴しています。
時候の挨拶として、ビジネスの文書やお手紙に用いると、季節感あふれる丁寧な印象を与えることができますよ。
ただし、使う際は時期を正しく把握し、書き出しには「謹啓」や「拝啓」をつけるのがマナーです。
心温まる言葉選びで、相手に春の訪れを感じさせてみてはいかがでしょうか。
この記事のポイントをまとめますと
- 清明の候は4月4日頃から19日頃まで使用される時候の挨拶
- 「せいめいのこう」と読む
- 「清浄明潔」が語源で、世の中が明るく清らかになる時期を表す
- 草木が芽吹き生き物が活発になる季節を意味する
- ビジネス文書やお手紙で使われることが多い
- 書き出しには「謹啓」や「拝啓」をつけるのが一般的
- 結びには季節感を出すことで文章に統一感が生まれる
- 相手への敬意を表す丁寧な表現
- 漢語調と口語調の例文が存在する
- 清明の候以外に春爛漫の候や麗春の候など、季節に合わせた挨拶が選べる


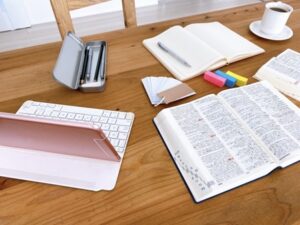
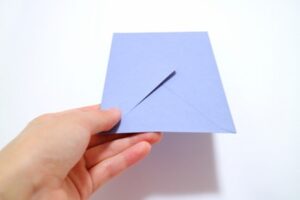

コメント