長雨の候とは、どんな時期に使うのか知っていますか?
この言葉は手紙を書くときに使われる、ちょっと特別なあいさつです。
でも、使い方や意味、読み方がわからなくて困っている方も多いかもしれません。
「長雨の候」はいつ使えるのか、どんなふうに書けばいいのか、例文や結びの文まで、詳しく知りたいですよね。
この記事では、「長雨の候」の正しい使い方や時期、意味や読み方、そして具体的な例文を紹介します。
これを読めば、手紙を書くときに自信を持って「長雨の候」を使えるようになりますよ。
- 長雨の候の意味と読み方がわかります
- 長雨の候を使う時期がわかります
- 長雨の候の正しい使い方と例文がわかります
- 長雨の候を使う際の結びの文の書き方がわかります
長雨の候を使う時期はいつ?
長雨の候は6月中旬から下旬に使える時候の挨拶になります。
一般的に中旬は11日から20日、下旬は21日から末日を指すため、長雨の候は6月11日から末日まで使える時候の挨拶ということになりますね。
長雨の候の意味や読み方は?
長雨の候は「ながあめのこう」と読みます。
時候の挨拶は音読みすることが多く、長雨を音読みすると‘ちょうう’になりますが、長雨の候の場合は訓読みで「ながあめ」となります。
これに対し候は音読みで「こう」と読むので、長雨の候の読み方はやや複雑と言えますね。
長雨とは書いて字の如く長く降り続く雨のことを指し、候には時期や時候などの意味があることから、長雨の候は「長く雨が降る梅雨の時期になりましたね」という意味になります。
長雨の候の正しい使い方は?
6月に降る長雨を梅雨と言いますが、6月以外にも長く雨が降る時期はあり、春の長雨は春雨、秋の長雨は秋雨と言います。
特に秋雨は「秋雨前線が」のようにニュースや天気予報で聞くことも多く、台風シーズンと重なることなどから、「秋に長く雨が降る場合にも、長雨の候を使ってもよいのでは?」と思う方がいるかも知れません。
しかし、時候の挨拶の中で長雨とは梅雨に限定した表現となり、梅雨の時期以外に使うことはできません。
そのため、春や秋に長く雨が降っていても、長雨の候は使わないようにしましょう。
長雨の候を使った例文
時候の挨拶は普段使わない表現のため、いざ手紙やはがきなどを送る時にどのように書いたらよいのか悩んでしまう方は多いでしょう。
そこでここでは、長雨の候を使った例文をご紹介します。
ビジネスで使う場合
- 謹啓 長雨の候、貴社におかれましては益々ご隆盛の趣、慶賀の至りに存じます。毎々格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
- 拝啓 長雨の候、貴社におかれましてはいよいよご発展の由、心からお喜び申し上げます。平素は格別のご高配をいただき心から感謝申し上げます。
- 拝啓 長雨の候、貴店にはご清栄の段、何よりと存じます。日頃は格別のお引き立てをいただき、ありがたく御礼申し上げます。
目上の人に使う場合
- 謹啓 長雨の候、〇〇様にはますますご壮健のことと拝察いたしお慶び申し上げます。
- 拝啓 長雨の候、皆様にはいよいよご清福のことと拝察し、お慶び申し上げます。
親しい人に使う場合
- 長雨の候、紫陽花が大輪の花を咲かせるころとなりました。ご無沙汰してしまいましたが、お元気ですか。
- 長雨の候、プール開きのニュースにいよいよ本格的な夏の始まりを感じる今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。
なお、親しい人には漢語調の時候の挨拶を使う必要はありません。
漢語調とは長雨の候のような〇〇の候と書くもので、時候の挨拶の中では丁寧な表現になります。
ビジネス関係者や目上の人に送る手紙やはがきなどに漢語調を使うのはよいのですが、親しい人に使うと相手がよそよそしさを感じてしまうこともあるでしょう。
そのよう場合は、漢語調よりもカジュアルな口語調を使うのがおすすめですよ。
口語調の例文としては、「雨ばかりで気がめいりそうな毎日ですね。お元気にしていますか」のような書き出しがよいでしょう。
長雨の候の結び文
結び文とは文章の締めくくりに書く文です。
結び文には季節に関係なく使える定型文がありますが、時候の挨拶の季節感に合わせた結び文を使うと、文章全体に統一感が出ますよ。
ここでは、長雨の候を使った場合の結び文の例文をご紹介します。
- 青葉の色あざやかなこの季節、ますますのご発展をお祈り申し上げます。謹言
- 時節柄、体調を崩しませんよう御身おいといください。敬具
- 日増しに暑くなってきますが、夏バテしないように気をつけて下さいね。かしこ
長雨の候を使うときに注意すること
長雨の候を使って手紙やはがきなどを書くときは、親しい人以外であれば最初に必ず頭語をつけるようにしましょう。
特にビジネス関係者や目上の人に送る手紙やはがきなどには、「謹んで申し上げます」という丁寧な意味を持つ「謹啓」や「拝啓」を使います。
これらの頭語には相手への敬意を表す意味合いがあるため、頭語をつけずにいきなり「長雨の候・・」と書き出してしまうと、マナーとしてはNGになりますよ。
「拝啓 長雨の候」のように、時候の挨拶の前につけるようにしましょう。
また、頭語をつけたら文章の終わりには結語を入れて下さい。
頭語と結語は対になっており、「謹啓」の結語は「謹言」または「謹白」、「拝啓」の結語は「敬具」もしくは「敬白」となります。
女性のみ、どの頭語でも結語に「かしこ」を使うことができますが、「かしこ」はややカジュアルな印象があるため、ビジネス関係者や目上の人に送る手紙やはがきなどには使わない方がよいでしょう。
長雨の候以外の6月の時候の挨拶はある?
長雨の候は晴れが続いている時には使いにくい時候の挨拶ですよね。
そこでここでは、長雨の候以外に6月に使える時候の挨拶をご紹介します。
手紙やはがきなどを送る相手の住んでいる地域の状況に合わせて、時候の挨拶を選んでみましょう。
芒種の候
6月4日頃から6月20日頃まで使える時候の挨拶です。
芒種は二十四節気の一つで、稲や麦などの穀物の種を撒く時期という意味があります。

深緑の候
6月全般に使える時候の挨拶です。
深緑の候には、「木々の葉の緑が濃くなっていく時期になりましたね」という意味がありますよ。
深緑の候には読み方が同じ新緑の候がありますが、意味や使える時期が違うので注意して下さい。

桜桃の候
6月5日頃から7月5日頃の仲夏の時期に使える時候の挨拶になります。
桜桃とはさくらんぼの別称です。
桜桃の候には「さくらんぼのおいしい季節になりましたね」という意味がありますよ。

黄梅の候
6月16日頃~21日頃に使える時候の挨拶になります。
黄梅とは七十二候の「梅子黄」のことを指す言葉です。
黄梅の候には「青々とした梅の実が黄色く色づく時期になりましたね」という意味がありますよ。

小夏の候
6月下旬から7月上旬に使える時候の挨拶で、小夏には旧暦では夏の半ば(仲夏)を指す言葉となっています。
小夏の候を5月や6月上旬に使うのは間違いなので注意しましょう。

Wordであいさつ文や定型文を挿入する方法
仕事上で取引先の相手にあいさつ文を送る、目上の人に手紙やはがきを出す時などに、「書き出しに悩んでしまい、なかなか作業が進まない」なんてことはよくあるのではないでしょうか。
そのような時はWordを利用してみましょう。
Wordにはあいさつ文のテンプレートがあるので、参考にすると作業が捗りやすくなりますよ。
ここではwordを使ったあいさつ文や定型文の挿入方法をご紹介します。
手順
①Wordを開きます
②挿入タブをクリックします
③テキストのところにある「あいさつ文」をクリックします
④あいさつ文の挿入を選びます
⑤何月のあいさつ文を作成するのか、最初に月を選びましょう
⑥月のあいさつ、安否のあいさつ、感謝のあいさつをそれぞれ選びます
⑦選んだら「OK」をクリックしてください
⑧Wordに選んだ文章が表示されます
ポイント
Wordではあいさつ文だけではなく、あいさつ文の後に続ける「起こし言葉」や「結び言葉」も選ぶことができますよ。
挿入タブ→テキストのあいさつ文をクリックした後、起こし言葉もしくは結び言葉を選んでください。
長雨の候のまとめ
「長雨の候」は、6月中旬から下旬にかけて使われる時候の挨拶です。
「ながあめのこう」と読み、梅雨の時期を表します。
この挨拶は、特にビジネス関係や目上の人に対して使うときにぴったりです。
例文も多く、親しい人にはもう少しカジュアルな表現を使うのもおすすめです。
時候の挨拶は、季節感を大切にする日本の文化の一部ですので、相手に合った表現を選ぶと良いでしょう。
長雨の候を使うときは、頭語や結語も忘れずに付けるのがポイントです。
この記事のポイントをまとめますと
- 長雨の候は6月中旬から下旬に使われる時候の挨拶
- 読み方は「ながあめのこう」
- 梅雨の時期を表す
- 使える期間は6月11日から末日まで
- 「長く雨が降る梅雨の時期になりました」という意味
- ビジネス関係や目上の人に使うと丁寧
- 頭語として「謹啓」や「拝啓」を使う
- 結語として「謹言」や「敬具」を使う
- 親しい人にはカジュアルな表現が適している
- 漢語調はフォーマルな場面に適している
- 春や秋の長雨には使わない
- 例文があると書きやすい
- 親しい人には口語調が自然
- 定型文を使うと便利
- Wordのテンプレート機能も利用できる
- 他の時候の挨拶も考慮するべき
- 長雨の候を使うときは季節感を大切にする


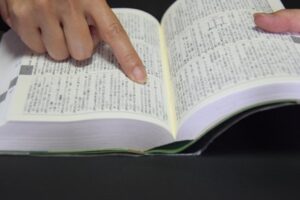





コメント