秋晴の候を使う時期や読み方、使い方と例文について解説しています。
秋晴は漢字から、何となくの意味が想像しやすいですよね。
とは言え、秋晴の候を使う時期などは、よくわからないという方が多いでしょう。
そこで今回は、秋晴の候の使い方を詳しく調べてみました。
秋晴の候を使う時期はいつ?
秋晴の候は、主に9月下旬から10月中旬に使用される時候の挨拶です。
この時期は、澄み渡る青空と涼しい風が特徴で、多くの人々にとって心地よい季節となります。
具体的な使用時期
秋晴の候の使用時期に関しては厳密な決まりはありませんが、一般的には以下の期間が適しています。
| 月 | 期間 | 特徴 |
|---|---|---|
| 9月下旬 | 9月21日~30日 | 夏の暑さが和らぎ、爽やかな風が吹く |
| 10月上旬 | 10月1日~10日 | 日中は暖かく、朝晩は涼しくなる |
| 10月中旬 | 10月11日~20日 | 紅葉が始まり、秋の深まりを感じる |
ただし、秋晴の候を使う時期については、あまり厳密に捉える必要はありません。
秋晴の意味に合う状況であれば、例えば9月中旬や10月下旬に使用しても問題ありません。
日本の気候は年によって異なるため、その年の天候や地域の特性に合わせて使うことができます。
このように、秋晴の候は、9月下旬から10月中旬を中心に、その時期の美しい秋空を表現するのに最適な言葉です。
挨拶文や手紙に添えることで、季節感を伝えるとともに、受け取る相手に心地よい印象を与えることができるでしょう。
秋晴の候の意味や読み方は?
秋晴の候は、日本語で「しゅんせいのこう」と読むのが一般的ですが、「あきばれのこう」と読んでも間違いではありません。
時候の挨拶では音読みが主流であり、秋晴も音読みで「しゅんせい」となります。
しかし、俳句や日常の会話では「あきばれ」と読むことも多く見受けられます。
このように、どちらの読み方も正しいとされています。
音読みと訓読みの違い
| 読み方 | 例 | 説明 |
|---|---|---|
| 音読み | しゅんせいのこう | 公式な場面や文章に適している |
| 訓読み | あきばれのこう | 俳句や日常会話で親しまれている |
候の読み方
「候(こう)」は、時期や時候を表す際に用いられます。
例えば、「春の候(しゅんのこう)」「夏の候(かのこう)」などと使われ、季節の移り変わりを感じさせる表現です。
このため、「秋晴の候」も「秋らしい澄み切った空が広がる時期になりましたね」という意味を持ちます。
秋晴の意味
秋晴とは、秋特有の澄んだ空気と高く広がる青空を指す言葉です。
秋晴の日は、気温が穏やかで過ごしやすく、視界がクリアになるため、遠くの山々や景色が美しく見えることが特徴です。
このような日を楽しむために、散歩やアウトドア活動が一層魅力的になります。
「秋晴の候」は「しゅんせいのこう」と「ちきばれのこう」どちらの読み方も正しく、状況に応じて使い分けることができます。
音読みは公式な場面に、訓読みは俳句や日常会話に適しています。
「秋晴の候」を使うことで、秋の美しい季節感を伝え、心温まる挨拶をすることができるのです。
秋晴の候の正しい使い方は?
季節の挨拶文である時候の挨拶は、日本の美しい四季を感じさせる言葉の一つですが、これらの多くは旧暦に基づいているため、新暦とは季節感にズレが生じることがしばしばあります。
まず、旧暦における「立秋」は新暦の8月7日頃にあたります。
この時期はまだ夏の暑さが続いており、秋の気配を感じるには早すぎるように思えますね。
しかし、日本の文化ではこの日を境に秋の挨拶文が使われ始めるのです。
一方で、「秋晴の候」という表現について考えてみましょう。
これも同様に立秋を過ぎたら使えるのではないかと思われるかもしれません。
しかし、「秋晴の候」は旧暦や二十四節気に直接結びついているわけではありません。
実際の季節感、つまり新暦に合わせて使用するのが正しいのです。
具体的には、秋晴を実感できる9月から10月に使うのが適切です。
この時期は、気候が穏やかで空が澄み渡り、まさに「秋晴れ」を感じることができます。
そのため、以下のようなタイミングで「秋晴の候」を使うと良いでしょう。
| 時期 | 表現の使用例 |
|---|---|
| 9月初旬 | 「残暑も和らぎ、秋晴の候となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。」 |
| 9月中旬 | 「秋晴の候、皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。」 |
| 10月初旬 | 「爽やかな秋晴の候、日々のご多幸をお祈りいたします。」 |
これらの例からもわかるように、「秋晴の候」は9月から10月にかけての季節感に合った表現として使用することで、相手に自然な季節感を伝えることができます。
また、この時期の気候の特徴として、湿度が低く爽やかな風が吹き、空気が澄んでいることが多いため、このような表現が特に相応しいと言えるでしょう。
最後に、「秋晴の候」を使う際には、その背景にある季節の移ろいを感じながら、相手の健康や幸せを願う気持ちを込めることが大切です。
日本の美しい四季を感じさせるこの表現を、ぜひ正しい時期に用いて、より丁寧で心のこもった挨拶をしてみてください。
時候の挨拶を使った具体的な書き方(基本文例)
文例をご紹介しますが、基本的な構成が決まっていますので、まずは基本形をどうぞ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1.頭語 | 拝啓 |
| 2.時候の挨拶・書き出し | 〇〇の候、貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 |
| 3.本文・用件 | 本文の内容はここに記入します。手紙を書こうと思った気持ちを思い出しながら、筆を進めてください。 |
| 4.結びの言葉 | 〇〇の季節も過ぎましたが、御社のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。 |
| 5.結語 | 敬具 |
| 6.日付 | 令和〇〇年〇月〇〇日 |
| 7.送り主 | 秋晴太郎 |
| 8.宛先 | 〇〇〇〇様 |
ポイント:
- 頭語と結語は決まり文句です。これらはそのまま使用します。
- 時候の挨拶では、季節感を出すことが大切です。季節に合った挨拶を選び、天候や気候に言及して具体的な情景を思い浮かべられるようにします。また、相手の健康を気遣う言葉を加えることで、相手への思いやりを表現します。
- 句読点やスペースを適切に使い、読みやすい文章を心掛けます。
- 親しい友人に対しても、基本的な形式を押さえつつ、個人的なメッセージを加えることで、温かみのある手紙を作成できます。
秋晴の候を使った例文
秋晴の候を使った文章は、普段使い慣れていないという方は多く、書き出しに悩んでしまうものです。
そこでここでは、秋晴の候をビジネスで使う場合、目上の人に使う場合、親しい人に使う場合に分け、それぞれ例文をご紹介します。
例文を参考にオリジナルの文章を考えてみましょう。
ビジネスで使う場合
目上の人に使う場合
- 拝啓 秋晴の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
- 謹啓 秋晴の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
- 敬啓 秋晴の候、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
- 謹白 秋晴の候、貴台におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
- 拝呈 秋晴の候、皆様におかれましては、ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
親しい人に使う場合
- 秋晴の候、すっかり過ごしやすくなりましたね。お元気にお過ごしでしょうか。
- 秋晴の候、爽やかな青空が広がる季節となりました。最近はどんな秋を楽しんでいますか?
- 秋晴の候、心地よい風が吹く毎日ですね。元気に秋を満喫していますか?
- 秋晴の候、澄んだ空気に秋の深まりを感じる頃となりました。お変わりありませんか?
- 秋晴の候、清々しい日々が続いていますね。秋の味覚は楽しめていますか?
なお、親しい人には、必ずしも秋晴の候を使う必要はありません。
秋晴の候のような〇〇の候の形は、時候の挨拶では漢語調と言って、丁寧な表現となります。
ビジネス関係者や目上の人に送る手紙やはがきなどに使うのはよいのですが、親しい人に使うとよそよそしさを感じてしまうことが多いようです。
親しい人に時候の挨拶を使う時は、漢語調よりもカジュアルな口語調を使うのがよいでしょう。
秋晴の候を口語調で書く場合は、「雲一つない澄み渡った空の下、楽しく体を動かせる時期になりましたね。いかがお過ごしでしょうか」のような書き出しでよいでしょう。
秋晴の候の結び文
結び文とは文章の締めくくりに書く文のことです。
結び文には季節に関係なく使える定型文がありますが、時候の挨拶の季節感に合わせた結び文を入れると、文章全体に統一感が出ます。
ここでは、秋晴の候を使った場合の結び文の例文をご紹介します。
- 清々しい秋空の下、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。敬具
- 紅葉が美しさを増す季節、皆様のご健勝とご多幸を心からお祈りいたします。謹白
- 実りの秋を迎え、貴社の更なるご繁栄を心よりお祈り申し上げます。敬具
- 澄み切った空気に秋の深まりを感じる頃となりました。くれぐれもご自愛ください。草々
- 爽やかな秋風が心地よい季節となりました。皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。敬白
秋晴の候を使うときに注意すること
ビジネス関係者や目上の方に送る手紙やはがきで、いきなり「秋晴の候」で始めるのはマナー違反となります。このような場合、文章の冒頭に必ず頭語を付けることが求められます。頭語を使うことで、手紙全体の丁寧さと礼儀正しさを示すことができます。
頭語にはさまざまな種類がありますが、一般的によく使われるのは「謹啓」と「拝啓」です。「謹啓」は「拝啓」よりもさらに丁寧な表現であり、特に重要な取引先やお世話になった恩師などに送る手紙には「謹啓」を使うことが適しています。
また、頭語を付けた場合、文章の締めくくりには結語を使う必要があります。頭語と結語は対になっており、それぞれの対応関係を理解することが重要です。「謹啓」の結語は「謹言」もしくは「謹白」、「拝啓」の結語は「敬具」または「敬白」となります。以下に具体的な組み合わせを表にまとめます。
| 頭語 | 結語 |
|---|---|
| 謹啓 | 謹言、謹白 |
| 拝啓 | 敬具、敬白 |
さらに、結語の入れ方については、適切な結び文の例文を参考にするとよいでしょう。
なお、女性の場合は、どの頭語を使用しても結語に「かしこ」を使うことができます。
しかし、「かしこ」はややカジュアルな印象を与えるため、ビジネス関係者や目上の方に対しては避けた方が無難です。
例として、ビジネスの場面で使用する場合の手紙の書き出しと結びの例を示します。
手紙の例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 頭語 | 謹啓 |
| 時候の挨拶 | 秋晴の候、貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。 |
| 本文 | 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。(中略) 今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 |
| 結語 | 謹言 |
このように、ビジネス文書や礼儀を重んじる場面では、適切な頭語と結語を使用することが大切です。
これにより、相手に対する敬意と配慮が伝わり、良好な関係を築く一助となるでしょう。
秋晴の候以外の9月の時候の挨拶はある?
秋晴の候は、秋らしく爽やかな天気ではないと使いにくい時候の挨拶ですよね。
そのような場合は、秋晴の候以外に9月に使える時候の挨拶を覚えておくと便利でしょう。
ここでは、9月に使える秋晴の候以外の時候の挨拶をご紹介します。
涼風の候
涼風の候は8月下旬から9月上旬に使える時候の挨拶です。
涼風の候には「夏も終わりに近づき、秋めいた涼しい風が吹く時期になりましたね」という意味があります。

爽秋の候
爽秋の候は9月上旬から中旬に使える時候の挨拶になります。
爽やかな秋と書く通り、「爽やかで心地のよい季節になりましたね」という意味がありますよ。

白露の候
白露の候は、9月7日頃から21日頃に使える時候の挨拶になります。
白露は二十四節気の一つで、「草や木に白い露がつく時期になりました」という意味があります。

秋分の候
秋分の候は9月22日頃から10月7日頃まで使える時候の挨拶です。
秋分は秋分の日が有名で、これには昼と夜がほぼ同じ長さとなる日という意味がありますよね。
時候の挨拶における秋分は二十四節気の一つであり、次の節気である寒露までを指す期間になるため、秋分の候も同期間使える時候の挨拶になりますよ。

仲秋の候
仲秋の候は9月7日頃から10月7日頃まで使える時候の挨拶です。
仲秋とは旧暦の秋の半ばを指す言葉で、二十四節気の白露から寒露までの期間が該当します。

Wordであいさつ文や定型文を挿入する方法
仕事上で取引先の相手にあいさつ文を送る、目上の人に手紙やはがきを出す時などに、「書き出しに悩んでしまい、なかなか作業が進まない」なんてことはよくあるのではないでしょうか。
そのような時はWordを利用してみましょう。
Wordにはあいさつ文のテンプレートがあるので、参考にすると作業が捗りやすくなりますよ。
ここではwordを使ったあいさつ文や定型文の挿入方法をご紹介します。
手順
①Wordを開きます
②挿入タブをクリックします
③テキストのところにある「あいさつ文」をクリックします
④あいさつ文の挿入を選びます
⑤何月のあいさつ文を作成するのか、最初に月を選びましょう
⑥月のあいさつ、安否のあいさつ、感謝のあいさつをそれぞれ選びます
⑦選んだら「OK」をクリックしてください
⑧Wordに選んだ文章が表示されます
ポイント
Wordではあいさつ文だけではなく、あいさつ文の後に続ける「起こし言葉」や「結び言葉」も選ぶことができますよ。
挿入タブ→テキストのあいさつ文をクリックした後、起こし言葉もしくは結び言葉を選んでください。
秋晴の候のまとめ
秋晴の候は9月下旬から10月中旬に使える時候の挨拶ですが、天気や天候の状況によっては9月中旬や10月下旬に使っても問題はありません。
秋らしい清々しい時期に、秋晴の候を使って大切な方へ手紙やはがきを送ってみませんか?




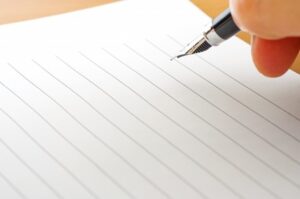

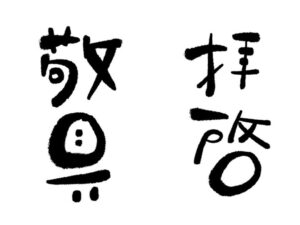

コメント