白露の候を使う時期や読み方、使い方と例文について解説しています。
白い露と書く白露は、雨が多い時期に使える時候の挨拶なのでしょうか。
白露の候や意味や使うタイミングを知りたい方は多いですよね。
そこで今回は、白露の候の使い方を詳しく調べてみました。
白露の候を使う時期はいつ?
「白露の候」とは、日本の伝統的な時候の挨拶の一つで、主に9月7日頃から9月23日頃までの期間に使用されます。
この時期は、夏の暑さが和らぎ、秋の気配が感じられる頃です。
「白露の候」を使う理由
「頃」と表現される理由には、以下のような背景があります。
- 二十四節気に基づく: 「白露」は二十四節気の一つで、太陽の位置によって1年を24等分したものです。日本では、これを基に季節の移ろいを感じ取り、挨拶に反映しています。「白露」は太陽が黄経165度に達する時期に当たり、具体的には毎年9月7日頃です。
- 自然現象の観察: 「白露」は「白い露」という意味で、朝晩の気温が下がり、草花に露が白く見えるようになることから名付けられました。この露が見られる期間が「白露の候」の期間とされています。
- 暦と実際の気候のズレ: 日本の気候は年によって若干の変動があるため、厳密に日付を決めるのが難しいのです。そのため「頃」として、ある程度の幅を持たせています。
「白露の候」は、日本の季節感を大切にする美しい表現であり、9月7日頃から9月23日頃までの期間に使用するのが適切です。
この時期に送る挨拶状や手紙に、この表現を添えることで、相手に対する思いやりや季節の移ろいを感じさせることができます。
ぜひ、日常のコミュニケーションに取り入れてみてください。
白露の候の意味や読み方は?
「白露の候」は、季節の挨拶として用いられる言葉で、「はくろのこう」と読みます。
つい「しろつゆ」や「しらつゆ」と読んでしまいたくなりますが、時候の挨拶では音読みが基本ですので、「はくろ」と読むのが正しいです。
同様に、「候」は「そうろう」と読みがちですが、ここでは「こう」と読みます。
白露の候の意味
白露とは、夏の終わりから秋の初めにかけて、特に9月上旬頃の朝晩に感じられる涼しさの中、草木に露が降りて白く見える様子を表した言葉です。
この「白露」という現象は、日本の四季の変化を感じさせる美しい情景の一つです。
候には、「時期」や「時候」という意味があります。
したがって、「白露の候」とは「草に朝露がつく時期になりましたね」という季節の移り変わりを知らせる言葉です。
これは、自然の美しさを感じさせるとともに、その時期特有の気候の変化を表現しています。
「白露の候」は、日本の美しい季節の移ろいを感じさせる言葉であり、正しく理解して使うことで、相手に季節感を伝えることができます。
特に、手紙やメールなどで季節の挨拶として使用する際には、その意味や読み方をしっかりと押さえておくことが重要です。
自然の美しさや季節の変化を表現することで、より丁寧で親しみのあるコミュニケーションが図れるでしょう。
白露の候の正しい使い方は?
白露の候(はくろのこう)は、日本の二十四節気の一つである「白露」を示す言葉です。
旧暦(太陰暦)では、月の満ち欠けによって暦を決めており、1ヶ月が29日または30日となるため、現在の太陽暦(新暦)とは季節感にズレが生じます。
このズレを解消するために、古代中国で考案され、日本でも用いられるようになったのが二十四節気です。
二十四節気とは、一年を24等分し、それぞれの期間に季節を表す名称を付けたものです。
白露は、その一つであり、現在の暦では9月上旬から中旬にあたります。
白露の候の現代的な使い方
しかし、新暦と旧暦には約1ヶ月の誤差があるため、現代の白露の時期にはまだ残暑が続いていることが多く、朝露が見られることは少ないです。
にもかかわらず、時候の挨拶や季節の表現として「白露の候」を使用することには意味があります。
これは、二十四節気が日本の伝統的な文化や風習の一部として根付いているからです。
実際の気候条件とは異なる場合でも、白露の候は9月上旬から中旬に使うのがマナーとなります。
これは、旧暦に基づく時候の挨拶が現代でも尊重され、用いられているためです。
例えば、ビジネスやプライベートの手紙やメールにおいて、「白露の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます」といった挨拶文を使うことで、相手に季節感を伝えつつ、古き良き日本の文化を感じさせることができます。
二十四節気とその期間
| 節気の名称 | 新暦の期間 |
|---|---|
| 立春 | 2月4日頃 |
| 雨水 | 2月19日頃 |
| 啓蟄 | 3月6日頃 |
| 春分 | 3月21日頃 |
| 清明 | 4月5日頃 |
| 穀雨 | 4月20日頃 |
| 立夏 | 5月5日頃 |
| 小満 | 5月21日頃 |
| 芒種 | 6月6日頃 |
| 夏至 | 6月21日頃 |
| 小暑 | 7月7日頃 |
| 大暑 | 7月23日頃 |
| 立秋 | 8月7日頃 |
| 処暑 | 8月23日頃 |
| 白露 | 9月8日頃 |
| 秋分 | 9月23日頃 |
| 寒露 | 10月8日頃 |
| 霜降 | 10月23日頃 |
| 立冬 | 11月7日頃 |
| 小雪 | 11月22日頃 |
| 大雪 | 12月7日頃 |
| 冬至 | 12月21日頃 |
| 小寒 | 1月6日頃 |
| 大寒 | 1月20日頃 |
この表を参考にして、季節の移ろいを感じながら、二十四節気に合わせた時候の挨拶を取り入れてみてくださいね。
このように、白露の候は実際の気候状況に関係なく、二十四節気の期間に合わせて使うことが正しいとされています。
これにより、季節感と日本の伝統文化を大切にする心を伝えることができるのです。
時候の挨拶を使った具体的な書き方(基本文例)
文例をご紹介しますが、基本的な構成が決まっていますので、まずは基本形をどうぞ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1.頭語 | 拝啓 |
| 2.時候の挨拶・書き出し | 〇〇の候、貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 |
| 3.本文・用件 | 本文の内容はここに記入します。手紙を書こうと思った気持ちを思い出しながら、筆を進めてください。 |
| 4.結びの言葉 | 〇〇の季節も過ぎましたが、御社のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。 |
| 5.結語 | 敬具 |
| 6.日付 | 令和〇〇年〇月〇〇日 |
| 7.送り主 | 白露太郎 |
| 8.宛先 | 〇〇〇〇様 |
ポイント:
- 頭語と結語は決まり文句です。これらはそのまま使用します。
- 時候の挨拶では、季節感を出すことが大切です。季節に合った挨拶を選び、天候や気候に言及して具体的な情景を思い浮かべられるようにします。また、相手の健康を気遣う言葉を加えることで、相手への思いやりを表現します。
- 句読点やスペースを適切に使い、読みやすい文章を心掛けます。
- 親しい友人に対しても、基本的な形式を押さえつつ、個人的なメッセージを加えることで、温かみのある手紙を作成できます。
白露の候を使った例文
白露の候は普段使い慣れていない方も多く、手紙やはがきなどで使うときに書き出しに悩んでしまう方は多いのではないでしょうか。
特にビジネス関係者や目上の人に送る手紙やはがきなどでは、失礼がないように気を遣いますよね。
そこでここでは、白露の候を使った例文をケース別にいくつかご紹介します。
手がはがきなどを送る相手に合わせて例文を参考に、オリジナルの文章を作成してみましょう。
ビジネスで使う場合
- 拝啓 白露の候、貴社におかれましてはますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。
- 拝啓 白露の候、秋の気配が感じられる今日この頃、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。
- 拝啓 白露の候、日ごとに涼しさが増し、貴社のご発展をお祈り申し上げます。
- 拝啓 白露の候、秋の訪れを感じる季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
- 拝啓 白露の候、貴社のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。
目上の人に使う場合
- 拝啓 白露の候、朝夕の涼しさが心地よい季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
- 拝啓 白露の候、しだいに秋の気配が感じられる今日この頃、貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。
- 拝啓 白露の候、日ごとに秋の深まりを感じる時節となりましたが、貴殿にはお変わりありませんか。
- 拝啓 白露の候、実りの秋を迎え、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。
- 拝啓 白露の候、涼風が心地よく感じられる季節となりました。お元気でお過ごしのことと存じます。
親しい人に使う場合
なお、親しい人へ送る手紙やはがきなどでは、必ずしも白露の候を使う必要はありません。
白露の候のような〇〇の候は漢語調という表現で、時候の挨拶の中でも丁寧なものになります。
ビジネス関係者や目上の人に送る手紙やはがきなどでは必須ですが、一方で親しい人に使うとよそよそしさを感じてしまう方も多いようです。
親しい人へ送る手紙やはがきなどでは、漢語調よりもカジュアルな口語調の時候の挨拶を使うのがおすすめですよ。
白露の候を口語調にするなら、「朝露が降りる時期になりましたね。お元気にしていますか」のような書き出しでよいでしょう。
白露の候の結び文
結び文とは文章の締めくくりに書く文です。
結び文には季節に関係なく使える定型文がありますが、時候の挨拶の季節感に合わせた結び文を使うと、文章全体に統一感を出すことができますよ。
白露の候を時候の挨拶に使った文章であれば、秋の始まりを感じさせる結び文がよいでしょう。
ここでは、白露の候を使った場合の結び文の例文をご紹介します。
- 朝夕の空気に秋の気配が感じられる頃となりました。皆様におかれましては、季節の変わり目にご自愛くださいますようお願い申し上げます。敬具
- 虫の音が心地よく響く季節となりました。どうぞ秋の夜長をお楽しみください。皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。謹白
- 秋の味覚が豊かに実る時期となりました。食欲の秋を存分に楽しまれ、ますますのご活躍をお祈り申し上げます。敬具
- 澄み切った青空が広がる季節となりました。爽やかな秋風とともに、皆様のご多幸を心よりお祈り申し上げます。謹白
- 夜露に濡れた草花が美しく輝く頃となりました。秋の訪れとともに、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。敬具
白露の候を使うときに注意すること
白露の候を使用する際は、送る相手にふさわしい頭語と結語を選ぶことが重要です。
以下に、その注意点を詳しく説明いたします。
まず、手紙やはがきの冒頭には「頭語」を添えることが一般的です。
頭語とは、手紙の最初に書く挨拶の言葉で、「こんにちは」の意味を持ちます。
一般的な頭語には「謹啓」と「拝啓」があり、それぞれ丁寧な意味合いを持っています。
- 謹啓:「謹んで申し上げます」という意味を持ち、特にビジネス関係者や目上の方に使うのが適しています。例えば、重要な取引先や上司への手紙には「謹啓」を用いると良いでしょう。
- 拝啓:「拝して申し上げます」という意味があり、こちらも丁寧な表現ですが、「謹啓」ほど厳粛ではないため、親しい上司やビジネス関係者に適しています。
親しい友人や家族に対しては、特に頭語をつける必要はありませんが、丁寧な印象を与えたい場合には、簡単な頭語を使うことも考えられます。
次に、頭語を使用する際には、必ず対応する「結語」で文章を締める必要があります。
頭語と結語はセットで使うのが基本です。
- 謹啓の結語:謹言、謹白
- 拝啓の結語:敬具、敬白
例えば、ビジネス文書で「謹啓」を使った場合、最後は「謹言」または「謹白」で締めるようにしましょう。
同様に、「拝啓」を使った場合は「敬具」または「敬白」で締めます。
特に女性が使う場合、「かしこ」という結語を使用することができます。
この結語は親しみやすさを出すためのもので、ビジネスや目上の人には避けるのが望ましいです。
「かしこ」はややカジュアルな印象を与えるため、友人や親しい関係の人への手紙に使うのが適しています。
以下の表にまとめましたので、参考にしてください。
| 頭語 | 結語 | 使用シーン |
|---|---|---|
| 謹啓 | 謹言、謹白 | ビジネス関係者、目上の人 |
| 拝啓 | 敬具、敬白 | 親しいビジネス関係者、目上の人 |
| なし | かしこ(女性のみ) | 親しい友人、家族 |
このように、相手や状況に応じて頭語と結語を選び、丁寧な文章を書くことで、より一層相手に対する礼儀と配慮を示すことができます。
白露の候を使う際には、これらの点に注意し、心のこもった手紙を送るように心がけましょう。
白露の候に関連するその他の表現
白露の候は二十四節気の白露の期間にしか使うことができません。
それ以外の9月に使える時候の挨拶が知りたいですよね。
また、白露の候が使える期間であっても、白露の候以外に使える時候の挨拶を覚えておくと便利でしょう。
ここでは、白露の候以外に9月に使える時候の挨拶をご紹介します。
涼風の候
8月下旬から9月上旬に使える時候の挨拶です。
涼風の候には「秋めいた涼しい風が吹く時期になりましたね」という意味がありますよ。
秋が深まり身を凍らせるような冷たい風は涼風と言わないので、使う時期には注意して下さい。

重陽の候
9月1日から9月9日まで使える時候の挨拶になります。
重陽とはご節句の一つで、縁起の良い陽数の最大値である9が2つ重なる9月9日に菊を鑑賞したり、菊酒や栗ご飯を食べながら無病息災を願う行事を指します。

爽秋の候
9月上旬から中旬に使える時候の挨拶です。
爽やかな秋と書く通り、秋の始まりのすがすがしい時期に使える時候の挨拶になりますよ。

秋分の候
9月22日頃から10月7日頃まで使える時候の挨拶です。
秋分は二十四節気の一つで、次の節気の寒露までの期間を指す名称になります。

仲秋の候
9月7日頃から10月7日頃まで使える時候の挨拶です。
仲秋には旧暦の秋の半ばという意味があり、旧暦では二十四節気の白露から寒露までの期間を指す言葉になりますよ。

秋風の候
9月全般に使える時候の挨拶になります。
秋風には秋に吹く風という意味がありますが、時候の挨拶で使う場合には秋の始まりに吹くやや涼しい風という意味になります。
秋本番から秋の終わりに吹く冷たい風ではないので、10月や11月に秋風の候は使えません。

Wordであいさつ文や定型文を挿入する方法
仕事上で取引先の相手にあいさつ文を送る、目上の人に手紙やはがきを出す時などに、「書き出しに悩んでしまい、なかなか作業が進まない」なんてことはよくあるのではないでしょうか。
そのような時はWordを利用してみましょう。
Wordにはあいさつ文のテンプレートがあるので、参考にすると作業が捗りやすくなりますよ。
ここではwordを使ったあいさつ文や定型文の挿入方法をご紹介します。
手順
①Wordを開きます
②挿入タブをクリックします
③テキストのところにある「あいさつ文」をクリックします
④あいさつ文の挿入を選びます
⑤何月のあいさつ文を作成するのか、最初に月を選びましょう
⑥月のあいさつ、安否のあいさつ、感謝のあいさつをそれぞれ選びます
⑦選んだら「OK」をクリックしてください
⑧Wordに選んだ文章が表示されます
ポイント
Wordではあいさつ文だけではなく、あいさつ文の後に続ける「起こし言葉」や「結び言葉」も選ぶことができますよ。
挿入タブ→テキストのあいさつ文をクリックした後、起こし言葉もしくは結び言葉を選んでください。
まとめ
白露の候は9月7日頃から9月23日頃まで使える時候の挨拶になります。
白露は二十四節気の一つなので、実際の意味通りに草木に朝露がついていなくても使うことができます。
地域によっては10月や11月に朝露が見えるようになりますが、そのタイミングでは白露の候は使えないので注意しましょう。


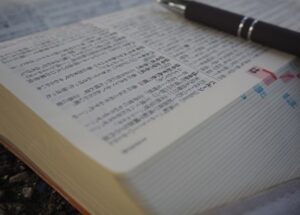













コメント