門松の飾り方!飾ってはいけない日はある?
お正月になったら当たり前のように飾る門松ですが、門松はどうして飾るのでしょうか。
門松を飾る理由や正しい飾り方を知りたいと思っていませんか?
門松は飾ってはいけない日や、飾る期間が決まっています。
そこで今回は、門松の飾り方について調べてみました。
門松の正しい飾り方は?
日本の新年を象徴する門松は、古くから伝わる装飾であり、幸運と繁栄を家庭にもたらすとされています。
この伝統的な飾り方には、自然の要素が巧みに組み合わされ、家の入り口を飾ることで、新年を迎える準備を表します。
しかし、その配置には特定の規則があり、それには深い意味が込められています。
門松の配置
門松は通常、家の玄関や門の前に設置され、来るべき年に対する敬意と期待を示します。
伝統的には、2本の松が一対として配置され、それぞれが雄松と雌松を表します。
これらは、自然界のバランスと調和を象徴しており、家族の健康と幸福を願う意味が込められています。
雄松と雌松の特徴
| 属性 | 雄松(黒松) | 雌松(赤松) |
|---|---|---|
| 樹皮の色 | 黒っぽい | 赤茶っぽい |
| 葉の特徴 | 長くて太く、硬い | 短くて細く、柔らかい |
| 配置 | 玄関に向かって左側 | 玄関に向かって右側 |
| 地域の特色 | 関西では白い葉牡丹を添える | 関西では赤い葉牡丹を添える |
竹の配置と意味
門松には竹も使用され、これには「出飾り」という配置があります。
3本の竹はそれぞれ異なる長さを持ち、外側に中の竹、内側に長い竹、そして短い竹という順番で配置されます。
これは、天・地・人の調和を象徴し、自然界の秩序を表しています。
一本の門松について
かつては一本の門松で飾ることもありましたが、現代では一対での飾り付けが一般的です。
もちろん、スペースの制約などで一本だけを設置することもありますが、その場合でも意味合いを理解し、適切に配置することが大切です。
色彩による識別
門松に添えられる花、特に牡丹には色による意味があります。
白い牡丹は雄を、赤やピンクの牡丹は雌を象徴しており、これによってさらに門松の美しさが引き立てられます。
現代の門松
現代では、この伝統的な装飾に新しい解釈を加えることもあります。
例えば、ミニマリストの家庭では、シンプルなデザインの門松を選ぶことがあります。
また、アパートやマンションなどの限られたスペースに合わせて、小さなサイズの門松が用意されています。
門松はただの飾りではなく、新年を迎えるにあたっての心構えとも言えるでしょう。
この美しい伝統を守りつつ、それぞれの家庭のスタイルに合わせてアレンジすることで、門松は現代の日本の家庭においても変わらぬ価値を持ち続けています。
門松はいつからいつまで飾るの?
新年を迎える準備として、日本の多くの家庭では門松を飾る習慣があります。
この風習は、家々に幸福と繁栄をもたらすとされる神々を迎え入れるためのものです。
しかし、この美しい伝統には、いつからいつまで飾るべきかという具体的な期間があります。
この期間は「松の内」と呼ばれ、地域によって異なることが特徴です。
松の内の期間
| 地域 | 開始日 | 終了日 |
|---|---|---|
| 関東 | 12月13日 | 1月7日 |
| 関西 | 12月13日 | 1月15日 |
開始日の由来
12月13日は、「すす払い」と呼ばれる大掃除の日です。
この日に家の隅々まで清掃し、新年を清潔な状態で迎える準備をします。
清掃が終わると、古来より家々では正月飾りを施し始め、その一環として門松も設置されます。
終了日の背景
関東と関西で松の内の終了日が異なるのは、歴史的な出来事に由来しています。
徳川幕府三代目将軍・家光の月命日が1月20日にあたるため、関西ではそれを避ける形で1月15日までとされています。
一方、関東では鏡開きの日を1月11日に設定し、それに合わせて松の内も1月7日までとなりました。
門松の撤去と安全性
門松は松を主材料としていますが、松は油分を多く含むため、乾燥する冬の時期には火災のリスクを高めます。
江戸時代、町が大火で大きな被害を受けた経験から、火災予防の観点で幕府は門松の早めの撤去を奨励しました。
このような歴史的背景が、現代における門松の飾り付け期間に影響を与えています。
現代における門松
現代では、この伝統は形を変えつつも引き継がれており、多くの家庭や企業、公共の場所で見ることができます。
門松を飾ることは、新年の祝福と共に、歴史と文化を尊重する行為としても重要です。
それぞれの地域の風習を守りつつ、安全に注意を払いながら、新年を迎える準備をすることが大切です。
門松を飾ってはいけない日は?

門松は12月13日の事始め(正月の準備を始める)以降に飾り始めますが、特に近年は12月25日のクリスマスも大きなイベントとなっているので、クリスマスが終わってから正月準備に取り掛かる人が多くなっていますよね。
それ自体は問題はないのですが、年末の忙しくなる時期に門松を飾る上で、注意したいのが「飾ってはいけない日」があることです。
門松を飾るべきではない日
29日と31日は、門松を飾るのに適さないとされています。
29日は数字の「2」と「9」が「重苦しい」という言葉遊びに繋がり、不吉な日とされています。
一方、31日は「一夜飾り」となり、新年を迎える準備としては遅すぎるとされ、神様に対する敬意を欠く行為と見なされています。
門松を飾る推奨日
28日は、その数字が末広がりで繁栄を意味するため、縁起が良いとされています。
この日に門松を飾ることは、新年に向けての幸運を最大限に引き寄せる行為とされています。
現代の風潮と門松
現代では、12月25日のクリスマスが終わると、多くの人々が新年の準備に取り掛かります。
この変化は、国際的な祝日の影響を受け、日本独自の伝統と西洋文化が融合していることを示しています。
30日に関する異なる見解
30日に門松を飾ることについては、意見が分かれます。
一部では、旧暦の大晦日に相当するため、避けるべきとする声もありますが、特に問題がないとする意見も存在します。
門松飾りの最適なタイミング
以下の表は、門松を飾るのに最適な日、避けるべき日、そしてその理由をまとめたものです。
| 日付 | 状況 | 理由 | 推奨行動 |
|---|---|---|---|
| 28日 | 推奨 | 末広がりの数字で縁起が良い | 門松を飾る |
| 29日 | 避ける | 不吉な日とされる数字の組み合わせ | 飾らない |
| 30日 | 不定 | 意見が分かれるが旧暦の大晦日 | 個人の判断に委ねる |
| 31日 | 避ける | 一夜飾りとなり神様に失礼 | 飾らない |
門松を飾る際は、これらの日付とその背景を理解し、尊重することが大切です。
伝統を守りつつ、それを現代の生活に取り入れることで、文化の継承者としての役割を果たすことができます。
なぜ門松を正月に飾るのか?その理由は?
なぜ日本では新年に門松を飾るのでしょうか?
この習慣の背後には、豊かな歴史と文化が息づいています。
正月とは:神々の歓迎
正月、それは単なる年の始まりではありません。
日本では、この時期を「歳神様」を迎える聖なる日として重んじています。歳神様は、五穀豊穣を司る神であり、農業を基盤とする日本の歴史において、非常に重要な存在です。
この神は、年に二度、新年とお盆の時期に山から降りてきて人々の間に滞在するとされています。
新年には、家々が飾り付けられ、歳神様の到来を祝います。
門松の役割:神様への道しるべ
門松は、この神聖な訪問者を迎えるためのシンボルです。
松は古来より神が宿る木とされ、神聖視されてきました。
その常緑の姿は、永遠の生命を象徴し、新年の祝福と繁栄を願う日本人の心を表しています。
また、「待つ」という言葉が「松」と響きが似ていることから、神様を待つ意味も込められていると言われています。
玄関の守り:しめ縄と鏡餅
門松と並んで、しめ縄もまた玄関に飾られます。
これは神域と現世を分ける結界としての役割を持ち、不浄なものの侵入を防ぐとされています。
一方で、鏡餅は家の中に迎え入れた歳神様の依り代となり、神様が再び山に戻るまでの間、家庭に幸福と豊穣をもたらすと考えられています。
門松の構成要素
門松はただの松の枝ではありません。
それぞれの要素には特別な意味があります。
以下の表は、門松を構成する主な要素とその象徴する意味を示しています。
| 要素 | 意味 |
|---|---|
| 松の枝 | 長寿と繁栄 |
| 竹 | 強さと成長 |
| 梅の枝 | 忍耐と純粋 |
| 縄 | 神聖な領域の境界 |
| 飾り | 各地域の風習に基づく祝福 |
このように、門松は単なる装飾ではなく、新年を迎えるにあたっての希望と祈りを形にしたものなのです。
日本の家々が新年に門松を飾る背景には、豊かな自然への敬愛と、神々への畏敬の念があります。
それは、新しい年がもたらす未知の可能性と、家族の絆を祝福するための、美しい伝統と言えるでしょう。
門松を飾る時の注意点
門松は日本の新年を象徴する伝統的な飾り物であり、家の繁栄と幸福を願う意味を込めて、門前や玄関前に設置されます。
しかし、現代の住宅環境は多様化し、特に都市部では門松を飾るためのスペースが限られているのが現実です。
ここでは、限られたスペースや規則に挑戦されている方々のための、門松を飾る際の現代的なアプローチをご紹介します。
閉鎖空間の工夫
多くのマンションやアパートでは、玄関前が共有スペースとなっており、個人の装飾品を置くことが制限されています。
また、一軒家であっても、公共の道路にはみ出してしまうような飾り付けは、地域の規則や町内会の合意によって禁止されている場合があります。
これらの状況においては、以下のような代替案を検討することが推奨されます。
代替案の提案
| 代替案 | 説明 |
|---|---|
| 壁掛け型門松 | 切り枝の松を家の壁に飾るスタイル。伝統的な意味合いを保ちつつ、スペースを取らずに実践可能です。 |
| 紙製門松 | 紙に描かれた門松を壁に貼る方法。自治体が提供することもあり、環境に優しく、取り扱いが容易です。 |
| ミニチュア門松 | 小さな門松を室内に飾ることで、スペースの制約を感じることなく、新年を祝うことができます。 |
| デジタル門松 | デジタルフレームに門松の画像を表示するなど、現代技術を利用した飾り方です。 |
伝統の継承と環境への配慮
門松の伝統は、自然から松を取ってきて家の入り口に飾るというシンプルなものから始まりました。
現代においても、この伝統を尊重しつつ、環境保護の観点から、生木を使わずに代替素材を用いることが推奨されています。
自治体によっては、自然保護を目的とした紙製の門松を配布している場合もありますので、地域の情報を調べてみるのも良いでしょう。
新年を迎えるにあたり、門松を飾ることは日本の美しい伝統です。
しかし、住環境や規則によっては、従来の方法で飾ることが難しい場合もあります。
そんな時は、壁掛け型や紙製、ミニチュア、デジタルといった様々な代替案を検討し、新しい形で伝統を継承していくことが大切です。
伝統と現代性を融合させた門松の飾り方を通じて、新年の幸せと家族の繁栄を祈りましょう。
門松の処分はどうしたらいい?
新年の祝いが終わり、松の内(通常は1月7日まで)が明けると、これらの門松は適切に処分されなければなりません。
ここでは、伝統的な処分方法から現代的なアプローチまで、門松の処分に関する詳細なガイドを提供します。
伝統的な処分方法:お焚き上げと地域の火祭り
日本の多くの地域では、小正月に合わせて神社で行われる「お焚き上げ」という儀式が一般的です。
この儀式では、門松を含む正月飾りが神聖な火に投じられ、その煙と共に新年の神様が天に帰るとされています。
この風習は、新しい年の始まりに古い年の残りを清めるという意味合いを持ちます。
地域によるバリエーション
| 地域 | 行事の名称 | 特徴 |
|---|---|---|
| 一般 | どんど焼き | 正月飾りを燃やし、その火で焼いた餅を食べる |
| 関西 | どんどん焼き | 同上 |
| 東北 | どんと焼き | 同上 |
| 九州 | 左義長 | 同上 |
これらの行事では、正月飾りを燃やした火で焼いた餅を食べることで、健康と長寿を願います。
家庭での処分方法
神社への持参が難しい場合や、地域によっては火祭りが行われない場合もあります。
そのような状況では、門松は家庭用ごみとして処分することが可能です。
ごみ処分時の心得
- 清めの儀式: 門松は神様を迎えるための飾りであるため、塩やお酒で清めることで、その神聖さを敬いつつ処分します。
- 包装: 清めた後、半紙や新聞紙で丁寧に包みます。これは、神聖なものを直接ごみとして扱わないための配慮です。
- 自治体のルールに従う: ごみの分別や出し方は、居住する自治体の規則に従ってください。不明な点は、自治体のウェブサイトやお問い合わせ窓口で確認しましょう。
門松の処分は、単なる物の廃棄以上の意味を持ちます。それは新年の祝いを締めくくり、次の年へと向かう準備をする重要なプロセスです。
伝統的なお焚き上げから家庭での処分まで、どの方法を選択するにせよ、門松に対する敬意を表し、新しい年の清々しいスタートを切るための適切な手順を踏むことが大切です。
門松の正しい飾り方のまとめ
門松を飾る場合は、12月13日から1月7日(もしくは15日)の松の内に飾ります。
ただし、12月28日と31日については縁起が悪いとされるため、避けた方がよいでしょう。
12月の下旬に門松を飾るなら、縁起が良い28日がお勧めです。
松の内が明けたら、門松は神社のお焚き上げや自治体のどんど焼き(地域によって呼び方が違います)に持参し、焼いて処分します。
お焚き上げやどんど焼きに持参できない時は、一般の家庭ごみとして処分することもできます。
松は昔から神様の宿る神聖な木とされているため、丁寧に正しく扱うことで歳神様をしっかりとお迎えすることができます。
とは言え、近年の住宅事情により必ずしも門松を飾らなくても、紙の門松で代用することもできます。
あまり難しく考えず、自分のできる範囲で歳神様をお迎えしましょう。










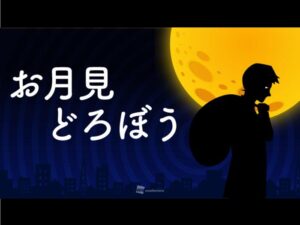


コメント