春が訪れると、私たちは「春日の候」という美しい言葉を手紙や挨拶に使いたくなりますよね。
でも、「春日の候」って一体いつからいつまで使うのが正しいの?意味や読み方は?
そして、この挨拶をどのように手紙に活かせばいいのか、例文や書き方、特に書き出しや結びに悩む方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな疑問や悩みを解決するために、「春日の候」の使い方から、心温まる書き出しや結びの例文まで、わかりやすくご紹介します。
春らしい挨拶を通じて、あなたの想いを素敵に伝える方法を一緒に探っていきましょう。
- 「春日の候」を使う正しい時期がいつからいつまでかがわかります。
- 「春日の候」の読み方やその意味について理解できます。
- さまざまなシチュエーションでの「春日の候」の使い方や例文を知ることができます。
- 手紙や挨拶文での「春日の候」の正しい書き出しと結びの書き方が学べます。
春日の候を使う時期はいつ?読み方や意味は?
春日の候を使う時期はいつからいつまで?
春日の候は4月上旬から下旬まで使える時候の挨拶になります。
つまり、4月中であれば春日の候を使っても問題がないということになりますね。
時候の挨拶の中には使える期間が短いものもありますが、春日の候は1ヶ月間使えるので比較的長く使える時候の挨拶と言えるでしょう。
春日の候の読み方
ですが、春日はかすがと読んでしまう方が多いのではないでしょうか。
そのため、「かすがのこう」や「はるひのこう」「はるびのこう」と読んでも間違いにはなりません。
ただし、候をそうろうと読むのは間違いになりますよ。
春日の候の意味
春日の候は、「春の暖かさが訪れ、心地よい日々が続いていること」という意味です。
「春日」は、春の日を直接的に示していますが、この時期を象徴するのはただの日差しではありません。
暖かく、時には優しく皮膚を撫でるような光が、私たちの周りを満たしてくれるのです。
そして、「候」という言葉には、季節や気候、そして時の流れを感じさせるニュアンスが含まれています。
従って、「春日の候」は、春特有の温もりとそれがもたらす心地よさを伝える言葉として、長い間親しまれてきました。
この表現は、特に日本の伝統的な手紙や挨拶文でよく使われます。
そこでは、季節の変わり目を相手に伝え、その時期が持つ豊かな自然や気候の変化を共有する意味合いがあります。
「春日の候」を用いることで、受け取る人に対して、「現在の心地よい春の暖かさや穏やかな気候を感じ取ってほしい」という願いが込められています。
春日の候の正しい使い方は?

春日の候は4月中ならいつでも使うことができる時候の挨拶です。
しかし、地域によっては3月中旬くらいから春の陽気が訪れるところもありますし、反対に5月上旬にようやく暖かさが続く地域もありますよね。
このような地域なら、3月や5月でも春日の候を使ってもよいのではないか?と思う方もいると思います。
ですが、新暦の3月は旧暦では2月に該当し、春といっても初めの時期(初春)となります。
初春は寒い日と暖かい日を繰り返して少しずつ暖かくなる時期のため、春日の候はふさわしくないと言えるでしょう。
5月に関しては、例年5月5日頃には暦の上で夏となる立夏を迎えます。
夏に入ったのに春日の候を使うのは間違いになってしまうので、春日の候は4月中に使うのが正しい使い方になりますよ。
春日の候を使った例文
特にビジネス関係者や目上の人への手紙やはがきでは、失礼がないように気をつける必要があるため、「何を書いたらよいのかよくわからない」と困ってしまうこともあるでしょう。
そこでここでは、春日の候を使った例文をご紹介します。
ぜひ参考になさってみてください。
ビジネスで使う場合
書き出し文
- 謹啓 春日の候、貴社にはますますご清栄の由大慶に存じます。毎々格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
- 拝啓 春日の候、貴社におかれましてはなお一層のご発展のことと大慶至極に存じます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
- 拝啓 春日の候、貴社におかれましては益々ご盛栄の御事慶賀の至りに存じます。日頃は格別のお引き立てをいただき、ありがたく御礼申し上げます。
結び文
- 新年度が始まり、お忙しい中とは思いますが、これからも変わらぬご支援とお心遣いをお願いいたします。
- 突然の寒さが戻ってきていますので、どうかお身体を大切にされて、風邪をひかれないようご注意ください。
- 新年度の始まりでお忙しいとは思いますが、今後とも引き続きご支援とご厚誼を賜りたく存じます。
目上の人に使う場合
書き出し文
- 謹啓 春日の候、〇〇様にはますますご壮健のことと拝察いたしお慶び申し上げます。
- 拝啓 春日の候、〇〇様にはいっそうご活躍のことと慶賀の至りに存じます。
- 拝啓 春日の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
結び文
- 空気も心地よい季節となりました。ご一同様におかれましてもどうぞお健やかにお過ごしください。
- 春も終わりに近づいています。○○様におかれましては、健康を意識して素晴らしい日々をお過ごしください。
- 春が深まるにつれて、皆様がこれからも活躍されることを心から願っています。
親しい人に使う場合
書き出し文
- 桜の便りが耳に届く時期になりましたね。いかがお過ごしでしょうか。
- 春の訪れを告げる初めての蝶を見かける季節です。〇〇様はお元気でいらっしゃいますか。
- 桜のつぼみがふくらみ始めるこの季節、皆様が健康で過ごされていることを願っております。
結び文
- 開花宣言が囁かれる季節、花が美しく咲くように、どうか健康で充実した日々をお送りください。
- 冬の後に疲れが現れやすいこの時期、どうぞご自愛ください。
- 菜の花が風に揺れるこの春の季節に、〇〇様も変わらずお過ごしください。
春日の候の結び文
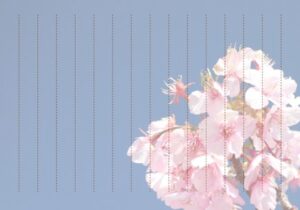
結び文には季節に関係なく使える定型文がありますが、時候の挨拶に合わせた結び文にすることで文章全体に統一感や風情が出ます。
手紙やはがきの端々から季節を感じられると嬉しいものですよね。
そこでここでは、春日の候を時候の挨拶に使った場合の、結び文の例文をご紹介します。
なお、結び文に季節感を盛り込むときは、時候の挨拶と結び文の言葉が重ならないようにしてください。
・新年度を迎えられ、ご多忙のことと存じます。どうぞご自愛専一にてお過ごし下さい。
・春風が心地よい季節となりました。皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。
・急に寒さが戻る日があります。風邪など引かないように気をつけてくださいね。
春日の候を使うときに注意すること

ビジネス関係者や目上の人に送る手紙やはがきに春日の候を使うときは、文章の書き出しに必ず頭語をつけましょう。
頭語とは「拝啓」や「謹啓」などのことで、「つつしんで申し上げます」という意味があります。
親しい友人などへの手紙やはがきでは、時候の挨拶が書き出しでも十分に丁寧なので頭語をつける必要はありません。
しかし、ビジネス関係者や目上の人の場合は、時候の挨拶で始める文章はやや丁寧さに欠けてしまいます。
春日の候を使うなら、「拝啓 春日の候、~~~・・」のように書くのがよいでしょう。
また、頭語をつけたときは文章の最後に結語をつけて締めてください。
「拝啓」の結語は「敬具」または「敬白」、「謹啓」の結語は「謹言」もしくは「謹白」になりますよ。
春日の候以外の4月の時候の挨拶はある?

手紙やはがきを送る相手の地域の状況などに合わせて、臨機応変に時候の挨拶を使いたいですよね。
4月には春日の候以外にも使える時候の挨拶があります。
ここでは、春日の候以外の4月の時候の挨拶をご紹介します。
春暖の候
3月中旬から4月中旬まで使える時候の挨拶になります。
春暖には春の暖かさが続いているという意味があるため、寒さが強い地域や、反対にすでに気温が高く夏のような陽気になっている地域へ送る手紙やはがきには使わない方がよいでしょう。
桜花の候
3月下旬から4月中旬まで使える時候の挨拶になります。
桜が咲いている時期に使える時候の挨拶なので、相手の状況によっては使わない方がよい場合もあります。
陽春の候
4月初めから終わりまで使える時候の挨拶になります。
陽春とは春の麗らかな陽気で満たされている様子を表しています。
春暖と同じように、手紙やはがきを送る地域の状況などに合わせて使うのがよいでしょう。
春爛漫の候
4月中に使える時候の挨拶です。
春爛漫とは春の花が咲き乱れる様子を表す言葉になります。
花の種類は問わないので、春に使いやすい時候の挨拶になりますね。
麗春の候
4月下旬から5月上旬に使える時候の挨拶になります。
麗春とはひなげしのことで、麗春の候はひなげしが咲く時期に使える時候の挨拶です。
ひなげしは6月まで咲きますが、麗春の候が使えるのは遅くても5月上旬までとなりますよ。
晩春の候
二十四節気の清明(例年4月4日頃)から立夏(例年5月4日頃)の前日まで使える時候の挨拶になります。
立夏を過ぎると暦の上では夏となり、晩春の候は使えないので注意しましょう。
Wordであいさつ文や定型文を挿入する方法
仕事上で取引先の相手にあいさつ文を送る、目上の人に手紙やはがきを出す時などに、「書き出しに悩んでしまい、なかなか作業が進まない」なんてことはよくあるのではないでしょうか。
そのような時はWordを利用してみましょう。
Wordにはあいさつ文のテンプレートがあるので、参考にすると作業が捗りやすくなりますよ。
ここではwordを使ったあいさつ文や定型文の挿入方法をご紹介します。
手順
①Wordを開きます
②挿入タブをクリックします
③テキストのところにある「あいさつ文」をクリックします
④あいさつ文の挿入を選びます
⑤何月のあいさつ文を作成するのか、最初に月を選びましょう
⑥月のあいさつ、安否のあいさつ、感謝のあいさつをそれぞれ選びます
⑦選んだら「OK」をクリックしてください
⑧Wordに選んだ文章が表示されます
ポイント
Wordではあいさつ文だけではなく、あいさつ文の後に続ける「起こし言葉」や「結び言葉」も選ぶことができますよ。
挿入タブ→テキストのあいさつ文をクリックした後、起こし言葉もしくは結び言葉を選んでください。
春日の候のまとめ
春日の候は、「しゅんじつのこう」と読みますよ。
この挨拶は、4月中の暖かな日々を指し、心地よさを感じさせますね。
意味は春の温もり溢れる気候を楽しむ様子。ビジネスや目上の方への手紙では、「謹啓」や「拝啓」から始め、季節感あふれる結び文で心を込めて。
春らしい暖かさを感じる4月にぴったりの挨拶、春日の候を使って、相手に心地よい春の訪れを伝えてみませんか。
この記事のポイントをまとめますと
- 春日の候は4月上旬から下旬まで使用可能
- 読み方は「しゅんじつのこう」
- 「かすがのこう」「はるひのこう」も正しい読み方として受け入れられる
- 意味は春の温もりと心地よさを指す
- 3月は新暦であっても初春にあたり、春日の候には不適切
- 5月5日以降は夏とみなされ、使用不適切
- 親しい人へは季節の変わり目を感じさせる文を
- 結びには季節感を反映した言葉を選ぶ
- 文書の書き出しと結びに頭語と結語を用いる
- 春日の候は地域の気候や文脈に合わせて柔軟に使用する




コメント