皆さんは「陽春の候」という言葉を耳にしたことはありますか?
「いつからいつまで使えるの?」「正しい読み方は?」「具体的な意味は何?」など、この美しい季節の挨拶について、気になる点がたくさんあるかもしれませんね。
また、手紙やメールでの使い方、特に書き出しや結びの書き方に頭を悩ませている方も少なくないでしょう。
そこで、この記事では「陽春の候」の適切な使用期間、意味、読み方から、実際の例文を用いた使い方まで、わかりやすく解説します。
文章をもっと心温まるものにするためのポイントもご紹介するので、どうぞお楽しみに!
- 「陽春の候」を使う適切な時期が4月初めから終わりまでであることがわかります。
- 「陽春の候」の読み方が「ようしゅんのこう」であることを理解できます。
- 「陽春の候」の意味や、春を感じさせる表現の豊かさを学べます。
- 手紙やメールでの「陽春の候」の使い方、特に書き出しや結びの具体的な書き方がわかります。
陽春の候を使う時期はいつ?読み方や意味は?
陽春の候を使う時期はいつからいつまで?
陽春の候は4月初めから終わりまで使える時候の挨拶になります。
時候の挨拶の中では、月の途中で使えなくなるものもありますが、陽春の候の場合は4月中であればいつでも使えるので覚えやすいですよね。
陽春の候の読み方
「ようはるのこう」、「ようしゅんのそうろう」ではないのでご注意ください。
陽春の候の意味
「陽春の候」は「春の日差しが降り注ぎ、暖かな春の日ですね」という意味があります。
「陽春」という部分は、春特有の暖かく柔らかな陽気を指し、心地よい温もりが感じられることを伝えます。
一方、「候」は季節や天候を意味し、特定の時期や気候の状態を示しています。
この組み合わせから、「陽春の候」は春の暖かな気候、すなわち冬の寒さから解放され、生命が再び活動を始める時期を美しく象徴する言葉となっています。
「陽春の候」は単なる季節の変わり目を指す言葉ではなく、新たな始まりの象徴とも言えるでしょう。
冬の静けさから春の動きへと自然が移り変わるこの時期は、私たちにとっても何か新しいことを始める絶好の機会を提供してくれます。
この美しい日本の言葉は、春の暖かさや生命の息吹を感じさせるだけでなく、人々の心にも温かい春の光を届けてくれることでしょう。
それはまるで、自然の中で繰り広げられる一つ一つの小さな奇跡を、優しい言葉で伝える詩のようなものです。
陽春の候の正しい使い方は?

時候の挨拶は二十四節気に基づいて使うものが多いのですが、陽春の候は二十四節気に基づいた時候の挨拶ではありません。
二十四節気に基づいた時候の挨拶では、実際の気候や状況と時候の挨拶が合わなくても、決められた期間に使うことができるのですが、陽春の候は「春の陽気に満ち溢れる時期」を実感できるタイミングで使うのがよいでしょう。
つまり、新暦では4月に使うのがよいとされています。
このように、時候の挨拶には二十四節気(旧暦)と新暦が混在しているため、使うときにはタイミングに注意が必要な場合があります。
陽春の候を使った例文

手紙やはがきを書くときは、送る相手に失礼のないようにしたいもの。
ですが、ビジネス関係者や目上の人に書く手紙やはがきの書き出しに悩んでいる人は多いでしょう。
そこでここでは、陽春の候を使った例文をご紹介します。
手紙やはがきを書くときに参考になさってみてください。
ビジネスで使う場合
書き出し文
- 謹啓 陽春の候、貴社におかれましては益々ご盛栄の御事慶賀の至りに存じます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
- 拝啓 陽春の候、貴社にはますますご清栄の由大慶に存じます。日頃は格別のお引き立てをいただき、ありがたく御礼申し上げます。
- 拝啓 陽春の候、貴社におかれましてはなお一層のご発展のことと大慶至極に存じます。毎々格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
結び文
- 春が近づいてきた感じがします。貴社のますますのご発展をお祈り申し上げます。
- 新しい年度が始まり、貴社一層ご多忙の事と存じますがどうぞご自愛ください。
- 今年も飛躍の季節を迎えました。貴社のさらなる進歩を心からお祈りしています。
目上の人に使う場合
書き出し文
- 謹啓 陽春の候、〇〇様にはますますご壮健のことと拝察いたしお慶び申し上げます。
- 拝啓 陽春の候、〇〇様にはいっそうご活躍のことと慶賀の至りに存じます。
- 拝啓 陽春の候、ご一同様のますますのご清祥お慶び申し上げます。
結び文
- 春爛漫の美しい季節です。伸びゆく花に負けないご活躍を心よりお祈り申し上げます。
- 温かい日々が続いておりますが、まだ寒さが戻ることもありますので、くれぐれもお体にはお気を付けください。
- 新天地での〇〇様のご活躍、心より願っております。
親しい人に使う場合
書き出し文
- つくしが顔を出し始め、春の訪れが感じられます。
- 暖かい春の日差しを感じると、気持ちも明るくなりますね。〇〇様はいかがお過ごしでしょうか?
- 穏やかな日々が続いており、もうすぐ初夏が訪れます。皆様はお健やかにお過ごしでしょうか?
結び文
- 新年度の始まりは多忙を極めることと存じますが、どうぞご自愛ください。
- 心地よい春の到来を迎え、皆様の健康と幸せを心より願っております。
- 気候が温かくなり、外に出やすい時期ですが、体調にはくれぐれもお気を付けください。
結び文とは?

結び文とは文章の締めくくりに書く文のことで、ビジネス文章では季節に関係なく使える定型文があります。
ですが、時候の挨拶と結び文の季節感を合わせることで、文章全体に統一感や風情が出ますよ。
ここでは、陽春の候を時候の挨拶に使った場合の、結び文の例文をご紹介します。
- 時期柄、健康には十分にご留意なされ、さらにご活躍されますことを祈念申し上げます。
- 春光うららかな好季節、皆様のご多幸をお祈りいたします。
- 新年度でお忙しいことと存じますが、体調など崩されませんようご自愛ください。
陽春の候を使うときに注意すること

陽春の候などの〇〇の候は漢語調といって、時候の挨拶の中でも丁寧な表現となりますが、主にビジネス関係者や目上の人に送る手紙やはがきの場合、これだけではマナーとしてOKとは言えません。
ビジネス関係者や目上の人に手紙やはがきを書くときは、陽春の候の前に頭語をつけましょう。
頭語とは「拝啓」や「謹啓」などのことで、これらには「つつしんで申し上げます」という意味があります。
また、頭語をつけたら文章の終わりは結語で締めてください。
「拝啓」の結語は「敬具」または「敬白」、「謹啓」の結語は「謹言」もしくは「謹白」になりますよ。
なお、同じ頭語でも「前略」は丁寧な表現ではないので使わないようにしましょう。
親しい人への手紙やはがきでは、「拝啓」などの頭語をつける必要はありません。
陽春の候以外の4月の時候の挨拶はある?

麗らかな春の陽気を感じさせる時候の挨拶は、陽春の候以外にもあります。
ここでは、4月に使える陽春の候以外の時候の挨拶をご紹介します。
春暖の候
3月中旬から4月中旬まで使える時候の挨拶になります。
ただし、春暖の候については明確に使える時期が決まっているわけではなく、4月いっぱいまで使っても問題がない場合もあります。
春暖とは春の暖かさが続いているという意味なので、すでに初夏のような暑さになっている場合は使わない方がよいでしょう。
桜花の候
一般的には3月下旬から4月中旬まで使える時候の挨拶になります。
桜の咲く時期という意味ですが、地域によっては桜がすでに散っていたり、まだ咲いていない場合もありますよね。
そのため、桜花の候を使うときは手紙やはがきを送る地域によっては使えない場合もあります。
春爛漫の候
4月中に使える時候の挨拶です。
春爛漫とは春の花が咲き乱れる様子を表す言葉のため、本格的な春が到来してさまざまな花が咲く時期に使える時候の挨拶になりますよ。
麗春の候
4月下旬から5月上旬に使える時候の挨拶になります。
麗春とはひなげしのことで、ひなげしが咲く時期に使える時候の挨拶になりますよ。
ひなげしは4~6月に咲くので、4月上旬や中旬でも使ってよいとされています。
晩春の候
二十四節気の清明(例年4月4日頃)から立夏(例年5月4日頃)の前日まで使える時候の挨拶になります。
晩春とは春を3つに分けた(初春・仲春・晩春)の最後になり、夏に近づいている時期になりますよ。
Wordであいさつ文や定型文を挿入する方法
仕事上で取引先の相手にあいさつ文を送る、目上の人に手紙やはがきを出す時などに、「書き出しに悩んでしまい、なかなか作業が進まない」なんてことはよくあるのではないでしょうか。
そのような時はWordを利用してみましょう。
Wordにはあいさつ文のテンプレートがあるので、参考にすると作業が捗りやすくなりますよ。
ここではwordを使ったあいさつ文や定型文の挿入方法をご紹介します。
手順
①Wordを開きます
②挿入タブをクリックします
③テキストのところにある「あいさつ文」をクリックします
④あいさつ文の挿入を選びます
⑤何月のあいさつ文を作成するのか、最初に月を選びましょう
⑥月のあいさつ、安否のあいさつ、感謝のあいさつをそれぞれ選びます
⑦選んだら「OK」をクリックしてください
⑧Wordに選んだ文章が表示されます
ポイント
Wordではあいさつ文だけではなく、あいさつ文の後に続ける「起こし言葉」や「結び言葉」も選ぶことができますよ。
挿入タブ→テキストのあいさつ文をクリックした後、起こし言葉もしくは結び言葉を選んでください。
陽春の候のまとめ
陽春の候は、春らしい暖かな日差しを感じる4月にぴったりの時候の挨拶です。
「ようしゅんのこう」と読み、春の訪れと新たな始まりの象徴を美しく表現します。
この挨拶は、ビジネスの書き出しから親しい人への手紙まで、さまざまな場面で活用でき、文章に季節感と心温まる雰囲気を添えることができます。
結び文と合わせて、春の訪れを感じさせる優雅な言葉選びで、相手に温かい思いを伝えましょう。
この記事のポイントをまとめますと
- 陽春の候は4月初めから終わりまでの時候の挨拶
- 読み方は「ようしゅんのこう」
- 意味は春の日差しが暖かなことを指す
- 春特有の柔らかな陽気を表現
- 季節や天候を意味する「候」を含む
- 新たな始まりの象徴としても解釈される
- ビジネス文書や私信で広く使われる
- 結び文で季節感を表現することが推奨される
- 頭語には「拝啓」や「謹啓」を使い、文末には適切な結語を
- 他に4月に使える時候の挨拶として春暖の候、桜花の候などがある


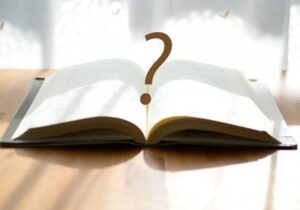








コメント