お盆飾りの時期と飾り方!
お盆の時期になると、仏壇の前にお盆飾りを行いますが、お盆飾りとは一体どのようなものを指すのでしょうか。
また、お盆の時期は夜になると提灯に灯かりが灯されますが、どうして提灯を飾るのかその意味を知っていますか?
何となく習慣として行っていることですが、お盆にはそもそも先祖を供養し、祀るといった重要な意味があります。
お盆飾りもやはり先祖にちなんだ意味があるのかも知れませんね。
毎年、当たり前のように飾っているお盆飾りも、その意味をしっかりと知ることで心構えや準備の仕方も大きく変わりそうです。
そこで今回は、お盆飾りの意味や時期、飾り方などについて調べてみることにしました。
お盆飾りの意味や由来は?

お盆になると、先祖や故人の霊をお迎えするために盆棚を作って、お盆飾りをしますよね。
子どもの時、果物や野菜、花などが並んでいる光景を見て不思議だなと思った方も多いと思いますが、お盆飾りにはそれぞれに意味があります。
そこでここでは、お盆飾りの意味や由来についてご紹介したいと思います。
(ただし、宗教によってお盆飾りの飾り方や飾る物が違うため、ここでは一例を挙げてご紹介したいと思います)
盆提灯
先祖や故人があの世からこの世に帰ってくる時に、盆提灯の灯りを目印にしていると言われています。
盆花
ミソハギ(禊萩)、ミソハギ科。日本、朝鮮半島。
お盆の仏前に供える盆花、精霊花として昔から使われて来ました。
供物に水を注いで清める禊の花という意味です。
水辺を好み田圃の畔や川辺で見かける事から溝萩とも呼ばれます。
全草を乾燥させ民間薬として下痢や喉の渇きに使われたそうです。 pic.twitter.com/a6Rg90thiX— もっぷん (@RoFpVqO0WMVDweY) August 9, 2020
女郎花(おみなえし)、桔梗、なでしこ、みそはぎ、百合などを飾りますが、先祖や故人が好きだった花を飾っても構いません。
みそはぎの花には悪霊を払うという意味があります。
そうめん
3日目昼の霊具膳
お盆といえば、そうめん。
細く長くと長寿を願う意味もあったり、
精霊様の牛馬が戻られる時お土産を括るための紐。
という謂れもあったり。
我が家では三日目の昼のお膳はそうめんと決まっています。
薬味を平椀に。生姜はNGなので胡麻たっぷり
壺椀は紅ズイキの酢の物枝豆のせ pic.twitter.com/VUfxlvCOCr— 和 (@o96rara) August 15, 2021
先祖や故人があの世に帰る際、荷物を背負う時の紐に見立てていると言われています。
また、細く長い形状から喜びがそのように続くように、という意味があるそうです。
ほおずき
お盆に飾る鬼灯(ほおずき)は、ご先祖さまが帰ってくるときの灯りに、という提灯みたいな意味があるそうです。
昨日マダムの両親から野菜といっしょにもらったものです。
ちなみにお義父さん作の木彫りのアクセサリーとお義母さん作の、ほおずきの繊維を使ったお飾り。#器用すぎです pic.twitter.com/PaTna2MjyX— 長尾徹 東大阪のモンガトウのシェフです (@mgateau1) August 13, 2019
先祖や故人が帰ってくる際に足元を照らす光、ともし火という意味があると言われています。
茄子の牛、きゅうりの馬
今日は鶴岡のお盆です
お盆に
ご先祖様が
行き来する乗り物として
精霊馬と精霊牛を飾ります足の速い馬に乗って
ご先祖様が早く戻ってこれるように
(きゅうり)足の遅い牛に乗って
ゆっくり帰れるように(なす)という意味があるそうです
『伊藤喜久井と門下生たち』開催中 pic.twitter.com/rhGwEUNfhL
— 致道博物館 (@chido1950) July 13, 2017
先祖や故人があの世からこの世に帰ってくる時に、乗ってくる乗り物という意味があります。
水の子
本日はお盆の入り。
こちらは水の子といいお水に茄子や胡瓜を賽の目に切り水に浮かべ、本来はミソハギの枝を添えるもの。(こちら妙香寺バージョン)お盆は先祖供養の他、施餓鬼会という餓鬼道にいる苦しんでる方々に施しをし、ひいてはあまねく人々を救う意味もあるそうです。#お盆 pic.twitter.com/YtxMEMXQ3g— 妙香寺香宮堂 香宮 かん (@kounomiyakan) August 12, 2021
蓮の葉を皿に敷き、その上に賽の目に切ったきゅうりや茄子、洗ったお米などを盛りつけます。
水の子には、お盆の時期に帰る場所のない霊を供養するという意味があるそうです。
笹竹
笹竹を飾るのは、結界を張るという意味があります。
笹竹に縄をくくり、結界を作ります。
お盆飾りとは?飾る時期はいつからいつまで?

お盆飾りとは、お盆の際に作られる盆棚(精霊棚)の飾りのことを言います。
お盆飾りの中に盆提灯がありますが、これは先祖が浄土(あの世)から私達の住む世界(この世)に戻ってくる時に、家を間違わないように目印として行っていた迎え火に由来しています。
迎え火とは本来、外で焚く野火のことを言っていましたが、近年の住宅事情では難しい側面もあり、盆提灯を灯すことが多くなっています。
また、お盆飾りはお盆の期間である8月13日~16日に飾ります。
しかしこの期間は新暦によるもので、一部の地域では現在も旧暦によるお盆を行っている場合もあり、その時は7月13日~16日がお盆となります。
お盆飾りに必要なものは?
お盆の時期にナスやきゅうりを使って人形のような物を作ったことはないでしょうか。
これは精霊馬と呼ばれるもので、先祖が移動の際に使う乗り物と言われています。
キュウリの馬には、足の速い馬に乗ることで、先祖があの世からこの世に少しでも早く戻って来るようにという願いが込められ、ナスの牛には、歩みののろい牛に乗ることで先祖があの世にゆっくりと戻って行くようにという願いが込められています。
お盆飾りの飾り方
お盆飾りは地域や宗派によって様々あり、一概に「こちらが正しい」とは言えないのですが、ここでは一般的なお盆飾りについてご紹介したいと思います。
お盆飾りではまず、盆棚と呼ばれるひな壇状の棚を仏壇の前に設置します。
しかしこれも必ずひな壇でなければならないと言った決まりはなく、座卓などで代用されても構いません。
その棚の四隅に笹竹を立てたら、その笹竹に縄を張ります。
これには結界を張る意味があるそうですが、こちらも必ずそうしなければならないという決まりはありません。
ちなみに縄にはほおづきやそうめんなどを吊るします。
ほおづきは迎え火と同じ意味を持つ盆提灯と似た形であることから、目印になるとして飾られ、そうめんは先祖が浄土に帰る際に荷物を背負う紐の代わりになるという考えや、喜びが長く細く続くようにと縁起を担いでいるからと言われています。
お盆飾りの処分はどうしたらいいの?

お盆飾りは、昔は自宅で焚き上げたり(燃やす)、川に流したりしていましたが、現在はそのような処分の仕方は環境保全上できません。
では、お盆飾りの処分はどうしたらいいのでしょうか。
お供えしたお菓子や果物などは消費期限が問題なければ、下げた後に食べることもできますが、傷んでしまったり生花などは枯れてしまうこともありますよね。
これらは普通に生ごみ(可燃ごみ)として出すことができますが、お供えしたものをそのように扱うのに戸惑う方も多いのではないでしょうか。
そのような場合は、白い紙を用意しそれに包んで捨てるのがよいでしょう。
他のごみと一緒にするのがちょっと・・という場合は、ごみ袋を別にします。
その際、塩でお清めしてから白い紙で包み、ごみ袋に入れるようにすると、抵抗なくできるのではないでしょうか。
なお、絵柄のついた提灯は来年以降も使用することができるので、捨てずにとっておきましょう。
片付ける時には埃を丁寧に払ってから保管するようにして下さい。
まとめ
お盆飾りの提灯やナス、キュウリなどの飾り物には、先祖に対する深い思いやりが込められていたのですね。
今年のお盆はこのことを思い出しながら、先祖を敬い、感謝する気持ちを持ってお迎えしたいと思います。
お盆の関連記事
初盆(新盆)とは?初盆の仕方や準備に必要なものと作法や迎える時期は?

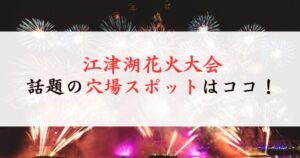
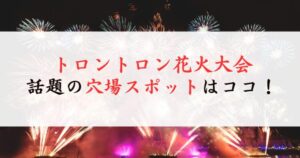
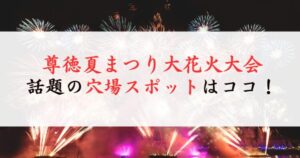
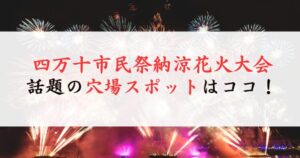
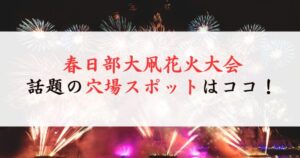
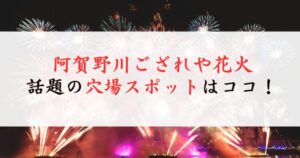
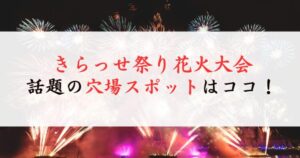
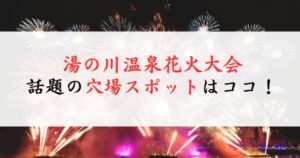
コメント