国民の祝日が増えても休日が増えないって本当?
ゴールデンウィークが、その年によって5連休だったり6連休だったり、3連休と3連休の飛び石だったりと、連休の日数が変わるのはどうしてなのでしょうか。
それには、国民の祝日と国民の休日が関係しているのですが、国民の祝日はよく見聞きするものの、国民の休日はあまり知られていなく、初めて聞いたという方も多いのでないかと思います。
そこで今回は、国民の祝日と国民の休日の違いや意味を調べてみました。
また、国民の祝日が増えても休日が増えない可能性についても詳しくご紹介したいと思います。
国民の祝日と国民の休日の違いは?
祝と休の一字が違うだけで、両方とも休日であることは間違いありません。
と言うことは漢字以外は違いがないのでは?と思うかも知れませんが、実はこの2つには明確な違いがあります。
国民の祝日は、祝日法という法律に基づいて決められている休日になります。
1月1日が休みなのは、元日を祝日とすることが法律で定められているからです。
一方の国民の休日は、祝日と祝日の間の平日を休みにすることで連休を作る場合に用いられます。
国民の祝日とは?

国民の祝日は、昭和23年に施行された「国民の祝日に関する法律(祝日法)」によって決められている休日です。
現在は「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを国民の祝日と名づける」を趣旨としていますが、元は皇室行事に関わる神事だったものが多く、敗戦後にGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)によって禁止されたものを名称を改称して復活させたものが多くなっています。
また、祝日法の改正によって祝日の数が増え現在は16となっていますが、これに皇室の慶弔などその年限りの祝日が加わることもあります。
国民の休日とは?

国民の休日は、祝日と祝日に挟まれた平日を休日とすることで、連休とするためのものです。
現行法では9月の「敬老の日」と「秋分の日」に挟まれる平日のみ
振替休日は正式な名称ではないものの、祝日法に定められている国民の祝日並びに国民の休日と同様に、休日として制定されています。
祝日が増えても土日祝が勤務なら休日は増えない?

労働規定により、土日祝を休日としている会社は、祝日が増えるとその分休日も増えることになります。
しかし、土日祝を休日と定めていない企業や、変形労働時間制を採用している場合には、祝日が増えても休日が増えない可能性があります。
変形労働時間制とは、労働基準法で定められている一週間に40時間未満の労働を超える労働を許可するもので、繁忙期など特別な時期のみ採用する(一週間や一ヵ月単位)場合やフレックスタイム制度を導入している企業が、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があるものです。
このようなことから、働いている会社が上記のどちらかに当てはまる場合は、祝日が増える=休日が増えるということにならないケースもあります。
国民の休日の日って祝日なの?

国民の休日は祝日ではありませんが、祝日と同じ祝日法によって定められています。
祝日に挟まれた平日を休日としているもので、ゴールデンウィークの他、敬老の日(祝日)と秋分の日(祝日)に挟まれた平日が休日となるケースもあります。
現行法では9月の「敬老の日」と「秋分の日」に挟まれる平日のみ
2025年の国民の祝日はいつあるの?
【2025年の祝日一覧】
| 月 | 日 | 曜日 | 祝日の名称 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1 | 月 | 元日 |
| 8 | 月 | 成人の日 | |
| 2月 | 11 | 日 | 建国記念の日 |
| 12 | 月 | 振替休日 | |
| 23 | 金 | 天皇誕生日 | |
| 3月 | 20 | 水 | 春分の日 |
| 4月 | 29 | 月 | 昭和の日 |
| 5月 | 3 | 金 | 憲法記念日 |
| 4 | 土 | みどりの日 | |
| 5 | 日 | こどもの日 | |
| 6 | 月 | 振替休日 | |
| 7月 | 15 | 月 | 海の日 |
| 8月 | 11 | 日 | 山の日 |
| 12 | 月 | 振替休日 | |
| 9月 | 16 | 月 | 敬老の日 |
| 22 | 日 | 秋分の日 | |
| 23 | 月 | 振替休日 | |
| 10月 | 14 | 月 | スポーツの日 |
| 11月 | 3 | 日 | 文化の日 |
| 4 | 月 | 振替休日 | |
| 23 | 土 | 勤労感謝の日 |
1月の国民の祝日
●1月1日(元日)
1年の始まりである1月1日は、国民の祝日によって休日となっています。
元日は休みというのは日本においてとても一般的となっていますが、実は法律が施行されたのは昭和23年の新しい祝日法からとなっています。
それ以前も元日は休日となっていましたが、法が定める休日となったのはこの時からです。
●1月8日(成人の日)
「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」を趣旨として制定された祝日です。
1999年までは1月15日に固定されていましたが、2000年以降はハッピーマンデー制度(祝日を特定の日から土日明けの月曜日に移動させることで、連休にするもの)によって、1月8日~14日のどれかになるため、1月15日に成人の日がくることはありません。
また、成人の日は、元は小正月に元服の儀が行われていたことが由来とされています。
2月の国民の祝日
●2月11日(建国記念の日)
「建国をしのび、国を愛する心を養う」という趣旨により、昭和41年に制定されました。
元々は明治6年に「紀元節」(日本の初代天皇の神武天皇の即位日)として祭日となっていたものの、戦後にGHQの指示によって廃止されたものの、昭和41年に復活して祝日となった経緯があります。
●2月23日(天皇誕生日)
天皇の誕生日をお祝いする日ですが、2019年に年号が平成から令和に変わり、今上天皇への譲位によって2020年から変更となります。
3月の国民の祝日
●3月21日(春分の日)
「自然をたたえ、生物をいつくしむ」ことを趣旨としていますが、昼と夜の長さが(ほぼ)同一となる日を春分日としています。
春分日は毎年異なりますが、通例では3月20日もしくは3月21日のいずれかになっています。
4月の国民の祝日
●4月29日(昭和の日)
「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」ことを趣旨としていますが、元は昭和天皇の誕生日→みどりの日と2度の変更経て、2007年に制定された祝日となっています。
5月の国民の祝日
●5月3日(憲法記念日)
昭和22年に日本国憲法が施行されたことを記念し、翌年の昭和23年に制定された祝日です。
「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」を趣旨としています。
●5月4日(みどりの日)
元は昭和天皇の誕生日が4月29日であったことから、ゴールデンウィークを形成する休日の一つとされていたのですが、昭和64年に年号が昭和から平成に変わり天皇がお御代替えしたことで、天皇誕生日が12月23日へと改められたことを機に、当初は4月29日をみどりの日として祝日に制定していました。
さらに平成17年の法改正により、みどりの日は5月4日に移動され、4月29日は昭和の日と変更されています。
なお、みどりの日は「自然にしたしむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ」ことを趣旨としています。
●5月5日(こどもの日)
端午の節句である5月5日に、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」ことを趣旨として昭和23年より制定されています。
6月の国民の祝日
6月は国民の祝日はありません。
7月の国民の祝日
●7月15日第3月曜日(海の日)
平成8年に施行された当初は7月20日と固定でしたが、現在は7月の第3月曜日となっています。
「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」と趣旨としています。
8月の国民の祝日
●8月11日(山の日)
平成26年に制定され、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ことを趣旨としています。
9月の国民の祝日
●9月16日第3月曜日(敬老の日)
平成14年までは9月15日の固定となっていましたが、平成15年より9月の第3月曜に変わっています。
「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」ことを趣旨としています。
●9月22日(秋分の日)
春分の日と同様に、昼と夜の長さがほぼ同じ秋分日を祝日としています。
例年9月22日か9月23日のいずれが1日となります。
「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」ことを趣旨としています。
10月の国民の祝日
●10月14日(スポーツの日)
昭和39年に行われた東京オリンピックの開会式が10月10日だったことから、この日とスポーツの日(体育の日)として、「スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう」ことを趣旨として祝日にしています。
現在はハッピーマンデー制度により10月の第2月曜日となっています。
なお、2020年1月1日より、名称もスポーツの日(体育の日)からスポーツの日へと変更になりました。
11月の国民の祝日
●11月3日(文化の日)
明治天皇の誕生日であり、日本国憲法が公布された日です。
「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨としています。
なお、文化の日から半年後の5月3日に日本国憲法は施行され、その日を憲法記念日としています。
●11月23日(勤労感謝の日)
元は新嘗祭という天皇行事による休日だったのですが、GHQによって禁止された後、勤労感謝の日として復活して祝日制定となりました。
「勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」ことを趣旨としています。
12月の国民の祝日
12月は国民の祝日はありません。
国民の祝日と国民の休日の違いのまとめ
国民の祝日と国民の休日は、同じ祝日法によって決められる休日ですが、その意味合いは大きく異なります。
また、祝日法によって定められる休日には振替休日もありますが、振替休日は国民の休日ではなく、祝日が日曜となる場合に適用される休日です。



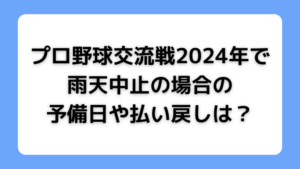






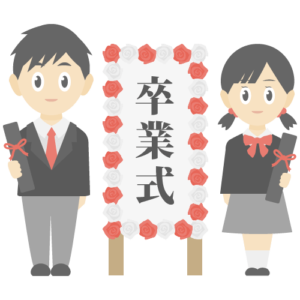
コメント