2025年の十日戎はいつ?福笹や熊手などの縁起物の飾り方や飾る方角は?
十日戎とは何?と思われる方も多いかもしれませんね。
特に関西地方以外の方には、なじみの薄いこのお祭りは、実は商売繁盛を願う大切な行事なのです。
十日戎では、福笹や熊手などの縁起物が重要な役割を果たしますが、これらをどのように選び、どのように飾るのか、意外と知らない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、十日戎の魅力と、縁起物の選び方や飾り方について、わかりやすくご紹介します。
新年の幸運を家族で分かち合うための、素敵な文化を一緒に学びましょう。
- 十日戎が毎年1月9日から11日に行われる関西の伝統的なお祭りであること
- 福笹や熊手などの縁起物の意味とその飾り方
- 今宮戎神社をはじめとする十日戎の主な神社について
- 縁起物を飾る際の方角の重要性
- 翌年の十日戎での縁起物の返納方法とその意味
十日戎とは

十日戎とは、「とおかえびす」と読み、その名にもある通り七福神の一人であるえびす様に、商売繁盛や大漁を祈願するお祭りです。
関西地方では、「えべっさん」という愛称で親しまれており、お正月の祝い事と並ぶほどの盛り上がりを見せます。
特に大阪の今宮戎神社では、数十万人の参拝者で賑わい、神社周辺は祭りの雰囲気に包まれます。
屋台が立ち並び、福笹を手にした人々の笑顔が印象的です。
また、十日戎には、えびす様への感謝の気持ちを表すために、特別な儀式や舞が奉納されることもあります。
これらの伝統的なパフォーマンスは、見る者を魅了し、お祭りの歴史と文化を感じさせてくれます。
2025年の十日戎はいつ
2025年の十日戎の期間は、毎年と同じように1月9日から11日までの3日間行われ、10日に行うのが本戎、その前日の9日に行うのが宵戎、10日の翌日の11日に行うのを残り福(戎)と呼びます。
この期間には、それぞれ特別な意味を持つ日があります。
- 宵戎(よいえびす):1月9日 宵戎は、十日戎の初日にあたります。この日は、お祭りの前夜祭のような位置づけで、多くの人々がえびす様に初めてのお参りをします。夜には、提灯や飾り付けが美しく、神社周辺は祭りの雰囲気に包まれます。
- 本戎(ほんえびす):1月10日 本戎は、十日戎のメインイベントとされる日です。この日は、最も多くの参拝者で賑わいます。商売繁盛や幸運を願う人々が、えびす様に祈りを捧げます。
- 残り福(のこりふく):1月11日 残り福は、十日戎の最終日です。この日は、祭りの終わりを惜しむような雰囲気があり、最後のチャンスとしてえびす様にお参りする人々でにぎわいます。
十日戎は、ただのお祭りではなく、地域の絆や商売人の心意気を感じることができる特別な時間です。
2025年も、多くの人々がこの伝統を守り、新たな年の幸運を願いに集まることでしょう。
十日戎「とおかえびす」七福神の一柱である戎神(えびす様)を祀る神社の祭礼。主に西日本が盛んで商売繁盛を願って多くの人々が参拝し、縁起物を飾った笹や熊手を授かるなど祭り行事は各神社で1月10日から数日間行われております。特に大阪に有る今宮神社は、全国の十日戎の中でも最も賑わいます。 pic.twitter.com/cOAEWGiTSU
— とっこさん (@98t_nt) January 10, 2022
十日戎の由来

戎とは、上記でも触れた通り七福神(恵比寿、大黒天、福禄寿、毘沙門天、布袋、寿老人、弁財天)の一人である恵比寿様のことを指しています。
恵比寿様と言えば、ふくよかでほがらかな表情が有名ですよね。
一般的に商売繁盛の神とされていますが、その姿をよく見ると右手に釣り竿、左手に鯛を持っていることから漁業の神ということがわかります。
十日戎の由来については、恵比寿様が生まれたのが1月10日だったため、そのお祝いをして始まったという話や、徳川家康によって滅ぼされた豊臣秀吉を信仰していた人々が、秀吉の御神像の代わりに恵比寿様をお祀りするようになったのが十日戎の始まりという話など諸説あります。
日本三大えびす神社

・西宮神社
この3つは、日本三大えびす神社と言われています。(京都ゑびす神社ではなく、堀川戎神社が入るという説もあります)
西宮神社は、全国に3500社あるえびす神社の総本社であり、毎年、1月10日に行われる「福男」が有名ですよね。
福男は正式名称を「開門神事福男選び」と言い、朝6時の開門と同時に本殿に向かって走り、1位になった人が福男としてその年一年、福を運ぶと言われています。
十日戎を知らないという人でも、福男は知名度が高く、テレビのニュースなどで見たことがあるという場合が多いのではないでしょうか。
今宮戎神社は、商売繁盛の神社として関西では大変人気のある神社で、1月10日の十日戎には毎年100万人もの参拝客が訪れることでも知られています。
十日戎がよく知られている西日本の中でも、最も賑わいを見せるのが今宮戎神社となっています。
京都ゑびす神社は「京のえべっさん」として有名で、主に交通安全祈願にご利益があると言われています。
十日戎の縁起物の飾りの種類

十日戎に行くと、福笹や熊手を手にしている人をよく見かけますが、これらには一体どのような意味があるのでしょうか。
福笹
福笹は商売繁盛の縁起物です。
その名の通り、笹の葉に様々な縁起物を飾り付けたものです。
この福笹には、「野の幸」「山の幸」「海の幸」といった自然の恵みを象徴する飾りがつけられています。
これらは、それぞれ畑や山、海からの豊かな収穫を意味し、人々の生活が豊かになることを願っています。
また、笹の元は竹ですが、竹は冬の寒い時期でも青々としてまっすぐに伸びていることから、商売での苦難や逆境にも耐えるとされています。
十日戎で「商売繁盛!笹持ってこい!」という掛け声が聞かれるのもそのためです。
しかし、笹持ってこいという言い方がちょっとしっくりこない気がしませんか?
これは、昔は自分でとってきた笹に吉兆と呼ばれる縁起物をつけていたからと言われています。
つまり、掛け声には「笹を持ってきたら商売繁盛にさせてあげるよ」という意味があると言われています。
福笹には「吉兆」や「小宝」と呼ばれる飾りも付けられます。
これらの飾りには、具体的に「あわびのし」「銭叺(ぜにかます)」「銭袋(ぜにぶくろ)」「末広」「小判」「丁銀」「打ち出の小槌」「大福帳」「烏帽子(えぼし)」「臼」「米俵」「鯛」といったアイテムが含まれています。
これらはそれぞれ、金運上昇、商売繁盛、豊かな収穫、幸運などを象徴しており、持ち主に幸せをもたらすとされています。
今宮戎神社(十日戎)に参拝
致しました。
福笹を頂き、商売繁盛の神様
『えべっさん』
の福を授かりました。 pic.twitter.com/Toz6i2Qi8B— 龍.宮 (@y_miya1) January 12, 2022
熊手
熊手は、文字通り熊の手を模した形をした縁起物で、幸運や財をかき集める力があるとされています。
商売人の間では特に人気があり、店先などに飾られることが多いです。
十日戎の期間中、多くの人々が神社に参拝し、これらの縁起物を購入します。
これは、神社から授与される「御神徳(ごしんとく)」をいただくという信仰の表れであり、参拝者はこれらの縁起物を通じて神様の恵みを受けると考えられています。
十日戎で熊手を買ったら福引きで1等当たってもう1つ熊手を貰った。めっちゃ商売繁盛! pic.twitter.com/rRrsL1ST6z
— 芍 (@pivoine__) January 10, 2022
十日戎の福笹や熊手など縁起物の飾り方
十日戎で選んだ福笹や熊手、それらはただの飾りではありません。
日本の伝統に根差した、幸運を招くための大切なアイテムなのです。
では、これらの縁起物をどのように飾れば良いのでしょうか。
ここでは、その正しい飾り方についてお話ししましょう。
福笹と熊手の飾り方
- 神棚がある場合: 神棚があるご家庭では、福笹や熊手を神棚に飾ります。これは、お札と同じように神聖なものとして扱うためです。
- 神棚がない場合: 神棚がない場合は、家の中で最も清潔で、大人の目線より高い場所に飾るのが適切です。これには特に決まった場所はありませんが、幸運を家に招き入れる意味で、玄関やリビングなど、家族が集まる場所がおすすめです。
- 固定の重要性: 飾る際は、福笹や熊手が落ちないようにしっかりと固定しましょう。安全かつ見栄え良く飾ることが大切です。
- 定期的なお手入れ: 長期間飾っていると、ほこりが積もることがあります。時々、下ろしてほこりを払い、清潔に保つことが大切です。
- 熊手の特別な扱い: 熊手は特に、金運や福を招くとされています。掃除の際には、招く仕草をすることで、さらに運気を高めることができると言われています。
縁起物を飾る意味
これらの縁起物を飾ることは、単に伝統を守るだけでなく、家族の幸福や健康、繁栄を願う日本の美しい文化の一つです。
毎年、十日戎でこれらのアイテムを手に入れ、家に飾ることで、新しい年の幸運を家族全員で分かち合うことができるのです。
福笹や熊手を飾る際は、これらの背景を思いながら、心を込めて飾りましょう。
それが、より多くの幸せを家庭に招き入れる秘訣かもしれませんね。
十日戎の縁起物の飾る方角は?
日本の伝統的な行事である十日戎において、福を招くために用いられる縁起物、特に福笹や熊手を飾る際の方角について、その重要性と正しい方法をご紹介します。
この風習は、古くから日本の文化に根付いており、多くの方々が年始に行う重要な儀式の一つです。
縁起物を飾る際の方角
| 縁起物 | 正しい飾り方 | 誤った飾り方 | 重要性 |
|---|---|---|---|
| 福笹 | 南向きに飾る(部屋の北面) | 南に飾る | 方角によって福の流れが変わる |
| 熊手 | 東向きに飾る(部屋の西面) | 東に飾る | 方向性が福を呼び込む鍵 |
南向き・東向きに飾る理由
- 南向き:日本では、南は暖かく、繁栄や成長を象徴する方角とされています。そのため、福笹を南向きに飾ることで、家庭や事業の繁栄を願う意味が込められています。
- 東向き:東は、太陽が昇る方向であり、新しい始まりや清新さを象徴します。熊手を東向きに飾ることで、新たな幸運や好機の到来を願うとされています。
注意点
- 方向の誤解:多くの方が、南や東に直接飾ると誤解してしまうことがありますが、重要なのは縁起物が南向きや東向きになるように配置することです。
- 意味の喪失:方向を間違えてしまうと、縁起物を飾る本来の意味が失われてしまいます。福を正しく招き入れるためにも、方角には細心の注意を払いましょう。
十日戎において福笹や熊手を飾る際は、これらの点に注意して、家庭や事業に幸運が訪れるよう心掛けましょう。
日本の美しい伝統を大切にし、それぞれの家庭に幸せが訪れることを願っています。
十日戎の縁起物の処分の仕方は?
福笹や熊手の処分方法
- 一年間の飾り付け
- 福笹や熊手は、購入したその年の十日戎から翌年の十日戎まで、家や店に飾ります。これは、一年間の幸運と繁栄を願う行為です。
- 返納と新たな購入
- 翌年の十日戎には、古い福笹や熊手を神社に持ち帰り、新しいものを購入して再び飾ります。この習慣は、感謝と新たな願いを込めた行動です。
- 掛け声の意味
- 「商売繁盛!笹持ってこい!」という掛け声には、商売繁盛を願う意味の他に、「感謝を込めて来年もまた参拝してください」という願いが込められています。
- 神社への持参
- 購入した神社に持参できない場合、他の神社に持って行っても構いませんが、念のため事前に確認することをお勧めします。
- どんど焼き
- 自宅での処分
- 神社に行けない場合は、家庭ごみとして処分することも可能です。ただし、縁起物としての敬意を払い、塩やお酒で清めた後、紙に包んで処分するのが良いでしょう。
このように、十日戎の縁起物の処分方法には、伝統と敬意が込められています。
一年間の幸運を感謝し、新たな年への願いを込めて、これらの縁起物を丁寧に扱うことが大切ですね。
十日戎に関するよくある質問
十日戎とはどういう意味ですか?
十日戎は、毎年1月9日から11日までの3日間にわたって、七福神の中の漁業、商売繁盛、五穀豊穣の神、戎(恵比寿)様を祭る行事です。9日は宵戎(よいえびす)、10日は本戎(ほんえびす)、11日は残り福と称されます。
えびす講と十日戎の違いは何ですか?
十日戎とえびす講の違いは、十日戎は関西のえびす講の一部であり、えびす講は全国的に見られ、えびす様を祀って豊漁や商売繁盛を祈願する祭礼です。関西以外では、新暦または旧暦の10月20日や11月20日前後に行われることが多いです。
十日戒の11日は残り福とは何ですか?
残り福は、残り戎(のこりえびす)とも呼ばれ、十日戎の最後の日(1月11日)には、誰かが取り残した物の中や、最後に残った物の中には、思いがけなく価値のある物が残っているということです。
大阪で十日戎と言えばどこですか?
大阪で十日戎で有名なのは、今宮戎神社です。今宮神社は大阪市浪速区にあり、「恵比寿(えびす)天」という商売繁盛の御利益があると言われる七福神の一人を祀っています。地元の大阪人からは「えべっさん」という通称で親しまれ、この名前の方がより知られています。
十日戎で飾るものは何ですか?
十日戎で飾るものは、「福笹」や「あわびのし」「銭叺」「銭袋」「末広」「小判」「丁銀」「打ち出の小槌」「大福帳」「烏帽子」「臼」「米俵」「鯛」を含んでいます。神社での参拝時に十日戎の福笹などを授かるのは、「御神徳」を受け入れる信仰の表れです。
十日戎はいつからですか?
十日戎は、毎年1月9日から11日まで行われます 商売繁盛、家運隆盛を願う参拝者が押し寄せ、毎年百万人を数えます。
十日戎の初日はなんて呼ばれますか?
十日戎の初日(1月9日)は、「宵えびす」と呼ばれています。そして、10日は「本えびす」と称され、11日の最終日は「残り福」と呼ばれます。関西での新春の終わりを飾るこの期間には、一年の幸福を祈る多くの人々が集まります。
十日戎のまとめ
十日戎(とおかえびす)は、毎年1月9日から11日まで行われる、商売繁盛を願う関西地方の伝統的なお祭りです。
この期間、福笹や熊手などの縁起物を神社で授かり、家や店に飾ります。
特に、大阪の今宮戎神社は賑わいを見せます。
飾り方には、方角や清潔さが大切で、翌年には古い縁起物を神社に返納し、新しいものを購入します。
十日戎は、新年の幸運を家族で分かち合う素敵な文化です。
※まだ十日戎に行ったことがないという方は、酉の市をイメージしてみるとよいかも知れません。
この記事のポイントをまとめますと
- 十日戎は「とおかえびす」と読み、毎年1月9日から11日に行われる
- 主に関西地方で盛んで、商売繁盛を願うお祭り
- 七福神の一人、恵比寿様を祀る行事
- 福笹や熊手などの縁起物が特徴
- 福笹には自然の恵みを象徴する飾りがつく
- 熊手は幸運や財をかき集める力があるとされる
- 縁起物の飾り方には、方角や清潔さが重要
- 今宮戎神社は大阪で最も賑わう十日戎の神社
- 翌年の十日戎で古い縁起物を神社に返納し、新しいものを購入
- 十日戎は家族の幸福や健康、繁栄を願う文化
- どんど焼きで古い縁起物を焚き上げることも
- 十日戎は新年の幸運を家族で分かち合う行事







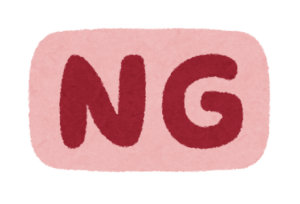




コメント