2025年五月人形を出すと良い日はいつ?飾るタイミングや片付けるタイミングは?
5月5日の行事と言えば現在は「子どもの日」ですよね。
子どもの日は「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」を趣旨としていますが、元は男の子の健やかな成長を願う行事で、端午の節句と呼ばれています。
そのため、男の子がいる家庭では五月人形を飾ると思いますが、五月人形はいつからいつまで飾るものなのでしょうか。
いつ出すのかがよくわからなくて、困惑している方もいるかも知れませんね。
そこで今回は、五月人形を出すタイミングや片付けるタイミングについて調べてみました。
五月人形を飾る理由も合わせて解説していきます。
五月人形をいつ出すのがベスト?

五月人形を出すのは、一般的には3月中旬の春分の日から、遅くても4月の中旬までがよいと言われています。
ただし、地域によっては「端午の節句の飾りなので、端午の節句の一週間くらい前に飾るのがよい」とするところや、「縁起物なので、早ければ早いほどよいので、女の子のお祝いである上巳の節句(ひな祭り)が終わったらすぐに出す」という方もいらっしゃるようです。
このようなことから、早い方なら3月の上旬から、遅くても5月5日の一週間前の間に出すとよいのではないでしょうか。
なお、日取りについては大安吉日に出すのがよいなど、決まりがあるわけではないので、特に気にする必要はなさそうです。
2025年の五月人形を出すと良い日はいつ?
五月人形を飾るのに最適な日を選ぶことは、特別な意味を持ちますね。
2025年の春分の日から4月末までの間に、運気を高める「吉日」がいくつかあります。
これらの日に五月人形を飾ることで、家族に幸運をもたらすとされています。
以下の表に、各吉日とその特徴をまとめましたので、スケジュールを確認しながら、最適な日を選んでみてください。
| 日付 | 曜日 | 吉日の種類 |
|---|---|---|
| 3月15日 | 金 | 一粒万倍日、天赦日、寅の日(特別な吉日) |
| 3月22日 | 金 | 一粒万倍日 |
| 3月27日 | 水 | 一粒万倍日、寅の日 |
| 3月29日 | 金 | 鬼宿日 |
| 3月30日 | 土 | 巳の日 |
| 4月3日 | 水 | 一粒万倍日 |
| 4月6日 | 土 | 一粒万倍日 |
| 4月8日 | 月 | 寅の日 |
| 4月9日 | 火 | 一粒万倍日 |
| 4月11日 | 木 | 巳の日 |
| 4月18日 | 木 | 一粒万倍日 |
| 4月20日 | 土 | 寅の日 |
| 4月21日 | 日 | 一粒万倍日 |
| 4月23日 | 火 | 巳の日 |
| 4月26日 | 金 | 鬼宿日 |
| 4月30日 | 火 | 一粒万倍日、甲子の日 |
特に、2025年3月15日は、「一粒万倍日」と「天赦日」と「寅の日」が重なる、非常に稀な最強の吉日とされています。
この日に五月人形を飾ることで、一年を通じての良い運勢を期待することができそうです。
スケジュールの許す限り、この日を狙ってみるのも良いでしょう。
五月人形はいつまで飾るの?

子どもの日に飾るものと言えば、こいのぼりを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。
片付けるのは5月5日を過ぎたらできるだけ早い時期、遅くても5月中には片付けるようにするのがよいと言われています。
そして、五月人形もこいのぼりと同じ期間に飾るものと言われています。
これは、子どもの日にこいのぼりが飾られるのも、元の端午の節句が関係しているからで、端午の節句には男の子の健康を願い、武家や貴族の家庭では兜や鎧、幟(のぼり)を飾っていました。
しかし、庶民にはこれらを買うお金がなかったため、兜や鎧は紙製のものを手作りし、幟の代わりに五色の吹き流しを飾るようになりました。
それがやがて、中国の「登竜門」の伝説にあやかり、鯉の幟を各家庭で立てるようになったと言われています。
つまり、こいのぼりも五月人形と同じように男の子の成長を願う意味があり、同じ時期に飾り始めるものなのです。
もし、「五月人形はいつから飾って、いつくらいに片付けたらいいの?」と困っている場合は、近所でこいのぼりを立てている家を見つけ、その家と同じ時期に五月人形を出して片付けるようにするとよいでしょう。
片付けるタイミングはいつ?

五月人形を片付けるタイミングについても、特に決まりはないようです。
とは言え、端午の節句という特別な行事に飾るもののため、季節が過ぎたら早めに片付ける方が多いと言われています。
5月は梅雨に入る時期でもあるので、いつまでもそのままにしておくと梅雨が始まり、カビが生えてしまうことも考えられます。
そのため、五月人形は端午の節句が終わったら、天気がよくて乾燥している日にほこりなどをきちんと払って、片付けるのがよいでしょう。
なお、五月人形は雛人形のようにずっと飾ったままだと婚期を逃すと言った言い伝えがないことや、インテリアとして映えることから一年中飾る方もいるようです。
これに関しては特に問題がないとする人がいる一方で、行事のための飾りであるため片付けた方がよいという意見もあります。
五月人形を飾る理由

端午の節句に五月人形を飾るのは、「五節句」が関係していると言われています。
五節句は中国から伝わった季節の行事で、陰陽五行説を由来とする暦日です。
陰陽五行説とは、万物が「陰」と「陽」(陰陽)、「木」「火」「土」「金」「水」(五行)に分かれるとする自然哲学なのですが、この中で奇数は陽、偶数は陰となり、1月7日、3月3日、5月5日、7月7日、9月9日のように、奇数が重なる日は陽×陽=陰となり、陰の気が強くなると考えられていました。
そのため、1月7日を人日の節句、3月3日を上巳の節句、5月5日を端午の節句、7月7日を七夕(しちせき)の節句、9月9日を重陽の節句として、邪気が入り込みやすい季節の変わり目として邪気祓いの行事を行っていたのです。
その一方で、鎌倉時代になると武士の家庭では、梅雨の時期に入る前に鎧や兜を家の中で干して手入れが行われていました。
ちょうどその時期が端午の節句と重なることから、そもそもの行事の意味である厄払いと、武士を守る役割を果たす兜や鎧を飾ることで、その家に生まれた男の子の成長を見守るという意味になったと言われています。
なお、5月5日を端午の節句としたのは、元々端午に「月の初めの午(うま)の日」という意味があり、やがて午が五と同じ発音であることから、毎月5日を示すようになり、さらに5月5日を限定するものに変わっていったと言われています。
五月人形はいつ買えばいい?

五月人形は、2月の下旬から店頭に並び始めますが、購入時期が遅くなればなるほど選択肢がなくなってしまうため、数ある中から好みや予算に合ったものをしっかりと選びたいという場合は、早めに行動をするのがお勧めです。
2月は上旬に節分、中旬にバレンタインデーと何かと行事が多い月ですが、五月人形の購入予定がある方は下旬にスケジュールを調整しておくとよいでしょう。
五月人形は何歳まで飾るの?

五月人形を何歳まで飾るかについては、特に決まってはいませんが、五月人形には男の子の厄を引き受けてくれるため、一般的な意味合いで親の手から離れる成人式が一つの基準となっているようです。
つまり、20才になるまでは飾り、20才以降は飾らないという方が多いようです。
ただしこれも、あくまでも「そのような方が多い」というだけであり、子どもが成人し実家を出た後でも飾っている方もいれば、7才を過ぎたら飾らないと言う方もいます。
また、子どもの成長度合いに関係なく、毎年5月5日に合わせて飾るのが面倒になってしまったり、購入してしばらくは飾っていたけれど、ある年に飾るのを忘れてしまってからはそのまま飾らなくなってしまったという場合もあるようです。
このようなことから、五月人形を何歳まで飾るかについては、各家庭で違うということになります。
なお、五月人形を飾る飾らないに関係なく、置き場所などに特に困っていないようであれば、手放さずにずっと手元に置いておくという方が多いようです。
菖蒲を飾る理由は?
菖蒲は昔から薬草として知られ、煎じて飲むと腹痛に効くとされ、葉を浴槽に入れた菖蒲湯に浸かると無病息災の効果があると言われていました。
また、菖蒲には強い香りがあり、邪気祓いにも使用されていました。
このような風習が中国から日本へと伝わった際、武家社会において「菖蒲」が「勝負」と同じ発音であることから、縁起を担ぐ武士の間で人気となり、端午の節句には男の子の健康や出世を願って、菖蒲を飾るようになったと言われています。

五月人形はいつ出すのまとめ
五月人形は、一般的には3月中旬の春分の日から4月中旬までに出し、5月5日の端午の節句が終わったらできるだけ早く片付けるのがよいと言われています。
また、五月人形の購入を考えている場合は、2月の下旬から販売数が増えてきますが、時期が遅くなるにつれ選択肢が少なくなっていくことから、なるべく早くに購入しておくのがよいでしょう。







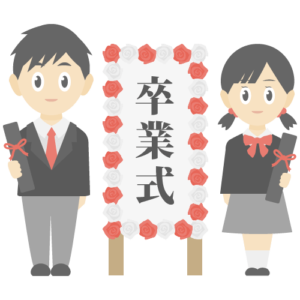

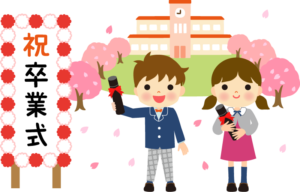
コメント