菖蒲湯はいつ入るの?意味や由来と入り方は?
5月5日の端午の節句といえば、こいのぼりやちまきを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか?
実はもう一つの定番行事、菖蒲湯も忘れてはいけません。
冬至に入る柚子湯は馴染み深いですが、菖蒲湯は少し謎めいている気がしませんか?
「菖蒲って、結局何?」
「なぜ特別な日に入るんだろう?」
そんな疑問を抱えている方も少なくないはずです。
この機会に、菖蒲湯の意味や背景について深掘りしてみましょう。
そもそも菖蒲湯とは何か、その起源や作り方、さらには健康や美容にもたらす効果、子どもの日とのつながり、そして楽しむ際の注意点まで、幅広くお話しします。
菖蒲湯はいつ入るのか?
5月は、新しい気候に体が慣れずに、体調を崩しやすい時期ですよね。
そんな時に役立つ、古くから伝わる健康の秘訣があるんですよ。それが、「菖蒲湯」です。
菖蒲湯を楽しむ習慣は、遠い昔、中国から伝わってきました。
元々は「端午の節句」という行事の一環で、悪いものを遠ざけて、健康であることを願う意味が込められていたんです。
日本に伝わると、この美しい習慣は少し変わり、特に5月5日に菖蒲をお風呂に入れて楽しむことが一般的になりました。
では、なぜ菖蒲なのでしょうか?
それは、菖蒲が昔から健康を守る薬草として知られていたからです。
5月は季節の変わり目でもあり、人々が体調を崩しやすい時期。
そんな時に菖蒲の力を借りて、健康を願うわけですね。
中国での端午の節句では、菖蒲を細かく刻んで酒に混ぜて飲んだり、その葉を家の軒下に吊るす習慣がありました。
しかし、日本では、これを少しアレンジして、お風呂に菖蒲を入れて楽しむ風習が根付いています。
これにより、菖蒲の香りと効能を全身で感じることができるんです。
この素敵な習慣を通して、健康で穏やかな毎日を送れるように願いましょう。
5月5日の端午の節句を迎える際には、ぜひ菖蒲湯でリラックスするのもいいですね。
菖蒲湯の意味や由来
爽やかな香りをお風呂に広げ、心身をリラックスさせてくれますが、そもそもなぜ菖蒲湯に入るのでしょうか?
その歴史と込められた願いを、分かりやすくご紹介します。
菖蒲湯の起源:古代中国の厄払い
強い香りを持つ菖蒲は、邪気を祓うと考えられていました。
古代中国では、5月は病気や災厄が起こりやすい時期とされ、菖蒲を用いた厄払い行事が行われていました。
これが日本に伝わり、菖蒲湯として親しまれるようになったのです。
菖蒲湯に込められた願い
菖蒲湯には、単に体を清めるだけでなく、厄除けや健康祈願の願いが込められています。
菖蒲の香りにはリラックス効果があり、疲労回復や血行促進にも効果があるとされています。
武家社会における菖蒲湯
日本に端午の節句が伝わった当時、武家社会では男の子の成長を願って菖蒲湯が行われていました。
菖蒲の「尚武(しょうぶ)」という読み方に、「勝負に強く、武勇に優れた男に成長してほしい」という願いを込めたのです。
現代における菖蒲湯
現代では、男女関係なく、家族みんなで健康を祈願して菖蒲湯を楽しむ家庭が増えています。
菖蒲湯は、端午の節句の伝統行事として、これからも大切に受け継がれていくでしょう。
菖蒲湯の作り方は?

菖蒲湯は、購入した葉菖蒲を10本ほどにまとめて輪ゴムなどで括ったら(お風呂の排水溝に詰まるのを避けるため)、浴槽に入れるだけで簡単に作れることができます。
給湯式の場合は、束ねた菖蒲を浴槽に置き、その上からやや高めの温度のお湯を注ぎましょう。
沸かすタイプのお風呂は、水を張った浴槽に菖蒲を浸し、やや高めの温度で沸かします。
菖蒲湯は湯船に菖蒲が浮かんでいる様子が何とも風情がありますが、それよりも効果や効能を求めるという方は、菖蒲を細かく刻んでガーゼや布に包むか(輪ゴムなどで口はしっかり締める)、だしパックなどに入れ、洗面器に入れた後に熱湯を注ぎ、そのまま15分ほど浸して菖蒲の成分をしっかりと抽出させてから、お湯を張った湯船に洗面器のお湯と菖蒲を入れるのがお勧めです。
この方法だと菖蒲を入れるだけよりも成分がお湯に溶けだしやすくなり、香りもさらに立ちやすくなります。
また、小さなお子さんと一緒に入る時も、誤って葉を口に入れることがないので安心です。
菖蒲湯の入り方

菖蒲湯は、浴槽に菖蒲を入れるだけで簡単に行うことができますが、ちょっとしたコツを抑えるだけで効果や効能をアップすることができます。
① 葉と茎の部分を10本程度束ねる
菖蒲の独特の香りは葉から、薬効は根茎に多く含まれています。
そのため、どちらもしっかりと効果を得るために、葉と茎を合わせて10本程度まとめて浴槽に入れるとよいでしょう。
バラで入れる場合は、お風呂が詰まらないように注意をして下さい。
② やや高めの温度で入れる
42~43度の高い温度でお湯を入れると、菖蒲の香りが出やすくなります。
入る時は水を入れてお好みの温度まで冷まして下さい。
③ 頭に巻いてみよう
菖蒲の葉を頭に巻くと、頭がよくなると言われています。
はちまきの要領で頭に巻いて、「頭がよくなりますように」と願い事をしてみましょう。
菖蒲湯を楽しむポイント
- 菖蒲は、生葉でも乾燥葉でも使用できます。
- 菖蒲の代わりに、よもぎや艾草を使用しても良いでしょう。
- 菖蒲湯は、追い焚きせずに使い切りましょう。
- 入浴後は、菖蒲の葉や根を湯船から取り出してください。
菖蒲湯の効能・効果は?
1. 香り成分でリラックス&リフレッシュ!
菖蒲にはセスキテルペンやオイゲノールなどの香り成分が含まれています。
これらの成分には、以下のような効果があるとされています。
- 血行促進:体の隅々まで栄養を届け、冷え性やむくみ改善に役立ちます。
- リラックス効果:心を落ち着かせ、ストレス解消や安眠に効果的です。
- 殺菌効果:皮膚の炎症を抑え、ニキビや肌荒れ予防に役立ちます。
- 防虫効果:虫よけ効果があり、夏の虫対策にもおすすめです。
2. 爽やかな香りで気分転換!
菖蒲の爽やかな香りには、気分転換や疲労回復効果も期待できます。
仕事や家事などで疲れた時、菖蒲湯でゆっくりと体を温めれば、気分もリフレッシュできますよ。
菖蒲湯とこどもの日との関係

「こどもの日に菖蒲湯に入る」という言い方は、正確に言えば間違いとなります。
なぜなら、菖蒲湯に入るのはこどもの日だからではなく、その日が端午の節句だからです。
これまでご紹介した通り、菖蒲湯は中国から伝わった端午の節句で厄払いに菖蒲が使われていたことが始まりです。
端午の節句は長らく宮中行事として行われていましたが、やがて武士の間に広まり、それが庶民へと浸透して現在のような形になりました。
その過程の中で、菖蒲の葉を門に飾ったり、お酒に浸して飲むだけではなく、銭湯に浮かべて菖蒲湯として浸かり、男の子の成長や出世を願いました。
このようなことから、菖蒲湯は端午の節句で行われる風習の一つと言えます。
一方でこどもの日は、男の子に限らず女の子においても「人格を重んじ、幸福をはかる」ことを趣旨とした国民の祝日です。
こどもの日だからと言って、実は端午の節句のように決まった風習や行事があるわけではありません。
端午の節句とこどもの日は同じ5月5日ですが、菖蒲湯についてはこのような違いがあると知っておくとよいかも知れませんね。
菖蒲湯の注意点は?

菖蒲湯を行う時は、サトイモ科の葉菖蒲を購入するようにしましょう。
一般的に菖蒲と言ったら、葉菖蒲ではなく、アヤメ科の花菖蒲を思い浮かぶ方が多いようで、菖蒲湯に花菖蒲を入れてしまうことがあります。
花菖蒲を入れても、葉菖蒲のような効果は期待できないため、菖蒲の種類を間違えないようにして下さい。
また、葉菖蒲の有効成分は葉よりも根茎の方に多く含まれています。
そのため、葉菖蒲を購入する時はなるべく根茎部分が多いもの、根が付いているものを選ぶとよいでしょう。
菖蒲の葉は鋭いため、小さなお子さんと入る時は肌を傷つけないよう、十分に注意をして下さいね。
菖蒲湯はどこに売っている?

菖蒲湯に使う菖蒲の葉(葉菖蒲)は、普段は売っているところを見かけませんが、時期になるとスーパーや生花店、ホームセンターなどで販売されます。
しかし、4月の末から5月5日までと販売している期間が短いことや、数多く売られているわけではないので、すぐに売り切れになってしまうなど、場合によっては手に入らないかも知れません。
そのため、絶対に手に入れたいならあらかじめお店で予約しておくか、インターネット通販を利用してみてはいかがでしょうか。
菖蒲湯は葉菖蒲さえ手に入れば、後はお湯に浸けるだけで楽しむことができます。
なお、葉菖蒲が品切れでも、最近は乾燥させて細かくしたものを不織布に入れた商品が販売されています。
浴槽に大きな葉菖蒲が浮かぶわけではないので、雰囲気は少し違ってしまうかも知れませんが、できるだけゴミを出したくないという方はこちらの商品を検討してみるのもよいかも知れません。
菖蒲湯に関するよくある質問
赤ちゃんや妊婦さんも菖蒲湯に入っていいの?
まず赤ちゃんですが、基本的には問題ありません。
しかし、生後3ヶ月くらいまでは入れないほうが良いとされます。
生後間もない赤ちゃんは肌のバリア機能ができあがっていないため、肌荒れを起こす可能性があります。
また、菖蒲の葉が直接触れることで、肌を傷つけてしまう恐れも。
入れる場合も短時間にとどめ、最後に体を洗い流しましょう。
一方、妊婦さんは菖蒲湯に入っても、何ら問題はありません。
注意したいのは、菖蒲とヨモギが一緒になった、菖蒲湯用のセットを購入する場合です。
ヨモギには、陣痛を促進する作用があります。
セットを購入する際には、ヨモギが入っていないことを必ず確認しましょう!
菖蒲湯の地域性は?
ほぼ日本中に伝わる習慣なのですが、関西など一部地域では菖蒲湯に入る習慣がないこともあるようです。
また、「菖蒲をそのまま束にしてお湯にいれる」「細かく刻んでお湯に浮かべる」「細かく刻んだものを袋に包んで入れる」など地域やご家庭によっていろいろな入浴方法があるようです。
菖蒲湯は女の子でも入って良い?
端午の節句の風習として菖蒲湯に入って勝負に勝つというゲン担ぎされることもあるかと思いますが、菖蒲湯にはこの他にも邪気を祓うという意味も込められているため、女の子しかいない家庭でも菖蒲湯に入ることは良いことかと思います。
この他にも菖蒲湯には血行を良くしたりする体に良い成分がたくさんありますので、この日は家族そろって菖蒲湯にゆっくり入るのもいいかもしれませんね。
菖蒲湯のまとめ
菖蒲湯に入れる菖蒲は、中国から伝わった端午の節句において、厄払いに使われていたものです。
端午の節句は日本に伝わった後、貴族→武士→庶民という過程を経て全国に広まっていきますが、その中で門に飾ったり、お酒に浸して飲んでいたものが、お湯に浸けて入る菖蒲湯に変わっていったと言われています。
端午の節句はこどもの日と同じ5月5日に行われるため、菖蒲湯=こどもの日と思っている方も多いですが、厳密には端午の節句の風習となります。
とは言え、どちらもこどもの幸せや健康を願うことに変わりはないので、5月5日には菖蒲湯に浸かってこどもの成長を願うのがよいでしょう。



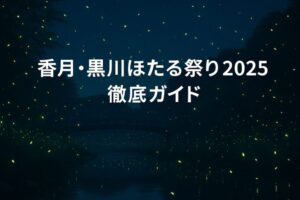






コメント