こどもの日とは何をする日?過ごし方はどうしたらいい?
大人になり、風に泳ぐ鯉のぼりやお店に並ぶ柏餅を見ていると、こどもの日が近いことを感じますが、自分がこどもの時は、こどもの日は単にゴールデンウィークの一つで、学校が休みでラッキーくらいのイメージしかなかったではないでしょうか。
こどもの日とは一体、どのような意味なのか、その由来や何をする日なのかなど、大人になった今、こどもにきちんと話せるようになりたいと思いませんか?
そこで今回は、こどもの日について調べてみました。
端午の節句との関係などをご紹介します。
こどもの日とは何をする日?

こどもの日には、様々な風習や行事が行われますが、それは一体どのような理由で行われているのでしょうか。
鯉のぼりをあげる
近年は住宅環境などから、自宅の庭で屋根の高さを超えるような大きいものは見かけなくなりましたが、こどもの日と言えば「こいのぼり」を思い浮かべる方も多いと思います。
こいのぼりの由来は中国にあり、登龍という滝を色々な魚が昇ろうとしたところ、鯉だけが昇り切ることができ龍となったことから、鯉が立身出世の象徴となったという話が元になっています。
『登竜門』という言葉がありますが、これはまさに鯉の滝登りが元となった言葉で、男の子の出世を願って親がこいのぼりを立てたことが始まりと言われています。
五月人形を飾る
五月人形の鎧や兜は、武士にとって身を守る大切な防具です。
そのため、五月人形を飾るのは災いからこどもを守るという願いが込められています。
なお、こどもの日の時期は旧暦ではちょうど梅雨にあたり、武士の家では梅雨になる前に家の中で防具に風通しを行う「虫干し」が行われていました。
これが江戸時代になると庶民に伝わり、かと言って同じように鎧や兜がないことから、紙などで作って飾っていました。
柏餅を食べる
柏の葉は新芽が出るまで落ちないことから、家系が途絶えない、子孫繁栄などの縁起物として食べられるようになったと言われています。
これは江戸時代からの風習であり、日本独自のものと言われています。
菖蒲湯に入る
菖蒲は古くから厄払いの効果や薬効があると言われており、薬草として使われたり、菖蒲湯に浸かって体の疲れをとったり体調管理に役立てられていました。
それが武家社会において、菖蒲が勝負に繋がることから縁起がよいと言われるようになり、庶民にも広まったと言われています。
こどもの日の過ごし方

こどもの日には、こいのぼりや五月人形を飾りますが、これはこどもの日の前から準備することですよね。
菖蒲湯に浸かるのも多くの方は夕方から夜にお風呂に入ると思いますし、柏餅を食べるのもほんの一瞬の時間です。
では、こどもの日として過ごす一日の大半は、みなさんどのように過ごしているのでしょうか。
こどもの日は、動物園や水族館などこどもが利用する多くの施設で料金が割引になるなどのサービスがあるので、割引を目当てに外出したり、近場の公園で遊んだり、自治体によってはイベントやお祭りが開催されていて、そちらに出掛ける場合が多いようです。
こどもの日にはこどもが楽しめるイベントを行うという方が多いですが、こどもの日の趣旨には「母に感謝する」という言葉もあります。
いつも頑張って育児をしてくれているお母さんに、「ありがとう」と伝えてみるのもよいかも知れません。
2025年のこどもの日はいつ?
これはその年によって変わるわけではなく、毎年5月5日となります。
5月5日はゴールデンウィークの最終日です。
世界各国にもこどもの日がある?

こどもの日は日本以外にも、世界各国にあることをご存知でしょうか。
お隣の韓国では、日本と同じこどもの日という意味の「オリニナル」が5月5日に行われます。
内容も日本と同じで、動物園や水族館などが無料になったり、各種イベントなどでこどもにとって楽しい一日となっています。
また、メキシコでは4月30日がこどもの日となっています。
日本のように学校が休みにはなりませんが、学校で盛大なパーティーが開かれたり、大人からこどもへのプレゼントが恒例となっており、こどもの日の前はクリスマスのようにプレゼントを選ぶ大人で賑わうそうです。
さらにインドでは、こどもが大好きだった初代首相のジャワハルラール・ネルーにちなみ、誕生日をこどもの日に制定しており、毎年11月14日に学校や地域で様々なイベントが行われています。
端午の節句との関係は?

こどもの日は元々、「端午の節句」と呼ばれる五節句の一つです。
五節句とは中国から伝わった季節を表す名称で、他に1月7日の人日の節句、3月3日の桃の節句、7月7日の七夕の節句、9月9日の重陽の節句があります。
中国では万物が陰と陽に分かれるとされ(陰陽思想)、奇数は陽、偶数は陰となりますが、陽が二つ重なって陰となる上記の日は邪気が入り込みやすいとされ、厄払いの儀式が行われていました。
端午の節句のその一つで本来は邪気祓いが行われていましたが、厄を祓うために使われていた菖蒲が勝負に通じることや、鎧や兜を飾る風習などが合わさり、やがて男の子の誕生や健康を祝う行事へと変わっていったと言われています。
なお、端午の節句の端には初めて、午には午の日という意味があり、午は「5」と同じ読み方をすることから、毎月5日を指すようになり、それがいつしか5月5日を示すようになったと言われています。
端午の節句が男の子のお祝いとして庶民に広まったのは江戸時代になってからですが、その後、昭和23年の祝日法によって男の子に限定するのではなく「こどもの日」として名称が変わり、制定されました。
こいのぼりの選び方は?

こいのぼりに使われている素材は、大きく分けてナイロンとポリエステルの2種類。
ポリエステルはナイロンに比べて発色が良く、色落ちしにくいという特徴がありますが、価格はナイロンよりも割高。
そのため、サイズが大きくなればなるほど、当然ながらポリエステルの方が値段が高くなります。
このようなことから、同じ価格でサイズが違うと前提するなら、とにかく大きいこいのぼりが欲しいという場合は価格的にはナイロンがお勧めになり、ベランダなどに飾る小さめのタイプであれば、色が鮮やかなポリエステルがよいでしょう。
また、こいのぼりと一口に言っても有名なデザイナーが手掛けたものや、より日本風な画調が際立つもの、かわいらしいものなど様々にあります。
こいのぼりのデザインの好みに応じて選ぶというのも、一つの選び方と言えるでしょう。
こどもの日の意味や由来

こどもの日とは、国民の祝日にあたり、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」ことが趣旨となっています。
こどもの日という名称から、当然ながらこどものための日だということはわかりますが、実は同時にお母さんにも感謝を示す日でもあるのです。
なお、国民の祝日は昭和23年7月20日に施行された『国民の祝日に関する法律(祝日法)』によって定められております。
こどもの日のまとめ
こどもの日は元々、端午の節句と呼ばれる厄払いの儀式や由来となっており、菖蒲が勝負に繋がる菖蒲湯に浸かったり、鎧や兜を虫干しする時期と重なったことから、やがて男の子の誕生や健康を願う行事へと変わっていきました。
そこからさらに昭和に入り、祝日法によって男女問わずこどもの健康や幸福を願う日に制定されました。
こどもの日の関連記事
端午の節句の関連記事
2025年の国民の祝日一覧
| 月 | 日 | 曜日 | 祝日の名称 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1 | 月 | 元日 |
| 8 | 月 | 成人の日 | |
| 2月 | 11 | 日 | 建国記念の日 |
| 12 | 月 | 振替休日 | |
| 23 | 金 | 天皇誕生日 | |
| 3月 | 20 | 水 | 春分の日 |
| 4月 | 29 | 月 | 昭和の日 |
| 5月 | 3 | 金 | 憲法記念日 |
| 4 | 土 | みどりの日 | |
| 5 | 日 | こどもの日 | |
| 6 | 月 | 振替休日 | |
| 7月 | 15 | 月 | 海の日 |
| 8月 | 11 | 日 | 山の日 |
| 12 | 月 | 振替休日 | |
| 9月 | 16 | 月 | 敬老の日 |
| 22 | 日 | 秋分の日 | |
| 23 | 月 | 振替休日 | |
| 10月 | 14 | 月 | スポーツの日 |
| 11月 | 3 | 日 | 文化の日 |
| 4 | 月 | 振替休日 | |
| 23 | 土 | 勤労感謝の日 |
1月の国民の祝日
●1月1日(元日)
1年の始まりである1月1日は、国民の祝日によって休日となっています。
元日は休みというのは日本においてとても一般的となっていますが、実は法律が施行されたのは昭和23年の新しい祝日法からとなっています。
それ以前も元日は休日となっていましたが、法が定める休日となったのはこの時からです。
●1月8日(成人の日)
「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」を趣旨として制定された祝日です。
1999年までは1月15日に固定されていましたが、2000年以降はハッピーマンデー制度(祝日を特定の日から土日明けの月曜日に移動させることで、連休にするもの)によって、1月8日~14日のどれかになるため、1月15日に成人の日がくることはありません。
また、成人の日は、元は小正月に元服の儀が行われていたことが由来とされています。
2月の国民の祝日
●2月11日(建国記念の日)
「建国をしのび、国を愛する心を養う」という趣旨により、昭和41年に制定されました。
元々は明治6年に「紀元節」(日本の初代天皇の神武天皇の即位日)として祭日となっていたものの、戦後にGHQの指示によって廃止されたものの、昭和41年に復活して祝日となった経緯があります。
●2月23日(天皇誕生日)
天皇の誕生日をお祝いする日ですが、2019年に年号が平成から令和に変わり、今上天皇への譲位によって2020年から変更となります。
3月の国民の祝日
●3月21日(春分の日)
「自然をたたえ、生物をいつくしむ」ことを趣旨としていますが、昼と夜の長さが(ほぼ)同一となる日を春分日としています。
春分日は毎年異なりますが、通例では3月20日もしくは3月21日のいずれかになっています。
4月の国民の祝日
●4月29日(昭和の日)
「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」ことを趣旨としていますが、元は昭和天皇の誕生日→みどりの日と2度の変更経て、2007年に制定された祝日となっています。
5月の国民の祝日
●5月3日(憲法記念日)
昭和22年に日本国憲法が施行されたことを記念し、翌年の昭和23年に制定された祝日です。
「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」を趣旨としています。
●5月4日(みどりの日)
元は昭和天皇の誕生日が4月29日であったことから、ゴールデンウィークを形成する休日の一つとされていたのですが、昭和64年に年号が昭和から平成に変わり天皇がお御代替えしたことで、天皇誕生日が12月23日へと改められたことを機に、当初は4月29日をみどりの日として祝日に制定していました。
さらに平成17年の法改正により、みどりの日は5月4日に移動され、4月29日は昭和の日と変更されています。
なお、みどりの日は「自然にしたしむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ」ことを趣旨としています。
●5月5日(こどもの日)
端午の節句である5月5日に、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」ことを趣旨として昭和23年より制定されています。
6月の国民の祝日
6月は国民の祝日はありません。
7月の国民の祝日
●7月15日第3月曜日(海の日)
平成8年に施行された当初は7月20日と固定でしたが、現在は7月の第3月曜日となっています。
「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」と趣旨としています。
8月の国民の祝日
●8月11日(山の日)
平成26年に制定され、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ことを趣旨としています。
9月の国民の祝日
●9月16日第3月曜日(敬老の日)
平成14年までは9月15日の固定となっていましたが、平成15年より9月の第3月曜に変わっています。
「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」ことを趣旨としています。
●9月22日(秋分の日)
春分の日と同様に、昼と夜の長さがほぼ同じ秋分日を祝日としています。
例年9月22日か9月23日のいずれが1日となります。
「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」ことを趣旨としています。
10月の国民の祝日
●10月14日(スポーツの日)
昭和39年に行われた東京オリンピックの開会式が10月10日だったことから、この日とスポーツの日(体育の日)として、「スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう」ことを趣旨として祝日にしています。
現在はハッピーマンデー制度により10月の第2月曜日となっています。
なお、2020年1月1日より、名称もスポーツの日(体育の日)からスポーツの日へと変更になりました。
11月の国民の祝日
●11月3日(文化の日)
明治天皇の誕生日であり、日本国憲法が公布された日です。
「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨としています。
なお、文化の日から半年後の5月3日に日本国憲法は施行され、その日を憲法記念日としています。
●11月23日(勤労感謝の日)
元は新嘗祭という天皇行事による休日だったのですが、GHQによって禁止された後、勤労感謝の日として復活して祝日制定となりました。
「勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」ことを趣旨としています。
12月の国民の祝日
12月は国民の祝日はありません。



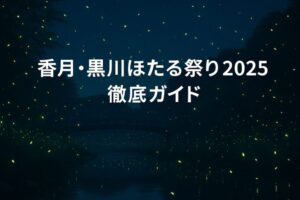






コメント