薄暑の候と聞いて、皆さんはどのようなイメージを持ちますか?
この美しい季節の挨拶は、いつからいつまで使えばいいのか、そしてその正しい読み方や意味は何なのでしょうか。
多くの方が、手紙やはがきにこの言葉を使いたいと思っても、どのように書き始め、どんな例文を参考にすればいいのか、そしてどのように締めくくれば良いのかについて、迷ってしまうことがあるかもしれません。
そんな悩みを解決するため、この記事では「薄暑の候」の使い方から読み方、意味、そして実際に手紙やはがきでの書き出しから結びの文まで、わかりやすく解説します。
これを読めば、あなたも「薄暑の候」を自信を持って使いこなせるようになるでしょう。
- 「薄暑の候」の使う時期がいつからいつまでなのかがわかります。
- 「薄暑の候」の読み方とその意味について理解できます。
- 手紙やはがきでの「薄暑の候」の使い方や例文が具体的にわかります。
- 「薄暑の候」を使った書き出しと結びの表現方法について詳しく知ることができます。
薄暑の候を使う時期はいつ?読み方や意味は?
薄暑の候を使う時期はいつからいつまで?
薄暑の候は5月上旬から6月上旬に使える時候の挨拶になります。
具体的には、二十四節気の立夏(例年5月5日頃)から芒種(例年6月4日頃)の前日までとなります。
薄暑の候に限らず、時候の挨拶は現在使われている新暦ではなく、旧暦(太陰暦)に基づいて使うのがマナーになりますよ。
旧暦では1~3月が春、4~6月が夏、7~9月が秋、10~12月が冬となりますが、この中で薄暑の候に該当するのは4月になりますね。
旧暦と新暦には1ヵ月~1ヵ月半ほどのズレがあることから、旧暦4月は新暦の5~6月に該当することになります。
薄暑の候の読み方
候はそうろうと読んでしまいそうになりますが、正しくは「こう」ですね。
薄暑の候の意味
薄暑の候は「初夏になり少し汗ばむような季節になりましたね」という意味になります。
「薄暑」という言葉は、直訳すると「薄い暑さ」を意味し、夏の訪れを告げる初夏の気候を表しています。
この時期には、日差しの強さは増しますが、まだ暑さが厳しくないため、ほんのりとした暖かさを感じることができます。
このやわらかな暑さが、ほのかに汗ばむような心地良さをもたらし、季節の移り変わりを感じさせてくれるのです。
一方で、「候」という言葉には、時候や気候、季節という意味が含まれています。
漢字そのものが持つ「待つ」という意味合いから、季節の変化を待つ心情や、その時期ならではの気候を指すことがあります。
日本では、手紙の挨拶や季節の変わり目を伝える際に「候」を用いることが一般的で、受け取る側にその時期特有の情景や気持ちを想起させる力があります。
「薄暑の候」という表現は、初夏の訪れとそれに伴う穏やかな暑さを感じさせる言葉であり、日本の四季を感じさせる独特の表現のひとつです。
薄暑の候の正しい使い方は?

薄暑の候が使える5月上旬から6月上旬は、地域によっては真夏のような気温になるところもありますよね。
薄暑の意味は「初夏になり少し汗ばむような季節」なので、30℃を越えるような気温が連日続くような状況には、ややふさわしくないと言えるでしょう。
そのため、手紙やはがきを送る相手の地域の状況によっては、他の時候の挨拶を使うのがよいかも知れませんね。
とは言え、この期間中であれば、気温が高くても薄暑の候を使う分には問題ないですし、マナー違反というわけでもありません。
そもそも時候の挨拶では旧暦と新暦との季節感のズレが生じやすいことから、使われている言葉と季節感があまり合っていないケースもあります。
薄暑の候を使った例文

実際に薄暑の候を使って手紙やはがきを書く時に、例文があると参考になりやすいですよね。
ここでは、薄暑の候を使った例文をご紹介します。
ビジネスで使う場合
書き出し文
- 謹啓 薄暑の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
- 拝啓 薄暑の候、貴社いよいよご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。
- 拝啓 薄暑の候、貴社いよいよご隆盛のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のお引き立てをいただき、ありがたく御礼申し上げます。
結び文
- 若葉が香るこの時期にあたり、貴社がさらに発展されることを心から願っております。
- 五月の晴れた空が輝くように、貴社の一層の発展を心から祈念しております。
- 真夏を思わせる季節になりましたが、貴社の皆様が更に繁栄されることを深く願っております。
目上の人に使う場合
書き出し文
- 謹啓 薄暑の候、〇〇様にはますますご壮健のことと拝察いたしお慶び申し上げます。
- 拝啓 薄暑の候、皆様にはますますご清祥のことと存じます。
- 拝啓 薄暑の候、御一同様におかれましては更なるご活躍の由、お喜び申し上げます。
結び文
- 次第に暖かい日が増えて参りました。どうかご自愛くださいまして、体調管理には十分ご注意ください。
- 夏の訪れが日に日に近づいております。〇〇様がこれからも益々輝かしい成果を達成されることを心より願っております。
- 春の終わりと夏の始まりが重なるこの時期、皆様方のさらなる繁栄を心からお祈りしております。
親しい人に使う場合
書き出し文
- 鯉のぼりが空に舞う、広大な空が広がる時期になりました。○○様は、このような季節をどのようにお過ごしでしょうか。
- 木々が緑豊かに輝く、美しい季節です。○○様におかれましては、引き続きご活躍されていることと思います。
- 心地よい風が吹く季節になり、新鮮な空気を感じることができます。この時期、○○様はいかがお過ごしでしょうか。
結び文
- 紫陽花が美しく咲き誇る季節が到来しました。どうかこれからも健康でいらっしゃいますように。
- まだたまに寒さを感じる日がありますので、どうか風邪など召しませんようご自愛ください。
- 山々が新緑で輝くこの時期に、〇〇様もますますご健康でお過ごしいただけますよう願っております。
結び文とは?
ビジネス関係の文章であれば、「今後も変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます」や「ご厚情を賜り、誠にありがとうございます」などの定型文がありますが、文章の冒頭に時候の挨拶を使った場合は、結び文も季節にちなんだ言葉を入れると統一感が出ますよ。
ここでは、薄暑の候を時候の挨拶に使った時の結び文の例文をご紹介します。
- 風薫る新緑の時節、ますますのご発展をお祈り申し上げます。
- 爽やかな初夏のみぎり、皆様方のご無事息災を心よりお祈りいたします。
- 暑い季節になっていきますが、くれぐれもご自愛ください。
薄暑の候を使うときに注意すること

薄暑の候は漢語調と呼ばれる表現の一つで、時候の挨拶の中でも特に丁寧な言い方になります。
そのため、文章の冒頭に薄暑の候などの時候の挨拶を入れるだけで十分と思ってしまう方もいるかも知れません。
しかし、ビジネス文書(取引先や会社の上役などに送る手紙やはがき)や目上の人に送る手紙やはがきとしては、時候の挨拶が文章の最初になるのは丁寧さに欠けると言えます。
より丁寧にするには頭語を付けることが大切です。
頭語とは「拝啓」や「謹啓」などのことで、「拝啓 薄暑の候、~・・」とすることで、マナーとして問題のない文章の体裁になりますよ。
また、頭語を使った場合には必ず結語を使って下さい。
結語は文章の最後に入れるもので、「拝啓」や「謹啓」の結語は「敬具」や「敬白」、「拝啓」よりもさらに丁寧ないい方である「謹啓」の結語は「謹言」もしくは「謹白」になりますよ。
薄暑の候以外の5月の時候の挨拶はある?

近年は春が短く、あっという間に真夏のような天気が続く年が増えていますよね。
そのため、薄暑の候を使うタイミングがないということもあるでしょう。
そこで、薄暑の候以外に5月に使える時候の挨拶をご紹介します。
新緑の候
5月上旬から下旬に使える時候の挨拶になります。
若葉が芽吹き、町や風の香りが緑に包まれる時期という意味になりますよ。
日本は南北に長い地形のため、初夏の訪れは沖縄と北海道では違います。
沖縄では5月上旬はすでに真夏の天気ですし、北海道ではやっと桜が咲くタイミング。
そのため、薄暑の候と同様に手紙やはがきを送る地域の状況に合わせて使うのがよいかも知れませんね。
薫風の候
5月上旬から下旬に使える時候の挨拶になります。
若葉の香りがする初夏の風が吹く時期という意味になりますよ。
こちらも薄暑の候や新緑の候と同様に、手紙やはがきを送る地域の状況に合わせるのがよいでしょう。
立夏の候
例年5月5日頃から21日頃までに使える時候の挨拶になります。
立夏は二十四節気の一つで、夏の始まりを表す名称。
初夏にふさわしい言葉ですし、手紙やはがきを送る時の気候状況にも左右されないので、使いやすい時候の挨拶と言えるでしょう。
初夏の候
例年5月5日頃の立夏から、例年6月6日頃の芒種の前日まで使える時候の挨拶になります。
使える時期は薄暑の候と同じですが、夏の始めという意味なので、どのような状況でも使いやすい時候の挨拶と言えるでしょう。
Wordであいさつ文や定型文を挿入する方法
仕事上で取引先の相手にあいさつ文を送る、目上の人に手紙やはがきを出す時などに、「書き出しに悩んでしまい、なかなか作業が進まない」なんてことはよくあるのではないでしょうか。
そのような時はWordを利用してみましょう。
Wordにはあいさつ文のテンプレートがあるので、参考にすると作業が捗りやすくなりますよ。
ここではwordを使ったあいさつ文や定型文の挿入方法をご紹介します。
手順
①Wordを開きます
②挿入タブをクリックします
③テキストのところにある「あいさつ文」をクリックします
④あいさつ文の挿入を選びます
⑤何月のあいさつ文を作成するのか、最初に月を選びましょう
⑥月のあいさつ、安否のあいさつ、感謝のあいさつをそれぞれ選びます
⑦選んだら「OK」をクリックしてください
⑧Wordに選んだ文章が表示されます
ポイント
Wordではあいさつ文だけではなく、あいさつ文の後に続ける「起こし言葉」や「結び言葉」も選ぶことができますよ。
挿入タブ→テキストのあいさつ文をクリックした後、起こし言葉もしくは結び言葉を選んでください。
薄暑の候のまとめ
薄暑の候は、初夏の気配が感じられる5月上旬から6月上旬にかけての季節を指します。
読み方は「はくしょのこう」で、二十四節気の立夏から芒種の前日までがその期間。
旧暦の4月、新暦でいうと5~6月に相当し、「初夏になり少し汗ばむような季節」という意味を持っています。
手紙やはがきで使う際は、相手の地域の気候を考慮して、丁寧な挨拶文として活用しましょう。
爽やかな季節の移り変わりを感じさせる美しい表現ですね。
この記事のポイントをまとめますと
- 薄暑の候は5月上旬から6月上旬に使う時候の挨拶
- 読み方は「はくしょのこう」
- 旧暦の4月に相当し、新暦では5~6月
- 初夏のやわらかな暑さを意味する
- 二十四節気の立夏から芒種の前日までが期間
- 暑さが厳しくない初夏の気候を表す
- ビジネス文書では頭語として使う
- 結び文には季節にちなんだ言葉を入れる
- 文章冒頭での丁寧な挨拶として活用
- 薄暑の候以外にも5月には新緑の候、薫風の候などがある


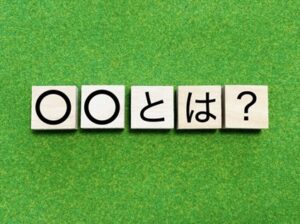

コメント