秋のお彼岸2025年はいつからいつまで?主な行事は?
お盆が終わって一ヵ月くらい過ぎると、秋のお彼岸がやってきます。
どちらもお墓参りを行うため、中には「お盆にお墓参りをしたのに、どうして秋のお彼岸でもお墓参りをするの?」と不思議に思う方もいるかも知れません。
言われてみたら確かに、お盆と秋のお彼岸は日付も近く、短期間にお墓参りに行く意味があるのなら知りたいですよね。
そこで今回は秋のお彼岸について調べてみました。
秋のお彼岸とはそもそもどのような由来があるのか、秋のお彼岸の日程の決め方や、2025年の秋のお彼岸はいつなのかなどの疑問を解説していきます。
秋のお彼岸2025年はいつからいつまで?
2025年
- 秋彼岸入り 9月19日(木)
- 中日(秋分の日・祝日) 9月22日(日)
- 秋彼岸明け 9月25日(水)
となっています。
秋のお彼岸(彼岸)の日程の決め方については、後述しているためここでは詳しくは省略しますが、秋分の日が9月23日(土曜)のため、その日を中日として前後3日間の合計7日間を秋のお彼岸とします。
なお、秋のお彼岸となる最初の日を彼岸入り(2025年であれば9月19日)、秋分の日を彼岸の中日、秋のお彼岸の最終日(2025年であれば9月25日)を彼岸明けと言います。
また、彼岸は年に2回あり、彼岸と言うと春彼岸のことを指す場合もあります。
この場合、秋のお彼岸は「後の彼岸」と呼ぶこともあります。
秋のお彼岸の日程の決め方は?
なぜなら、秋のお彼岸は秋分の日を中日として、前後3日間の合計7日間となるからです。
秋分の日は前年の2月に国立天文台が作成する「暦象年表」によって日付が公布され、それに基づいて閣議決定されます。
そのため、2年後、3年後の秋分の日はおよその推測はできても確定ではありません。
また、秋分の日は、天球の見かけ上の太陽の通り道(黄道)と、地球の赤道を天球まで伸ばした天の赤道が交わる点(秋分点)を太陽が通過する日である秋分日に基づいています。
秋分日と秋分の日は言葉がとても似ていますが、秋分の日は「祖先をうやまい、なくなった人々としのぶ」ことを趣旨とした国民の祝日となっています。
秋分日と秋分の日は同じ日ですが、その意味合いは異なり、秋のお彼岸はあくまでも秋分の日を中日にした7日間となっているため、国民の祝日である秋分の日が閣議決定された後に官報に掲載されて初めて、その年の秋のお彼岸の日程がわかります。
秋のお彼岸とは?
秋のお彼岸にはお墓参りをする風習が今も続いていますが、例年8月13~16日ころにあるお盆に対し、秋のお彼岸は例年9月19日~25日ころとなっており、1ヵ月程度の間隔しかない中で、「どうして2回もお墓参りをするの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
その理由は、お墓参りをする目的が違うからです。
お盆は盂蘭盆会という仏教行事と日本で浸透していた農耕儀礼、祖霊信仰が合わさり現在のような形になったと言われています。
一方で秋のお彼岸(彼岸)は「波羅蜜多(パーラミター)」が元となっており、僧侶が悟りを開くために行う修行です。
パーラミターの漢訳が至彼岸となることから、お彼岸と呼ばれるようになったと言われています。
お彼岸はなぜ7日間もあるのか?
「お彼岸」は、「到彼岸」という意味で、煩悩や迷いから悟りの開けた世界へ至ること、そのために行う修行を指します。
それは、仏教者たちの修行期間であり、悟りの境地にたどり着くために、迷いや煩悩を断ち切って悟りの境地に至るための修行です。
この修行は、「波羅蜜多」と呼ばれ、「六波羅蜜」と「十波羅蜜」の2種類があり、仏教の主要流派である大乗仏教では六波羅蜜が実践されています。
六波羅蜜は、6つの項目に分かれた修行で、お彼岸の7日間のうち、中日である春分の日と秋分の日は祖先を偲び、それ以外の6日はこの六波羅蜜を1日ひとつずつ修めるとされています。
それが、お彼岸が7日間ある理由です。
秋のお彼岸の風習や行事
彼岸(極楽浄土)と此岸(現世)が最も近くなるため、先祖供養を行うのがよいとされています。
とは言え、お墓のある地元から離れて、遠くで暮らしている方の場合、お盆とお正月の年に2回実家に帰省するのが精一杯で、秋のお彼岸や春彼岸にお墓参りに行くのは難しいこともあるのではないでしょうか。
その時は無理にお墓参りをする必要はありません。
自宅に仏壇があれば仏壇に手を合わせ、なければ心の中で手を合わせてもよいでしょう。
大切なのは祖先をうやまう気持ちです。
/
おはスカイ✈️
\#おは戦20920sn本日は秋のお彼岸の墓参りへ
ご先祖、祖父祖母にご挨拶
故人は生命の根元
根元を蔑ろにして
人生が栄えることはない枝葉の生活も
無残に枯れる墓を洗い経を唱え
手を合わすこうして身を清め
明日からの未来を
ご先祖に恥ないように
正しく生きることを誓う pic.twitter.com/7z1jSKlsK1— スルースカイ✈︎日曜休み@仏教好きなコピーライター (@ots3548) September 19, 2020
お彼岸の花について
菊には昔から邪気を祓う力があると言われており、彼岸だけではなく弔事にも使われますよね。
菊はハウス栽培されているので通年販売されていますが、本来の旬は9月から12月の秋から冬にかけてと言われているので、秋のお彼岸にはお勧めの花と言えるでしょう。
菊以外では、ユリやトルコキキョウ、カーネーションもお勧めです。
カーネーションと言えば、母の日に贈る花のイメージがありますが、母の日は1970年のアメリカで、亡き母への追悼の意味を込めて教会で白いカーネーションを配ったのが始まりと言われています。
そのため、彼岸にお供えする花としてカーネーションは人気があります。
カーネーションは赤のイメージがありますが、お墓や仏壇にお供えする場合は白や薄い色のものを選ぶとよいでしょう。
なお、秋のお彼岸であればケイトウもお勧めです。
ケイトウは鶏の頭に似ていることからその名前がつけられましたが、色のバリエーションが多く、茎が細いので他の花と一緒に飾りやすいなどの特徴があります。
彼岸花について
秋になると、田んぼのあぜ道や墓地の土手などから咲く真紅の花が見られます。
この花は「曼珠沙華」とも呼ばれ、『法華経』にも登場します。
彼岸花は不吉な花とされ、家に持ち帰ると火事になるという迷信があります。
しかし、この花は毒性が強く、農業や墓地の畦道で植えられるなど活用されてきたこともあります。
ただし、彼岸花は毒性が強いため、子供が手に取ってしまうと危険です。
だから、「持ち帰ると火事になる」と警告することになったのだと思われます。
春彼岸と秋のお彼岸との違い

彼岸には春彼岸と秋のお彼岸がありますが、この2つにはどのような違いがあるのでしょうか。
日付が違う
春彼岸は春分の日を中日とした前後3日間の合計7日間なのに対し、秋のお彼岸は秋分の日を中日にした前後7日間となっており、春彼岸は3月、秋のお彼岸は9月となっています。
お供え物が違う
春彼岸にはぼた餅、秋のお彼岸にはおはぎをお供えします。
ただし、この2つは実は同じ物であり、違うのは名前のみです。
ぼた餅は牡丹の咲く春にちなんで付けられ、おはぎは萩の花が咲く秋にちなんでいます。
なお、原料となる小豆の収穫時期が秋であるため、秋のお彼岸のおはぎは皮がやわらかい小豆をそのまま使ったつぶ餡を使うことが多く、収穫から時間が経っているため春彼岸のぼた餅は皮を取り除いてすりつぶしたこし餡を使っていることが多いと言われています。
お彼岸について

彼岸とは、サンスクリット語の波羅蜜多(パーラミター)の漢訳である「至彼岸」を略したものです。
彼岸は仏教の概念では、煩悩や欲から脱した悟りの境地、つまりは極楽浄土のことを指しています。
一方で、私達が暮らす世界は煩悩に溢れた此岸(しがん)と呼ばれます。
仏教の発祥国であるインドでは、彼岸の時期になると、僧侶は布施(ふせ)、持戒(じかい)、忍辱(にんにく)、精進(しょうじん)、禅定(ぜんじょう)、智慧(ちえ)の6つの修行を行い、これを六波羅蜜と言います。
修行が行われる期間は、彼岸があると言われている真西と此岸であるこの世がある真東が最も近づく日、春分の日と秋分の日を中日にした7日間になります。
これが日本に伝わると、先祖や故人の霊が暮らす彼岸と、私達の住む此岸の距離が最も近くなる彼岸にお墓参りをすることで、より丁寧な先祖供養になると考えられるようになりました。
なお、彼岸にお墓参りをするのは日本独自の風習であり、仏教の発祥国であるインドや中国では行われていません。
また、彼岸の由来には、日本では仏教が伝わる以前より太陽信仰の「日願」が根付いており、この日願と彼岸が結び付いて今のような形になったという説もあります。
まとめ
2025年の秋のお彼岸は、9月20日から9月26日となっています。
秋のお彼岸は秋分の日を中日とした前後3日間の合計7日のことを言い、秋分の日は前年の2月に国立天文台が暦象年表に掲載後、閣議により決定されるため、2~3年後以降は現時点ではわかりませんが、毎年9月22日~23日となっているので、秋のお彼岸もその前後になります。
なお、彼岸には春彼岸もありますが、意味や由来などは秋のお彼岸と同じで、違うのは日付とお供え物(春彼岸はぼた餅、秋のお彼岸はおはぎ)くらいです。





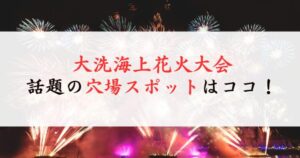
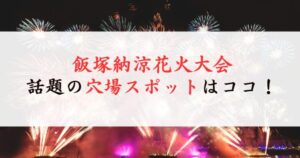
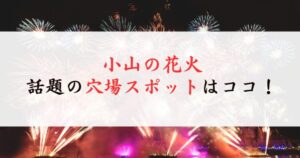
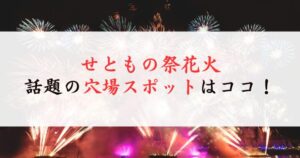
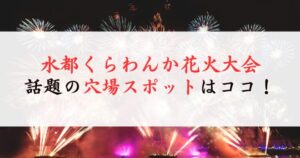
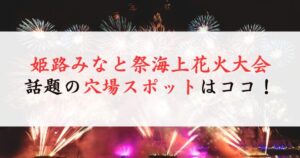
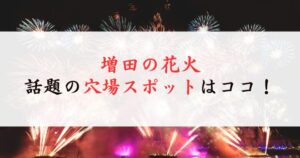
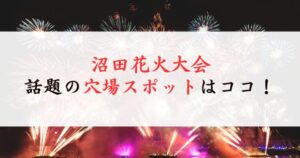
コメント