彼岸花の花言葉は?不思議な花、彼岸花の豆知識
彼岸花は、お彼岸の頃(9月中旬ごろ)に赤い花をつけるため、お彼岸の頃に咲く花として親しまれています。
田んぼの畦道などに群生し、なんとなく秋の訪れを感じさせる風物詩。
また、曼珠沙華(マンジュシャゲ)とも呼ばれ、サンスクリット語で「天界に咲く花」の意味で、おめでたい兆しとされています。
開花期間が、1週間ほどなのに、秋の彼岸と時を同じくするかのように開花する彼岸花は、あの世とこの世が最も通じやすい時期に咲く花でもあります。
そのな彼岸花の神秘性と花言葉などや成長サイクルなどをまとめてみました。
彼岸花の花言葉は何?
彼岸花には、鮮やかな赤だけでなく白や黄色いものもあります。
ここでは、代表的な赤い彼岸花と白い彼岸花の花言葉をご紹介します。
赤い彼岸花の花言葉
- 「情熱」
- 「独立」
- 「再会」
- 「あきらめ」
- 「悲しい思い出」
- 「想うはあなた一人」
- 「また会う日を楽しみに」
秋の花として親しまれる彼岸花
別名はリコリスや曼珠沙華「彼岸」の時期に咲く花として知られ、開花期は9月。
赤の彼岸花の花言葉は、
情熱/独立/再開/悲しい思い出不吉な花とも言われる理由が解りません。
呼び名は曼珠沙華が好き。
まるで秋の紅葉のようです。 pic.twitter.com/offlQGkr8v— にゃおねこ (@nyaonenko327) August 26, 2022
白い彼岸花の花言葉
- 「また会う日を楽しみに」
- 「想うはあなた」
などありますが、一般的な彼岸花の花言葉は、「悲しい思い出」だそうです。
墓前に咲いた彼岸花を眺めながら、亡き人を偲んで悲しみがよみがえる、そういう想いからつけられたのではないでしょうか。
【白彼岸花】
「天界に咲く花」という意味を表す花。
「地獄花」や「死人花」という呼び名も存在する花です。
花言葉は『また会う日を楽しみに』 pic.twitter.com/kxcuvNLgZF— 世界の花図鑑 (@wld_hana) September 18, 2020
彼岸花には、色々な呼び名があります。
曼珠沙華
「曼珠沙華(まんじゅしゃげ/かんじゅしゃか)」は、サンスクリット語で天界に咲く花という意味。
おめでたい事が起こる兆しに赤い花が天から降ってくる、という仏教の経典から来ています。
葉見ず花見ず
花のある時期には葉がなく、葉のある時期には花がないという特徴から、「葉見ず花見ず(はみずはなみず)」と呼ばれています。
死人花・幽霊花
お彼岸の頃に咲くから、このような呼び名になったと言われています。
毒花・痺れ花
彼岸花にはアルカロイドという毒があるため、「毒花(どくばな)」「痺れ花(しびればな)」などと呼ばれています。
その反面、でんぷんを多く含んでいるため食用可能でして、毒は水にさらすと抜けるため、昔は飢餓に苦しい時に毒を抜いて食用にすることもあったそうです。
彼岸花の不思議
彼岸花には、50cmくらいにすらっと伸びた茎に鮮やかな花だけがついていて、葉っぱが全く見あたりません。これも妖しく見える原因のひとつですが、実は、花が終わってから葉が出てくるのです。
しかも、普通の植物とは逆のサイクルで!
ちなみに、冬になると、多くの植物は枯れますが、彼岸花は、たわわに繁った葉のままで冬を越します。
ということで、彼岸花は花が咲き終わってから葉が出てくるので「葉無し草」とも言われるとか・・・。
彼岸花は不吉な花?その由来や特徴とは?

秋の彼岸に赤い花を咲かせることから、その名がついたと言われる彼岸花。
彼岸花は中国が原産ですが、稲が伝わった時に球根が混ざっていて、その際に一緒に日本に伝わったと言われています。
彼岸花は別名「曼珠沙華」と言いますが、これはインドの仏教における天界に咲く四華の一つとされているのが由来です。
彼岸花には地域ごとの呼び名も含めると、実に1,000以上の別名があると言われています。
さらに、彼岸花は種子を持たず球根で増えていくこと、秋彼岸の時期になるとその年の天候がどれだけ荒れてもぴったりに咲くこと、血しぶきを思わせる赤い花を咲かせること、墓地の周辺によく咲いていることから、日本では不気味な存在として昔から忌み嫌われていました。
しかし、彼岸花はとても生命力の強い花で、暑さや乾燥にも負けずに花を咲かせることができます。
また、強い毒を持っているため、昔は畑の周りや墓地の周辺に植えて、ねずみやもぐらを駆除していたようです。
墓地の近くに多く咲いているのは、当時は埋葬が主流だったため、死体を動物が荒らさないようにするためです。
なお、彼岸花の毒は水に晒すと抜けることから、食糧危機の時にはあちこちに生えている彼岸花を食料代わりにしていたという記録もあります。
なぜ春分の日と秋分の日に墓参りをするの?
この日は昼と夜の長さがほぼ等しくなるので、太陽が真西に沈みます。
極楽浄土(あの世)は西方にあるとされているため、あの世とこの世が交わる日と考えられていました。
極楽浄土と最も心が通じやすい日なので、先祖の供養をするためにお墓参りをするようになりました。

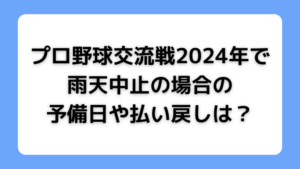






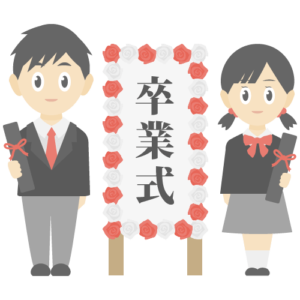
コメント