帰忌日に避けたほうがいいことは?
「黒」や「忌」という漢字が入っている日というのはそれだけでどうしてもマイナスイメージが強くついてしまいますが、はたして今回紹介する帰忌日は何に該当するのでしょうか。
そもそもこの帰忌日の意味や由来、読み方はどうなっているのか、2025年だといつになるのかも詳しく解説してまいります。
凶日だったとしても、どのような凶日なのかもしっかりと見ていきましょう。
帰忌日とは?
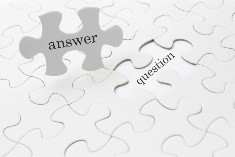
帰忌日とは、天棓星(てんぼうせい)という精が地上に降りてきて人が帰宅するのを妨害する凶日です。
いわゆる帰忌という単語が天棓星の精という意味があるので、この言葉を覚えれば結びつけられるでしょう。
ただし、由来については納得できる情報がありませんでした。
Wiki(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%A6%E6%B3%A8%E4%B8%8B%E6%AE%B5#%E9%AC%BC%E5%AE%BF%E6%97%A5)などには「正倉院に納められている具注暦にも記載されている」という情報がありますが、他のサイトでアップされている情報もほぼこれ一択なので、これ以上由来についてネット上で探るのは難しい状態になっています。
つまり、奈良時代からこの帰忌日というのは定められていたようで夜空の星の精という考え方が古代からあったのでしょう。
帰忌日はどのように誕生したのかの推察!
こちらの「Weblio辞書(https://www.weblio.jp/content/%E5%B8%B0%E5%BF%8C%E6%97%A5)」には「陰陽道で、旅行・帰宅・結婚などを忌む日」と記載されていますが、陰陽道とのつながりがこれ以外に見つかりませんでした。
なので陰陽道以外のつながりも推察したいと思います。
個人的に二十八宿に関わりがあるかもしれないと思って調べて見ましたが、どうやらつながりはなさそうなので、また別のところが発祥なのでしょう。
占星術が発祥と考えると、当時の日本の事を考えればインド占星術や中国の天文学などからきていると思われます。
日本にも占星術はありますが、インド占星術や道教由来の天体神信仰などが混ざってできた占星術が本格的に誕生したのは調べた限りでは平安時代なので、奈良時代に日本人が考えて帰忌日を設定したとは考えにくいのです。
おそらく中国やインドの占星術を元にしてそこで陰陽道とミックスされて帰忌日は誕生したんだと思います。
帰忌日の読み方

帰忌日は色んな読み方があるのですが、おそらく全部単語登録されていません。
答えは「きこにち」「きしにち」「きこび」「きこじつ」「きいみび」となりますが、Windows10の筆者のパソコンで全部入力しても帰忌日という単語にはなりませんでした。
現在のカレンダーでは「きいみ」と記載されるとのことですが、やはりこれでも変換不可能です。
本格的にこの凶日をチェックするという人は単語帳に登録して活用してください。
やはり凶日にも色々とありますが、仏滅や赤口といった六曜以外の凶日はかなりマイナーなので、一発変換できるのは稀なのでしょう。
帰忌日以外にも十死日や受死日という凶日がありますが、これも一発変換できませんでした。
2025年の帰忌日はいつ?
| 日にち | 節月 | 六曜 | 十二直 | 干支の日 |
| 2025年1月3日 | 11月 | 友引 | 満 | 寅の日 |
| 2025年1月13日 | 12月 | 友引 | 閉 | 子の日 |
| 2025年1月25日 | 12月 | 友引 | 閉 | 子の日 |
| 2025年2月7日 | 1月 | 先負 | 閉 | 丑の日 |
| 2025年2月19日 | 1月 | 仏滅 | 閉 | 丑の日 |
| 2025年3月2日 | 1月 | 仏滅 | 閉 | 丑の日 |
| 2025年3月15日 | 2月 | 先勝 | 閉 | 寅の日 |
| 2025年3月27日 | 2月 | 先勝 | 閉 | 寅の日 |
| 2025年4月6日 | 3月 | 大安 | 成 | 子の日 |
| 2025年4月18日 | 3月 | 赤口 | 成 | 子の日 |
| 2025年4月30日 | 3月 | 赤口 | 成 | 子の日 |
| 2025年5月13日 | 4月 | 先負 | 成 | 丑の日 |
| 2025年5月25日 | 4月 | 先負 | 成 | 丑の日 |
| 2025年6月7日 | 5月 | 赤口 | 成 | 寅の日 |
| 2025年6月19日 | 5月 | 赤口 | 成 | 寅の日 |
| 2025年7月1日 | 5月 | 赤口 | 成 | 寅の日 |
| 2025年7月11日 | 6月 | 大安 | 執 | 子の日 |
| 2025年7月23日 | 6月 | 大安 | 執 | 子の日 |
| 2025年8月4日 | 6月 | 先勝 | 執 | 子の日 |
| 2025年8月17日 | 7月 | 友引 | 執 | 丑の日 |
| 2025年8月29日 | 7月 | 友引 | 執 | 丑の日 |
| 2025年9月11日 | 8月 | 仏滅 | 執 | 寅の日 |
| 2025年9月23日 | 8月 | 仏滅 | 執 | 寅の日 |
| 2025年10月5日 | 8月 | 大安 | 執 | 寅の日 |
| 2025年10月15日 | 9月 | 先負 | 満 | 子の日 |
| 2025年10月27日 | 9月 | 先負 | 満 | 子の日 |
| 2025年11月9日 | 10月 | 赤口 | 満 | 丑の日 |
| 2025年11月21日 | 10月 | 赤口 | 満 | 丑の日 |
| 2025年12月3日 | 10月 | 先勝 | 満 | 丑の日 |
| 2025年12月16日 | 11月 | 友引 | 満 | 寅の日 |
| 2025年12月28日 | 11月 | 友引 | 満 | 寅の日 |
参考URL: https://rekichu.com/senjitsu/?y=2025
基本的に凶日や吉日を設定するときは高確率で日の干支と二十四節気の節気から決めることが多いのですが、この帰忌日もその例に漏れずこの2つによって定められております。
具体的には1月・4月・7月・10月は丑の日、2月・5月・8月・11月は寅の日、3月・6月・9月・12月は子の日というルールです。
ザックリと12日に1回ほどこの帰忌日があるということなので、365日を12で割ると単純計算で30回発生するということもわかります。
帰忌日に避けたほうがいいことは?

帰忌日に避けた方がよいとされる事柄は「旅行」「里帰り」「結婚」「転居」です。
「凶星の精が人家の門戸をふさいで家には入れない日」なので、大々的な帰宅が必要な事柄や帰ってくるという事がNGとなっている事柄との相性が悪いのだと思います。
また、お金の貸し借りやモノの貸し借りもNGとするという説もあるので注意しましょう。
お金が返ってくるとかモノが返却されるという行為もNGとして引っかかるようです。
旅行の場合はこの帰忌日と帰宅する日が一致しなければ個人的には問題ないと考えています。
この転居や引っ越しとも相性が悪い凶日とされていますので、引っ越しをするタイミングには注意した方が良いかもしれません。
縁起の良くない日はいつ?
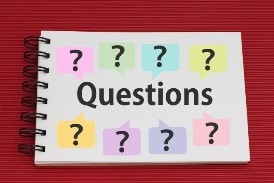
縁起のよくない日というのは実は探せば探すほど出てくるので、どこまでのラインを自分で引くのかが大切になります。
六曜しか気にしないという人は仏滅や赤口が縁起の悪い日となりますので、それらを避ければ良いですし、受死日や十死日や不成就日などの縁起がよくない日が気になるのならばそれらもチェックして意識すれば良いのです。
ただし、縁起が悪い日を大量に調べていくと、ほぼすべての日が何らかの縁起が悪い日となってしまいますので行動できなくなってしまいます。
このように凶日だけをひたすらピックアップするとカレンダーが埋め尽くされてしまう状態になってしまうので、できる限り絞り込むことが大切になります。
引っ越しや転居に帰忌日はNGだけどこれは守るべき?
基本的に凶日や吉日というのは科学的根拠がほとんど無い迷信めいたものとなっております。
なので、自分自身のモチベーションアップに利用すべきモノでありますし、その地方事のルールや風習に即した動きをするだけでも十分なのです。
確かに、帰忌日は引っ越しや転居にNGと言われていますが、はっきり言って知名度がものすごく低いので仮に帰忌日に引っ越しや転居をしても引っ越し先のご近所から嫌な顔をされることは非常に低いでしょう。
それよりも三隣亡という建築や引っ越しとNGとされており、今でも建築業界では気にしている人達が多い凶日を避けた方が良いのです。
引っ越しや地鎮祭に六曜を気にする人も多いのですが、それよりも三隣亡であるかどうかを気にする人は今の建築業界にも多いので、引っ越しや転居をするときは個人的に帰忌日よりも三隣亡かどうかをチェックした方が良いと思います。
ちなみに、引っ越しにかかる費用は忙しさや混み合う時季によってだいぶ変わりますので、あえて仏滅や赤口といったあまり予約されにくい日を活用するのも、お得に引っ越し業者を使うテクニックとなっております。
帰忌日のまとめ
以上、いかがだったでしょうか。
今回は帰忌日について詳しく解説いたしました。
帰忌日は帰宅や帰ってくるというワードが凶になってしまうという面白い凶日です。
1年にだいたい30回ほど存在する凶日ではありますが、不成就日や受死日ほど極悪な凶日ではありませんので、そこまで強く意識する必要は個人的には無いと思われます。
それよりも凶日を意識しすぎて自分の行動が阻害される方が問題なので、意識するのもほどほどにしましょう。










コメント