夏土用とは何か、なんとなく聞いたことはあるけれど、実はよく知らないという方も多いのではないでしょうか。土用の丑の日にうなぎを食べる理由や、いつからいつまでの期間なのかなど、気になることがたくさんありますよね。この記事では、夏土用とはどんな意味があるのか、過ごし方のポイントや昔からの風習まで、やさしく丁寧にご紹介していきます。詳しくは本文で紹介します。
- 夏土用とはどんな時期なのか、その意味や由来がわかる
- 2025年の夏土用の期間や土用の丑の日がいつかの目安がつく
- なぜ夏にうなぎを食べるのか、その理由や歴史が納得できる
- 土用期間に気をつけたい過ごし方や風習について知ることができる
夏土用とは?
夏土用とは、季節の変わり目にあたる「土用(どよう)」のうち、夏の終わりから秋の始まりにかけての期間を指します。一般的には「土用の丑の日」にうなぎを食べる習慣が有名なため、土用といえば夏を思い浮かべる方が多いかもしれません。
なぜ「夏土用」が特別に知られているのか
夏土用が他の土用(春・秋・冬)に比べて注目されるのは、やはり「土用の丑の日」の存在が大きいです。この日は夏バテ防止のために栄養価の高いうなぎを食べる風習が根づいており、毎年ニュースや広告でも多く取り上げられます。そのため、「土用=夏」と思っている人も多いのですが、実際には土用は年に4回、各季節の変わり目に存在しています。
土用の起源と「陰陽五行説」との関係
土用の由来は、中国の古代思想「陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)」にあります。この思想では、自然界のあらゆるものを「木・火・土・金・水」の5つの要素(五行)に分類し、それぞれを季節に当てはめています。春は木気(もっき)、夏は火気(かき)、秋は金気(きんき)、冬は水気(すいき)とされる中で、残った「土気(どき)」が割り当てられるのが、季節と季節の間にあたる「土用」なのです。
つまり、土用とは単なる「夏の暑い時期」ではなく、「次の季節に切り替わる前の調整期間」と考えるとわかりやすいです。特に夏土用は、暑さのピークと重なるため体調を崩しやすく、古くから「体をいたわるべき時期」とされてきました。
夏土用の期間と過ごし方
夏土用は、毎年7月20日前後から始まり、約18日間続きます。この期間の最終日は「立秋(りっしゅう)」の前日であり、暦の上では夏の終わりとされています。
この時期は、気温や湿度が高く、体力を消耗しやすいのが特徴です。そのため、うなぎをはじめとする栄養価の高い食べ物を摂って体力を補ったり、水分補給をしっかり行うなど、体調管理がとても大切です。また、古くから土用の間には「土いじり」や「引っ越し」など、土を動かす行為を避けたほうがよいとされてきました。これは「土の気」が乱れやすいと考えられていたためで、今でも一部ではこうした習わしを守る地域もあります。
季節を感じる大切なタイミングとして
夏土用は、単に「うなぎを食べる時期」というだけではなく、自然のリズムや人の体調を整える節目の時期でもあります。昔の人は、季節の変化に敏感で、それに合わせた生活の工夫をしてきました。現代においても、このような知恵を取り入れることで、心身ともに健やかに過ごす手助けになるでしょう。
夏の土用は、季節の移ろいを感じながら、自分の体と向き合う貴重なタイミングでもあるのです。
2025年の夏土用はいつからいつまで?
2025年の夏土用は、7月19日(土)から8月6日(水)までの期間です。この期間は、一年のうちでも特に暑さが厳しい時期とされ、体調管理や食事に注意が必要とされる伝統的な暦の一部です。夏土用を正しく理解することで、日々の暮らしに役立てることができます。
夏土用の由来と意味
「土用(どよう)」とは、古代中国の五行思想に基づく暦の区分の一つで、季節の変わり目に当たる期間を指します。具体的には、春・夏・秋・冬それぞれの季節の終わり、次の季節に移る前の約18日間が「土用」です。夏の土用は立秋(2025年は8月7日)の直前、つまり7月中旬から8月初旬にあたります。
この時期は、季節が夏から秋へと移ろうとする不安定な時期であり、昔から体調を崩しやすいとされてきました。そのため、「土用の時期には無理をせず、身体を労わることが大切」とされてきたのです。
2025年の夏土用と「丑の日」
2025年の夏土用は7月19日から始まり、8月6日まで続きます。この間には「土用の丑の日(うしのひ)」が2回あり、1回目が7月19日(土)、2回目が7月31日(木)です。
「土用の丑の日」とは、土用の期間中に巡ってくる十二支の「丑(うし)」の日を指します。この日にうなぎを食べる習慣は江戸時代に広まったもので、夏バテ防止に栄養価の高いうなぎを食べるという生活の知恵から生まれました。
| カテゴリー | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 土用の期間 | 夏土用 | 2025年7月19日~8月6日 |
| 土用の丑の日 | 1回目 | 2025年7月19日(土) |
| 土用の丑の日 | 2回目(二の丑) | 2025年7月31日(木) |
現代の暦とのズレとその理由
夏土用は「旧暦」の暦法や中国の気候を元にしているため、現在の日本の季節感とは少しずれがあります。二十四節気は中国の黄河流域の気候に基づいて作られており、日本列島の四季の移り変わりとは完全には一致しません。たとえば、「立秋」はまだ暑さが厳しい8月上旬にあたるため、「秋」と言われても実感が湧きにくいのです。
それでも二十四節気や土用は、自然の流れや生活リズムを見直す良いきっかけになります。古くからの暦の知恵を、現代の暮らしに合わせて活用することが求められています。
夏土用を健康に過ごすために
夏土用は暑さがピークを迎える時期でもあり、体力が奪われやすくなります。この期間は無理をせず、栄養バランスの良い食事や十分な睡眠を心がけることが大切です。冷房の使いすぎや水分不足にも注意し、適度な運動や休息で体調を整えましょう。
また、土用の期間は土を動かす作業(庭の手入れや工事など)は避けた方が良いとされる伝承もあります。これは「土用殺(どようさつ)」という考え方に基づくもので、土をつかさどる神様の領域を侵さないようにするための配慮とされています。
暦の知恵を暮らしに活かす
夏土用は、ただ暑い時期を指すだけでなく、昔の人々が自然と向き合いながら暮らしてきた知恵の一つです。今の私たちも、その考え方を大切にしながら、心と体のバランスを保ち、季節の変わり目を穏やかに過ごしたいものです。2025年の夏土用も、無理をせず自分をいたわる期間として活用しましょう。

夏土用の風習や行事は?
夏土用には、暑さへの備えとしてさまざまな風習や生活の知恵が受け継がれています。特に「土用の虫干し」や「梅干しの天日干し」は、昔から続く季節の節目ならではの習慣です。これらは単なる行事ではなく、健康と暮らしを守るための工夫が詰まった大切な風習といえるでしょう。
湿気を追い出す「土用の虫干し」
夏土用の代表的な風習のひとつが「虫干し」です。これは梅雨が明けて本格的な暑さが始まるこの時期に、着物や書物、家具などを風通しのよい場所で陰干しして湿気を取るという昔ながらの知恵です。湿気の多い日本の夏では、カビや害虫の発生を防ぐために理にかなった習慣でした。
現代では、着物のある家庭は少なくなっていますが、洋服や寝具、本、革製品など、しまい込んでいる物の手入れとして応用できます。とくにクローゼットの中にある季節外れの衣類や、普段あまり使わない礼服などを取り出し、風を通しておくことはとても効果的です。これにより、カビや臭いの予防になるだけでなく、持ち物の状態を見直す良い機会にもなります。
梅干しづくりの仕上げ「天日干し」
もうひとつの夏土用の行事としてよく知られているのが、梅干しの天日干しです。梅干しは、梅雨の時期に漬け込み、土用の頃に晴天が続く日を選んで、3日ほど天日に干す「土用干し」という作業を行います。これは保存性を高めるだけでなく、梅の旨みや酸味を引き立て、風味を整えるために欠かせない工程です。
梅干しは日本の伝統的な保存食であり、暑さに負けない体づくりにも一役買ってくれます。近年では市販品を利用する人が多いものの、自家製の梅干しを仕込む家庭では、夏土用の天日干しが一種の行事として楽しまれています。

暮らしの中に活かせる夏土用の知恵
こうした夏土用の風習には、「湿気を取り除く」「食べ物を長持ちさせる」といった、夏の不快な気候を乗り切るための工夫が込められています。エアコンや除湿器などが普及した現代でも、自然の力を利用した虫干しや天日干しは、環境にやさしく、身の回りを整える心地よい習慣といえるでしょう。
| カテゴリー | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 住まいの工夫 | 土用の虫干し | 着物や衣類、本などを陰干しして湿気を追い出す習慣 |
| 食の知恵 | 梅干しの天日干し | 漬けた梅を3日ほど日光に当て、保存性と味を高める工程 |
季節の節目として意識することが大切
夏土用の風習は、ただ昔の名残として残っているわけではなく、今の暮らしにも取り入れやすいヒントが詰まっています。日常の中で立ち止まり、家の中を見直したり、手間をかけて食べ物を仕込んだりすることで、心にもゆとりが生まれます。季節の変わり目を大切にする日本の文化が息づく、心豊かな風習といえるでしょう。
夏土用と「土用の丑の日」との関係
土用の丑の日とは「土用期間の丑の日」のこと
「土用の丑の日」と聞くと、多くの人が夏にうなぎを食べる習慣を思い浮かべるのではないでしょうか。しかし実は、「土用の丑の日」は夏だけの特別な日ではありません。四季すべてに「土用」は存在し、それぞれの季節に「丑の日」もあるため、年に何度も「土用の丑の日」があるのです。
土用とは、季節の変わり目にあたる約18日間の期間を指します。これは、古代中国の五行思想(木・火・土・金・水)をもとに、日本でも取り入れられた暦の考え方です。春・夏・秋・冬の各季節が終わる直前に「土」の気が強くなる期間があるとされ、それが「土用」と呼ばれます。そして「丑の日」とは、昔の暦で日にちを十二支(子、丑、寅、卯…)で数えていたことから、土用期間中の「丑」にあたる日を指すのです。
なぜ夏の土用が特別視されるのか
では、なぜ「夏土用の丑の日」だけがこれほど知られているのでしょうか。それは、夏の土用が一年の中でも特に体に負担がかかりやすい時期であるからです。梅雨明け後の高温多湿な気候により、食欲不振や倦怠感など、いわゆる「夏バテ」が起きやすくなります。そのため昔の人々は、この時期を健康に乗り越えるために、食事や養生に特に気を配っていました。
その一環として定着したのが、「土用の丑の日にうなぎを食べる」という風習です。うなぎは栄養価が高く、特にビタミンAやB群、良質な脂質を多く含むことから、疲労回復やスタミナ補給に効果があるとされてきました。このような背景から、夏の「土用の丑の日」は、ほかの季節に比べて特別視され、現代に至るまで広く知られるようになったのです。
古来の夏土用の過ごし方
うなぎ以外にも、夏土用にはさまざまな風習がありました。たとえば、柿の葉を入れた薬草風呂に入ることで体の熱を冷まし、免疫力を高めるといった工夫がされていました。また、体調管理の一環としてお灸を据える人も多く、東洋医学に基づく養生が暮らしの中に根づいていたことがわかります。こうした伝統的な方法は、現代においても健康維持のヒントとして見直されつつあります。
| カテゴリー | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 土用 | 時期 | 季節の変わり目にある約18日間 |
| 丑の日 | 十二支のひとつ | 土用期間中の「丑」に当たる日 |
| 夏土用 | 健康管理の重要性 | 高温多湿で体力を消耗しやすい時期 |
| 風習 | 養生や食事の工夫 | うなぎ、薬草風呂、お灸などが伝統的 |
季節を意識した暮らしの知恵として
「夏土用の丑の日」は、単なる年中行事ではなく、昔の人々が季節の移り変わりに敏感に反応し、体調管理に努めていた証でもあります。土用や丑の日の意味を知ることで、食や暮らしに対する意識も少し変わるかもしれません。現代の私たちも、この伝統的な知恵を暮らしに取り入れることで、より健やかな毎日を過ごすヒントが得られるのではないでしょうか。

土用の丑の日に鰻を食べる理由は?
土用の丑の日に鰻を食べる習慣は、夏の暑さを乗り切る知恵として今も受け継がれています。栄養価の高い鰻を食べて体力をつけようという考えが根底にありますが、実はこの習慣には意外な歴史的背景があります。
夏バテ対策としての鰻の栄養価
結論から言えば、土用の丑の日に鰻を食べる理由は、栄養をしっかり摂って夏バテを防ぐためです。鰻にはビタミンAやB群、D、E、カルシウム、鉄分など、体に必要な栄養素が豊富に含まれており、特にビタミンB1は疲労回復に効果的です。暑さで食欲が落ちがちな時期に、こうした栄養が摂れる鰻はとても理にかなった食べ物といえます。
実は夏が旬ではなかった鰻
しかしながら、鰻の本来の旬は夏ではなく、秋から冬にかけての時期です。冬眠に備えて脂がのる晩秋〜初冬が一番おいしい時期とされています。そのため、夏場は鰻の売れ行きが落ち込み、販売業者にとっては悩みの種でした。
土用の丑の日と平賀源内の発想
そんな中、江戸時代の学者であり発明家でもある平賀源内が登場します。ある鰻屋が夏に鰻が売れないと相談したところ、源内は「“本日は土用の丑の日”と書いた貼り紙を店先に出してはどうか」と提案しました。当時、「土用の丑の日には“う”のつく食べ物を食べるとよい」との言い伝えがありました。鰻は「う」のつく食べ物としてぴったりだったのです。
この貼り紙は今で言うキャッチコピーのようなもので、人々の注目を集め、実際に鰻は飛ぶように売れたと伝えられています。この出来事をきっかけに、土用の丑の日に鰻を食べるという文化が定着していきました。
習慣と知恵が結びついた日本独自の文化
このように、土用の丑の日の鰻は単なる風習ではなく、栄養面での理にかなった食文化であり、さらに商業的な工夫が重なった結果でもあります。江戸時代の知恵と現代の食文化が結びついた、非常にユニークな習慣といえるでしょう。
体調を崩しやすい季節だからこそ、栄養を意識した食事を取ることは大切です。土用の丑の日に鰻を食べるという文化には、昔の人々の暮らしの知恵と工夫がしっかりと息づいているのです。
土用にしてはいけないこと
土を動かす行為は控えるのが基本
土用の期間中には、「土を動かすことを避けるべき」とされています。これは、古来より土の神様とされる「土公神(どくじん)」が地中に宿ると考えられていたためです。この時期に土を掘ったり耕したりすると、その神様の怒りを買い、不運を招くと信じられてきました。こうした信仰は、農耕社会で自然を敬いながら暮らしてきた日本人の暮らしに根付いています。
たとえば、家庭菜園で畑を耕したり、庭の植え替えを行ったりすることも避けられることがあります。実際に、建設業界でも土用の期間は新築の基礎工事を見送る業者があるほどです。土木工事のような大がかりな作業だけでなく、個人レベルのガーデニングや鉢植えの植え替えも、できれば控えるのが安心でしょう。
土用は「季節の変わり目」だからこそ無理をしない
土用は年に4回、春・夏・秋・冬の季節が切り替わる直前に訪れる期間です。この時期は気候が不安定になりやすく、体調を崩しやすい時期でもあります。そのため、「無理をせず、心身を休めることが大切」とも言われています。
たとえば、土用の丑の日にうなぎを食べる習慣があるのも、滋養をつけて暑さに備えるという考えからきています。つまり、土用は体に無理をさせるのではなく、ゆっくりと過ごして次の季節に備えるための準備期間とも言えるのです。
引っ越しや転職など「大きな変化」は避けるべき理由
土用の期間は、土の上にある運気も不安定になりやすいとされます。そのため、人生に大きな影響を与えるような出来事――たとえば引っ越しや結婚、転職といったことは、この期間中には行わない方がよいとされています。
特に引っ越しや家の建築など、土地に深く関わる行動は、土公神への配慮から慎むべきとされてきました。また、転職や結婚のように生活が一変するような出来事も、安定した運気の時期に行うほうが良いと考える人も少なくありません。精神的にも不安定になりがちなこの時期は、慎重な判断が求められるのです。
暦と向き合い、無理のない暮らしを心がける
結論として、土用の期間は「無理をせず、変化を控え、静かに過ごす」ことが良いとされています。これは古くからの習わしではありますが、現代においても、季節の変わり目に体をいたわり、生活を見直す機会として活かすことができます。
信仰に基づく行動だけでなく、気候や体調の変化に合わせた暮らしをすることが、心と体のバランスを保つためには大切です。土用の意味を知り、無理のないペースで日々を過ごすことが、結果として健やかな生活につながっていくのではないでしょうか。

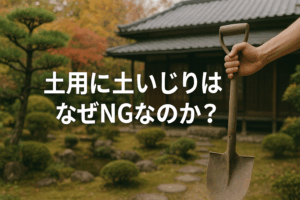

土用殺の意味とは?凶方位とされる理由と向き合い方
土用殺とは何か?その意味
土用殺(どようさつ)とは、土用の期間中に避けるべきとされる「凶方位(運気を下げる方向)」のことを指します。とくに旅行や引っ越し、長距離の移動といった行動を取る際に、この方角を避けた方が良いとされており、昔から風水や陰陽道などで大切に扱われてきました。結論として、土用殺は特定の期間・方角に対して注意を促すものであり、「行動を控える時期と方位を知るための指標」として活用するのが良いとされています。
なぜ土用殺が存在するのか?理由と背景
土用の期間とは、立春・立夏・立秋・立冬の直前、各季節の変わり目にあたる約18日間のことを指します。この期間は「土の気」が最も強まる時期とされ、風水や暦の考え方では、この時期に土を動かす(例:引っ越し、旅行、建築など)行動を避けるべきとされています。
特に夏の土用は「丑の日」が含まれていることで有名ですが、この時期に向かって良くないとされる方角が「土用殺」として定められています。これは十干や十二支によって毎回異なりますが、たとえば夏土用では「未(ひつじ)」が干支となるため、未の方位である南西が土用殺にあたります。
実生活での影響と避け方の具体例
例えば、家族旅行を計画している際に、夏土用の期間に南西の地域へ旅行に行く計画があったとします。この場合、土用殺の考え方では「凶方位に向かうと、体調不良やトラブルに見舞われる恐れがある」とされているため、できれば方角をずらしたり、旅行の時期を変更したりするのがよいとされています。
また、「どうしてもその方角に行かないといけない」という場合には、長期滞在を避けたり、現地で慎重に行動したりといった心がけを持つことでリスクを和らげることができます。
| カテゴリー | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 時期 | 夏の土用 | おおよそ7月中旬〜8月上旬 |
| 土用殺方位 | 夏の干支「未」 | 南西 |
| 注意点 | 行動制限 | 旅行や引越しは慎重に |
土用殺の考え方と上手な向き合い方
土用殺の考え方は、単なる迷信と捉えるか、生活の知恵とするかで意味合いが大きく変わります。科学的な根拠があるわけではありませんが、土用という不安定な時期に無理をしないという姿勢自体は、現代でも心と体を守るうえで有効な教訓になります。
特に夏土用は、暑さや疲れから体調を崩しやすい時期でもあります。そうした時期に「無理に行動せず、慎重になる」という土用殺の教えは、現代人の生活リズムにもマッチしています。
つまり、土用殺は「避けるべき方位に神経質になる」のではなく、「今は慎重に過ごす時期」という全体的な生活リズムの調整に役立てるのがポイントです。旅行や重要な行動を計画する際は、こうした知恵を参考にしながら、自分にとって無理のない選択をすることが、より豊かな日々につながっていくでしょう。

春夏秋冬の土用一覧
土用といえば「夏の土用の丑の日」が有名ですが、実は四季それぞれに土用の期間が存在します。春・夏・秋・冬の季節の変わり目に訪れるこれらの土用は、体調を整えるタイミングや行動を控えるべき時期としても知られています。そこで今回は、春夏秋冬すべての土用について、特徴や過ごし方を一覧形式でわかりやすくご紹介します。
春夏秋冬の土用と過ごし方一覧
以下の表は、2025年の春夏秋冬それぞれの土用期間、食べると良いとされる食べ物、気をつけたい方角(「土用殺」)をまとめたものです。
| 季節 | 土用の期間 | 良いとされる食べ物 | 丑・辰などの日 | 土用殺の方角 |
|---|---|---|---|---|
| 春土用 | 4月17日~5月4日 | 「い」のつくもの、白い食べ物 | 戊の日(4/23) | 南東 |
| 夏土用 | 7月19日~8月6日 | 「う」のつくもの、黒い食べ物 | 丑の日(7/19, 7/31) | 南西 |
| 秋土用 | 10月20日~11月6日 | 「た」のつくもの、青い食べ物 | 辰の日(10/26) | 北西 |
| 冬土用 | 1月17日~2月2日 | 「ひ」のつくもの、赤い食べ物 | 未の日(1/26) | 北東 |

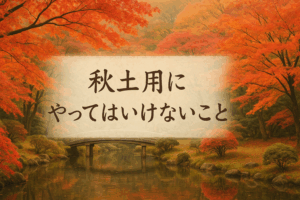
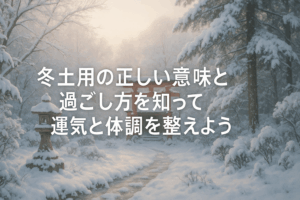
土用の食べ物に込められた意味
それぞれの土用では、特定の言葉の頭文字や色を持つ食べ物を摂ると良いとされています。これは、その季節特有の気に対して、身体の調子を整えるための伝統的な知恵です。たとえば夏土用の「うなぎ」などは、暑さで弱りがちな体に栄養を与えるスタミナ食として知られています。
また、「色」に注目するのも重要なポイントです。春は白、夏は黒、秋は青、冬は赤といった色分けは、五行思想に基づいたもので、自然の流れに合わせて体をいたわるという考えに根ざしています。
方角に注意する「土用殺」
「土用殺(どようさつ)」とは、土用の期間中に特定の方角へ向かうことを避けるべきとされる考え方です。旅行や引っ越しなど、大きな移動を控えることで、トラブルや不調を避けることができるとされています。これは昔ながらの風習ですが、現代でも「計画的な行動の指針」として参考にされる方も多いです。
季節の節目を意識する暮らしの知恵
土用は単なる暦上の期間ではなく、体調や生活を見直すきっかけでもあります。日常に追われがちな現代だからこそ、こうした季節の節目を意識することで、心身ともに整った生活を送ることができるでしょう。
自然のリズムと調和した暮らしを意識することで、心地よい毎日を手に入れるヒントになります。土用の時期は、無理をせず、静かに次の季節を迎える準備期間として活用してみてはいかがでしょうか。
夏土用とは何かを理解し、暮らしに活かすためのまとめ
- 夏土用は夏の終わりから秋の始まりにかけての約18日間を指す暦の区分である
- 土用は年に4回あり、春・夏・秋・冬それぞれの季節の変わり目に存在する
- 「夏土用」が特に知られているのは「土用の丑の日」との関係による影響が大きい
- 2025年の夏土用は7月19日から8月6日までで、丑の日は7月19日と7月31日の2回ある
- 「土用」は陰陽五行説に基づく概念で、季節の調整期間としての意味を持つ
- 夏土用は特に暑さが厳しく体調を崩しやすいため、養生の期間とされている
- 土用期間中は土を動かす行為(耕作・引っ越し・工事など)を避けるのが習わしである
- 「土用殺」とはその時期に避けるべき凶方位のことで、旅行や移動時に注意が必要
- 夏土用の代表的な風習に「虫干し」や「梅干しの天日干し」がある
- 「土用の丑の日」に鰻を食べる風習は江戸時代の平賀源内の発案が由来とされる
- 鰻はビタミン類が豊富で夏バテ予防に適した栄養価の高い食品である
- 鰻の旬は秋から冬だが、夏に売れ行きが悪かったため販促目的でも風習化された
- 土用期間は心身を労わり、大きな変化を控える時期としても意識されている
- 昔の人々は土用を自然と調和して暮らすための生活の知恵として活用していた
- 現代でも暦の知恵を取り入れることで、季節の変わり目を健やかに過ごせるようになる
土用の関連記事
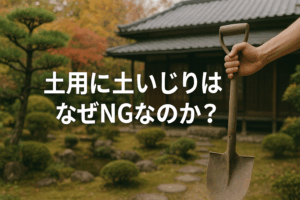




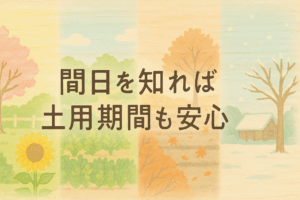


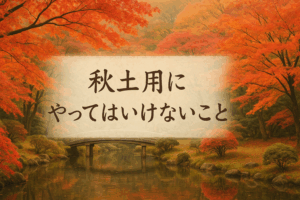
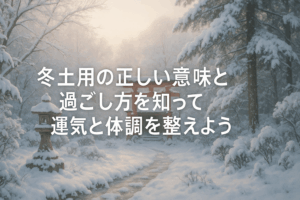















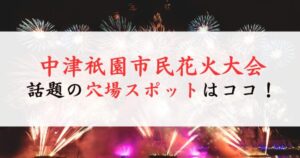




コメント