復日は縁起がいい?
暦注にもいろんな種類がありますが、なんとなく文字から吉凶が推察出来るものも多いのです。
しかし、今回紹介する復日は名前だけではどのような日なのか推察できず、由来や意味まで見通すことは難しいでしょう。
復日の読み方や2025年はいつが該当するのかも含めて、皆様にとって気になる情報を満載でお届けします。
同じような意味があると言われている重日との違いもチェックしていきましょう。
復日とは?

復日とは「良いことはさらにプラスに働いて、悪いことはさらにマイナスに働く日」という意味があります。
重日と全く同じ意味を持っているのです。
由来はかなり色々と調べましたが、気になる情報は「コトバンク」のモノです。
それを見た限りでは陰陽道における五行の考え方が基本になっているという事がわかります。
陰陽道は古代中国で生まれた自然哲学思想ではありますが、日本独自の進化を遂げている呪術や占術の技術体系そのものですので、そこが元となっているということは復日は日本独自に誕生したモノと考えて間違いないでしょう。
個人的に気になることは同じように日本独自で作られたモノと推察出来る重日とほとんど同じ意味にしているということです。
同じ意味を持たせるのなら、わざわざ別の暦注を用立てる必要は無いと思ってしまいます。
復日の読み方
前者の「ふくにち」はなんとなく読めると思いますが「ぶくび」はちょっと読みにくいでしょう。
昔のカレンダーは「ぶく日」と記載していたと言われているので、おそらく「ふくにち」よりも「ぶくび」と読んでいた人が多いと思われます。
ただし、どちらにしても変換では出てきませんので単語登録して使いましょう。
それだけでも知名度がそこまで高くないと言うことがわかってしまいます。
その言葉が現代社会においてどれだけ浸透しているのかを調べる簡易的なバロメーターがこの単語登録されているかどうかなので、気になる単語が出てきたらスマートフォンやパソコンを使って入力して見てください。
2025年の復日はいつ?
2025年の復日は現在の暦(普通のカレンダーで見た時)では下記の通りです。
| 日にち | 節月 | 六曜 | 日干支(節月) | 十支 |
| 2025年1月4日 | 11月 | 先負 | 丁卯 | 丁 |
| 2025年1月6日 | 12月 | 大安 | 己巳 | 己 |
| 2025年1月15日 | 12月 | 仏滅 | 戊寅 | 戊 |
| 2025年1月16日 | 12月 | 大安 | 己卯 | 己 |
| 2025年1月25日 | 12月 | 友引 | 戊子 | 戊 |
| 2025年1月26日 | 12月 | 先負 | 己丑 | 己 |
| 2025年2月6日 | 1月 | 友引 | 庚子 | 庚 |
| 2025年2月10日 | 1月 | 先勝 | 甲辰 | 甲 |
| 2025年2月16日 | 1月 | 先勝 | 庚戌 | 庚 |
| 2025年2月20日 | 1月 | 大安 | 甲寅 | 甲 |
| 2025年2月26日 | 1月 | 大安 | 庚申 | 庚 |
| 2025年3月1日 | 1月 | 先負 | 甲子 | 甲 |
| 2025年3月8日 | 2月 | 仏滅 | 辛未 | 辛 |
| 2025年3月12日 | 2月 | 仏滅 | 乙亥 | 乙 |
| 2025年3月18日 | 2月 | 仏滅 | 辛巳 | 辛 |
| 2025年3月22日 | 2月 | 友引 | 乙酉 | 乙 |
| 2025年3月28日 | 2月 | 友引 | 辛卯 | 辛 |
| 2025年4月1日 | 2月 | 赤口 | 乙未 | 乙 |
| 2025年4月4日 | 3月 | 先負 | 戊戌 | 戊 |
| 2025年4月5日 | 3月 | 仏滅 | 己亥 | 己 |
| 2025年4月14日 | 3月 | 友引 | 戊申 | 戊 |
| 2025年4月15日 | 3月 | 先負 | 己酉 | 己 |
| 2025年4月24日 | 3月 | 赤口 | 戊午 | 戊 |
| 2025年4月25日 | 3月 | 先勝 | 己未 | 己 |
| 2025年5月4日 | 3月 | 仏滅 | 戊辰 | 戊 |
| 2025年5月8日 | 4月 | 仏滅 | 壬申 | 壬 |
| 2025年5月12日 | 4月 | 友引 | 丙子 | 丙 |
| 2025年5月18日 | 4月 | 友引 | 壬午 | 壬 |
| 2025年5月22日 | 4月 | 赤口 | 丙戌 | 丙 |
| 2025年5月28日 | 4月 | 赤口 | 壬辰 | 壬 |
| 2025年6月1日 | 4月 | 仏滅 | 丙申 | 丙 |
| 2025年6月8日 | 5月 | 先勝 | 癸卯 | 癸 |
| 2025年6月12日 | 5月 | 大安 | 丁未 | 丁 |
| 2025年6月18日 | 5月 | 大安 | 癸丑 | 癸 |
| 2025年6月22日 | 5月 | 先負 | 丁巳 | 丁 |
| 2025年6月28日 | 5月 | 先負 | 癸亥 | 癸 |
| 2025年7月2日 | 5月 | 先勝 | 丁卯 | 丁 |
| 2025年7月13日 | 6月 | 先勝 | 戊寅 | 戊 |
| 2025年7月14日 | 6月 | 友引 | 己卯 | 己 |
| 2025年7月23日 | 6月 | 大安 | 戊子 | 戊 |
| 2025年7月24日 | 6月 | 赤口 | 己丑 | 己 |
| 2025年8月2日 | 6月 | 先負 | 戊戌 | 戊 |
| 2025年8月3日 | 6月 | 仏滅 | 己亥 | 己 |
| 2025年8月8日 | 7月 | 大安 | 甲辰 | 甲 |
| 2025年8月14日 | 7月 | 大安 | 庚戌 | 庚 |
| 2025年8月18日 | 7月 | 先負 | 甲寅 | 甲 |
| 2025年8月24日 | 7月 | 先負 | 庚申 | 庚 |
| 2025年8月28日 | 7月 | 先勝 | 甲子 | 甲 |
| 2025年9月3日 | 7月 | 友引 | 庚午 | 庚 |
| 2025年9月8日 | 8月 | 先勝 | 乙亥 | 乙 |
| 2025年9月14日 | 8月 | 先勝 | 辛巳 | 辛 |
| 2025年9月18日 | 8月 | 大安 | 乙酉 | 乙 |
| 2025年9月24日 | 8月 | 大安 | 辛卯 | 辛 |
| 2025年9月28日 | 8月 | 先負 | 乙未 | 乙 |
| 2025年10月4日 | 8月 | 仏滅 | 辛丑 | 辛 |
| 2025年10月11日 | 9月 | 大安 | 戊申 | 戊 |
| 2025年10月12日 | 9月 | 赤口 | 己酉 | 己 |
| 2025年10月21日 | 9月 | 先負 | 戊午 | 戊 |
| 2025年10月22日 | 9月 | 仏滅 | 己未 | 己 |
| 2025年10月31日 | 9月 | 先勝 | 戊辰 | 戊 |
| 2025年11月1日 | 9月 | 仏滅 | 己巳 | 己 |
| 2025年11月8日 | 10月 | 大安 | 丙子 | 丙 |
| 2025年11月14日 | 10月 | 大安 | 壬午 | 壬 |
| 2025年11月18日 | 10月 | 先負 | 丙戌 | 丙 |
| 2025年11月24日 | 10月 | 先負 | 壬辰 | 壬 |
| 2025年11月28日 | 10月 | 先勝 | 丙申 | 丙 |
| 2025年12月4日 | 10月 | 友引 | 壬寅 | 壬 |
| 2025年12月9日 | 11月 | 先勝 | 丁未 | 丁 |
| 2025年12月15日 | 11月 | 先勝 | 癸丑 | 癸 |
| 2025年12月19日 | 11月 | 大安 | 丁巳 | 丁 |
| 2025年12月25日 | 11月 | 大安 | 癸亥 | 癸 |
| 2025年12月29日 | 11月 | 先負 | 丁卯 | 丁 |
同じような意味を持っている重日も1年間に60回ほどありますので、同じような日が1年に約130回も発生するということになります。
1年の30%以上がこの「良いことはさらにプラスに働いて、悪いことはさらにマイナスに働く日」という日になりますので、重日とセットで覚えておきましょう。
復日の決め方について
復日の決め方は二十四節気の節入で区切って後はその日の十干で決まります。
正月と7月は甲の日と庚の日、2月と8月は乙の日と辛の日、3月と6月と9月と12月は戊の日と己の日、4月と10月は丙の日と壬の日、5月と11月は丁の日と癸の日となっているのです。
このように十干は甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10種類からなるのですが、復日はその中に2つが必ず該当するようになっているので、5日に1回は訪れるという計算になります。
つまり、1年が365日と考えるとだいたい72回はこの復日が発生するということになるのです。
2025年は71回ほど復日が発生することが上述してあることかわかっているので、この単純計算もある程度あっているということがわかります。
復日は縁起がいい?

先ほど記載したように復日は「良いことはさらにプラスに働いて、悪いことはさらにマイナスに働く日」になりますので、吉日でも凶日でもありません。
その日の行動次第ではプラスにもマイナスにもなる日なのです。
むしろ善行を積むと大吉に変ずる日になりますので、縁起が良い日と考えた方が良いでしょう。
また、旅行や金銭の貸し出しにも大きなプラスとなると言われているので覚えておいてください。
NG行動となってくるのが、婚礼や葬儀はなっているので注意しましょう。
結婚と相性が悪いと言われている理由は再婚に繋がってしまうことが理由になっているようです。
復日と重日の違いは?
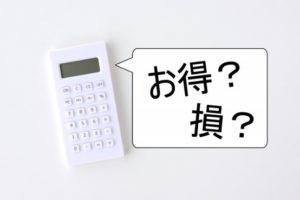
重日の意味は「良いことはさらにプラスに働いて、悪いことはさらにマイナスに働く日」ですので、はっきり言って意味は復日と全く一緒です。
違いは重日は陽が重なる巳の日という陰が重なる亥の日が該当するという決め方でしょう。
また、重日は治療や種まきとも相性が悪いという情報があります。
そして、重日で吉となる行動は善行以外に商品や不動産の回入れや新しい何かを取り入れるか始めるというのもあるので、これも違いになりそうです。
個人的にはこの程度の違いしかないと思ってしまうので、一緒にしてしまって良いと考えてしまいます。
しかし、重日は中国の易学からきているという情報もあり、陰陽五行思想からきている復日とは発祥が異なっています。
そのためこの2つを後から一緒にすることはできないのでしょう。
凶日は何がある?
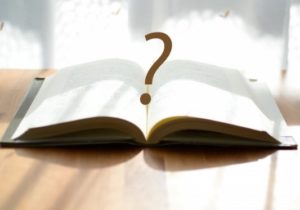
復日や重日は扱い方次第で凶日になってしまいますが、本格的な凶日というのは仏滅や赤口以外にも色々とあるのです。
有名どころとしては不成就日や受死日や十死日や三隣亡といったところでしょうか。
マイナーなところでは、帰忌日・天火日・地火日・大禍日・狼藉日・滅門日などが該当します。
このように凶日という扱いを受けている暦注は大量にありますが、知名度が低いモノがかなりありますので気になったモノは一つ一つ調べていく必要があるでしょう。
凶日の考え方について
凶日はこのようにかなり色んな種類がありますので、それらすべてを考慮すると行動が非常にしにくくなります。
なので、すべての凶日を考慮して日々を生きていくというのはやめた方が良いでしょう。
逆に吉日をすべてチェックするというのも大変ですので、ある程度気になったモノをピックアップするのが正解でしょう。
ただし、凶日には受死日や十死日のようにあらゆる吉日をすべて無効化してしまうようなものもありますので、このように影響力がでかすぎるモノを抜粋するというのもポイントになると思います。
しかし、暦注というのはあくまでも科学的根拠が無い迷信という意見も多数ありますので、あまり影響されすぎないことも重要になるのでしょう。
復日のまとめ
以上、いかがだったでしょうか。
今回は復日とはいったい何なのかを記載して参りました。
復日はこのようにちょっと変わった暦注であり、意味はほとんど重日と変わらないという不思議な日となっています。
善行を積めば積むほどプラスになってくれる日でもありますので、常に意識して行動することも大切になってくるでしょう。
良いことをすれば必ず良いことが返ってくるというのは一種の人生訓でもありますので、この意識は重要になるでしょう。











コメント