お年賀という言葉を聞くと、多くの人が新年の挨拶やギフトのことを思い浮かべるでしょう。
しかし、いつからいつまでが正しい時期なのか、どんなギフトが喜ばれるのか、正確には知らないという方も少なくないはず。
新年を迎えるこの特別な時期、間違った方法でお年賀を渡してしまうと、相手に不快な思いをさせてしまうかもしれません。
そんな心配を解消し、正しいお年賀の渡し方や喜ばれるギフト選びを知りたい方へ、この記事が役立つ情報を提供します。
初心者の方でも安心してお年賀を楽しむことができるように、わかりやすく解説しています。
- お年賀は新年の挨拶を意味する。
- お年賀の贈り物は、新年を迎える前に準備するのが一般的。
- お年賀の期間は、元日から松の内まで。
- お年賀のマナーには、相手の状況や関係性を考慮することが大切。
- お年賀を送る際の注意点やマナーを守ることで、相手との関係をより良好に保つことができる。
お年賀とは

お年賀とは、新年を迎える際に、親しい人々や取引先などに対して、新しい年の幸せや感謝の気持ちを伝えるための挨拶や贈り物の習慣のことを指します。
この慣習は、新しい年の年神様を迎えるための祭りから始まったとされています。
古くから、年神様を祀る神棚や仏壇にお供えする品物を「御年魂」と称し、これを互いに交換する風習がありました。
時が経つにつれて、この行為は手土産を持参する形に変わり、子供には「御年玉」、家族や知人には「お年賀」として贈られるようになりました。
現代では、新年の挨拶として「今年もよろしくお願いします」という意味を込めて、年始に訪問する際に持参することが一般的です。
特に、目下の者から目上の方への贈り物として行われることが多いです。
また、新年の初めには家族や友人、取引先などとの関係を再確認し、新しい年の幸せや感謝の気持ちを共有するための大切な機会となっています。
お年賀の意味と起源
お年賀は、日本の伝統的な新年の挨拶や贈り物の習慣として、長い歴史を持つものです。
平安時代、約1000年前には、この習慣が既に根付いていたことが記録に残されています。
その頃、宮中や高位の貴族たちは新年を迎えるたびに、お互いに特別な贈り物や挨拶を交換していました。
これは、現代におけるお年賀の礼状や贈り物の原点と言えるでしょう。
お年賀の背後には、新しい年の幸せや繁栄を祈願するという深い意味が込められています。
また、これは一年の安全や成功を祈るとともに、人々の絆を深めるための大切な機会ともなっています。
参考資料:お年賀の起源やマナーは?| Shaddyのギフトマナー辞典
お歳暮、お中元、お年賀の違い
お歳暮、お中元、お年賀の違いを詳しく解説します。
お歳暮
お歳暮は、年の終わりに近づく時期に行われる贈り物の習慣です。
これは、一年間の感謝の気持ちやお世話になった方への礼を示すためのものです。
多くの場合、冬の食材や温かいアイテムなど、季節に合わせた品物が選ばれます。
お中元
お中元は、夏の初め、特に7月の初旬に行われる贈り物の習慣です。
これは、暑さの中での健康を祈願し、また夏の暑さを乗り越えるためのエネルギーを提供する食品や飲料などを贈ることが一般的です。
お年賀
新年を迎える際に行われる挨拶や贈り物の習慣を指します。
これは、新しい年の始まりを祝うため、また新年の幸運や健康を祈願する意味が込められています。
お年賀として贈られるアイテムには、新年のカレンダーやお酒、お菓子などがあります。
これらの習慣は、日本の伝統的な文化の一部として、長い間受け継がれてきました。
それぞれの時期や目的に応じて、適切なアイテムを選び、相手の気持ちを考慮しながら贈ることが大切です。
お年賀いつまで? 正しい時期と期間

お年賀の時期は
新年を祝うための伝統的な日本の習慣で、お年賀の時期は、1月1日から始まる新年の初めの数日間を指します。
この特別な時期には、家族や友人、ビジネス関係者などとの絆を深めるために、お年賀状の交換や贈り物の贈呈が行われます。
お年賀状は、新年の挨拶や感謝の気持ちを伝えるための手段として、長い間日本の文化に根付いています。
また、お年賀の贈り物は、新年を迎えるにあたっての感謝や願いを込めて、様々なアイテムが選ばれます。
これらの習慣は、新しい年のスタートを祝うための重要な役割を果たしています。
お年賀の期間はいつまで?
お年賀の期間とは、新年を迎える際の挨拶や感謝の意を示すための特定の日数を指します。
お年賀を贈る正式な期間は、1月1日から3日の正月三が日です。
※ただ、お年賀は、元日は避けるのがマナーと言えます。同様に午前中も避けるのがよいでしょう。
しかし、この期間に間に合わない場合は、1月6日まで、または地域によっては1月7日、15日までの「松の内」の間に訪問するのが一般的です。
この期間は、新年の祝賀や挨拶を行うための最も適切な時期とされています。
特に、1月1日は元日として、新しい年の始まりを祝う日として重要視されています。
そのため、この日を中心に、家族や友人、知人に対してお年賀の挨拶や贈り物を行うことが一般的です。
この期間を過ぎると、お年賀の挨拶は控えるのがマナーとされています。
関東と関西での松の内の違い
「松の内」とは、新年を迎える際のお祝いや行事を行う期間を指す言葉です。
この期間中には、家々での飾り付けや、神社仏閣への初詣、さまざまな伝統的な行事が行われます。
しかし、この「松の内」の期間は、地域によって異なる特色を持っています。
特に、関東と関西の間でその期間の定義が異なることは、日本の文化の多様性を示す一例とも言えます。
関東地方では、新年を迎えてから1月7日までの期間を「松の内」としています。
この日は「人日(じんじつ)」とも呼ばれ、七草粥を食べる風習があります。
七草粥には、新しい年に健康で過ごすことを願う意味が込められています。
関西地方では、新年から1月15日までを「松の内」と定義しています。
この日は「小正月」とも称され、火祭りやどんど焼きといった行事が行われます。
関西地方では、この日に行われる行事を通じて、古い年の災厄を払い、新しい年の幸福を祈願します。
このような違いは、関東と関西の歴史的背景や気候、風土に起因するものと考えられています。
関東は、かつての幕府の所在地であり、公家文化の影響を受けた関西とは異なる風習や行事が根付いてきました。
また、関西地方の方が冬が長く、そのため新年の行事も長く続けられるという気候的な要因も考えられます。
このように、関東と関西の「松の内」の期間の違いは、それぞれの地域の歴史や文化、風習に深く根ざしています。
これを知ることで、日本の伝統や文化の奥深さをより深く理解することができるでしょう。
お年賀と寒中見舞いの違い
「お年賀」と「寒中見舞い」は、ともに新年の挨拶の一形態でありながら、その目的や時期に違いがあります。
以下、それぞれの特徴を詳しく解説します。
お年賀
- お年賀は、新年を迎える際の挨拶や感謝の意を示すためのものです。新しい年の始まりを祝うため、家族や友人、ビジネス関係者などに対して、贈り物やカードを送る習慣があります。
- この期間は、大抵の場合、1月1日から数日間とされています。
寒中見舞い
- 寒中見舞いは、お年賀の期間を過ぎた後、特に寒さが厳しい時期に行われる挨拶です。この挨拶は、受取人の健康や安全を気遣う意味合いが強いです。
- 寒中見舞いは、お年賀を送ることができなかった場合や、新年の挨拶を遅れて行う場合に、その代わりとして行われることもあります。
要するに、お年賀は新年の喜びや感謝を伝えるためのものであり、寒中見舞いは寒さの中での健康や安全を気遣うためのものです。
それぞれの挨拶には、異なる背景や意味が込められています。
お年賀の贈答マナーと注意点

お年賀を渡すタイミング
お年賀は、新年の挨拶としての役割を持つため、伝統的に1月1日から「松の内」までの期間に手渡しするのが一般的です。
この「松の内」とは、新年を祝う期間を指し、地域や家庭によって異なることがありますが、多くの場合、1月7日までを指します。
しかし、相手の生活スタイルや都合を考慮し、柔軟に日程を調整することが求められます。
例えば、相手が年末年始に旅行をしている場合や、特定の日に不在であることが予想される場合は、その前後の日程でお年賀を渡すことを検討すると良いでしょう。
重要なのは、心のこもった挨拶を伝えること。
そのため、相手の状況や都合を尊重し、最も適切なタイミングでお年賀を手渡すことが大切です。
お年賀の贈り方と最適な配送手段
お年賀は、新年の挨拶としての感謝や願いを込めて贈るものです。
その贈り方には、直接手渡しと郵送・宅配サービスを利用する2つの主な方法があります。
- 直接手渡し: これは、近所の方や頻繁に会う知人・友人に対して行われることが多い方法です。直接のコミュニケーションが取れるため、感謝の気持ちを伝えやすく、また、相手の反応も直接見ることができます。
- 郵送・宅配サービス: 遠方に住む方や、年末年始に直接会うことが難しい方へのお年賀は、郵送や宅配サービスを利用することが一般的です。この方法を選ぶ際のポイントは、相手の住所や関係性を考慮すること。例えば、ビジネス関係でのお年賀は、プロフェッショナルな宅配サービスを選ぶと良いでしょう。
最終的に、どの方法を選ぶかは、相手との関係性や状況に応じて柔軟に選択することが大切です。
お年賀の意味や目的を忘れずに、心を込めて贈りましょう。
お年賀の正しい渡し方は?
お年賀は、新年の挨拶としての意味合いを持つため、その渡し方にも一定のマナーが求められます。
まず、お年賀を手渡しする際には、相手の目をしっかりと見て、心からの感謝の気持ちを込めて挨拶をします。
この挨拶は、新年の幸せを祈るとともに、昨年中の感謝の意を示すものとなります。
次に、贈り物を渡す際のポイントですが、両手を使って渡すことが基本的なマナーとされています。
これは、相手への敬意を示すとともに、贈り物の大切さを伝えるためのものです。
また、お年賀の包みや袋には、自分の名前や住所を明記し、相手が誰からのものかを一目でわかるようにすることも忘れずに行いましょう。
さらに、お年賀を渡すタイミングも重要です。
新年の初め、特に1月1日から7日の間に渡すのが一般的ですが、事前に相手の都合を確認し、適切なタイミングで手渡しすることが望ましいとされています。
以上の点を心掛けることで、お年賀の渡し方におけるマナーを守ることができます。
新年の挨拶としてのお年賀は、相手への感謝の気持ちを伝える大切なもの。
正しいマナーを守りながら、心からの挨拶を伝えましょう。
お年賀を手渡す時の言葉
新年を迎えるこの特別な時期に、お年賀を手渡す際の言葉は、相手への敬意や感謝の気持ちを伝える大切な要素となります。
一般的には「新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします」という言葉が用いられることが多いです。
この挨拶は、新しい年の始まりを祝いつつ、今後の一年間の関係をより良好にしていきたいという意味が込められています。
以下は、さまざまなシチュエーションに応じたお年賀の挨拶の例です。
ビジネスの場での挨拶
「新年あけましておめでとうございます。昨年は大変お世話になりました。本年も変わらぬご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。」
親しい友人や家族への挨拶
「あけましておめでとう!昨年は色々とありがとう。今年も一緒に楽しい時間を過ごそうね!」
初めてのお隣さんや新しい環境の人々へ
「新年あけましておめでとうございます。初めての挨拶となりますが、今年もよろしくお願いいたします。」
長い間会っていない知人や友人へ
「新年あけましておめでとうございます。久しぶりのご挨拶となりますが、元気でお過ごしでしょうか。今年もよろしくお願いします。」
重要なのは、言葉を通して相手への感謝や期待を伝えること。
その際の言葉選びは、相手との関係性や状況を考慮しながら、心を込めて選ぶことが大切です。
お年賀ののしの選び方
お年賀の際に贈る品物にのし紙を添えるのは、日本の伝統的なマナーとして広く知られています。
こののし紙は、単なる装飾品ではなく、贈る相手への敬意や気持ちを伝える重要な役割を果たしています。
のし紙の色の選び方
| 対象 | 色の選び方 | 例 |
|---|---|---|
| 若い方 | 明るく華やかな色 | ピンク、明るい青、黄色 |
| 年配の方 | 落ち着いた色合い | 深緑、紺、茶色 |
| 女性 | 柔らかい色 | ピンク、紫、水色 |
| 男性 | シャープな色 | 青、緑、灰色 |
のし紙のデザインの選び方
| 対象 | デザインの選び方 | 例 |
|---|---|---|
| 親しい友人・家族 | カジュアルなデザイン | 花柄、アニメキャラクター |
| ビジネス関係・上司 | シンプルで格式のあるデザイン | 幾何学的な模様、無地 |
最後に、のし紙を選ぶ際は、相手の好みや趣味を考慮することも大切です。
心を込めて選んだのし紙は、贈る相手の心を温かくすることでしょう。
お年賀にお返しは必要?
お年賀を受け取った際に、多くの人が感じるのは「お返しは必要なのだろうか?」という疑問です。
しかし、お年賀の本来の意味を理解すると、お返しをする必要はないことがわかります。
お年賀は、新年の幸せを願う気持ちや、過去一年間の感謝を伝えるためのものであり、それに対して何かを返すという考え方は含まれていません。
さらに、お年賀を贈る際の心得として、贈る側がお返しを期待してはならないというマナーがあります。
これは、お年賀が相手に対する感謝や敬意の気持ちを伝えるためのものであることを再認識させるものです。
ただし、お年賀を受け取った際には、その気持ちを受け取ったことへの感謝を伝えることが大切です。
具体的には、お礼の言葉を添える、または新年の挨拶をするなどの形で、相手に感謝の気持ちを伝えることが望ましいとされています。
結論として、お年賀に対してお返しをする必要はありませんが、受け取った気持ちを大切にし、感謝の意を示すことが重要です。
手土産としてのお年賀の注意点
お年賀の時期に訪問する際の手土産としてお年賀を選ぶ場合、以下の点に注意して選択することが求められます。
相手の好みを尊重
お年賀は年の初めの挨拶としての意味合いが強いため、相手の好みや趣味を考慮してアイテムを選ぶことが重要です。
例えば、相手が甘いものが好きであれば、和菓子や洋菓子を選ぶと喜ばれるでしょう。
アレルギー情報の確認
お年賀として食品を選ぶ場合、相手やその家族が持つアレルギーを事前に確認し、それに合わせて商品を選ぶことが必要です。
アレルギー情報が不明な場合は、成分表示を確認できる商品を選ぶと安心です。
のし紙の取り扱い
お年賀を手土産として持参する場合、のし紙をつけるのは一般的ではありません。
のし紙は贈答品としての格式を示すものであり、手土産としてのカジュアルな雰囲気とは異なるため、適切ではありません。
包装の工夫
お年賀は特別な時期の贈り物であるため、包装にも工夫を凝らすと良いでしょう。
季節感のあるデザインや、新年を感じさせるモチーフを選ぶと、相手に喜ばれることでしょう。
お年賀を手土産として持参する際は、これらの点を心がけて選ぶことで、相手に喜んでいただけること間違いなしです。
喪中の場合のお年賀のマナー
喪中とは、家族が亡くなった際の一定期間を指し、この期間中は様々な社交行事を控えるのが日本の伝統的なマナーとなっています。
特にお年賀に関しては、喜びの気持ちを表現する行事であるため、喪中の家庭や個人に対しては控えるのが一般的です。
お年賀の贈り物や挨拶を控える理由としては、喪中の家庭や個人が喜びの気持ちを共有するのが難しいと考えられるからです。
そのため、喪中の相手には、喪中はがきを送ることで、お悔やみの気持ちを伝えるのが適切とされています。
喪中はがきは、相手に対する気配りや思いやりの気持ちを示すためのものであり、喪中の期間や理由を伝えるとともに、お年賀を控える旨を伝えることができます。
また、喪中の期間は家庭や宗教によって異なることがありますので、相手の状況を十分に理解し、適切な対応を心がけることが大切です。
喪中のマナーを守ることで、相手に対する敬意や思いやりの気持ちを示すことができます。
お年賀の人気ギフトと予算や相場

お年賀として喜ばれるギフトは何?
お年賀のギフト選びは、贈る相手の好みやニーズを考慮することが大切です。
また、お年賀として喜ばれるギフトとしては、食品や日用品、アクセサリーなどの実用的なものが一般的です。
また、最近では健康や美容に関する商品も人気があります。
以下は、お年賀として特に喜ばれるギフトの一例です。
| カテゴリ | アイテム | 詳細・特徴 |
|---|---|---|
| 食品 | 新鮮な果物 | 季節のフルーツや特産品。新年の健康を願うメッセージとして最適。 |
| 地域限定のお菓子 | 各地域の伝統や文化を感じられるお菓子。親しい人への贈り物として人気。 | |
| 伝統的な和菓子 | 日本の伝統を感じられる和菓子。老若男女問わず喜ばれる。 | |
| 日用品 | 高品質なタオル | 毎日の生活で使えるアイテム。肌触りや吸水性にこだわったものが好評。 |
| キッチン用品 | 料理好きや新婚の方へのギフトとして。実用的でデザイン性のあるものが人気。 | |
| アロマオイル | リラックス効果があり、香りで心と体を癒す。多種多様な香りが楽しめる。 | |
| 健康・美容 | スーパーフード商品 | 健康志向の方へ。栄養価が高く、体に良いとされる食材を取り入れた商品。 |
| オーガニックコスメ | 肌に優しい成分を使用。美容と健康を両立させたい方へのギフトとして。 | |
| 健康茶 | 体の内側から健康をサポート。様々なハーブや成分が配合されている。 |
お年賀として喜ばれるギフト選び方のポイントは?
お年賀のギフト選びは、単にプレゼントを贈る以上の意味があります。
それは、新しい年の始まりを祝い、相手への感謝の気持ちを伝える大切な機会です。
そのため、選ぶギフトには以下のポイントを考慮することが重要です。
相手の好みを尊重する
ギフト選びの基本として、相手の好みや趣味を考慮することが最も重要です。
例えば、相手が健康志向であれば、オーガニックの食品や健康グッズを選ぶと喜ばれるでしょう。
ライフスタイルを考慮する
相手の生活スタイルや家族構成を考慮してギフトを選ぶこともポイントです。
例えば、子供がいる家庭には、家族みんなで楽しめるギフトを選ぶと良いでしょう。
季節感を取り入れる
新年のギフトとして、季節の食材やアイテムを取り入れることで、その時期ならではの特別感を演出することができます。
トレンドを取り入れる
流行りのアイテムや話題の商品を取り入れることで、相手に新鮮な驚きを提供することができます。
オリジナリティを大切にする
市販のギフトセットだけでなく、自分なりのアイディアを取り入れて、オリジナルのギフトを選ぶことで、相手に深い感動を与えることができます。
最後に、ギフト選びは心のこもった気持ちを伝える手段です。
そのため、相手のことを思いやりながら、最適なギフトを選ぶことが大切です。
お年賀の予算や相場は?
| 贈る相手 | 関係性の例 | 予算の相場 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 親しい友人・親戚 | 高校・大学の友人、近所の親戚 | 3,000円〜5,000円 | 親しい間柄であれば、感謝の気持ちを伝えるための金額として適切。 |
| ビジネスの関係者・上司 | 取引先、部下からの上司へ | 5,000円〜10,000円 | ビジネスの関係性を維持・強化するため、また、敬意を示すための相場。 |
| 遠方の親戚・知人 | 年に数回しか会わない親戚、旧知の友人 | 2,000円〜4,000円 | 頻繁に交流がない場合でも、年末の挨拶としての意味合いが強い。 |
| 新しい関係 | 新しくできた友人、新しい職場の同僚 | 1,000円〜3,000円 | 初めてのお年賀として、控えめな予算で気持ちを伝える。 |
お年賀の時期を逃した場合の対応は寒中見舞いで

お年賀の時期を過ぎてしまったら寒中見舞いとして贈る
お年賀の時期を逃してしまったら、寒中見舞いとしての挨拶が一般的になります。
寒中見舞いは、お年賀のシーズンが終わった後、特に冷え込むこの時期に、相手の健康や安全を心から願う気持ちを表現するためのものです。
日本の伝統的な習慣として、新年の挨拶を逃した場合や、新年に何らかの理由で挨拶ができなかったときに、寒中見舞いとしてのメッセージや贈り物を送ることが推奨されています。
この習慣は、相手への気配りや心遣いを示す大切な文化として、多くの人々に受け継がれています。
そもそも寒中見舞いとは
8日以降で「寒中」の期間に「寒中見舞い」を持っていくのがいいでしょう。
寒中とは、1月7日~2月3日までです。
暦の寒の入りから小寒の始めから大寒の終わりの立春前までの約1ヶ月間といわれています。
寒中見舞いは、日本の伝統的な風習の一つで、お年賀のシーズンが終わった後の寒い時期に、人々の健康や安全を心から願い、その気持ちを伝えるための挨拶として行われます。
この風習は、深い感謝の意を込めて、新年の挨拶や過去一年間の感謝を伝えるためのものであり、贈り物やお返しを期待するものではなく、純粋に相手の健康や幸福を祈るものです。
特に、寒さが厳しい時期には、身体の健康を気遣うとともに、心の温かさを感じることができるこの風習は、日本の文化や人々の優しさを象徴しています。
立春を過ぎてしまうなら「余寒見舞い」に
立春の日を過ぎた後も、冷え込む日が続くことは珍しくありません。
このような時期に、人々の健康や安全を気遣うために「余寒見舞い」という習慣があります。
立春が春の始まりを告げる節目であるにも関わらず、実際の気温はまだ寒く、風邪やインフルエンザなどの病気が流行することも。
そこで、余寒見舞いは、友人や知人、家族などへの気遣いのメッセージとして、また、互いの健康を願う意味合いで行われるものです。
この習慣は、季節の変わり目の不安定な気候に対する人々の思いやりや気配りを形にしたものと言えるでしょう。
寒中見舞いの相場・金額は?
寒中見舞いは、新年の挨拶を遅れて行う際の贈り物やお礼の形として行われる伝統的な行事です。
その金額や相場は、贈る相手との関係性、年齢、家族の構成などの要因によって変動します。
寒中見舞いの相場・金額についての詳細
| 贈る相手 | 一般的な相場 | 詳細 |
|---|---|---|
| 親しい友人・親戚 | 3,000円〜5,000円 | 親しい間柄であれば、感謝の気持ちを込めてこの範囲の金額が適切とされています。 |
| ビジネスの取引先・上司 | 5,000円〜10,000円 | 公式な関係の相手には、礼儀正しく、またビジネスのエチケットを守るためこの金額が推奨されています。 |
最終的な金額は、自分の予算や相手との関係の深さを考慮して決めることが大切です。
適切な金額を選ぶことで、相手に感謝の気持ちを伝えることができます。
お年賀のまとめ
お年賀は、新年を迎える際に行われる伝統的な挨拶や贈り物のことを指します。
お年賀の意味や起源、贈答マナーや注意点、相手別の品物選びや予算、相場など、さまざまなポイントがあります。
お年賀を通して、新しい年の幸せや感謝の気持ちを伝えることができます。
適切なタイミングや方法でお年賀を行うことで、相手に喜んでもらえることでしょう。
この記事のポイントをまとめますと
- お年賀は新年の挨拶としての役割がある
- 正月三が日に贈るのが一般的である
- お年賀は年末に準備するのが良い
- お年賀の品物は相手の好みを考慮することが大切である
- お年賀のマナーを守ることで相手に喜ばれる
- お年賀の習慣は日本独特のものである
- お年賀の期間は1月1日から7日までとされている
- お年賀の品物の選び方には流行やトレンドも影響する
- お年賀は相手の健康や幸福を願う気持ちを込めて贈るものである
お年賀の時期の関連記事
おせちはいつ食べる?元日?大晦日?タイミングは地域によって違う!




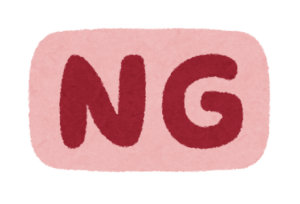




コメント